女性研究者キャリアパス支援プログラム
立命館大学に所属する専門研究員のうち、本大学において継続的な研究活動を引き続き行うことで今後の活躍が期待できると判断される優秀な研究者について、キャリアパスを積極的に支援することを目的としています。特定の分野に限定せず、人文社会科学から自然科学まで全ての分野を対象とした制度です。
採択者のコメント
 許 智香 衣笠総合研究機構 |
女性研究者キャリアパス支援プログラムに採択されて3年目になりますが、最も良かった点は、研究時間の安定的な確保です。研究に集中できた結果、2年目頃から仕事の依頼が増えました。以前は自分から論文を発表したり学会発表を申請していましたが、2021年度より招待講演を毎年行なっています。2022年6月にはweb公開の書評を依頼されて執筆しました。また同じ研究領域で活動している研究者との交流も増え、今年は5月に特集号への論文執筆の依頼を受けました。 今後は、科研費の課題(個人課題および共同研究課題)を中心に関連論文の執筆を進めていきたいと思っています。 |
|---|---|
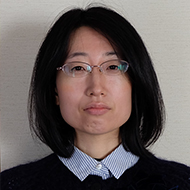 成田 千尋 衣笠総合研究機構 |
本制度に採択されて良かったと感じるのは、拘束時間が少ないため、自分のペースで研究を進めることができる点です。学内外での授業担当も4つまで可能なため、学外で教える経験も積みながら、個人研究と共同研究に取り組んでいます。また、昨年度は学部生や付属校の高校生向けに開催される「ライスボールセミナー」での研究発表の機会を頂き、学会や研究会以外の場での研究内容の伝え方についても考えさせられました。年度末に開催される任用者間の成果報告・交流会では、同じプログラムに採用されている方の研究の進展についてお話を聞くことができ、とても刺激になりました。自由な研究環境と、研究を発展させるための機会を頂けていることに感謝しています。 今後のキャリア形成に関しては、博士課程から沖縄返還を研究テーマとしてきましたが、昨年度は沖縄返還50年という節目だったために例年になく多くの依頼があり、まだ関連した原稿などの執筆に追われているため、まずは少しでも良い形で成果を残せるように努めたいと考えています。 |
 李 眞惠 衣笠総合研究機構 |
私は10年前に韓国出身の留学生として来日した後、研究者の道を行くことを選択しました。 本制度に採用された以降は、研究環境の良い本大学で研究活動を続けていくことが可能となりました。研究職従事者にとって、本制度はキャリアを断絶せずに研究活動を持続させていけることだけでなく、より安定した環境で多様なプログラムの積極的な支援を通じて、より質の高い研究成果を達成できる点が最も良いと考えています。今後、このような研究環境を積極的に活用し、挑戦し続け、活発に活躍する、何より男女共同参画推進とダイバーシティ研究環境実現に貢献する研究者になりたいと思います。 |
 向 静静 立命館アジア・日本研究機構 (採択時コメント) |
専門研究員から助教になり、学生の研究指導も行いつつ、教授や准教授の仕事を手伝うようになり、教員としての能力を身につけることができています。また、所属している立命館アジア・日本研究機構の教員会議に毎週出席するようになり、研究機構のイベントなどの運営にも参加しており、ワークショップや国際シンポジウム開催の企画に関するノウハウを蓄積しているところです。 さらに、国内や海外の研究者・大学から共同研究の誘いや講演の招待が多くなったのも、助教採用以降のことです。助教のキャリアを活かして、今後も社会へ還元できるような研究成果を発表し、キャリアアップに向けて頑張っていきたいと思います。 |
 鈴木 愛 OIC総合研究機構 |
女性研究者キャリアパス支援プログラムに採択していただき、肩書が「助教」となったことで、代表者の資格として助教以上を求められていた研究助成をいただくことができました。さらに時間的および精神的余裕を得られたことで、すぐには結果が出ない課題にも挑戦できるようになりました。また、採択結果と同時にいただいた審査員の先生の所見は、私には特別なものとなりました。専門分野が実践的学問であるため、現実社会の問題解決への貢献を大事にしてきましたが、その一方で、研究者としてどこまで行うべきか迷いもありました。しかし、社会実装へつなげる姿勢に対して好意的な評価をいただいたことで、自身のスタンスを貫く覚悟ができました。今後は、研究も社会実装もバランスよく行う研究者を目指すとともに、教育も積極的に行っていきたいと思います。 |