![]()
立命館から発信!!~心のバリアフリー~
波多野 愛さん(産業社会学部3回生)代表
吉田一貴さん(情報理工学部4回生)
小出優子さん(文学部3回生)
今年6月に発足した「MBF.com」は、障がいのある学生が有意義な大学生活を過ごせるよう、障がい者に対する偏見、差別や同情、また“障がい者との接し方がわからない”といった「心の壁(心のバリア)」を取り払う活動に取り組んでいる。団体名「MBF.com」である「メンタル(M)・バリア(B)・フリー(F)」は彼らの活動理念だ。

発足の中心となった吉田さんと小出さんは、普段授業で障がい学生をサポートする“障害学生支援室サポートスタッフ”だ。そのサポート活動の中で、「どんなにコミュニケーションを図っても障がい者の気持ちを理解していないのではないか」という悩みをもった。スタッフ同士の交流も少なく、悩みを解決できる場もなかった。そこで団体を立ち上げ、スタッフ同士の交流の場をつくることで障がい者支援を根強いものにしていこうと考えた。サポートを受ける障がい学生の本音を知って活動に生かすため、障がい学生にも参加を呼びかけた。代表の波多野さんは脳性麻痺の障がいのある学生である。
人々に障がい者に対する理解を深めてもらうため、学内では聴覚障がい者のための字幕や視覚障がい者のための音声ガイドを取り入れたバリアフリー映画上映会を開催している。聴覚障がい者のための字幕とは、例えば流れている音楽の解説や、誰がどの台詞を話しているのかがわかるものだ。健常者の学生にも目を閉じた状態での鑑賞を勧め、どう感じるのかを問いかけている。

また、企画主催にあたって、視覚障害の理解を深めるために何も見えない暗闇を体験するドイツ発祥の「ダイアログ・インザ・ダーク」を体験した。「ダイアログ・インザ・ダーク」とは参加者が暗闇の中で、視覚障がい者のサポートのもと食事や会計といったさまざまなシーンを体験する。小出さんは「ダイアログ・インザ・ダーク」を初めて体験したときのことをこう語る。「普段自分がサポートしている方に助けてもらうのが衝撃的でした。暗闇の中では視覚障がい者の方の方がプロフェッショナルなんです。」
学園祭ではゲーム感覚を取り入れた「ブラインドルーム」を講義室の一室に構え、恐怖だけでなく五感に刺激を与える全盲体験企画を開催した。そこでは単に暗闇を歩くだけでなく、大学生活そのものを味わい見えない世界を実感してもらえるよう、さまざまな工夫を施したという。またこうした企画の開催に加え、障がいについての勉強会を団体内で実施している。「まずは自分たちが学び、体験することで、“どうすれば障がい者の方の不安を取り払うことができるのか、障がい者の方が求める支援とは何か”を知ることができます。」と吉田さんは語った。

活動の中では「メンバーのさまざまな想いを一つに束ねることに苦労した。」と波多野さんは語る。例えば、「心の壁って、どんな壁?」「支援するって、どこまでするの?」と、それぞれ感じ方や考え方が異なるからだ。一方で大きな成長もあった。それは彼ら自身の“心のバリアフリー”が実現したこと。「最初は障がい者をなんとなく避けていたこともあったけど、健常者の友だちと何も変わらないと気づくことができました。人が高いところの物を取ろうとするとき台に乗って取るのと同じように、耳の聞こえない人とはメモをとって話せばいいと考えるようになりました。」と吉田さんは話す。
障がい者に対する「心の壁」は意識しないと残ったままだ。意識することで取り壊すことができる。だからこそ、まず意識してもらうことが大切だと3人は語った。目標は、身体のバリアフリーだけでなく“心のバリアフリー”を立命館から社会に発信していくことだ。
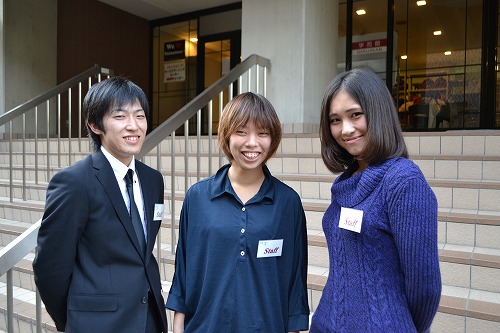
発足の中心となった吉田さんと小出さんは、普段授業で障がい学生をサポートする“障害学生支援室サポートスタッフ”だ。そのサポート活動の中で、「どんなにコミュニケーションを図っても障がい者の気持ちを理解していないのではないか」という悩みをもった。スタッフ同士の交流も少なく、悩みを解決できる場もなかった。そこで団体を立ち上げ、スタッフ同士の交流の場をつくることで障がい者支援を根強いものにしていこうと考えた。サポートを受ける障がい学生の本音を知って活動に生かすため、障がい学生にも参加を呼びかけた。代表の波多野さんは脳性麻痺の障がいのある学生である。
人々に障がい者に対する理解を深めてもらうため、学内では聴覚障がい者のための字幕や視覚障がい者のための音声ガイドを取り入れたバリアフリー映画上映会を開催している。聴覚障がい者のための字幕とは、例えば流れている音楽の解説や、誰がどの台詞を話しているのかがわかるものだ。健常者の学生にも目を閉じた状態での鑑賞を勧め、どう感じるのかを問いかけている。
また、企画主催にあたって、視覚障害の理解を深めるために何も見えない暗闇を体験するドイツ発祥の「ダイアログ・インザ・ダーク」を体験した。「ダイアログ・インザ・ダーク」とは参加者が暗闇の中で、視覚障がい者のサポートのもと食事や会計といったさまざまなシーンを体験する。小出さんは「ダイアログ・インザ・ダーク」を初めて体験したときのことをこう語る。「普段自分がサポートしている方に助けてもらうのが衝撃的でした。暗闇の中では視覚障がい者の方の方がプロフェッショナルなんです。」
学園祭ではゲーム感覚を取り入れた「ブラインドルーム」を講義室の一室に構え、恐怖だけでなく五感に刺激を与える全盲体験企画を開催した。そこでは単に暗闇を歩くだけでなく、大学生活そのものを味わい見えない世界を実感してもらえるよう、さまざまな工夫を施したという。またこうした企画の開催に加え、障がいについての勉強会を団体内で実施している。「まずは自分たちが学び、体験することで、“どうすれば障がい者の方の不安を取り払うことができるのか、障がい者の方が求める支援とは何か”を知ることができます。」と吉田さんは語った。
活動の中では「メンバーのさまざまな想いを一つに束ねることに苦労した。」と波多野さんは語る。例えば、「心の壁って、どんな壁?」「支援するって、どこまでするの?」と、それぞれ感じ方や考え方が異なるからだ。一方で大きな成長もあった。それは彼ら自身の“心のバリアフリー”が実現したこと。「最初は障がい者をなんとなく避けていたこともあったけど、健常者の友だちと何も変わらないと気づくことができました。人が高いところの物を取ろうとするとき台に乗って取るのと同じように、耳の聞こえない人とはメモをとって話せばいいと考えるようになりました。」と吉田さんは話す。
障がい者に対する「心の壁」は意識しないと残ったままだ。意識することで取り壊すことができる。だからこそ、まず意識してもらうことが大切だと3人は語った。目標は、身体のバリアフリーだけでなく“心のバリアフリー”を立命館から社会に発信していくことだ。
(左から)吉田さん・波多野さん・小出さん
MBF.com Facebook
https://ja-jp.facebook.com/ritsmbf
https://ja-jp.facebook.com/ritsmbf






