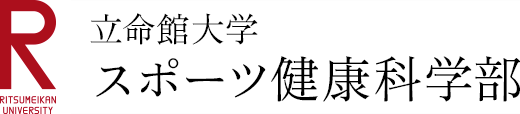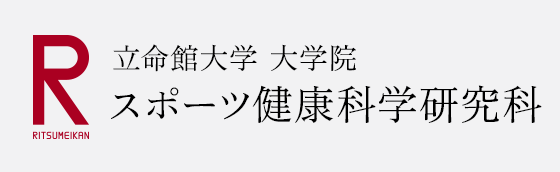2014/06/19 基礎生理学で川崎医療福祉大学 健康体育学科 准教授 矢野博巳先生の「免疫学」の講義がありました。
2014年6月19日3限目:基礎生理学に川崎医療福祉大学 健康体育学科 准教授 矢野博巳先生を外部講師として「免疫学」について授業をして頂きました。免疫系は複雑な調節機構により生体内で機能するが、できるだけわかり易く説明をして頂きました。
授業内容としては、免疫系の主役である白血球の説明があり、好中球、好酸球、好塩基球、単球、NK細胞、マクロファージ、Bリンパ球、Tリンパ球のそれぞれ階級や役割分担について解説しました。例えば、Tリンパ球は他の白血球を操作する司令塔的な役割を担っています。エイズなどはこのTリンパ球に攻撃するため、免疫系が破綻することから、免疫不全となります。
また、運動でも関係することに関しても説明がありました。運動後に起こる筋肉痛には免疫による筋の修復が行われます。しかしながら、壊れた筋細胞だけでは、マクロファージは動かない、ところが、正常な筋と壊れた筋があれば、壊れた筋を察知した正常な筋からマクロファージを呼び寄せています。ただし、この免疫機能はメタボな人の場合、マクロファージの働きは鈍くなります。一方、運動を習慣的に実施している人はマクロファージの動きは非常に優れています。
さらに、「運動をやりすぎると風邪をひきやすくなる」という仮説、「Jカーブモデル」についても説明がありました。その機序には、激運動後に免疫機能が一過性に低下させたことから、「オープンウィンドウ説」が現在では提唱されています。
しかし、実施にはその中で練習をしなければならない場合、どうすればいいのか?練習後の免疫機能の低下をどのくらいケアが必要なのか?それは、実験結果から、運動6時間後くらいまでは免疫機能が低下しているので、感染リスクを低下させるには、運動後6時間までは、コンディショニングをコントロールする必要があります。激運動練習後には、うがいや手洗い、着替えなど、からだや環境を清潔にしておくことがコンディショニングづくりに重要かもしれないなどの説明がありました。
新しい運動と免疫に関する情報も含め、スポーツ健康科学を学ぶ学生にとって有益な情報が盛りだくさんでした。