−デジタル技術 × アート−
多様性を認め合い、共生できる社会へ
最新技術を取り入れた
体験型アートを活用
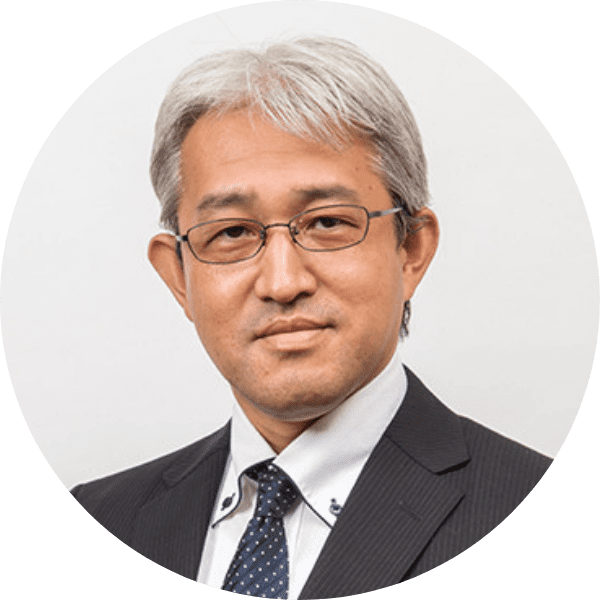
代表研究者:望月 茂徳


-

これ、和太鼓のリズムゲームですよね?
-
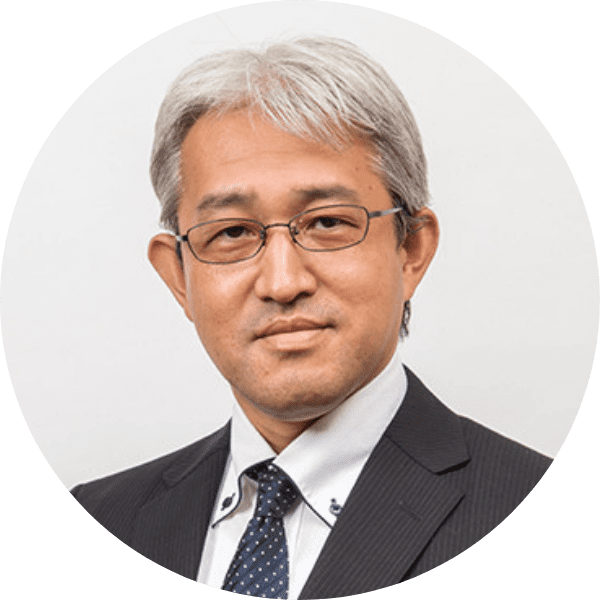
実はこれ、ゲームじゃないんです。私が専門としているのは、アートとして楽しめる体験型の映像作品を作ることで、手足が不自由でほとんど動かせない人も、ばちで太鼓をたたく代わりに、まばたきするだけで遊べるようになっているんですよ。
-

本当だ!太鼓を叩くと花火が上がって、タイミングよくまばたきすると、花火がきれいに開きました!タイミングを合わせるゲームだから、方法はなんでもいいですよね。
-
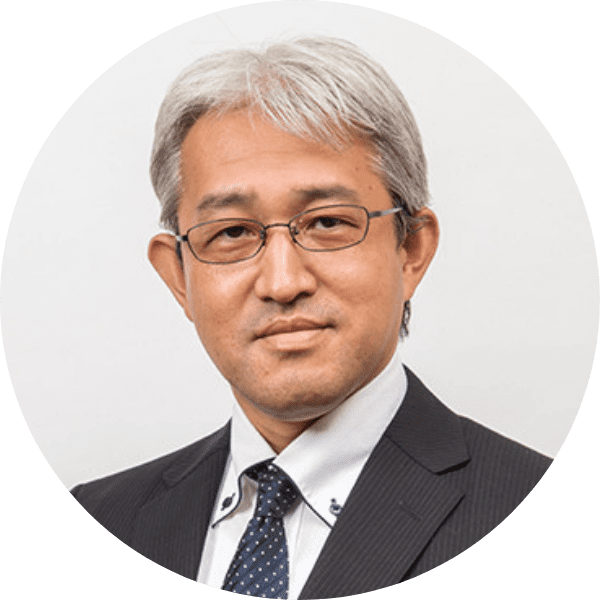
障害がある人もない人も、同じ画面を見ながら一緒に遊べる方がいいと思うんです。これから全員が本気で競い合える体験デザインを追求したり、楽しく遊ぶための新しい機能も搭載したりすることを考えているので、遊んだ後でアイデアを一緒に考えてもらえませんか?

-

もちろんです!ところで、先生はどうしてこのようなゲームを作っているのですか?
-
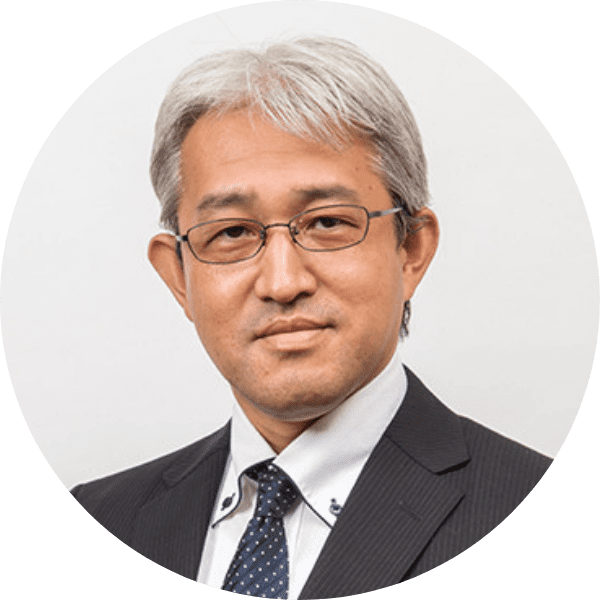
これらのアートが、それを社会課題の解決に活用できたらもっといいなと思うようになって。それで、最新のテクノロジーを取り入れることで、社会課題の解決に活用できる体験型アート作品をたくさん制作するようになりました。学生と一緒に制作した一部の作品を、ここで公開しています。多様な人に体験してもらって正直な感想を聞くフィールドとして、このオープンなラボを活用しているんですよ。
「クリエイティブであること」を社会課題解決の切り口に
少子高齢化にともなう社会のさまざまな変化への対応、多様性を認め合う共生社会の実現など、私たちの社会には多くの課題があります。
「アートを社会課題の解決に活用したい」と考えるのは、映像学部の望月茂徳先生です。映像を投影した空間の中で、人の動きに連動して映像が変化したり、音が鳴ったりする体験型メディアアートのアーティスト・研究者ですが、エンターテインメントとしての作品だけでなく、さまざまな社会課題の解決をテーマとした作品も多数制作してきました。


その一つが、アレルギーの子どもに治療の大切さや方法を楽しく理解してもらうための作品です。ぬいぐるみに映像を投影し、アレルギーの原因に対して治療薬を投与すると、体の中で変化が起こる様子がわかりやすく表現されます。「高齢化や人口減により医療機関はひっ迫していて、看護師が子ども目線で説明をする余裕がありません。アートの力を使い、楽しく理解してもらうことによって、医療をサポートし、未来を担う子どもをケアできないかと思ったんです」。
このラボでなら、訪れる子どもに体験してもらうことができます。最初は難しいとそっぽを向かれることもあったそうですが、少しずつ内容や表現を変えていくことで、反応が変わっていきました。「多くの人にフィードバックをもらい、医療従事者の方からも意見をうかがえたことで、どんなポイントをおさえるべきか、アートを使うメリットはどこにあるのかを探ることができました」。
多様性を認め合う共生社会の実現も、望月先生の目標の一つです。そこで開発したのが、誰もが楽しめる太鼓のメディアアートでした。「障害がある人が社会にバリアを感じるのは、障害のためではなく、社会の側が作っているバリアのためだと思うんです。そこに穴をあけるには、障害がある人とない人が、小さい頃から一緒に楽しい経験を積み重ねることが大切なのではないかなと思います」。
「やらなければ!」ではなく、みんなを楽しく巻き込みながら、気づきを得る。メディアアートにはそんな力があると先生は考えています。
いばらき×立命館DAYでの様子
-
voice 01
参加者の声
太鼓のゲームが楽しかったです。普通に叩くだけじゃなくて、まばたきでタイミングを合わせるのが大変だったけど、タイムラグもなかったので、手が動かせない人とでも一緒に楽しめると思います。
-
voice 02
学生の声
想定以上の数の方が楽しんでくださっている姿を間近で見ることができて、私たちもすごく嬉しく思いました。ゴミ分別の展示では、私たちは知識で分別するものだと考えていたのですが、子どもたちは、質感で判断したり、コンコンと叩いてみたり、裏面の表示を自分で確認したりして楽しそうに分別していたことが印象に残っています。
先生からひとこと
-
 研究者データベース
研究者データベース望月 茂徳
映像学部 教授
専門分野:インタラクティブ・メディア メディアアート
関連リンク
- Home
- SP LAB / SP LAB X
- 多様性を認め合い、共生できる社会へ 最新技術を取り入れた体験型アートを活用




多分社会をより良くするための切り口には、さまざまなものがあると思います。「早くなる」「便利になる」などもそうでしょう。私は「クリエイティブである」も、ひとつの切り口だと思っています。このラボに来て、新しいアートを体験することによって、そのことを知ってもらったり、一緒に考えてもらったりするきっかけになるといいなと思いますし、それが、このラボに来ていただくことの一番の価値でもあると思います。
これまでとは違う考え方、違う視点を持てるようになる、それが、課題を解決するためにもとても大切なのではないでしょうか。