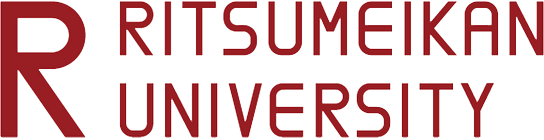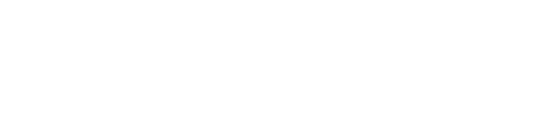井登 友一 Yuichi Inobori
教授
■ 専門分野:デザインとイノベーション ■ 研究テーマ: ・サービスデザインによるイノベーションの研究 ・エステティクス(美学=感性論)と創造性に関する研究
- 1995年3月 同志社大学文学部社会学科新聞学専攻 卒業 学士(文学)
- 2023年3月 京都大学経営管理大学院博士後期課程 修了 博士(経営科学)
- 2011年5月〜現在 株式会社インフォバーン 取締役副社長/デザイン・ストラテジスト
- 2015年4月〜2022年 京都女子大学 家政学研究科 非常勤講師
- 2018年4月〜現在 同志社女子大学 学芸学部 メディア創造学科 嘱託講師
- 2023年4月〜2025年3月 立命館大学 経営学部 授業担当講師
- 2025年4月~現在 立命館大学 経営学部 教授
これまでの実績・研究概要
新しい価値(イノベーション)を生みだすデザインについて研究しています。「デザイン」と聞くと、皆さんの多くは工業製品やスマホアプリなどの色や形などの見た目を美しく、カッコよくすることを思い浮かべるのではないでしょうか。それらのことはデザインの重要な役割ですが、わたしが研究しているデザインは「目には見えない体験」や「触れることができない経験や感情」のようなものを主に対象にしています。人びとにとっての良い体験を実現し、これまでには存在しなかったような新しい価値=意味を生みだせるような製品・サービスやビジネスをつくる原動力となるようなデザインのあり方と方法論を「サービスデザイン」と呼びます。わたしは、様々な人びとや企業がこの「サービスデザイン」を活用することで、新しい価値づくりを実践するための理論や方法論の開発に取り組んでいます。
研究の方向性
現代の産業領域におけるデザインでは、ユーザーのニーズを満たし、問題を解決することで快適な体験を実現してくれる製品やサービスを考える「人間中心デザイン」、「ユーザー中心デザイン」が当たり前のように前提とされています。もちろん、これらの考え方はデザインする上で当然欠かせない重要な概念ですが、果たしてユーザーのニーズに応え、ユーザーが抱える問題を解決してさえいれば、人々がわざわざ選んでくれ、これまでになかった経験や喜びに夢中になってくれるような製品やサービスをつくることができるのでしょうか?私の研究では、エンドユーザーだけでなく多様な関与者を対象として捉え、それらの関与者と製品やサービスを取り巻く関係性をデザインするサービスデザインの方法論を用いて、現時点で当たり前のものとして正当化されている製品やサービスの「意味の体制」を問い直し解体することで、「未来の当たり前」になり得る新しい意味を再構築するデザイン活動に取り組みます。
メッセージ
今の世の中では、「答えがはっきりしていてわかりやすいもの」や「すぐに役に立つこと」が好まれます。なぜなら「コスパ」や「タイパ」がいいからです。もちろん、それらは人間が賢く効率よく社会生活を送る上で大切なことではありますが、簡単に理解できることや、すぐに手に入れられるスキルはコスパやタイパはいいけれども、賞味期限が短いものでもあります。すぐには答えが出ないような曖昧な問いや、そもそも決まった正解すらないようなことを一生懸命考え、自分なりの考えをひねり出すことは悶々としてスッキリしないし、しんどいことかもしれません。けれども、そのような経験を積み重ねることは、思考力や構想力を鍛える何よりのトレーニングになります。社会に飛び込む前の大学で過ごす4年間は、一見コスパが悪いように見えたり、ムダや無意味に思えたりするようなことに対して、疑問や好奇心をフルに発動させて没頭できる貴重な時間です。ぜひ私たちと一緒に色々なことを探索しましょう。