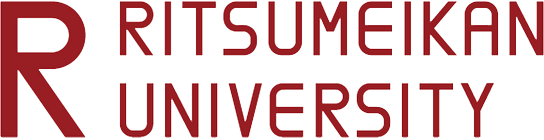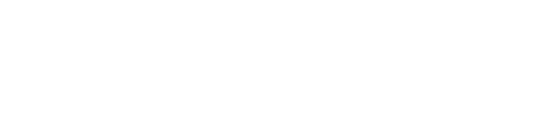デザインとアートを統合し、美的感性を育む
──まず新学部/新研究科のコンセプトについて教えてください。
八重樫:立命館大学デザイン・アート学部/デザイン・アート学研究科のコンセプトを一言で言えば、「美的感性」を育てるということです。この言葉に込めているのは、デザインやアートといった営みに深くかかわることでしか得られない美的感性を磨いていこうという意志です。ここを巣立った学生がそれぞれの場所で美的感性を発揮していくことで、その感性に根ざした価値判断やマインドセットが社会へ少しずつ波及していく。新学部/新研究科は、そうした拠点となることを目指しています。
──そのようなコンセプトが求められる背景を教えてください。
八重樫:近年では、技術開発やイノベーション創出をはじめ、企業の経営やまちづくり、環境問題など、さまざまな分野でデザイン思考やアート思考の重要性が叫ばれるようになっています。私は企業の戦略にデザインを導入していく「デザインマネジメント」を専門にしていますが、この領域に注目する人も増えました。デザインもアートも従来のデザイナーやアーティストのものだけではなくなり、ビジネスにかかわるひと全般や社会一般に「民主化」しつつあるのです。
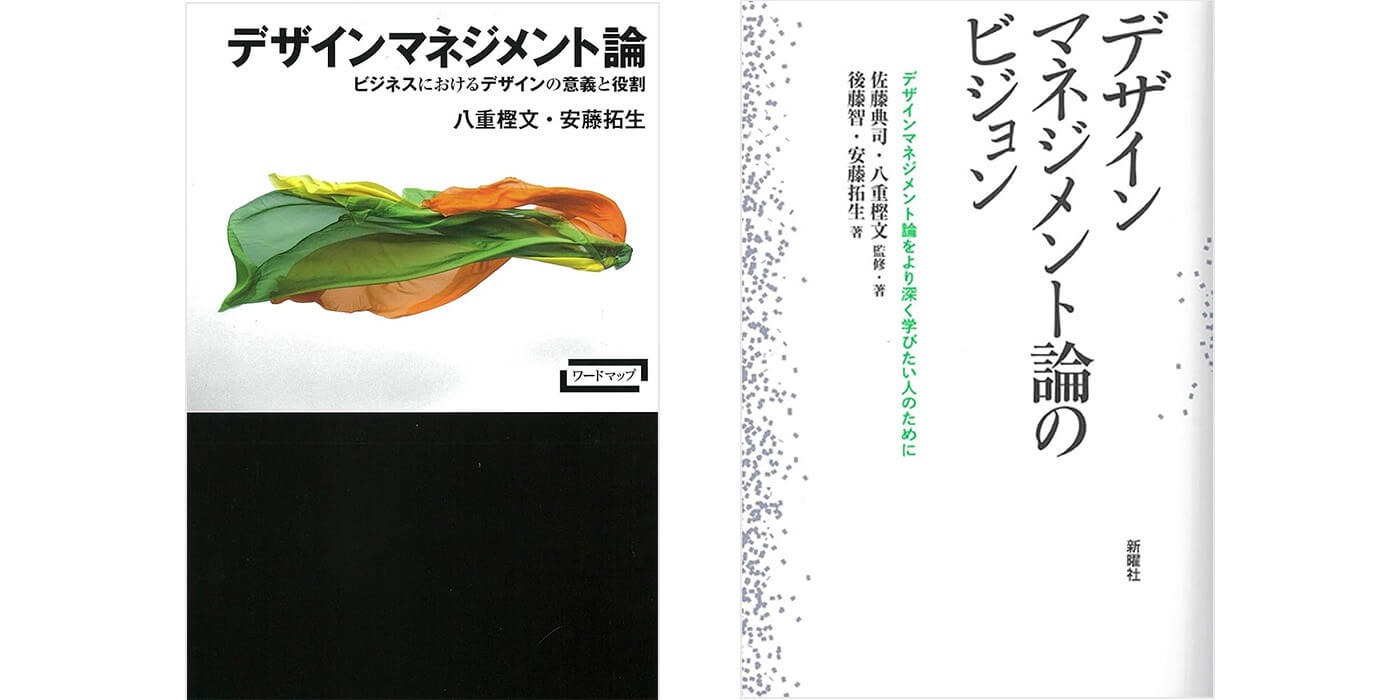
(左)八重樫文、安藤拓生『ワードマップ・デザインマネジメント論──ビジネスにおけるデザインの意義と役割』(新曜社、2019年)
(右)佐藤典司・八重樫文監修・著、後藤智・安藤拓生著『デザインマネジメント論のビジョン──デザインマネジメント論をより深く学びたい人のために』(新曜社、2022年)
デザインやアートに関心をもつ人が増えたのはよいことですが、その一方で、デザインのもつ価値として、問題解決の側面にばかり注目が集まっていると感じています。本来、デザインやアートがもつ価値には、個性にもとづくユニークなビジョンを提案することや社会に課題を投げかけること、創造的思考、他者との共創など、さまざまなものがあります。豊かな生活世界を創出していくためには、そうした価値を育む必要がある。そのために、美的感性というコンセプトが必要だと考えたのです。
──美的感性を中心に据えることで、どのような学問が展開されるのでしょうか。
八重樫:美的感性というコンセプトを基盤とすることで、これまでバラバラに議論されてきたデザインとアートを統合的に扱う新しいデザイン学を立ち上げられるのではないかと考えています。そうした統合的な視点を採用すると、既存の学問分野も少しずつ再構成されていくはずです。たとえば、情報学と人文学の新たな融合によって、情報人文美学のような学問が生まれるかもしれません。あるいは、デジタル環境にかんする学問と文化人類学の統合によって、デジタル文化人類美学のような領域が構想できるかもしれません。新たなデザイン学は、こうして新領域を含み込んで徐々にかたちづくられていきます。ただいろいろな領域を集めるのではなく、それらを統合・融合させるような学問の創出を目指しているというわけです。
プロジェクト中心の学びで、プロセスを直接経験する
──そうした新しい学問に挑戦するうえで、美的感性が求められるわけですよね。では、そんな美的感性を育てるためには、どのような学びが必要なのでしょうか。
八重樫:これまで哲学や美学といった学問では、美的感性を身につけるために必要な条件が議論されてきました。そこで言われていることは、「直接経験」の重要性です。具体的に言えば、ものづくりや表現のプロセスのなかに自ら参加し、それを直接的に経験するということです。
このような知見を踏まえて、新学部/新研究科では、多くの「プロジェクト」に参加することを通じて、学生がデザインやアートのプロセスを実際に経験しながら学べる体制を整えました。学内だけではなく、外部の企業や自治体とコラボレーションする機会も豊富です。
キャンパスのある京都という土地柄を活かして、伝統的な産業や文化のなかで新しいデザインやアートに挑戦することもできます。たとえば、立命館大学アート・リサーチセンターとの共同プロジェクトを予定しています。アート・リサーチセンターですでにおこなわれている活動として、京都の浮世絵や友禅などの伝統文化・工芸をもとにしたデジタルデータの制作と分析をはじめ、祇園祭をまるごとヴァーチャルな空間に移し替えて空間の位置情報や3Dデータを残すといったものがあります。新学部/新研究科で挑戦してみたいのは、こうしたアーカイブの対象をもっと拡げることです。過去のものを残すだけではなく、現在の取り組みや経験、これから起こる事象までを含めて未来に残し、伝え、継承することができると考えています。
ここには人文科学のデジタルアーカイブ論も、空間をアーカイブする先端的な技術開発も関わるでしょう。新学部/新研究科が目指すデザイン学のもとでは、そうしたさまざまな領域から知見を活用しながら、実際の都市を舞台にした研究プロジェクトが展開できると考えています。
さらに、京都の文化的な資源を別の場所へと展開するような連携のあり方も考えられます。本学は海外も含めさまざまな教育機関と連携してきた実績がありますから、国内外の大学とともに学んだり、共同研究したりといった活動を進めていきたいですね。

──そうしたプロジェクトで必要となるスキルや知識は、どのように学んでいくのでしょうか。
八重樫:さまざまなプロジェクトで必要なスキルや知識を得るために、分野横断的に履修できるカリキュラムを構成しました。デザインとアートを別け隔てなく学ぶことができる環境はなかなかないと思います。もちろん、いろいろな科目を闇雲に選んで、つまみ食いするのでは意味がありません。プロジェクトを発展させることを目指して、既存の常識にとらわれずに科目を履修し、新しい学問領域を創出するようなチャレンジを期待したいと思います。
たとえば、コミュニティを活性化するプロジェクトであれば、公民館や寄り合いといったリアルの場にかかわるコミュニティデザインや空間デザインの知見が必要になるかもしれません。それらにくわえて、情報化が当たり前になった現代のコミュニティにおいては、SNSやチャットなどのコミュニケーションサービスを設計したり、そのインターフェースをデザインしたりといたスキルも求められるかもしれません。そうした領域を超えた学びの先には、実空間とメタバース空間を横断するような新しい学問の誕生も期待できます。
「まだデザイナーがデザインしていないものをデザインする」
──八重樫教授ご自身のことも伺ってみたいと思います。デザインやアートにかんする新しい学問を生み出したいという情熱は、どのように芽生えたのでしょうか。
八重樫:私は小さい頃から、みんなと違うことをやろうと考えてきました。ところが、美術大学のデザイン科に入ったら、みんなが私と同じように「人と違うこと」を目指していたんです(笑)。最初は戸惑いましたが、自分はデザイナーがまだデザインしていないものをデザインしようと決意を新たにしました。
では、デザインという領域において、どうしたら本当に誰もやっていないことができるのでしょうか。そこで出会ったのが、師匠の向井周太郎先生です。向井先生は、デザインという行為そのものをデザインするという考え方を打ち出していました。この考え方には大きな影響を受けましたね。それ以来、デザインの本質を考えさせられるような、新しい領域のデザインに取り組むようになりました。
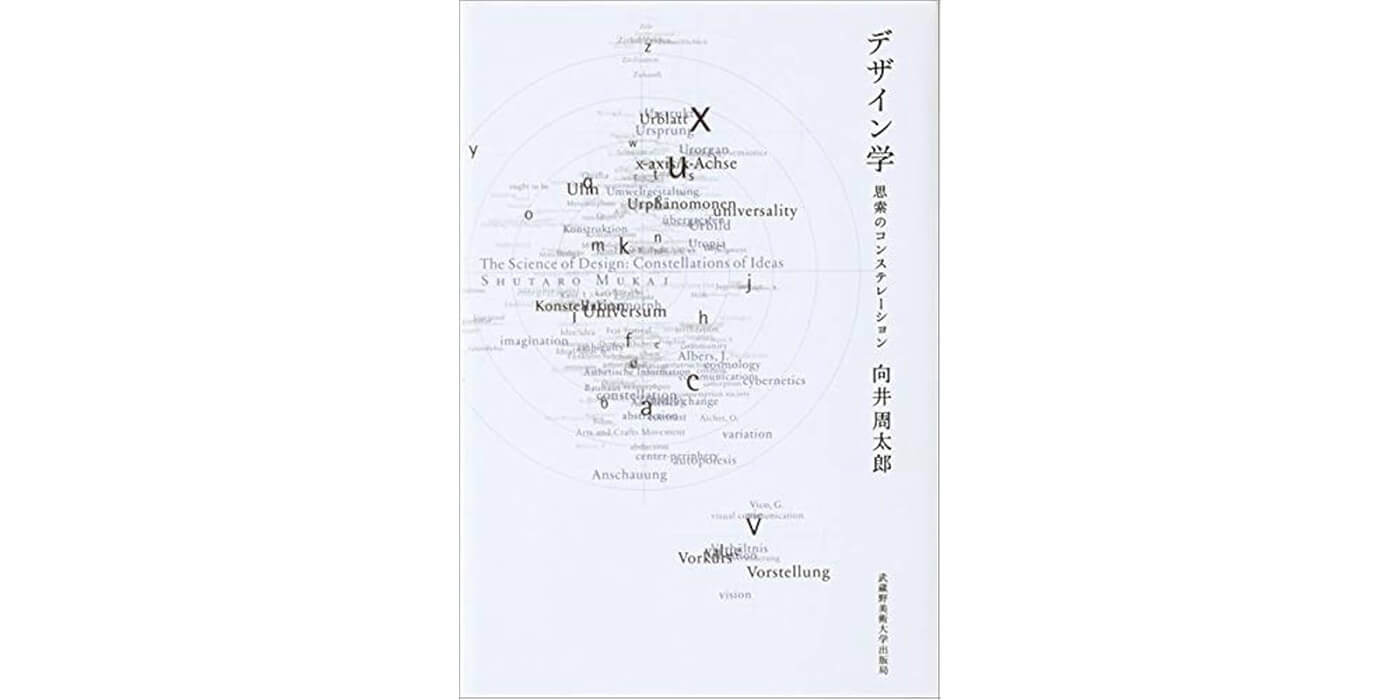
向井周太郎『デザイン学──思索のコンステレーション』(武蔵野美術大学出版局、2009年)
たとえば、情報教育です。2000年代初頭に、高校で情報の科目が必修になりました。しかし、当時の情報教育にはデザインの知見がほとんどなかったんです。ウェブページを作成する授業であっても、プログラミングのことばかりで、デザインのことはほとんど考えられていない。そこでデザインと情報教育をつなげる研究をしたり、教材開発をしたりといった仕事をしました。
──先ほどお話してくださったデザインマネジメントにかんする研究も、新しい領域のデザインということになるのでしょうか。
八重樫:そうですね。私が研究を始めたとき、この領域ではユーザー中心デザインという潮流が盛り上がっていました。その名の通り、デザインの中心にはユーザーがいる、ユーザーをよく観察し、問題を見出して解決しようというものです。
そのなかで興味深いと思ったのが、イタリアのロベルト・ベルガンティ教授の研究でした。ベルガンティは、こうした潮流とは正反対の考え方を打ち出していたからです。彼はユーザーを観察しその課題を解決するのではなく、これまでユーザーが気づいていない新しい意味や目的を与えるデザインが必要だと主張していました。言ってしまえば、「ユーザーを見るな」と言っていたのです。ベルガンティの考え方は、まさに新しいデザイン行為をデザインするものだと思いました。それで彼の著書を翻訳する仕事をしたんです。
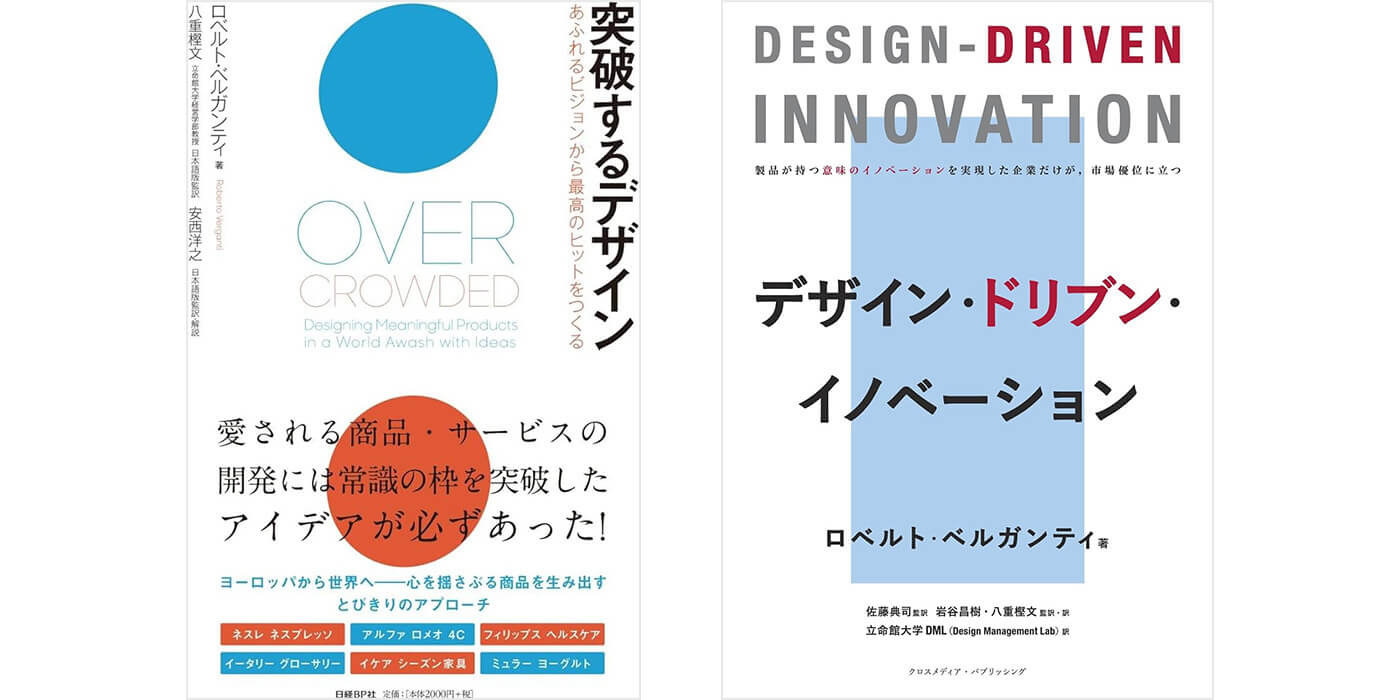
(左)ロベルト・ベルガンティ『突破するデザイン──あふれるビジョンから最高のヒットをつくる』八重樫文・安西洋之監訳、立命館大学経営学部DML訳(日経BP、2017年)
(右)ロベルト・ベルガンティ『デザイン・ドリブン・イノベーション──製品が持つ意味のイノベーションを実現した企業だけが、市場優位に立つ』佐藤典司監訳、岩谷昌樹・八重樫文監訳・訳、立命館大学経営学部DML訳(クロスメディア・パブリッシング、2016年)
世界を直接経験するための挑戦の場
──八重樫教授自身がチャレンジを続けてきたのですね。では、これから学生が新しい領域に挑戦していくために、新学部/新研究科ではどのような学習環境を用意しているか、改めて語っていただけますか。
八重樫:新学部/新研究科では、京都というまち全体をひとつのキャンパスに見立てています。地元の企業のオフィスやスタジオで共同プロジェクトを実施したり、京都にあるインキュベーション施設やファブラボで活動したり、大学から飛び出しさまざまな場所で学ぶというイメージです。学生や教員にとっても、企業や自治体の方々にとっても、京都全体が挑戦の場になるようにしていきたいと思います。まったく新しい産学連携や地域連携のあり方を模索したいですね。
デザインの実務やソフトウェアの使い方など、スキルや知識にかんする科目については、オンライン化・オンデマンド化を思い切って進めます。オンラインといっても、一方的に映像を見て学ぶだけではなく、バーチャルキャンパス上で双方向の学びができる環境をつくっていきます。
──最後に、新学部/新研究科を志す学生に期待することを教えてください。
八重樫:新学部/新研究科では、「まだ世の中には存在していないけれども、これは自分にしかできないはずだ」という強い思いをもった学生を求めたいと思います。キャリアという意味でも、すでにある「◯◯デザイナー」や「◯◯の専門家」を目指すだけではなく、領域を超えた新しいデザイナー像やアーティスト像を生み出すことを目標にしてほしいと思います。
そうした将来像の実現に向けて、新学部/新研究科においてはキャリア形成の支援も充実させていきます。総合大学としての本学には、進路指導を続けてきたノウハウと卒業生ネットワークの蓄積が豊富にあります。卒業後の進路を不安に思うことなく、充実した大学生活を過ごしてほしいですね。
新しい領域にチャレンジするのは、学生だけではありません。私も含めて教員陣も、誰でも想像できるような研究や実践ではなく、未知なる課題に挑戦します。もちろん、こうした挑戦はすぐにうまくいくものではありません。新しいものを生み出すためには、失敗を重ねる必要があるからです。大いに挑戦し、心ゆくまで失敗しましょう。そのための場所を用意したつもりです。社会に対して積極的に新たな挑戦をしたい学生を歓迎します。

学校法人立命館 総合企画室 室長/立命館大学 デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会 副委員長/立命館大学 経営学部 教授/立命館大学DML(Design Management Lab)チーフ・プロデューサー
1973年北海道江別市生まれ。武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業、東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。デザイン事務所勤務、武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科助手、福山大学人間文化学部人間文化学科メディアコミュニケーションコース専任講師、立命館大学文理総合環境・デザイン・インスティテュート准教授、同経営学部准教授を経て、2014年より同教授。2015、2019年度ミラノ工科大学訪問研究員。専門はデザイン学、デザインマネジメント論。
https://dml-ritsumei.jp/