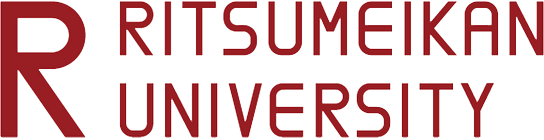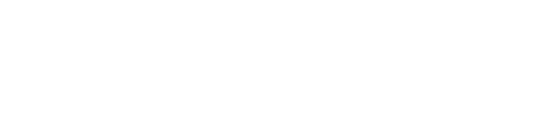なぜ美意識が注目されているのか
八重樫: 近年、世界のビジネスや経営の領域では、人間の感性や直感、哲学などを経営判断に取り入れる動きが加速しています。特に、日本でも「美意識」の重要性が注目されるようになり、そのきっかけのひとつとなったのが山口さんが2017年に出版された『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』でした。

──まず山口さんにお伺いします。この本が出版された当時の状況についてお聞かせください。
山口:
2017年にこの本を出した頃のビジネス書市場は「効率化」「ハック」「ロジカルシンキング」などが主流で、私の「美意識」というテーマはかなり突飛に思われていました。「売れないだろう」という声も多く、出版後半年ほどはほとんど反響がありませんでした。しかし、ある時期を境に、ビームス代表の設楽洋さんをはじめ、デザインやファッション関係の方々がSNSで紹介してくださり、これが転機となりました。そこから、デザインやアート関係者に共感をいただき、経営者層からも「経営の舵取りに美意識や直感を活かしてもいいんだ」と勇気づけられたという反応が広がったのです。
私はもともと戦略コンサルタントの経験を持っていました。そのため著述活動を始める際に、ビジネス書の書き手だと認められるまでの市場参入の戦略を考えました。まず外資系コンサルの知見をまとめた一般向けの本を出し、その次のステップで「美意識」という、より挑戦的なテーマに踏み込もうと考えたのです。これを私は、ビートルズのリリース戦略になぞらえて理解しています。彼らは初めは『プリーズ・プリーズ・ミー』のような親しみやすい作品を世に問い、徐々に『リボルバー』という実験的な作品へと進化しました。つまり私にとって、『美意識』本はまさに『リボルバー』に当たるものでした。
──当時の学術界やデザイン業界ではどのような議論がありましたか?
八重樫:
デザインやアートの世界では、「美意識」の重要性は自明のことすぎて、「美意識とは何か」を明確に説明する言葉や枠組みはあえて問われてきませんでした。だから、デザインやアートの外に対して美意識というものをよく説明できなかった。そこに山口さんが「意味」という概念を媒介にして説明を与えたことが、重要な転換点となったと思います。
私自身も2010年代から「意味のイノベーション」にかんする翻訳を手がけ、ロベルト・ベルガンティ『デザイン・ドリブン・イノベーション』などにかんして国内で議論を進めていました。その頃、特にデザインの領域では「私たちは何をデザインしているのか?」という問いが重要になっていました。かつてのデザインは「機能」が対象でしたが、徐々に「機能ではなく意味をデザインする」という視点に移っていきました。つまり、デザインやアートの本質とは、対象の持つ「意味」を問い直したり、再定義することではないかという議論が起きていました。学術界もデザイン業界もそうした理解が進んでいくなか、山口さんの美意識の議論が「意味」概念によって説明されていたことで、ビジネスの世界も含めて多くの人が腑に落ちるようになったのだと思います。
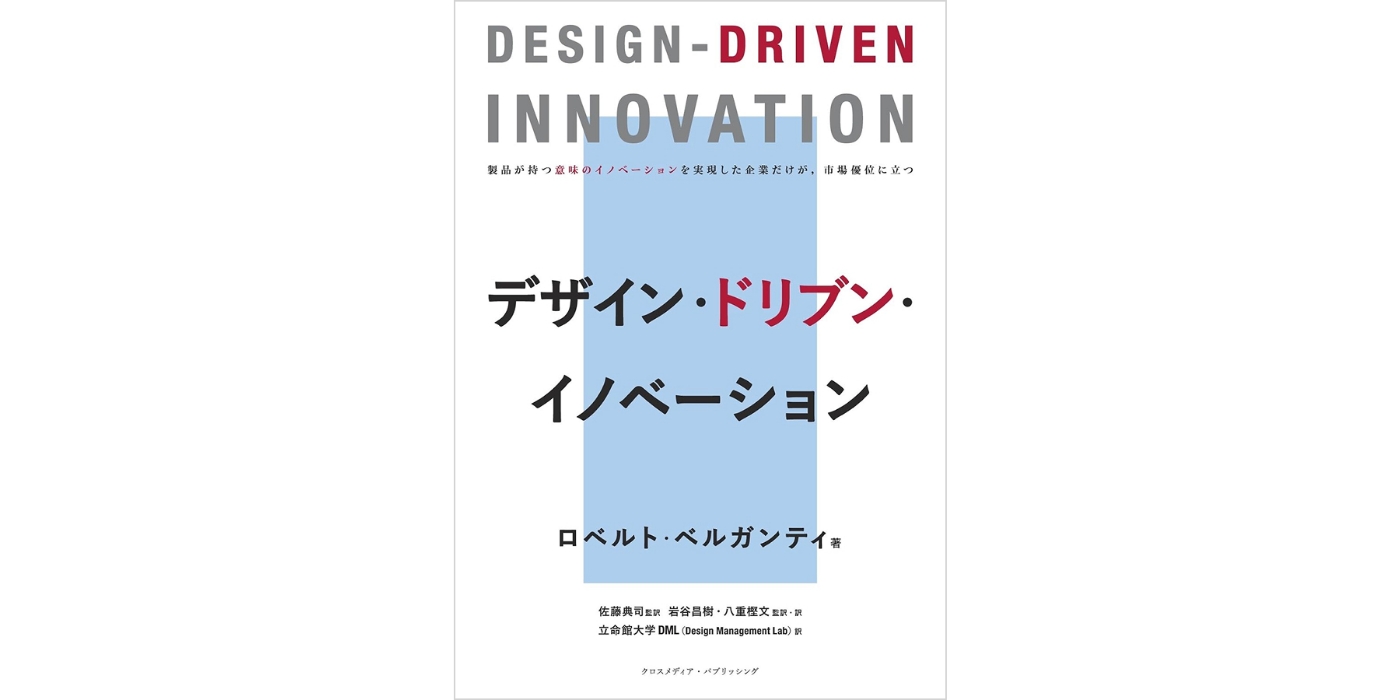
──製品が持つ意味のイノベーションを実現した企業だけが、市場優位に立つ』
佐藤典司監訳、岩谷昌樹・八重樫文監訳・訳、立命館大学経営学部DML訳
(クロスメディア・パブリッシング、2016年)
山口:
単なる見た目のデザインは容易にコピー可能ですが、「意味」や「ストーリー」が伴った企業価値は模倣が困難ですよね。つまり、企業の哲学や倫理観がブランディングの核となります。
たとえば、Googleが以前掲げていた「Don't be evil(邪悪になるな)」という理念のように、短期的な利益を犠牲にしても倫理を守る企業のほうが、長期的には成長を遂げます。もうひとつ象徴的な存在がAppleだと言えます。スティーブ・ジョブズは市場調査やロジックよりも、自らの哲学や直感を製品に反映する経営をおこない、競争優位性を生み出しました。ジョブズの経営には禅的な美意識があり、これは単なる外見の美しさを超えて企業の根本的な価値観や競争優位性につながっていました。2007年のiPhone登場時、日本の携帯電話業界は市場調査やマーケティングを重視していましたが、それだけでは競争力を維持できず、国内シェアは大きく低下しました。このように、デザイン面だけではなく倫理面を含めた「トータルな美意識」が、現代の経営において中心的な価値となっているのだと思います。
美意識を喪失した日本
──ビジネスの世界では、人文的な意味での教養や感性にくわえて、クリエイティビティや美意識の重要性が徐々に浸透してきたように思います。いっぽうで、日本ではなぜこれまで美意識が軽視されてきたのでしょうか?
山口:日本は近代化の過程で効率性や合理性を追求するあまり、海外から入ってくるものへの憧れが強くなり、自分たちがもともと持っていた美意識の価値を見失ってしまったのだと思います。明治以降の「殖産興業と富国強兵」という目標のもとでは、美意識を育む余裕がありませんでした。特に第二次世界大戦後の復興期には、最低限の生活インフラ整備が最優先となりました。住宅や都市デザインも簡素化・無機質化していきました。美意識が実感しにくい環境が世代を超えて連鎖してしまったと感じます。
戦後も同様の流れがあります。1950年前後の東京では、「文化都市」を目指して本郷から上野にかけて学問や芸術のエリアを作るという構想が当初はありました。しかし1964年の東京オリンピック開催を機に、都市景観の美しさよりも機能性が優先され、一級河川の埋め立てや高速道路建設が優先されます。このように、日本は美意識を二の次にする文化に変わってしまったのです。
八重樫: 私は以前イタリアに暮らしていましたが、日本と比較して非常に強く感じたのが、イタリアでは「物を直して使う」という習慣が生活に深く根付いていることでした。街を歩けば、あちこちで人々が建物や家具を修理し、壁を塗り直す光景を目にします。日本では新しい物を手に入れることが重視されますが、イタリアでは長く使い続けること自体が美意識の表れとして日常化しているのです。こうした違いは、単に個人の価値観ではなく社会全体の文化的背景に影響されていると思います。
山口: ヨーロッパにおける日常的な美意識の存在は、私も強く感じます。イタリアも日本と同じ敗戦国ですね。しかし戦後復興の際にイタリアで重視されたのは「まず家具を作る」ことでした。日本人の感覚ではインフラや道路整備が先だと思うかもしれません。しかしイタリアでは「美しいインテリアに囲まれて暮らすこと」が幸福の基盤と考えられ、利便性や効率性よりも美的な感覚が優先されました。ドイツのベルリンでも、戦後復興のために建設された集合住宅群、「ヴァイセ・シュタット」や「ズィードルング・シラーパーク」が近年世界遺産に登録されました。これらの住宅群には、ただ住宅を供給するだけでなく、美意識を重視し、長期的に価値のある都市空間を目指す思想が明確にありました。日本が「戦後だから仕方ない」と美意識を後回しにしたこととは大きく異なる価値観が息づいているのだと感じます。

Mo Photography Berlin/Shutterstock.com
美的感性から教育全体を再構築する──クリエイティブ・トランスフォーメーション
──ここまでの議論で、日本が美意識を失った歴史的背景が明らかになりました。ここで、八重樫先生にお伺いしたいと思います。美意識を取り戻すためには、どのような教育が必要でしょうか?
八重樫:
まず必要なのは、「クリエイティブ・トランスフォーメーション(CX)」とでも呼ぶべき大きな変革です。それは単に教育カリキュラムを改善するだけではなく、学部の構造や教育理念そのものを再構築することを意味します。従来のように美意識や創造性を特定の専門分野に限定するのではなく、あらゆる分野に美意識を組み込み、教育全体を根本的に見直す必要があります。
大切なのは、「クリエイティビティを教える」のではなく、「クリエイティビティを活用して学ぶ」という発想の転換です。つまり、知識を一方的に受け取る受動的な授業ではなく、学生自身がみずから創造的に問いを立て、能動的に探究していくプロセスを提供したいと思います。現在、本学では180人規模の学部を想定しています。本学での学部規模としては比較的小さいものの、それでも学年ごとに180人が同じ環境で学ぶ場となります。しかし、単に同じ知識を共有するだけではなく、その学び方自体を変えていくことが、この学部の大きな挑戦になるのではないかと考えています。さらに、この変革は大学教育だけでなく、小中高の一貫教育にまで広げていく必要を感じています。
山口: ある種のルネサンス人のようなかたちで、さまざまな専門知識を横断しながらクリエイティブに問題と向き合う人材が輩出されるイメージですよね。何らかの専門家を3名集めてプロジェクトをやるよりも、それぞれの専門性を橋渡しできる教養人が混じっているプロジェクトのほうがうまくいく、というような話かなと思います。
八重樫: おっしゃるとおり、リベラルアーツや教養の一環でアートやデザインを捉えていき、社会全体で美意識や創造性を評価できる土壌をつくることが重要だと考えています。というのも、どれほど優れたデザインやアイデアが生まれても、それを評価する立場の人々が美意識の価値を理解していなければ、社会には浸透しないからです。何を評価基準とし、何を大切にするのか、評価する側の意識を育てることも教育の役割です。私自身、デザイン教育や実務の現場で、評価者の美意識に疑問を感じるという経験を何度もしてきました。美しいものが社会に浸透するためには、評価者もまた、自分自身の感性を信じる力を養わなければなりません。
自らの美的感性に自信を
──山口さんにお伺いします。新たなクリエイティブ教育を受けた人々が、ビジネスにおいて果たすべき役割とはどのようなものでしょうか?
山口:
美意識に基づくリーダーシップの発揮ではないでしょうか。リーダーシップとは、単なる論理的思考を超えた「意思決定の力」です。すべてを論理で判断できるなら、そもそも人間のリーダーは不要です。いまの時代、AIにデータを入力すれば、もっとも合理的な結論を導くことができるでしょう。しかし現実には、データが不十分だったり、論理だけでは判断できない局面に直面したりすることが多い。そのようなときにこそ、直感をもって方向性を示せるリーダーが必要になります。
私は以前、アメリカのコンサルティング会社で、リーダーの資質を評価する「リーダーシップ・アセスメント」に携わりました。概して、リーダーにはさまざまな能力が求められます。なかでももっとも育成が難しいのが「コンフィデンス(自信)」だと言われています。論理的思考や分析的なスキルは訓練で比較的すぐに身につきますが、「自信を持って決断する力」を養うには長い時間が必要です。若い段階から、みずからの感性を信じ、迷わずにビジョンを示す力を育てていくことが重要です。
そして、こうした「コンフィデンス」を持つリーダーとなるには優れた美意識を備えている必要があります。たとえば芸術やデザインの世界では「正解」という概念はありません。「モーツァルトとマーラーのどちらが優れているか」という議論に意味がないように、人の心を動かす価値に唯一の正解は存在しません。大切なのは「自分はこれを美しいと思う」という感性を信じることであり、それを貫く自信を持つことです。異なる美意識の多様性を受け入れつつ、自分の美意識を確固とした軸に据えることができれば、それは揺るぎないリーダーシップの基盤となります。ですから、八重樫先生がおっしゃったクリエイティブ・トランスフォーメーションというのは、じつはリーダーシップ教育の本質にかかわるものを含んでいると思います。
八重樫: やや抽象的になりますが、確固たる自己が確立している場合、解決すべき問題をみずから設定することができるようになるのだと考えています。ところで、山口さんの最近の著書『クリティカル・ビジネス・パラダイム』では、指導的な企業の役割として「問題の生成」が挙げられていますよね。電気自動車を生産するTeslaは、化石燃料に依存する文明という問題を生成し、それに取り組んでいるわけです。このように、「この私」が社会や世界をどのように見るのかという視座があったうえで、ライフプロジェクトとして取り組むべき課題を自分で設定する──そのようなことができる人たちを育てる必要があると感じています。
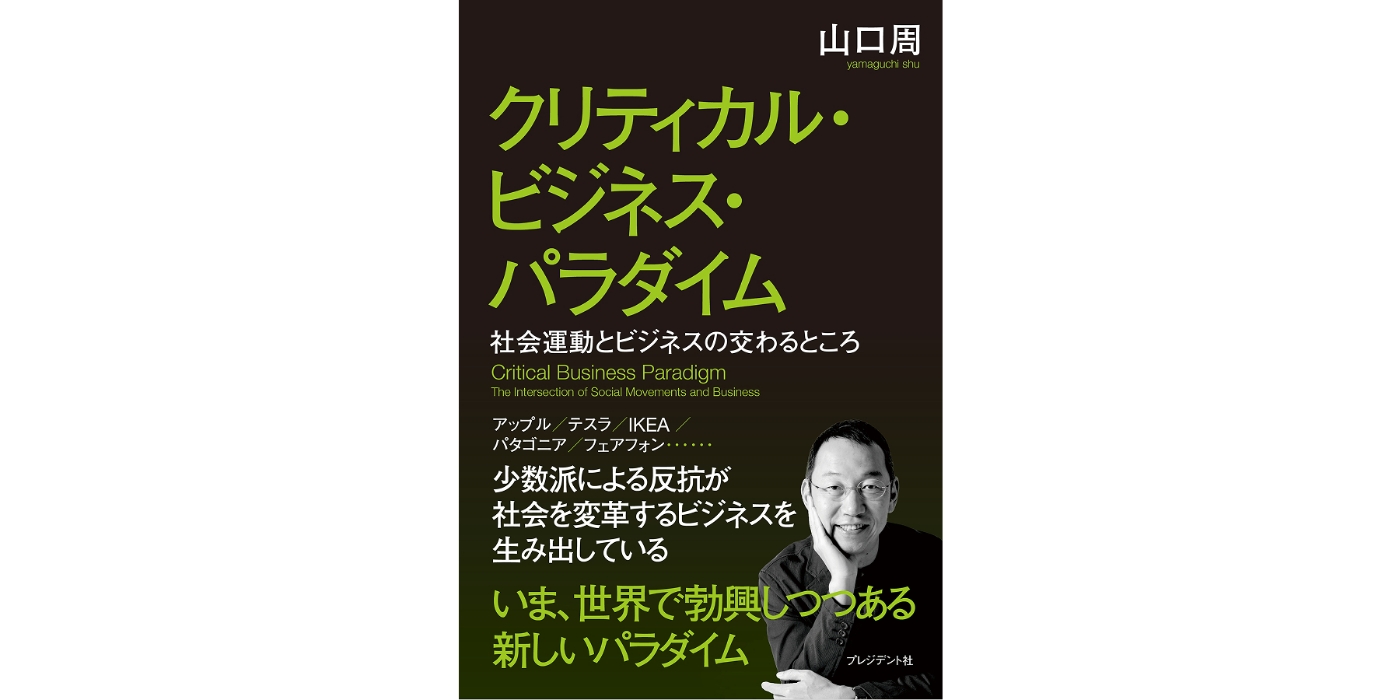
山口: まさに自分の感性を信じることの重要性が問われてきます。これにかんして、イタリアの職人の話を聞いたことがあります。50年間同じ工場で眼鏡の加工をしている職人が、「これはかっこ悪いから作りたくない」と言ってデザイナーが描いた図面を拒否することがあるそうです。いっぽう日本では、美意識に対する「正解探し」が蔓延しており、「自分が良いと思うものを貫く」力が弱いように感じます。みずからの感性を育む教育は求められていると言えるでしょう。
京都から日本の美意識を再構築する
──これまでの議論では、美意識がビジネスや社会のなかでどのように機能するかが議論されました。最後に、新学部/新研究科が位置する京都という場所の意味についても改めて考えたいと思います。
山口:
京都に学びの場を置く意義は非常に大きいと思います。日本で美意識を再評価し、深く学ぶには、やはり京都という選択が最適でしょう。私自身、いろいろな寺院を訪れるのが好きです。たとえば知恩院の仏殿では、4月の前半に三門に紫の布がかけられます。その光景には「ただ事ではない」と感じるようなかっこよさがあります。こうした空間に身を置くだけで、無意識のうちに感性が磨かれるのではないでしょうか。京都のように、歴史や文化が日常の中に息づいている場所で4年間を過ごすこと自体が価値になるでしょう。学外でも刺激的な体験が豊富にあるという意味で、京都は圧倒的なアドバンテージを持っています。
それにくわえて、日本の哲学や美意識を世界的な文脈で再評価し、発信していくことには大きな可能性──西欧社会が主導するビジネスに対するオルタナティブとしての可能性──があると思います。例えば、西田幾多郎の哲学を通じて日本独自の美意識を深め、それを現代のビジネスや社会問題の解決に応用することもできるでしょう。
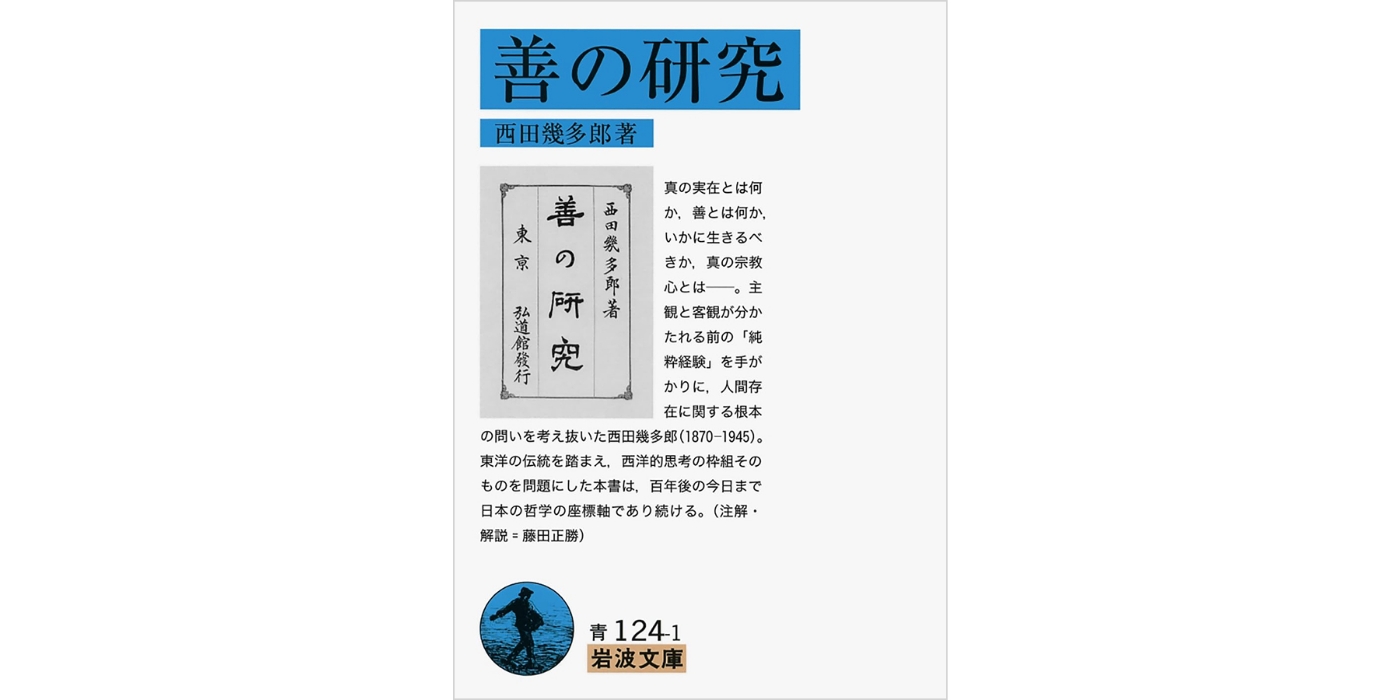
しかし、その価値を日本人自身が本当に認識し、活かせるかという課題はあります。むしろ、日本の美意識は外国人の視点によって再発見されることも多いからです。アン・モロー・リンドバーグやブルーノ・タウトなど、外国人が日本の美意識の価値を指摘し、日本人が再評価するということもこれまでありました。また、日本に留学した外国人が日本の文化に触れることで、「礼儀正しさ」や「思いやり」のような日本特有の価値観を身につけるケースもあります。
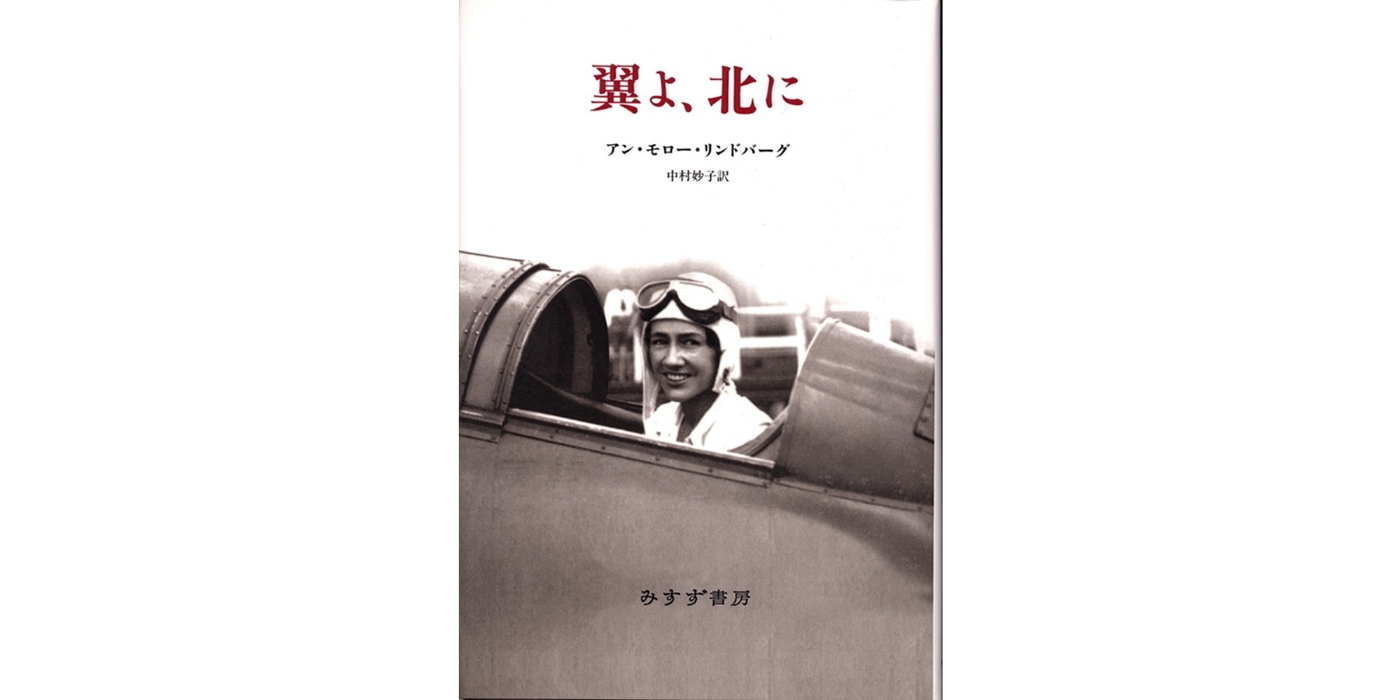
八重樫:
私は「日本的な美意識」という言葉にこだわりたいと思っています。ナショナリズム的視点ではなく、日本の美意識が持つ独自性がグローバルな文脈の中でどのように活かされるのかを探っていくことが重要だと考えています。将来的には海外からの学生を積極的に受け入れ、異なる視点を交えながら「日本の美意識」を議論し、学ぶ場を作りたいと思っています。
これに関連して、私が最近注目しているのが「人称」の問題です。これまでアートやデザインの営みにおいては、制作する主体が問題とされてきました。言い換えれば、これは「私が何かをつくる」という「一人称」の問題です。それが近年では、「私たちが何かをデザインすることによって、私たちはむしろデザインされた世界のなかに生きることになる」という受動性も含めた「二人称」の問題が議論されるようになりました。私はさらにこの問題が深まっていくと考えていて、やがては「私が美しいと感じている原因は何か」という歴史・文化的な問いに直面すると考えているのです。さらに、そういう関係のなかで未来の美しさの感性基準がつくられていくと思います。これはいずれも今はいない存在へのまなざしであり、三人称を超えた「四人称」とでも言えそうな、より抽象的な人称の問題になるでしょう。このような世界と自分のあり方を問うような視点も、日本の美意識と関わりがあると考えています。キャンパスで学生と一緒に探究していけたらいいですね。
山口: 今日の話を聞いていて、正直、これから新学部/新研究科で学べる学生が羨ましいと思いました。美意識を養うことは、単に知識を得るだけではなく、人生そのものの基盤を作ることにもつながると思います。ですから、これからこの場で学ぶ学生たちには、ぜひ思い切り楽しんでほしいですね。

1970年東京生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。株式会社ライプニッツ代表。
慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ、コーン・フェリー等で企業戦略策定、文化政策立案、組織開発等に従事した後に独立。
株式会社中川政七商店社外取締役、株式会社モバイルファクトリー社外取締役。
著書に『人生の経営戦略』『クリティカル・ビジネス・パラダイム』『ビジネスの未来』『ニュータイプの時代』『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』『武器になる哲学』など。