「学生だからこそ」重機がつくる明るい未来を伝えたい
学生目線で重機を研究、実際に操縦もして、その魅力を発信する学生団体「立命館重機部」。 団体を立ち上げ、代表を務めるのは椙山百合花さんだ。世界中で愛される日本の重機メーカーや重機を扱う現場で、彼女が見て学んだことについて話を聞いた。

家庭科の授業で農業重機の魅力に惹かれる
椙山さんが重機を好きになったきっかけは、高校2年生の時。家庭科の授業の一環で、米が収穫されるまでの様子をまとめた映像を視聴した。それまで第一次産業である農家は、肉体労働や手作業が多い印象を抱いていたが、稲刈り機一台で収穫するシステマチックな一面にイメージを覆された。重機を操縦できる人が一人いれば、広大な田畑を管理できることに感銘を受け、それ以来自ら重機のメーカーを調べるように。高校3年生になると、大学入学後は重機サークルや重機を扱う災害ボランティア団体に入部したいと思いを強くした。
「研究」・「操縦」・「発信」の立命館重機部を創部
立命館大学に入学後、重機を扱う課外活動団体を探したが見つけられなかった。椙山さんは気持ちを切り替え、自ら重機の団体を立ち上げることを決意。1回生の春、仲間たちと3人で「立命館重機部」を設立した。
しかし、その活動は想像よりもはるかに難しかった。当初、重機を操縦して農家の支援・被災地へのボランティアに取り組むことを構想していたが、計画は頓挫。農作業や防災活動のために重機を操縦するには、高度な操縦技術が求められるからだ。免許を取得したとしても、高いスキルを身につけるには多くの時間を要するため、実現可能性が低いと判断した。そこで椙山さんたちは、重機の操縦だけにこだわらず、「研究」・「操縦」・「発信」の三つの柱を軸として活動していくことを決めた。
「研究」については、重機メーカーが集まる展示会へ積極的に参加。ただ、重機メーカーの展示会に学生団体が参加することには、かなりのハードルがあったという。「展示会は重機を扱う企業向けに行われる営業の場。そもそも学生では参加できないものが数多くありました。また参加できたとしても、重機メーカーとは参加目的が異なるため、受け入れてもらうことに苦労しました。特に活動実績がない一年目は、立命館重機部の取り組みを理解してもらうことがとても難しかったです」。それでも粘り強く、展示会への参加を続けたことがきっかけとなり、活動に共感した重機メーカーの工場や舗装・解体現場を見学させてもらうなど、重機についての学びをさらに深めることができたという。
「発信」では、重機メーカー協賛の下、学内や地域のイベントに本物の重機を展示してその魅力を伝える企画を実施した。企画提案当初、前例がないために主催者との調整が難航。計画通りには進まなかった。例えば、地域の子どもたちも参加できる大学のイベントに出展した際には、学内への重機の搬入についての安全性が問われた。丁寧に大学の関係部署と調整を重ね、ようやく企画実現にこぎ着けたという。
立命館重機部のこうした取り組みは前例がなく、すべてがチャレンジの連続だった。それでも、椙山さんは開拓者として、「重機」を学び、多くの人にその魅力を伝えることにやりがいを強く感じていた。

愛媛県で舗装会社のインターンシップに参加
椙山さんの重機に対する熱意は、次第に周囲を動かしていった。活動一年目から立命館重機部の取り組みに関心を寄せていた経営学部の善本哲夫教授が二年目には顧問となり、その活動をサポート。善本教授の紹介で、愛媛県で道路舗装などのインフラストラクチャー整備を手掛ける企業へのインターンシップが実現した。立命館重機部に所属するメンバー9人のうち、椙山さんを含む3人が代表して参加。約2週間のインターンシップで、ロードローラー運転者特別教育や操縦訓練、機械整備、アスファルト施工などを経験した。
インターンシップを通じ、立命館重機部は大きな収穫を得た。それは、団体が掲げる活動の柱「操縦」についての学びだった。
まず椙山さんたちが驚いたのは、重機オペレーターの操縦技術の高さ。仮に椙山さんが10年以上かけても、同じレベルに到達するのは困難だと思ったほどだ。「バックホー(小型ショベルカー)のショベルをおろして、オペレーター側にまっすぐ引き寄せる基本的な動作ですら、簡単にはできません。単純な動きに見えるかもしれないですが、実際に自分で操縦してみてその難しさを痛感しました。重機オペレーターの操縦技術を見学させていただく機会がある度に、プロの操縦技術に圧倒されます」。
オペレーターの高い操縦技術と同時に、重機のICT化(Information and Communication Technology)が大きく進展していることにも椙山さんたちは驚いたという。日本の重機は自動操縦や安全装置が年々進化してきている。これまで職人技として、個人の感覚にゆだねられてきた高度な操縦技術がシステム化され、今では遠隔操縦やアシスト機能を搭載した重機が展示会で主流になってきている。
「重機自体の技術向上により、農業や建設業に従事する人々が働きやすくなる工夫がされていることは大きな発見でした。これらの業界は、働き手不足や高齢化などの社会課題に直面しています。ICT化を含め、さまざまな取り組みを進展させることで、社会課題を解決し、明るい未来へとつなげる動きは、もっと多くの人々に知ってもらいたい」と椙山さんは語る。

学生目線で伝える重機の魅力
インターンシップでの経験により、実際に重機を扱う現場での学びを深めた椙山さん。イベントへの出展や重機を製造する工場の見学など、立命館重機部の活動に熱を込める。活動三年目の現在は、展示会に参加すると、重機メーカーから協賛依頼の声がかかることも少なくないという。学生目線で現場を見ること、また操縦を楽しみ、その魅力を伝えようとする姿勢は、立命館重機部の大きな強みにもなっている。
「重機メーカーからの発信では伝わりにくい人たちに、大学生である私たちが発信することで、届けることができる重機の魅力があると思います。出展したイベントでは、『初めてこんなにも間近で重機に触れる体験をした』と同世代の学生や地域の子どもたちが驚いた様子で話してくれます。重機を街で見かけることがあっても、その現場まで近づくことは難しいと思います。イベントでの体験を通じて、重機が活躍する業界や、重機そのものに関心を持ってもらうことにつながればうれしいと思っています」。
またこうした取り組みは、立命館重機部が学生の課外自主活動団体として、立命館大学から支援※を受けていることで成り立っているという。「重機メーカーに見学して学んだり、イベントに出展して魅力を発信したりと、団体が掲げる『研究』・『操縦』・『発信』にかかる幅広い活動ができているのは、立命館大学のサポートのおかげです。支援を受けているからこそ、もっと活動の幅を広げて多くの人に重機の魅力を伝えることで、業界が抱える社会的課題にも目を向けてもらうきっかけをつくっていきたい」。
今後も工場見学や重機メーカーとの協賛イベントを控えている椙山さん。「学生×重機」の開拓者として、新たな道を拓き続ける彼女からますます目が離せない。
※校友会未来人財育成基金

PROFILE
椙山百合花さん
愛知県出身。趣味は散歩。景色を楽しみながら歩くことで、ブレインストーミングにもなりリフレッシュしている。
立命館重機部のXのアカウント:
@Rits_juki
立命館重機部のInstagramのアカウント:
@rits_juki
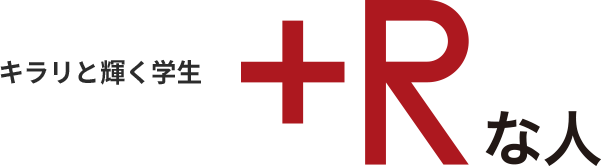
 最近の記事
最近の記事