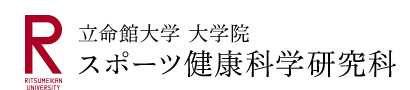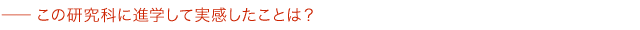院生の一日
2010年4月に開学したスポーツ健康科学研究科。
26名の1期生は、高い志と研究意欲をもって、学習と研究に打ち込んでいます。
そんな大学院生の一日の様子や進学の動機、研究テーマなどをインタビュー形式でご紹介します。

どのスポーツであっても選手は、常に「もっと強く」「もっと速く」「もっと高く」というように、パフォーマンス向上のため、あらゆる努力をします。私は、中学から始めた陸上競技の跳躍を選手として続けています。ずっとパフォーマンス向上にむけて本格的に学びたいと思っていましたが、現実的にスポーツ系の大学院進学を考え出したのは、大学3回生の頃でした。
できれば競技選手も続けながら、「理論(大学院で得る学術知識)」と「実践(スポーツの現場に応用する)」の両側面からパフォーマンス向上にむけた研究をしたいと強く考えるようになり、このスポーツ健康科学研究科への進学を決めました。
現在の研究の関心は、「負荷に対するアキレス腱の適応能力」です。スポーツの種類によって、筋肉のつき方に違いがあることは外見から容易に確認できますが、アキレス腱の差異は外見からは判断できません。私は、スポーツの種類によってアキレス腱にも差異があるだろうと想定しています。研究科の高度な設備・機器を活用してさまざまな測定を行い、解明していきます。
研究の領域は、ほかに「健康運動科学」「スポーツ健康マネジメント」があって、どの領域も合同ゼミ方式で「演習Ⅰ」の授業が進行しています。どの院生も、授業の予復習をしっかりしていますし、合同ゼミの発表は自分の研究関心に関するものですから、特に力が入ります。
研究科の院生共同研究室では、個人が集中して勉強や研究に取り組んだり、相談し合ったりして切磋琢磨しています。また、連休などのまとまった時間を利用して、実験・実習室での実験に専念するなど、充実した毎日を過ごしています。
研究はもちろん、教育にも熱心です。院生の知りたいこと・学びたいことを察知して、授業内容を工夫してくださったり、授業外でも、スポーツ健康科学セミナーと冠して、第一線で活躍されている研究者をお招きしての勉強会を企画してくださっています。ほかに、実験データの処理に欠かせない統計学習会を開いていただきました。このように、授業以外でも刺激を受ける機会を頻繁に提供してくださいます。
先生方の熱意に負けられない、期待に応えたい、という強い思いが、大学院生が研究と向き合う原動力の一つになっていることも確かです。
この研究科では、スポーツや健康に関わる「なぜ?」について究明したい、という研究向上心が教員・大学院生の共通の土台になっていると実感しています。また、スポーツや健康の現場で役立つ研究を教員も大学院生もめざしています。
先生方の研究業績、教育指導力、先端機器設備、院生の熱意をもってすれば、スポーツ健康科学分野のトップクラスの研究は、ここ立命館大学から世界に向けて発信していけると思います。
-
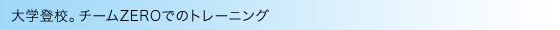

チームZERO
─トレーニング井戸端─
毎週水曜日の午前8時から、学部生・院生と教員とで体力強化の取り組みを行っている。 写真は、私の研究指導教員である伊坂教授。 -
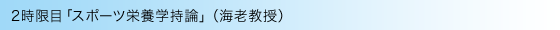

授業では、コンディション維持にむけた効果的なビタミン摂取のあり方についてまとめて、プレゼンテーション。併せて、実習としてヘルシーな餡かけ焼きそばを作る。脂質を抑えるため、豚肉をたっぷりの野菜に置き換えた。
-

研究室で、発表の最終チェック。
自分の研究に関わる海外の論文に目を通す。 -


応用スポーツ科学領域の教員全員と院生による合同ゼミ。自分の研究に関わる発表をする。厳しくも温かい助言が得られる。先生方の熱心な指導と期待に応えられるようにと、研究意欲がさらに増幅。
-

研究時間と調整しながら跳躍の練習をしている。目標は、全日本の表彰台。学部時代よりも、時間管理・自己管理が重要。研究科で学んだ知識をトレーニングに役立て、また後輩の指導にも活用。トレーニングで得た疑問が研究に活かされることもある。
-