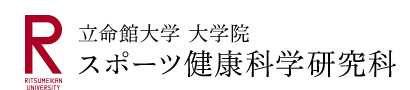ニュース
最新のニュース
2026.02.06
2026年度 研修生・研究生出願受付について
2026年度の研修生・研究生出願受付について、下記の通り、実施いたします。
出願希望の方は、要領をよく確認の上、オンラインで申請を行ってください。
<要項>
<オンライン申請>
▶在学生の方は、下記URLより申請ください。
▶在学生以外の方は、下記URLより申請ください。
<申請期間>
2026/3/5(木)9:00 ~ 2026/3/11(水)17:00
以上
2026.2.6
木下百花さん(本学部卒業生)の研究論文が「Medicine & Science in Sports & Exercise」に掲載されました
本学部を2025年3月に卒業した木下百花さん(現 フィンランド・ユバスキュラ大学 修士課程1年)が、本学部助教 前大純朗先生、同教授 伊坂忠夫先生らの研究チームと共同で取り組んだ研究論文
「Hypertrophic Effects of Single- versus Multi-Joint Exercise: A Direct Comparison Between Knee Extension and Leg Press」が、スポーツ医科学分野を代表する学術誌の一つである「Medicine & Science in Sports & Exercise」に掲載されました。
【研究概要】
筋肉量の維持・増加は、健康づくりや運動機能の向上に欠かせません。なかでも太ももの前側にある大腿四頭筋は、歩く・立つ・跳ぶといった日常動作からスポーツ動作まで幅広く働く、人体で最も大きな筋群です。一方で、筋力トレーニングの現場では、「1つの関節だけを動かす種目(単関節運動)」と「複数の関節を同時に動かす種目(多関節運動)」のどちらが筋肉を効率よく増やすのに有利かについて、明確な結論は得られていませんでした。
そこで本研究では、大腿四頭筋を鍛える単関節運動の代表であるニーエクステンションと、多関節運動の代表であるレッグプレスを、同一の参加者の左右の脚で実施し、直接比較しました。トレーニング未経験の若年成人が、週2回・12週間、同じ相対的強度および回数の条件でトレーニングを行い、介入前後でMRI(磁気共鳴画像法)を用いて、太ももやお尻など17種類の筋肉の体積変化を高精度に測定しました。さらに別の実験では、運動中の筋活動(筋の活動レベル)を筋電図で評価し、筋肉の増え方と運動中の筋活動との関係についても検討しました。
その結果、大腿四頭筋全体としては、ニーエクステンションとレッグプレスのいずれでも同程度の筋量増加が認められました。一方で、大腿四頭筋のうち股関節と膝関節をまたぐ大腿直筋は、ニーエクステンションでは大きく増加したのに対し、レッグプレスではほとんど増加しないことが示されました。逆にレッグプレスでは、大腿四頭筋に加えて、お尻の大殿筋や太もも内側の内転筋(特に大内転筋)も増加し、下半身全体の筋量増加がより顕著であることが確認されました。筋電図の結果もこれらの所見と概ね一致しており、種目によって「強く使われる筋肉」が異なることが、筋量変化の違いにつながることが示されました。
本研究は、「限られた時間で下半身全体を効率よく鍛えたい場合にはレッグプレスが有利になり得る」一方で、「大腿直筋を重点的に鍛えたい場合(特定の動作パフォーマンスの向上や、肉離れの多い部位への配慮など)にはニーエクステンションが重要である」ことを、MRIによる直接測定に基づいて示した点が大きな特徴です。
Journal website(オープンアクセス)
2026.01.27
【開催案内】2025年度スポーツ健康科学研究科博士課程前期課程 修士論文公聴会
2026.01.10
大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャー」に安藤 良介氏(独立行政法人日本スポーツ振興センター ハイパフォーマンススポーツセンター)をお招きし、講義をしていただきました。
2025年12月25日、1月8日の2日間にわたり、大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャー」に安藤 良介氏(独立行政法人日本スポーツ振興センター ハイパフォーマンススポーツセンター)をお招きし、講義を実施しました。
1日目は、安藤さんのこれまでのキャリアパス、独立行政法人日本スポーツ振興センター ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)の組織やミッション、アスリートに対してどのようなサポートをおこなっているのか、どのようなスポーツ医・科学研究を行っているのか、についてお話しいただきました。その中で、HPSCが担う役割の多様さ、アスリートに対する貢献を推進していく上での苦労について、また、今後展開していく、HPSCが総合型サポート(オリンピック・パラリンピックなど)についてお話しいただき、アスリートに貢献できる研究や課題を知ることができる講義となりました。学生にとってアスリートに対して貢献する研究を考えるための大きな刺激となりました。また、最後に、安藤さんから提示された課題に対して学生がグループワークに取り組みました。
2日目にはその成果をプレゼンテーションとして発表しました。各グループの発表に対し、安藤先生からは丁寧にご指導・ご助言をいただきました。
この2日間の講義は、学生にとって非常に有意義で、学びの多い貴重な機会となりました。御礼を申し上げます。
2026.01.06
I Wayan Yuuki さん(博士課程前期課程2回生)の研究論文が国際学術誌「Physiology & Behavior」に掲載されました。
本学スポーツ健康科学研究科博士課程前期課程2回生で、公益財団法人かめのり財団大学院留学アジア奨学生の I Wayan Yuukiさんが、スポーツ健康科学部教授の 橋本 健志先生、早稲田大学スポーツ科学学術院講師の 塚本 敏人先生らと共同で取り組んだ研究論文が、国際学術誌に原著論文として掲載されました。
研究の概要
忙しくて十分な運動時間を確保することが難しい現代社会において、日常生活の中で取り入れやすい「食事」による健康づくりは重要な課題です。学業や仕事、スポーツなどでは、集中して考えたり、素早く判断したりする力が求められます。こうした力は、抑制、記憶、判断といった高次脳機能から成る「認知機能」としてまとめて捉えられ、日常生活の質に大きな影響を与えます。運動が認知機能の向上に有効であることは、「Exercise is Medicine」という概念のもと、これまで多くの研究によって示されてきました。一方、現代社会においては、時間的制約などの理由から、十分な運動を継続することが難しい場合も少なくありません。そこで本研究では、日常生活の中で比較的取り入れやすい介入方法として「食事」に着目し、三大栄養素の一つである脂質の摂取が認知機能に及ぼす影響について検討しました。
本研究では、若年成人36名を対象に、ランダム化比較試験※1を実施しました。一般的な脂質である長鎖脂肪酸(LCT)油※2を対照とし、中鎖脂肪酸(MCT)油※3の効果を検証しました。効果検証は、単回摂取(1回の摂取による即時的な認知機能の変化)と、4週間の継続摂取(継続摂取による安静時の認知機能の変化)という2つの時間軸で行われました。
結果として、MCT油を単回摂取した場合、LCT油と比較して、認知機能の中でも抑制機能※4の向上が認められました。また、4週間にわたって継続的に摂取した場合には、摂取直後でなくとも、安静時における認知機能の一つである作業記憶※5の向上が確認されました。さらに、MCT油を単回摂取した際に認知機能の向上がみられた対象者は、4週間継続して摂取した場合にも、認知機能が向上する傾向が示されました。
本研究は、成人に対する運動や身体活動が認知機能に有益であるとする世界保健機関(WHO)の提言と並び、食事(栄養)が認知機能に影響を及ぼす可能性を示した研究の一つといえます。特に、若年者において、すでに健常で顕著な低下の認められない認知機能においても、一定の変化が認められた点は注目に値します。本研究成果は、学生や働き世代の人々にとって、時間的・身体的負担を伴わず、日常生活の中で取り入れやすい介入方法として、今後の検討に資する知見を提供するものと考えられます。
用語説明
※1 ランダム化比較試験
対象者をランダムに群に分け、介入の効果を比較する研究方法。
※2 長鎖脂肪酸(LCT)油
一般的な食用油に多く含まれる脂質。本研究では比較対象として使用された。
※3 中鎖脂肪酸(MCT)油
消化・吸収が速い脂質。脳の働きに関わるエネルギー代謝との関連が注目されている。
※4 抑制機能
不要な行動や衝動を抑え、適切な行動を選ぶための認知機能。
※5 作業記憶
情報を一時的に保持しながら処理する認知機能。
論文情報
雑誌名:Physiology & Behavior
論文名:Both a single dose and a 4-week daily regimen of medium-chain triglycerides boost certain aspects of cognitive function in young adults: a randomized controlled trial
執筆者名(所属機関名):I Wayan Yuuki(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科)、道羅絢斗(立命館大学総合科学技術研究機構)、松村哲平(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科)、福澤和志(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科)、村上嘉野(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科)、橋本海斗(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科)、塚本敏人(早稲田大学スポーツ科学学術院)、橋本健志(立命館大学スポーツ健康科学部)
掲載日時(現地時間):2025年12月22日
2026.01.06
大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャー」に國澤純先生(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 副所長)をお招きし、講義をしていただきました.
2025年11月13日および20日、大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャー」において、國澤純先生(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 副所長)をゲストスピーカーとしてお招きし、講義を実施しました。
講義では、先生がこれまで取り組まれてきた腸内環境および精密栄養に関する研究について、非常に分かりやすくご解説いただきました。腸内細菌叢が私たちの健康と密接に関係していること、またその構成が日々の「食」によって大きな影響を受けることについて、マウスからヒトまでを対象とした幅広い研究成果をご紹介いただきました。さらに、研究成果を社会実装へとつなげた具体的な事例も示していただき、研究から社会実装に至る一連のプロセスを、先生ご自身のご経験を交えながらご講義いただきました。学生にとって大変魅力的で刺激的な内容となりました。
また後半の部では、「腸内環境や精密栄養の観点から、新しい社会をどのように創造していくか」というテーマが提示され、学生はグループワークに取り組みました。各グループの発表に対して、先生からは示唆に富んだご指導・ご助言をいただき、広い視野に基づくコメントは学生にとって大変学びの多いものでした。
本講義は、学生にとって非常に有意義で、学びの多い貴重な機会となりました。改めまして、國澤先生に心より御礼申し上げます。
2025.12.23
2025年12月23日(火)「スポーツ健康科学と未来」にて、オーガイホールディングス株式会社の代表取締役社長である野田真一氏にお越しいただきました。
2025年12月23日(火)、学部科目「スポーツ健康科学と未来」に、オーガイホールディングス株式会社の代表取締役社長である野田真一氏をお招きし、歯や噛み合わせに関する口腔の大切さについてスポーツ健康科学との関連から講義をしていただきました。
最初に、適切な位置で噛み合わせることにより姿勢が良くなり、身体パフォーマンスが向上することを、本学部と連携して測定したデータも踏まえながらご説明いただきました。マウスピースや歯が抜けた際の義歯の作成には歯科技工士が必要とされますが、その後の生活への影響やパフォーマンスへの影響をデータとして取得するにはスポーツ健康科学分野の専門的な知識が必要であると学ばせていただきました。
続いて、日本のように高齢者人口が増加している中、高齢者の口腔機能を支援する入れ歯市場へ事業展開されている様子をお話しいただきました。具体的には、野田さんがお父様へ3Dプリンターで作成した入れ歯をプレゼントし、これまで食べられなかったものが久々に食べられるようになったおかげで、身体機能やメンタルヘルスが良好になったというお話は、非常に印象的でした。超高齢社会や歯科技工士不足という社会課題に対し、3Dプリンターや移動診療(歯科検診MaaS)を活用した次世代の歯科医療モデルを構築したり、技術革新だけでなく「入れ歯をギフトする(ギフトデンチャー)」という新たな文化を形成したりすることを通じ、食卓から家族の幸福を創出する未来をお伝えいただきました。
最後に、ビジネスの考え方にも触れていただき、スポーツ健康科学とビジネスの共通点を示しながら、目の前の「1人」を助けることから始まる課題解決のプロセスを学ばせていただきました。
野田さん、口腔とスポーツ健康科学についての貴重なご講演を誠にありがとうございました。
2025.12.24
大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャーII」に日本スポーツ振興センター国際情報戦略部 山田悦子 氏に講義をしていただきました
2025年12月4日(第10回)・11日(第11回)・18日(第12回)の3日間にわたり、大学院授業「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャーⅡ」に、日本スポーツ振興センター国際情報戦略部 山田悦子氏をお招きして、講義を行っていただきました。山田氏は、現在主に開発と平和のためのスポーツ(Sport for Development and Peace)を、各種団体の戦略等に組み込むための普及・啓発等に取り組まれ、パリ2024インパクト&レガシー戦略評価監督委員会の委員としてもご活躍されています。
第10回は、山田氏のこれまでのご経歴についてご紹介いただいた後、開発と平和のためのスポーツ(Sport for Development and Peace)に関する国際的な政策の潮流について、パリオリンピック・パラリンピックの成果について具体的に公表されている調査結果やパリ2024オリンピック市民マラソン“Marathon pour Tous”といった事例の紹介も含め詳しくお話しいただきました。また、受講生のグループで「オリンピック・パラリンピックの成功の是非について」グループ間で簡易的なディスカッションを行いました。そして、オリンピック・パラリンピックを軸に「誰にとっての成功なのか?」についての検討を行いました。
第11回は、日本スポーツ振興センターとsportanddev(国際NPO)が行ったスポーツを通じた社会課題の解決や持続可能な開発に関するアンケート調査結果の共有と解説をしていただきました。加えて、「運動習慣を身につけてもらうことを目的とした健康増進プログラムを実施した」というケースが提示され、成功したといえるかどうかのディスカッションを受講生のグループ間で行いました。さらに、日本スポーツ振興センターとsportanddevが開発した「SDGs達成へ向けたスポーツの活用ガイドブック」“Bridging the Divide in Sport and Sustainable Development: A guide for translating policy into practice and effective programme management”についてご説明いただきました。
第12回は、「パリ2024オリンピック・パラリンピック競技大会は成功したと結論づけられるのか?その理由は何か?」について受講生のプレゼンテーションが行われました。受講生のプレゼンテーションに基づいて、EBPMに基づく政策立案の重要性、パリ2024オリンピック・パラリンピックにおける招致段階からのレガシー&サスティナビリティ戦略、パリ2024インパクト&レガシー戦略評価監督委員会がレビューした各種レポートに基づく情報共有、フランス国内におけるアクティブデザイン(施設+インセンティブ)の実例、などについて詳しく解説していただきました。
日本スポーツ振興センター国際情報戦略部山田悦子氏による講義は、大学院生にとって開発と平和のためのスポーツ(Sport for Development and Peace)やパリ2024オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーについて学ぶ非常に有意義で貴重な機会となりました。お忙しい中、素晴らしいご講義をいただき、様々な示唆をいただいた山田氏に心から御礼を申しあげます。ありがとうございました。
2025.12.24
2025年12月17日、J-PEAKS国際連携セミナーを開催いたしました。
本セミナーでは、ポーランド・ポズナン大学のクリストフ・デュカレック・ミハルスキ先生(以降、クリス先生)をお招きし、アスリートのパフォーマンス向上を狙いとしたスポーツ栄養学的アプローチに関する多くの研究成果をご発表いただきました。
また、ご自身がポーランドナショナルチーム(ゴルフやローイングなど)に管理栄養士(チーフスタッフ)として現場の栄養サポートを実施している実践的な活動についてもご紹介いただきました。
さらには、学生に対して研究の面白さや、アクティブに色々と活動することの重要性についても熱く話していただきました。
本セミナー後の質疑応答では、複数の参加した学生から質問が寄せられ、活発な議論が展開されました。特に印象的だったのは、クリス先生はこれまで実施された研究成果をすべてアスリートに還元してきているということです。それだけ、常に実践的に応用することを意識して、リサーチクエスチョンを立てているとのことでした。また、同時に、それだけ良質で自信を持って実践応用可能な研究を遂行しているということだと思います。参加者一同、大変刺激を受けました。
ご参加いただいた皆様、ならびにクリス先生に心より感謝申し上げます。
2025.12.22
大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャー」に立石 法史氏(サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社研究部部長)をお招きし、講義をしていただきました。
2025年12月4日、11日、18日の3日間にわたり、大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャー」に立石 法史氏(サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社研究部部長)をお招きし、講義を実施しました。
1日目は、立石さんのこれまでのキャリアパス、サントリーでの仕事・役割、どのような研究・開発しているのか、商品開発までのプロセスまでお話しいただきました。その中で、1つの商品が開発・販売に至るまでの綿密な研究設計とエビデンスの構築、販売する際の工夫していく上での苦労についてお話しいただき、飲料の商品開発の詳細を知り得る貴重なご講義となりました。学生にとって大きな刺激となりました。
2日目は、立石さんから提示された課題に対して学生がグループワークに取り組み、3日目にはその成果をプレゼンテーションとして発表しました。各グループの発表に対し、立石さんからは丁寧にご指導・ご助言をいただきました。
この3日間の講義は、学生にとって非常に有意義で、学びの多い貴重な機会となりました。御礼を申し上げます。
2025.12.18
2025年12月16日(火)「スポーツ健康科学と未来」にて、スポーツ健康科学部・同研究科15周年企画として、修了生の角大地氏と矢沢大智氏にお越しいただきました。
2025年12月16日(火)、学部科目「スポーツ健康科学と未来」に、本研究科出身の株式会社アシックス スポーツ工学研究所の角大地氏と、スポーツチームでアナリストをされている矢沢大智氏をお招きし、スポーツ健康科学部・同研究科15周年企画として講義をしていただきました。
角氏は、本学部から博士後期課程まで在籍し、学位取得後、現在の株式会社アシックス スポーツ工学研究所に勤務されています。専門分野はトレーニング科学で、アスリートの競技力向上や人々の健康増進を目的に、研究活動に従事されています。講義では、アシックスでの基礎研究から商品開発までの一連の流れを、スポーツ科学の専門家としての業務も交えながらご紹介いただきました。中でも、陸上長距離レース中のペースの変動によるアスリートの生理的応答を検討した基礎研究や、実際の現場におけるAIを活用したレース戦略の立案に関するお話は非常に興味深く、アスリートへの科学的サポートの実践を具体的に理解することができました。
矢沢氏は、本研究科で修士の学位を取得し、現在はスポーツチームでアナリストとして勤務されています。矢沢氏には、データの収集からデータ分析、そして監督、コーチや選手への情報共有など、スポーツ現場で働くアナリストの仕事内容についてお話しいただきました。スポーツの練習・試合で得られるデータを基に、選手のパフォーマンス向上に向けた課題整理、分析、可視化を行い、現場での意思決定を支援していることをご紹介いただきました。
最後にパネルディスカッションを実施し、学生からの質問に答えていただきました。特にお二人のお話をうかがい、科学的に得られた知見や大規模データから得られた分析結果などを現場にフィードバックし、正しく理解して使ってもらうためには、人に伝えるスキルが重要であるということを感じました。今回は貴重なお話をしていただき大変刺激になりました。誠にありがとうございました。
2025.12.18
2025/12/22(月)~ 博士課程前期課程および博士課程後期課程(11月入試)の出願を開始します。
博士課程前期課程(一般・社会人・留学生)および博士課程後期課程(一般・社会人)
(2025年2月実施)入学試験の出願開始についてお知らせいたします。
試験日 :2026年2月1日(日)
出願開始:2025年12月22日(月)~2026年1月15日(木)
※出願は「Ritsu-Mate」を登録の上、出願書類の提出(郵送のみ)が必要です。
※出願書類の提出は、郵送に限ります。
日本国内からの郵送に限り、出願期間最終日の消印有効です。
日本国外からの郵送の場合は、出願期間最終日必着で出願書類の郵送手配を行ってください。
日本国内おおよび日本国外からの郵送について、やむを得ない事情(自然災害、紛争、テロ等)により、
出願期間における郵送が困難である際、必ず事前にスポーツ健康科学部事務室まで相談ください。
詳細 :立命館大学大学院入試情報サイト(入試要項および過去問題等が確認できます)
お問合せ:立命館大学スポーツ健康科学部事務室(研究科担当)spoken3@st.ritsumei.ac.jp
2025.12.17
【公聴会】スポーツ健康科学研究科博士学位授与申請論文(2025年度3月授与予定)に関わって
各位
標記、スポーツ健康科学研究科博士課程後期課程における2025年度3月授与予定の博士学位授与申請論文(甲号)について、【公聴会】を開催いたします。
参加希望者の方は、添付の「公示」より詳細情報を確認ください。
<公示>
以上
2025.12.17
2025年12月9日(火)「スポーツ健康科学と未来」にて、株式会社アリストルの代表取締役CEO宮崎学氏にお越しいただきました。
2025年12月9日(火)、学部科目「スポーツ健康科学と未来」に、株式会社アリストルの代表取締役CEO宮崎学氏をお招きし、講義をしていただきました。
まず、総合型スポーツクラブの業態や施設について、クイズを交えながら講義をしていただきました。クイズの中では、「総合型スポーツクラブで最も利用されている設備は?」や「総合型スポーツクラブ会員が会員向けアプリに最も求める機能は?」など、スポーツクラブに所属する顧客データから現場の声をもとに講義をしていただきました。学生は、クイズの答えに一喜一憂しながら、終始楽しそうにクイズに回答し、回答後には、宮崎さんからの解説があり学びも深まりました。また、クイズ正解者上位5名には、株式会社アリストルが実施するDXコンサルティング事業の一環であるAI/生成AIの開発支援、利活用支援のノウハウをまとめた書籍「生成AI爆速大全」をプレゼントしていただきました。
続いて、総合型スポーツクラブとDX戦略に関連し、ランチェスターの法則から総合型スポーツクラブの立ち位置と経営戦略についてお話しいただきました。施設が充実している総合型クラブの立ち位置を踏まえ、講義では顧客の活動実態(栄養・活動量・遺伝子等)を把握し、個別最適な体験価値を総合型スポーツクラブで提供するDX戦略の必要性についてお話ししてくださいました。
また、起業に興味がある学生へのメッセージとして、「起業は自分の想いを形にする一番の手段」とお話ししてくださり、今後の学生生活に極めて刺激となる講義となりました。
宮崎さん、自身の経営体験から現在の総合型スポーツクラブについて貴重なご講演をいただき誠にありがとうございました。
2025.12.15
本研究科博士課程前期課程2回生 渡部晴さんの研究が、日本野球学会第3回大会にて最優秀賞を受賞されました!
2025年12月13日(土)・14日(日)広島大学にて開催されました、日本野球学会第3回大会において、本研究科博士課程前期課程2回生の渡部晴さんが「糖質摂取が野球投手の糖代謝と投球パフォーマンスに及ぼす影響」について発表し、最優秀賞を受賞されました。
渡部さん、おめでとうございます!
2025.12.02
本研究科博士課程後期課程2回生新井陽豊さんの研究が、日本スプリント学会第36回大会にて優秀発表賞を受賞されました!
2025年11月29日(土)・30日(日)日本女子体育大学にて開催されました、日本スプリント学会第36回大会において、本研究科博士課程後期課程2回生の新井陽豊さんが「短距離走選手におけるスプリント誘発性の大腿部筋活動の性差」について発表し、優秀発表賞を受賞されました。
新井さん、おめでとうございます!
2025.11.28
大学院科目「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャーII」に日本スポーツ協会(JSPO)地域スポーツ推進部クラブ育成課の講師3名に講義をしていただきました
2025年11月6日(第6回)・13日(第7回)・20日(第8回)の3日間にわたり、大学院授業「スポーツ健康科学エグゼクティブレクチャーⅡ」に、日本スポーツ協会(JSPO)地域スポーツ推進部クラブ育成課(窪田章吾氏・吉村ひかり氏・藤原康太氏)をお招きして、講義を行っていただきました。
第6回は、地域スポーツ推進部クラブ育成課の講師3名(窪田章吾氏・吉村ひかり氏・藤原康太氏)のキャリアパスについて、また、窪田章吾氏から日本スポーツ協会(JSPO)の概要、総合型地域スポーツクラブ(総合型クラブ)の沿革や実態についてオンラインで講義を実施していただきました。また、受講生がSC全国ネットワーク登録クラブについての調べ学習を行いました。
第7回は、受講生によるSC全国ネットワーク登録クラブに関するプレゼンテーションと吉村ひかり氏によるフィードバック、また、吉村ひかり氏から部活動の地域展開についての説明の後、受講生で部活動の地域展開に関するディベートを行いました。そして、吉村ひかり氏から部活動の地域展開と総合型クラブに関する好事例の共有を行っていただきました。
第8回は、藤原康太氏から第6回・第7回の振り返りと総合型クラブの創設に関する概要と実態についての説明が行われ、受講生が考える理想の総合型クラブについてグループディスカッションと発表を行い、藤原康太氏と受講生で今後の総合型クラブのあり方についての検討を行いました。
日本スポーツ協会(JSPO)地域スポーツ推進部クラブ育成課の3名の講師による講義は、受講生にとって部活動の地域展開や総合型クラブは身近な話題で、大学院生にとって非常に有意義で学びの多い貴重な機会となりました。窪田章吾さん・吉村ひかりさん・藤原康太さん、本当にありがとうございました。
2025.11.25
本研究科博士課程前期課程1回生星凜武さんの研究が、第38回日本トレーニング科学会大会にて若手研究奨励賞(大賞)を受賞されました!
本研究科博士課程前期課程1回生の星凜武さんが第38回日本トレーニング科学会大会で「フィールドでの自発的低換気を用いた間欠的スプリントトレーニングの効果」について発表し、若手研究奨励賞(大賞)を受賞されました。
星さん、おめでとうございます!
2025.11.25
本研究科博士課程前期課程2回生西澤尚弥さんの研究が、第38回日本トレーニング科学会大会にて若手研究奨励賞を受賞されました!
本研究科博士課程前期課程2回生の西澤尚弥さんが第38回日本トレーニング科学会大会で「股関節屈曲または膝関節伸展トレーニングが筋力および疾走パフォーマンスに及ぼす影響」について発表し、若手研究奨励賞を受賞されました。
西澤さん、おめでとうございます!