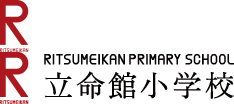さなぎ
5月後半になると,児童が主体的に動き出す場面が多くみられるようになってきました。立命館小学校では代表委員会という組織があり,各クラスの学級委員が定期的に集まって,話し合いをします。自分たちの日常の学校生活を振り返り,「こんなふうにすればもっと過ごしやすくなるのではないか」「みんなが安心して過ごすためにどんなことができるのか」などについて話し合ってくれています。
前回の代表委員会では,「あいさつ」「歩く」をしっかりできるように,話し合いを進めてくれました。この2つは,4月当初は先生から児童に伝えていたものですが,これらを児童同士で考えてくれるように変わってきました。同じ内容であっても,「主体者になる」というのは大きな変化,そして成長へとつながります。
私は,成長の話をするときに,「あおむし」の話をよくします。「あおむし」が成長すると,「さなぎ」になり,「蝶々」になっていきます。「あおむし」のまま,大きくなっていくわけではありません。そして成長するときには,「さなぎ」の期間が必要です。この時期は,思うようにいかないこと,しんどいこともあるかもしれません。でもそうやって殻をやぶる力がついたときに,羽を広げ,大きな世界へと飛び立つことができます。そして上空から「あおむし」をみたときに,「あんなときもあったな」と自分の成長を俯瞰し,自分の成長を感じるわけです。
だから,「先生からの指示を聞く」という状態から,「自分たちで考える」と変容することは,これからの成長を期待させるわけです。
学校内を歩いていると,ある学年のホワイトボードに,こんなことが書いてありました。
学年での過ごし方について,児童が学年集会でみんなに思いを伝えた後に書かれたものです。その学年集会では,具体的な項目も上げられましたが,学年の過ごし方の上位概念として,「相手を思いやる」という言葉がありました。自分たちでそれを大切にしようというメッセージ,そして相手を思いやって話をした姿こそ,みんなへの大きなメッセージとなったことと思います。みんなの前で話をした児童は,ドキドキしたでしょう。でも,それは「さなぎ」の状態を経験した証拠です。まだまだ「さなぎ」の状態が続くかもしれません。でも,その時期が必ず自分を必ず成長させてくれます。こんな動きがあちこちで出てきたことを誇らしく,そしてその様子をこれからも見守っていきたいと思います。
校長 小笹大道