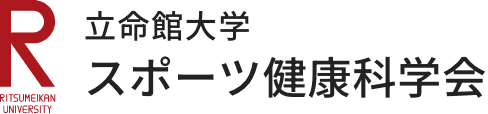News
ニュース
2018年度藍星賞受賞者
2018年度藍星賞受賞者リスト
- 1. 研究部門 福谷 充輝
- 2. 教育部門 日裏 徹也
- 3. 国際部門 細川 由梨 岡松 秀房
- 4. 社会連携部門 大橋 知佳
1)福谷先生は、大学院時代から現在に至るまで、一貫して筋収縮に関する研究を行っている。大学院生時代には、ヒト生体を対象に、筋力計、筋電図、電気刺激、超音波、MRIなどを用いて、神経生理学や筋形状の観点から筋収縮メカニズムを検証してきた。博士号を取得した後は、これまでの研究も継続しつつ、動物の摘出筋を使った研究にも着手しており、日本学術振興会の海外特別研究員という制度を利用して、筋収縮研究で世界的に著名なCalgary大学のHerzog研究室に留学し、単一の筋細胞、さらには単一の筋原線維を用いた力学測定を習得した。2018年4月にスポーツ健康科学部の助教となってからは、その手法を用いた研究をさらに発展させるため、日本の大型放射光施設SPring8の八木直人特別研究員や、筋疲労研究で世界的に有名なKarolinska研究所のHakan Westerblad教授との共同研究にも着手している。研究成果も出始めており、2018年には2本の論文がMedicine and Science in Sports and Exercise (MSSE)に掲載され、そのうちの一つである「Fukutani A, Herzog W. Residual Force Enhancement Is Attenuated in a Shortening Magnitude-dependent Manner. Med Sci Sports Exerc. 2018;50(10):2007-2014.」は、編集長の目に留まり、MSSE 2018年10月号の “News and Views” にて紹介された。2019年1月時点で4本の論文が国際誌にて査読中であり、それ以外にも国際誌の総説執筆を依頼されている状態であるため、引き続き多くの研究成果が期待できる。また、学生の指導にも力を入れ始めており、指導している学部生が、2019年7月の国際学会で発表する予定である。
このように、福谷先生は積極的に研究活動を進めており、世間で推奨されている国際化 (海外での研究成果発表、国際共同研究の展開) という観点からも申し分ない実績を有している。加えて、学生への研究指導を通じて、本学の教育発展への貢献も期待できる。
2)日裏氏は、2018年度の立命館慶祥高等学校陸上競技部の指導において、全国大会で2つの優勝を含む13の上位入賞を果たすなど、高い指導実績を残した。
特に、全国高校総体では、女子400mRにおいて北海道高校新記録を45秒91から45秒68へ大幅に塗り替えて優勝(高校記録でも歴代5位)するとともに、女子100mにおいて決勝に本校から2名が進出し、立命館旋風を巻き起こした。個別競技のみならず、総合成績においても立命館慶祥初の7位入賞を果たした。このときの最大の功労者である臼井は、日本陸連により東京オリンピックの強化選手として選ばれて話題となったが、日裏氏の早くからの懇切丁寧な進路指導により、学外流出を逃れ、スポーツ健康科学部への学内進学を決意させた。
国民体育大会においては、日裏氏は北海道女子の監督として初めてチームを率い、本校生徒4名の活躍もあり、皇后杯(女子総合)3位を獲得した。
加えて、立命館慶祥高等学校の授業においては、日裏氏は学校設置科目として「スポーツと健康」の担当教員として、高校での教育では実践することが難しい乳酸値の測定や筋力測定など、スポーツ健康科学部への進学を強力に促すとともに、スポーツ健康科学部への進学を前提とした授業を行っている。
進学実績でも、最も優秀な選手を立命館大学スポーツ健康科学部に進学させることはもちろん、早稲田大学スポーツ科学部への進学など、スポーツ学へのさまざまな進学実績を実現した。
3)細川先生は、アメリカのスポーツセーフティーに関する研究主管となるKorey Stringer Instituteで医科学委員および米国アスレティックトレーナーズ協会にて国際委員を務め、スポーツセーフティーに関する国際的な教育・研究・広報活動を通して日本のスポーツセーフティー向上に大きく貢献されている。また、適切な熱中症予防措置について最新の科学的根拠に基づき国内外で多数講演を実施するとともに、熱中症予防に関する研究に対して、国内および国外の様々な異分野の研究者と協働で取り組まれている。2018年度においては、10本以上の研究成果を輩出されており、大変優秀な業績を挙げられた。さらには、本学部・研究科の専門英語を担当し、学生の国際発信力およびプレゼンテーション能力を向上させることに尽力された。以上、本学部・研究科の国際化に大きく貢献された。
3)岡松 秀房 特任助教は、2014年スポーツ健康科学部に着任以来、一貫して GAT プログラム推進のための中心的な人物となり、ATC 取得を希望する学生の教育サポートに注力されてきた。岡松先生が、正課授業ならびに正課外授業において、非常に熱心に学生をサポート頂いた結果、これまでに2名の卒業生が ESU 大学大学院で学んでいる。また、今年度も新たな学生がアメリカの大学院に進学しようとしている。
岡松 先生は、GAT プログラムの協定校との連絡において、スポーツ健康科学部の主要窓口となっており、海外の大学とも度重なる交渉を重ね、GAT プログラムの協定作りをされてきた。その交渉の一端については、『立命館スポーツ健康科学』第八巻 (2018) にまとめられている。また、これまでの ATC 生活で培った幅広いネットワークを通じて、GAT ステップアップセミナーに何人もの講師を招き、ATC 取得を希望する学生のキャリア意識形成においても、大きな役割を果たしている。さらに、GAT プログラム協定校の拡大にも貢献された。
4)校友である大橋知佳さんは、2016年度にスポーツ健康科学部を卒業後、株式会社東大阪スタジアム(HOS)に就職され、主に運動・文化施設の運営管理業務を担当されてきた。なかでも、2016年度に本学に開設された「スポーツ健康コモンズ」においては、その委託運営管理業務を担当され、授業開講期の大学実習授業のサポート、スポーツ健康コモンズで開講されている学生・教職員向けの各種プログラムの講師として活躍されるととともに、近隣の地域の親子や、幼児・児童を対象とした運動教室を開設するなど大学と地域の連携において大きな貢献をされている。
特に、幼児・児童向けの教室においては、スポーツ健康コモンズの施設や正門前の芝生広場等を会場とする、コオーディネーショントレーニングをその内容として位置付け、参加幼児・児童の運動発達に即した基礎的運動スキルのバランスのよい向上を図ることで、参加者における積極的な成果や、その保護者から高い評価を得ているとともに、スポーツ健康コモンズを中心とした大学フロントゾーンの活性化にも大きな貢献をされている。
また、これらの教室を定期開講プログラムとするために、さらにプログラムの完成度を高めることを目的として、スポーツ健康科学部と連携しながら、新しいプログラムの開発に取り組まれるとともに、ご自身も社会人として働きながら大学院でさらに高度な学びをしようと、スポーツ健康科学研究科への進学を決意された。
このように、スポーツをもとに、子供と運動、地域と大学を強く結びつける行動力、さらにご自身の理想に向けて学び続ける姿勢は、スポーツ健康科学部のまさに輝く「星」として、在学生のロールモデルとしても、表彰されるに値する。
以上

表彰式の様子 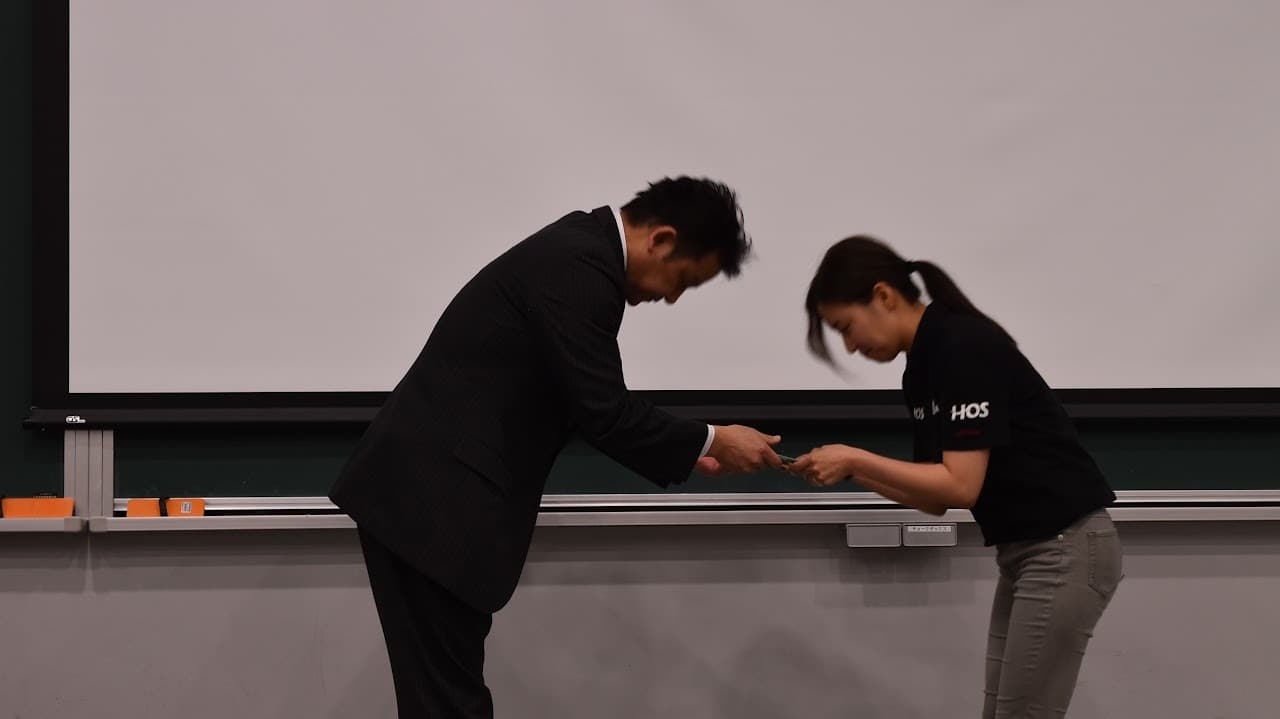
表彰式の様子 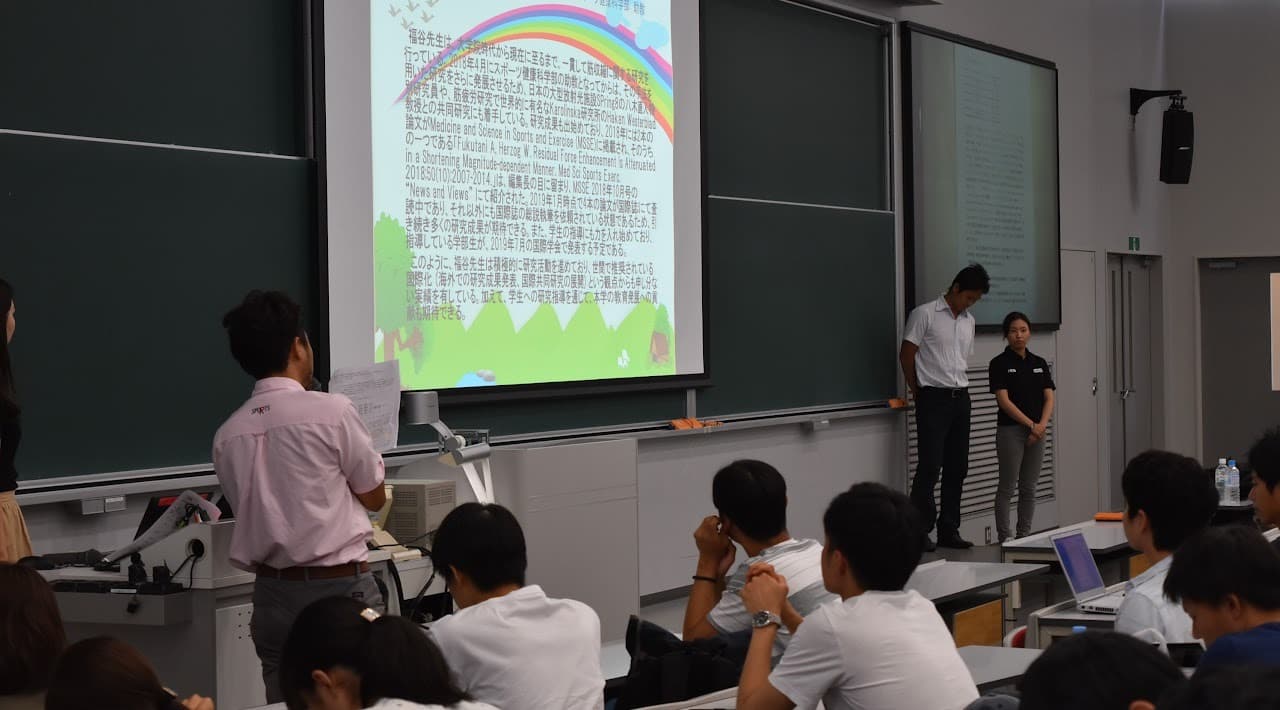
表彰式の様子 
表彰式の様子


日裏先生(北海道在住の為写真を送っていただきました) 
細川先生(東京都在住の為写真を送っていただきました)

岡松先生(別日にお渡ししました)