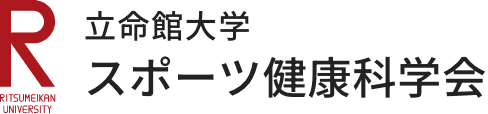News
ニュース
2019年度藍星賞受賞者
2019年度藍星賞受賞者リスト
- 1.研究部門 長谷川 夏輝
(立命館大学スポーツ健康科学部 研究員) - 2.教育部門 堀 美幸
(立命館法人 一貫教育部アスレティックトレーナー) - 3.国際部門 大塚 光雄
( 立命館大学 スポーツ健康科学部 助教) - 4.社会連携部門 佐藤 隆彦
(2016~2019 立命館大学 スポーツ健康科学部 助教)
1)長谷川氏は、2019年度、Experimental Gerontology誌に筆頭著者として「Aging-induced elevation in circulating complement C1q level is associated with arterial stiffness」を発表した。これまで、骨格筋の線維化に関わる補体とされたC1qが、加齢に伴う動脈硬化と関連することを横断研究によって明らかにしたものである。循環系疾患の理解を深める成果を挙げた当該功績は、研究部門における表彰に値する。
こうした精力的な研究活動と付随した研究業績に加え、今年学部・研究科開設10周年の節目を迎えるにあたって、学部・研究科、教職員すべてに対して実施した10周年記念ロゴの公募の中から、見事採択されたロゴを考案した。下記は、長谷川研究員がロゴに向けた想いである。まさしく、我々立命館大学スポーツ健康科学会員がこれまでを顧み、そして未来に向けて教育・研究活動を発展させていこうとする想いの縮図であり、藍星賞を受賞するにふさわしい功績である。
ロゴについて(長谷川氏より):立命館大学の学園ビジョン「挑戦をもっと自由に」のスローガンをもとに、スポ健10周年ロゴにもその在り方を示しています。スポ健に関わる人たちが、これまで歩んできた10年の歴史を感じるとともに、これからの10年でさらに未来を創造していくという意味合いを込め、10という数字を前面に出し、10周年であるという視認性を高めつつ、その中央に立命館の「R」を入れ込みました。また、さまざまな境界や自らの限界など、既存の枠を超えて未来をつくり出すという意味が込められた立命館のアイデンティティー「Beyond Borders」をロゴに記載するとともに、2本の線が「10」を突き抜けることで、これからのスポ健が10周年にとどまらず、さらに勢いよく世界に飛び出していく様子を表現しました。さらに、この角度の異なる2本の直線は頂点で1つに重なった形にも見えます。これは交わることがないと思われている2つの事象から1つの全く新しい発見・価値を生み出し、未来を拓いていくといった「創造と変革」や、スポ健の強みである、文理融合による総合的・学際的な教育および研究のイメージも表しています。
2)スポーツ庁は、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(2018.3)」において、運動部活動の合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組について示した。その中で、運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解すること、さらに、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行うことが望ましいとしている。
立命館附属学校は、運動部活動に意欲的に取り組んでおり、全国大会でも活躍をする部活動が多く、部活動を指導する教員等により熱心に指導されている。しかし、学校全体として組織的対応として、スポーツ医・科学の意見を取り入れ、競技力向上に取り組めていない部分もある。
堀氏は、ATC(Certified Athletic Trainer:米国公認アスレティックトレーナー)の資格を有しており、2019年度立命館大学附属学校を定期的に訪問され、運動クラブ活動に対して科学的・スポーツ医科学の知見を取り入れ、より効率的な指導のあり方を導入することにより選手の競技力向上に一層取り組みを行った。
具体的には立命館大学附属学校に対して下記の研修及び指導を積極的に行い、科学的なトレーニング指導や障害防止、運動部活動の組織に対する提言を行い、生徒・教員の運動部活動に対する意識変革及び主体的な運動部活動運営、短時間で効率的な活動について取り組むクラブが増加した。また、危機管理に対する提言を頂き、各附属学校に対して啓発・改善する取り組みを行う事ができた。
【附属学校に対する主な取り組み】
- 体育授業、運動クラブ活動における健康管理や組織運営あり方に関する指導
- クラブ活動指導者、競技者、マネージャーに対してスポーツ障害の予防及び再発予防についての啓発指導
- クラブ活動指導者、マネージャーに対してスポーツの現場での救急処置研修
- 運動クラブ活動に関する組織運営及び健康管理に関する研修
- 健康管理とクラブ組織運営のあり方に関する研修
- 指導者や選手をはじめ関係者に対する情報提供及び教育的指導
3)大塚氏は,国際スポーツバイオメカニクス学会において理事として同学会の運営を行うため,2019年3月に選挙に立候補した。推薦者は同時期に理事をしていたMarcus Lee博士であった。同学会に所属する世界中の会員によるインターネット投票の結果,選出された11名の理事の中に大塚氏が入ることができた。大塚氏は,2019年8月から2021年8月までの2年間,同学会における運営・企画をすることとなっている。
このように,国際的な学術機関をオーガナイズする大塚氏は,藍星賞を受賞するにふさわしい人物である。
4)佐藤氏は、京都府高等学校体育連盟理事長からの依頼を受け、京都府立鳥羽高等学校ウェイトリフティング部の科学サポートを行った。スポーツ健康科学部の研究機材を活用し、高等学校の指導現場では実施することの出来ない詳細なデータ取得を実施した。各選手から取得したデータを基に、フォーム改善に関わる専門的なフィードバックをバイオメカニクスの観点から行った。これらの成果を評価され、第54回全国高等学校体育連盟研究大会において、各発表者に個別のアドバイスを実施する助言者として招聘された。各発表に対して、研究デザインやデータの解釈について壇上で助言を行い、会場に赴いた高校体育連盟に所属する部活動顧問教員が研究的アプローチを行う上での示唆を与えた。各発表者への助言の後、全参加者に向け、近年の研究成果やバイオメカニクスの知識を交えた全体指導を実施した。このように、滋賀県で初めて開催された全国高等学校体育連盟研究大会の成功に大きく尽力した。加えて、スポーツ健康科学部においても、体験授業、サマースクール、ひらめきときめきサイエンス等において、専門的な実験機材を活用した学びを参加者に提供してきた。これらのアウトリーチ活動を通して、本学部と社会との連携を促した功績は表彰に値する。

長谷川氏が考案した10thロゴ 
2019年度受賞 大塚先生