マイクロソフト×立命館
試行錯誤の中で形づくられながら学生の可能性を掘り起こし、育てる
創発性人材育成プラットフォーム -
「QULTIVA(カルティバ)」でマイクロソフトと連携

OUTLINE
2025年6日13日午前。大阪いばらきキャンパスH棟のMicrosoft Base Ritsumeikanに、1人、また1人と、学生が集まってきました。彼らは、立命館がマイクロソフトと連携して取り組んでいる「QULTIVA」のメンバーです。普段はオンラインで動いているコミュニティですが、この日は、マイクロソフトの方がキャンパスへ来て、同社のAIアシスタントソフトMicrosoft Copilotの具体的な活用方法を直接説明してくれる貴重な機会とあって、最前列から席が埋まっていきました。オンライン参加の学生も多くいます。
この春から始動したマイクロソフトとの連携による「QULTIVA」は、マイクロソフトとメンバーそれぞれが試行錯誤しながら、マイクロソフトの製品、とりわけMicrosoft Copilotを使うことによってテクノロジーをビジネスや課題解決に活かす能力を育てるコミュニティとしての輪郭が浮かび上がりつつあります。さらに立命館の創発性人材育成プログラムであるQULTIVAを取り入れ、学生の可能性をさらに掘り起こすことも目指しています。
マイクロソフトとの連携によるQULTIVA 最新AIを活用した創発性人材育成プラットフォーム
EPISODE
EPISODE01
マイクソフトと学生の距離が
もっと近づけば
なにか新しい化学反応が起きるのでは?

2023年、立命館は、日本マイクロソフト株式会社と「連携・協力に関する協定書」を締結。2024年には、OIC新棟に、日本の教育機関で初めて「Microsoft Base Ritsumeikan」が設置されました。マイクロソフトが提供する製品・サービスを活用し、DXの実現やスタートアップ人材の育成に寄与するBase=発信基地として、学生のコワークキングスペースとしての利用や、常駐スタッフによる技術支援、マイクロソフト製品の体験型イベント、セミナーなどを行ってきました。
開設から1年。マイクロソフトと立命館の間で「マイクロソフトと学生の距離がもっと近づけば、なにか新しい化学反応が起きるのでは?」との期待が生まれ、それを実現するための検討が始まりました。Microsoft Corporation Worldwide Public SectorのEducation Industry Adviserで DX/AX戦略室長の阪口福太郎氏は話します。「オンラインを基本にしながら、チャンスがあればこのBaseも使ってできることはなんだろう?からスタートし、漠然と形になってきたのが、学生と社会人がより近い距離で刺激し合う『コミュニティの運営』でした」。
日本マイクロソフト株式会社 パブリックセクター事業本部 教育・社会基盤統括本部 教育戦略本部副本部長の石山氏は、マイクロソフトが大学でコミュニティを運営する意義を次のように語ります。「日本の課題である新しいビジネスの構築や人口減少の中での地域課題の解決に、大きな武器となるのがテクノロジーです。当社の製品を通して、テクノロジーをビジネスや課題解決に活かす能力、たとえうまくいかなくても試行錯誤できる能力を育てることにつながれば、単に当社のユーザーを広げるというだけでなく、日本の社会課題、ビジネス課題に対しての起点になり得る試みだと考えました」。
その時、立命館が提案したのは、独自の創発性人材育成プログラム「QULTIVA(カルティバ)」を、コミュニティの中で活用し、学生の能力をさらに掘り起こすことでした。「立命館さんも、試行錯誤しながら『QULTIVA』を活用されていると聞きました。我々も、「Microsoft Base Ritsumeikan」で多くの試行錯誤を重ねてきました。


じゃあ次は、それらを融合することもできるのではないかとの思いから、立命館とマイクロソフトが連携する『QULTIVA』というコミュニティを運営することで、私たちも試行錯誤してみようと考えました」(阪口氏)。立命館大学副学長で社会共創推進本部本部長の三宅雅人教授からも「ここはTRY FIELDです。失敗してもいいのでぜひ挑戦してください」との言葉がありました。「嬉しかったですね。だからこそ躊躇なく挑戦できたのだと思います」。
2025年4月、約80人の学生が参加して、マイクロソフトと連携して取り組む「QULTIVA」が始動しました。「マイクロソフトのツールを使いたい」「仲間を増やしたい」「起業を考えている」動機はさまざまですが、まだ明確な形のないコミュニティに飛び込んで、試行錯誤の中から何かをつかみたい、成長したいとの思いを持つメンバーたちです。
EPISODE02
自分の弱みを開示して人に助けを求める
その大切さを学び、
自分の殻を破ってほしい

対面とオンラインのハイブリッドで開催されたこの日のイベントでは、石山氏が、もし自分が起業を目指す学生だったらAIアシスタントをどのように使うかなどについて、具体的なシーンごとに紹介。阪口氏は、Microsoft CopilotとChat GPTの違い、そして、どんな場面では、どちらをどのように使うと良いかについて解説した後、Copilotに搭載されているツールの効果的な使い方についても詳しく紹介しました。講演後は、会場の学生からも、オンラインの学生からも、活発に質問が出ていました。
今、Teams上のコミュニティでは、「今、こんなことに興味を持っています」「こんなことをやりたいです」など、学生自身も手探りしながらの発信をしています。「やりたいこと」がある学生が、その実現を妨げる「自分にできないこと」に気づいたら?マイクロソフトのお二人は、まさにその点で学生の意識を変えたいと強調します。
「マイクロソフトでは、①自分の達成した成果②他者への貢献③他者の知見をどう活かしたか、この3つが評価の対象となります。人との信頼関係をいかに作るかも問われるのです。それが、影響力の拡大、ネットワークの拡大、そしてビジネスの拡大につながる。メンバーの皆さんには、その意識を今から持っておいてほしいと思います」(石山氏)。


「自力でなんとかしようと努力してきた学生の皆さんが、人の助けを借りたいと発信するのは怖いことかもしれません。誰もが『できる自分』でありたいでしょうから。でも、自分の弱みや自分に足りないことを積極的に開示して、人に助けてもらうのは、社会では当たり前のはずです。この『QULTIVA』では、そのことを学び、殻を破ってほしいと思っています」(阪口氏)。
すでに、自分から発信して周囲を巻き込んでいくことが、コミュニティを動かし、自分の成長にもつながるということを強く意識し、自分の殻を破り始めている学生もいます。創発性人材育成プログラムQULTIVAのコンセプトは「仲間とたがやすジブンとミライ」。
「今はまだ自分で自分をたがやしている学生さんが多いと思いますが、自分に足りないものを補ってくれる仲間と一緒にたがやすからこそ、1+1が2じゃなく、3にも4にもなる。ここは誰もがそれを体験できるコミュニティです」さらに「もっともっと学生さんとの距離を縮めたいですね。その時、学生さんの目線に合わせず、マイクロソフトの視点でコミュニケーションしようと思います。マイクロソフトはこんな見方でビジネスに取り組んでいるということにふれてほしいからです。もしかしたらレベルが高すぎてしんどいと感じる学生もいるかもしれません。でもしんどいと気づけたことに価値があると思ってもらえたらと思います。マイクロソフトは多様性を大切にし、多様な人がそれぞれの力を合わせることで価値が増大すると信じている会社です。ここで一人ひとりの学生さんが伸びたい方向に伸びていくのを応援できるならば、こんなに面白いことはありません」。


REFLECTION
プロジェクトを終えて、関わった方々の
振り返りをお聞きしました
-
Microsoft Corporation Worldwide Public Sector, Education、
Industry Adviser DX/AX戦略室長阪口 福太郎氏
マイクロソフトに入社後、一番思い知らされたのは「学びに終わりがない」ということでした。学生時代と違い、カリキュラムも教科書もありません。常に新しい何かが降ってきて、それを考える必要があります。全て一人でできるわけはありません。だから専門性というものができるし、専門性を保ち続けるためにすべての時間をそこに注ぐことになります。別の分野のことを知らなくても、同じように時間を使って専門性を保つ方と話すことで、新しい発想や着眼点に気づくこともできます。マイクロソフトの製品には毎年驚くような数の機能が追加されています。こんな時代にすべてのことを自分でやろうとすると、どこかで破綻がきてしまいます。他人から学ぶ、自分も他人にギブする。限りある時間の中で成果を上げるにはそれが必要だということを、このコミュニティの中で体感してほしいと思います。こんなに素晴らしい場所で学べるなんて、うらやましいの一言です。この環境をどう利用するのか、学生の皆さんに期待しています。

-
日本マイクロソフト株式会社
パブリックセクター事業本部 教育・社会基盤統括本部 教育戦略本部 副本部長石山 将氏
対面のイベントの価値というのは、仲間づくりであり、その仲間と一緒に創造性を発揮することでアイディアが創出されることにあると思います。今後も可能な限り対面でのイベントを開催したいですね。起業を考えている学生さんも多くおられました。今日お話ししたように、考えているだけではなく、とにかく挑戦してみる、試行回数をどんどん増やしていってほしいと思います。たとえ失敗したとしても、それは失敗ではなく、経験だということを理解してもらえたらと思います。

VOICE
イベント参加者の声
-
都香 貴央さん(経営学部 3回生)
自習スペースとして利用していたMicrosoft Base Ritsumeikanで、説明会を聴いたことが参加のきっかけです。立命館アジア太平洋大学(APU)に半年間の国内留学をしたことがあり、APUの学生や先生との距離をもっと縮めたいとも思っていたので、この『QULTIVA』への参加が1つのツールになるんじゃないかなと思いました。今日はMicrosoftの方が登壇される貴重な機会ですし、私自身もMicrosoft Copilotの使い方がまだ十分に理解できていないので、お話を聴きたいと思って参加しました。今後はAPUの方もこの『QULTIVA』に参加されると聞いたので、ぜひコミュニケーションをとりたいと思います。他学部の方との主体性ある意見交換ができる場として、マイクロソフトの方からのフィードバックをいただきながらセルフリフレクションもできる『QUALTIVA』の特性を活かしながら、さまざまなことに挑戦できたらと考えています。同じ学部の人とだけで閉じるのではなく、自分とは違う知見やスキルを持つ人からいろんな意見を聞いたり、自分にできない部分を助けてもらったりしながら、やりたいことを進めていきたいと考えています。

-
水口 歩実さん(経営学部 1回生)
正課外の活動をやってみたいと思っていた時に説明会があり、面白そうだなと思ったのが参加のきっかけです。Teamsの投稿内容をいつでも見られて、この人はこんなことに興味持ってるんだ、こんなこと頑張ってるんだと知ることが、私に大きな刺激とモチベーションを与えてくれています。私自身は、実はまだオンラインでのコミュニケーションに慣れていません。音声のタイムラグや、相手の表情が見えにくいことにまだ苦手意識があるので、これから慣れていきたいと思います。今後、物理的な距離のためにコミュニケーションをあきらめてしまうことがないように、まずはこの壁を乗り越えたいと思っています。今日は質問もしました。このような場での質問はやはり緊張しますが、グッと気持ちを上げて質問するようにしています。以前は、人に聞いたり頼ったりするのが少し苦手でしたが、今は、分からないことはすぐに聞くように努力しているところです。分からないことを恥じてしまうと、その後がどんどん苦しくなってしまうので、「私は1回生なんだから!」ということをモチベーションに、なんでも聞くようになりました。そうすると、相手の人の考えを知ることもできますし、「こういうことに困っている」と言ってもらえると、自分も動きやすくなるということもわかりました。最近、「今、こんなことを考えています」「こうしたいです」と自分から発信できる人に憧れています。せっかくこのような場を設けていただいているので、自分の考えや疑問を、もっともっと発信していきたいと思っています。

-
岡田 拓士さん(情報理工学部 4回生)
Microsoft Copilotが使えるのが魅力で説明会に参加したのですが、話を聞いているうちに、立命館を変えていく機会、ビジネス思考の考え方の人とつながれる機会など、自分にとって新しい機会と出会えるのではないかと考えて応募しました。今日はマイクロソフトの社員の方と直接お話しができる貴重な機会なので、対面で参加しました。今後の生成AIがどのように使われるか、どう対応していけばいいかという質問もして、ご意見を詳しく聞くことができました。「AIに使われる人間」ではなく「AIを使う人間」になれるように意識していきたいと思っています。

- 共催
-
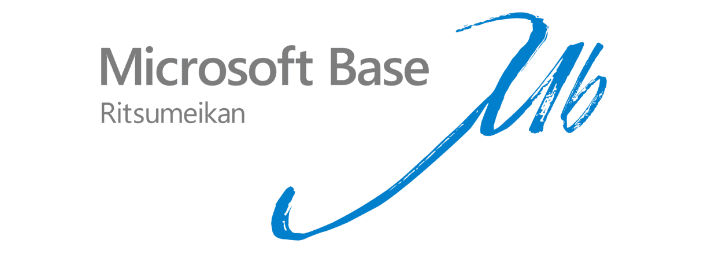

キーワード
- #Microsoft Base Ritsumeikan
- #QULTIVA
- #人材育成
- #自己啓発支援
- #スキルアップ
- #トレンド
- #ビジネスチャレンジ
- #スタートアップ
- #イノベーション
- #Copilot







