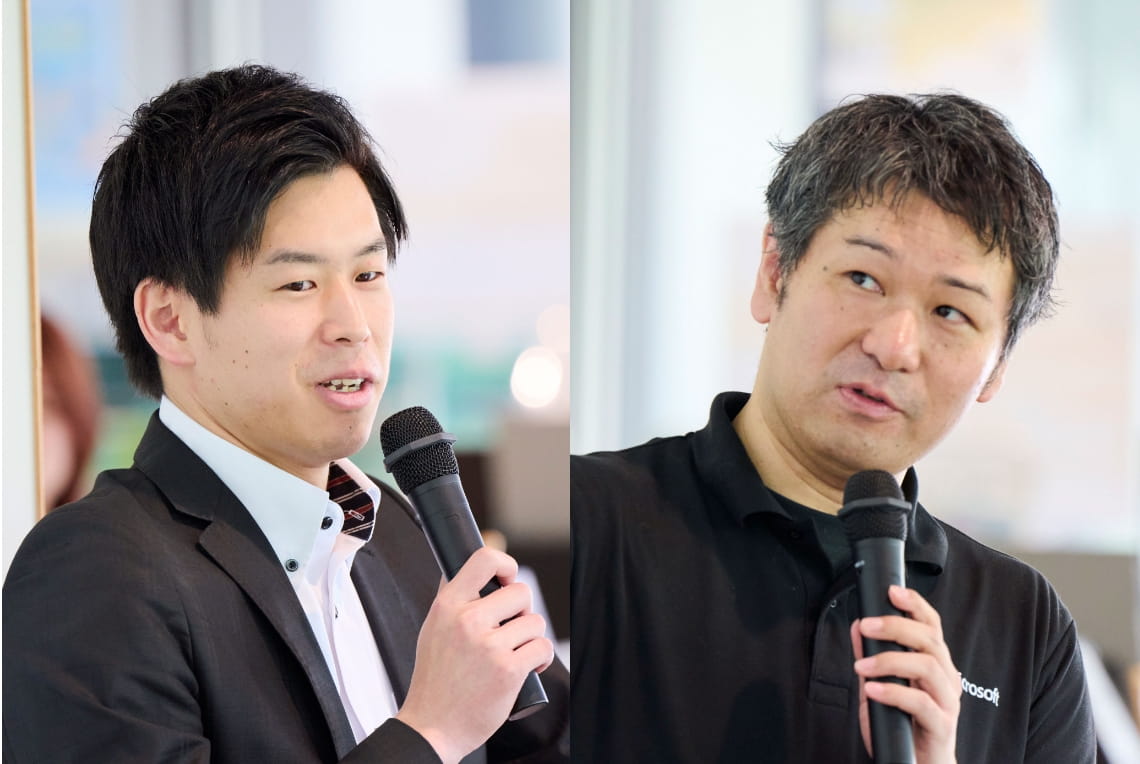マイクロソフト×立命館
生成AIの最新動向と未来予測を知り、考え、交流する
生成AI最前線2025~ビジネスと創造の未来を拓く~
Microsoft Base Ritsumeikanで開催

OUTLINE
2024年4月に日本の教育機関に初めて設置されたMicrosoft Base Ritsumeikanは、日本マイクロソフト株式会社より運営を委託されたカコムス株式会社により、これまでに数多くのイベントを開催してきました。立命館大学の学生や教職員だけでなく、一般の方、自治体の方も参加できるイベントはすでに150を超え、参加者数も累計で2700人を超えています。
2025年6月13日に開催されたイベントは「生成AI最前線2025~ビジネスと創造の未来を拓く~」。5月に米シアトルで開催されたばかりの開発者向け大型イベント「Microsoft Build 2025」で発表された内容をはじめ、まさに最新の生成AI技術の動向、実際の活用事例、今後の可能性について、マイクロソフト社のエバンジェリストによる解説が聞ける機会です。IT分野の動向を長く見続けてきた方々によるパネルディスカッションもあり、学生や教職員だけでなく、企業で技術を担当する方、生成AIに関心のある方など、多くの方が参加されていました。
梅雨の晴れ間で、入口をフルオープンにしたMicrosoft Base Ritsumeikanには心地よい空気が流れていました。参加者に美味しいコーヒーを提供しようと準備する立命館大学コーヒー研究会の皆さんのテーブルからは、香ばしいコーヒー豆の香りも漂っていました。
この日のイベントの内容を、順を追ってご紹介しましょう。
生成AIの最新動向と未来予測を知り、考え、人と交流するイベント Microsoft Base Ritsumeikanで開催
EPISODE
EPISODE01
全国30カ所の
Microsoft Baseから5拠点が報告
Microsoft Base Ritsumeikanの
運営状況も紹介

司会を務めるのは、カコムス株式会社の朝山悟氏。昨秋からMicrosoft Base Ritsumeikan に常駐し、利用者の相談にも応じているので、立命館の学生や教員にとってはおなじみの方です。
初めに、日本全国に30ケ所(2025年6月時点)あるMicrosoft Baseのうち、Microsoft Base Nagano、Microsoft Base Kanazawa、Microsoft Base Nishi-Umeda、Microsoft Base Ritsumeikan、Microsoft Base Kobeの5拠点から、どのような運営会社が、どのようなサービスを提供しているかについて、オンラインと対面での報告がありました。それぞれの地域や運営会社の特性によって、コンセプトや注力するサービスのあり方が少しずつ違うことが興味深い内容でした。
朝山氏によるMicrosoft Base Ritsumeikanの紹介では、立命館大学のTRY FIELDというコンセプトに共感したこと、なにかに挑戦しようとしている人に、マイクロソフトの技術を使ってどんなサポートできるのだろうかということを日々自問自答しながら活動しているというお話がありました。ワークスペースとして誰もが無料で利用できること、技術的なサポートが受けられること、AIをはじめとする新しい技術を知りたい、ビジネスに活かしたいといった相談も受け付けていること、立命館大学によってこれらがすべて無料で提供されていることなども紹介されました。
Microsoft Base Kobeの紹介をした神戸デジタルラボの衛藤昴氏は、走高跳で五輪出場経験もある選手でもあります。衛藤氏に対してAIを用いたフォームの分析システムで支援しているMicrosoft AI Co-Innovation Lab Kobeからも、同ラボの紹介と、支援内容についてのお話がありました。
休憩時間には、コーヒーを提供してくれた立命館コーヒー研究会RCSから、活動内容の紹介と、この日のコーヒーについての説明もありました。こだわりぬいた高級豆を使った香り高いコーヒーを提供してくれたRCSの皆さんに温かい拍手が送られました。

EPISODE02
AIエージェントが複数タスクを
自律的に解決する時代
「人間は面白いプロダクトづくりに
集中できる」

このイベントの2大セッションの1つが、「マイクロソフトが提供する生成AI最新ソリューションご紹介&最新の事例アップデート」と題した、マイクロソフト社による最新生成AI技術のプレゼンテーションです。まずはCloud & AI プラットフォーム統括本部 第一Azureソリューション本部長の織田開智氏が、同社のソリューショントに、マイクロソフトの生成AIである Copilotの機能が次々と組み込まれていることを紹介。WordやExcelの上で、ユーザーと対話しながらデータをきれいにまとめたり、PowerPointのシートを制作したりできること、さらには指示がなくても自律的に判断して作業できるようになっていることを、簡単なデモによって示しました。
次に、マイクロソフトの技術や製品に関する情報を開発者やコミュニティと共有する役割を担うマイクロソフトエバンジェリストでDigital Native Unit Account Executiveの佐竹祐亮氏が、5月に米シアトルで開催された開発者向け大型イベント「Microsoft Build 2025」で発表されたコンセプト「オープン・エージェンティック・ウェブ」を紹介。その中心にあるのが「AIエージェント」というキーワードです。
「デジタルおよびリアルの環境で状況を知覚し、意思決定を下しアクションを起こし目的を達成するためにAIの技法を適用する自律的または反自律的なソフトウェア」と定義されていて、ユーザーが細かく指示する必要もなく、情報ソースを探しながらプロアクティブにタスクをこなしてくれるもの。今、その精度が飛躍的に向上しつつあると佐竹氏は話しました。


最新の動向として、複数のエージェントがそれぞれ専門的に動き、かつそれらをまとめるオーケストレイトと呼ばれるエージェントが、エージェント同士のミーティングをファシリテイトして結論を出す、つまり、複数のタスクを協力して解決することもできるようになっているとのお話もありました。
プログラマ向けのサービスであるGitHub Copilotにもコーディングエージェントという機能が搭載され、誰もが自然言語を使って簡単にアプリを作れる時代になったこと、システム保守の領域においてもSRE エージェントが機能する世界が目の前にあることが紹介されました。「人間は、どのような価値を顧客に届けるか、いかに面白いプロダクトを作るかに集中して仕事を楽しむことができる世界がやってくると思います」佐竹氏はこう話を締めくくりました。
EPISODE03
「言語化の能力とアウトプットがさらに重要になる」(小杉氏)
「AI脅威論があっても、恐れず自分で使い続けることが大切」 (上原教授)

最後のセッションは、日本マイクロソフトの業務執行役員Cloud & AIプラットフォーム統括本部長である小杉靖氏と、立命館大学情報理工学部の上原哲太郎教授によるパネルディスカッションです。生成AIの普及に対して、「年齢に関係なく社会変革を興せる時代」(小杉氏) 、「若い人には、エキサイティングな時代に生まれたこと感じてほしい」(上原教授)との見方を示したお二人。
教育現場での活用は?との質問に上原教授は「立命館大学は生成AIをポジティブにとらえた大学の一つだったと思います」と話し、レポートなどへの活用に制限はせず、論文の引用と同じく、どの生成AIに対して、どのようなプロンプトを入力し、結果をどのように使ったかを明記するよう指示していることを紹介しました。
生成AIの未来については、「ビジネスにおいて人への投資が抑制され、デジタル技術への投資が増大していくのではないか」(小杉氏)、「現在は主にビジネス向けに開発されているが、教育に使えるものが求められていると思う」(上原教授)。
生成AIの印象的な使い方として、上原教授は、大阪大学の石黒浩教授が、自分のアンドロイドに自著を学習させて取材に応じていることをあげると、小杉氏は、石黒教授が膨大なアウトプットをデータで行ってきた点が重要だと指摘し、言語化の能力とアウトプットがさらに重要になってくるのではないかと話しました。


オンラインをふくむ参加者に向け、小杉氏は「倫理面の危惧はあっても、生成AIをきちんと使いこなすことが、技術を社会貢献に結びつける道を見出すことにつながる。自分自身で体験して慣れることが大切。そのためにもマイクロソフトの製品を使っていただきたい」と話し、上原教授は「AI脅威論があるが、恐れず使い続けることが大切。一方で、「人間にはAIより賢くあり続けるための努力が求められている。AIにできない能力を磨き続けることが大切」とのメッセージを伝えました。
イベントの最後はネットワーキングの時間です。参加者も、立命館の教職員も、マイクロソフトの皆さんも、ドリンクと軽食を手に自由なコミュニケーションを楽しんでいました。

REFLECTION
プロジェクトを終えて、関わった方々の
振り返りをお聞きしました
-
立命館大学 情報理工学部
上原 哲太郎教授
OICは、情報環境としても学習環境としても非常によく考えられたキャンパスだと思います。学生の皆さんにはその環境の素晴らしさを自覚してしっかり学んでいただくとともに、Microsoft Base Ritsumeikanという全国唯一のシステムをしっかり活用してほしいと思います。学生の皆さんにとっての宝は時間であり、機会であり、出会いであるというと思います。Microsoft Base Ritsumeikanは常にオープンで、授業の合間にも行けますし、さまざまなイベントも開催されています。活用することによって、学部の中だけではない学びが広がっていくと思います。

-
日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員
Cloud & AIプラットフォーム統括本部長小杉 靖氏
ディスカッションの中で、上原先生がお考えになっていること、教育現場で今求められていることについて、私自身もすごく考えさせられました。マイクロソフトの営利目的だけではない未来に対する責任として、また私個人としても、このような教育現場に対して何ができるか?を考えるきっかけになりました。また、マイクロソフトの社員として、このような素晴らしい環境にMicrosoft Baseがあるとことを嬉しく思いました。ネットの情報が氾濫している中で、大事なのは一次情報をどれだけ取れるかだと思います。Microsoft Base Ritsumeikanに行けば、マイクロソフトという世界の中で、どのようなソリュ―ションが提供されているか、今後どのような世界を見すえているかを直接知ることができるでしょう。リアルな場で、実際にそれを使われている方々と一緒に話をすることによって得られるものが一番いいと思います。ぜひ多くの学生さんに来ていただきたいと思います。

-
日本マイクロソフト株式会社
Cloud & AI プラットフォーム統括本部
第一Azureソリューション本部長織田 開智氏
Microsoft Base Ritsumeikanさんと一緒に今回のイベントを企画しました。立命館大学に来て、地域の方との距離の近さを感じました。届けたいメッセージを、大学というハブを通して広く届けられるのではないかと思いました。
AIの時代にあってマイクロソフトが大事に考えているのは人と人とのつながりです。こうして地域の方も歩かれているキャンパスで、Microsoft Base Ritsumeikanが無料で開放されていることがすごく魅力的だと感じます。コミュニティに所属し、人とつながることの価値がますます高まっていく世の中で、そこがMicrosoft Base Ritsumeikanの魅力だなと思いました。
このような環境で学んでいるデジタルネイティブの学生さんたちとこれから一緒に働くということを改めて意識し、気合を入れてしっかり学び続けなければいけないと感じたことが私自身の大きな気づきでした。
-
日本マイクロソフト株式会社 Digital Native Unit Account Executive
佐竹 祐亮氏
普段は企業の方に向けてお話しすることが多いのですが、今日は学生さんもたくさんいらっしゃるということで、働くことの楽しさを伝えようと、将来に向けた話もさせていただきました。とても楽しい登壇でした。
Microsoft Base Ritsumeikanは、開放的で、素晴らしいロケーションと雰囲気ですね。H棟の見学もさせていただき、非常に恵まれた環境だと感じました。気軽に企業様とのつながりが持てるという点でもメリットが大きいと思います。今後も機会があればぜひ登壇させていただきたいですし、立命館の学生さんと、今後のキャリアや仕事の進め方などのお話とができるような機会があればありがたいです。
-
Microsoft AI Co-Innovation Lab Kobe 所長
友井 貴士氏
参加している学生の皆さんのいきいきした表情を見ていると、私も非常に嬉しくなりました。神戸のラボで開催したハッカソンに参加してくだった立命館の学生さんが、楽しそうに成果報告をされていたのも良かったですね。学生の皆さんには、恵まれた環境があるというところを認識していただき、ぜひ今後ともですね、有効に活用していただければと思っています。
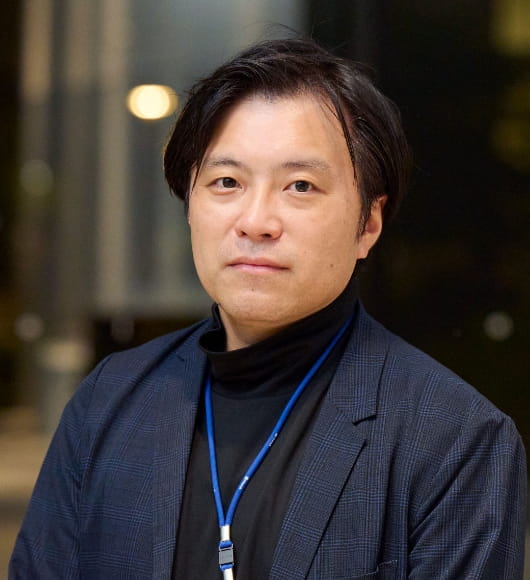
-
Microsoft Base Ritsumeikan運営 カコムス株式会社 グループ戦略統括本部 研究開発室長
朝山 悟氏
オンライン参加をふくむ260名の方に予約をいただき、多くの方にお話を聴いていただけたことがとても嬉しく思いました。パネルディスカッションでの「アウトプットをしっかり出していこう」というお話が非常に響きました。このイベントが、生成AIを使ってどんどんアウトプットするきっかけになっていたらいいなと思います。セキュリティなどの問題もありますが、それを周囲からながめて考えるのではなく、自分で体験する中から気づきを得ていってほしいと思います。このベースには、普段から多くの学生さんが「こんなことがやりたい」と相談に来てくれています。我々のサポートにプラスして、生成AIもうまく利用できるということを今日は伝えられたかなと感じています。
昨年の10月にMicrosoft Base Ritsumeikanへ着任した時、私はTRY FIELDのコンセプトに涙を流すほど感動し、こんなにすごいことを考える大学で、地域も巻き込んで何かを生み出せる場所があるということにも心を動かされました。TRY FIELDに寄り沿い、情報発信をしながら、創発性人材を育成することのサポートをやっていきたい、そこから生まれるものに関わっていきたいと考えています。
VOICE
イベント参加者の声
-
学生:経営学部3回生
サークル活動で普段から利用させていただいています。大学のMicrosoft Baseはここにしかないという価値もあると思いますし、目につきやすい場所で、イベント時にもかなり人を集められる点でもありがたい環境です。開発に関わる難しい話はよくわかりませんでしたが、AIを活用することはできるんじゃないかと思います。
-
学生:情報理工学部2回生
AIに関心があり、その技術を実際に職場でどう使っているのか、これからAI技術がどうなるかが気になって参加しました。課題の資料づくりや試験勉強に生成AIをよく使っています。
印象にのこったお話がたくさんありました。Copilotの実際の使い方、AIが生成したものをエージェントAIが判定する話などが時に興味深かったです。 -
製造業開発職:50歳代
開放的な雰囲気の場所ですね。一般の人も無料で使えるのもいいと思います。
今後、何事にもAIのウエイトが増え、使っている人と使えない人の差がどんどん開いていくんだろうなと思いました。ある程度のキャッチアップが必要なのだと思います。私自身は生成AIを仕事の中で毎日のように使っています。各社から良いものが出てきて、精度も上がってきていると感じています。内容よってはまたこのようなイベントに参加したいと思います。 -
コンサルティング会社勤務:30歳代
立命館大学政策科学部の卒業生です。仕事の中で最新技術を活用してデジタルのものを作ることが多いので、今日はMicrosoft Build 2025の紹介に興味があって参加しました。特に印象に残ったのは、最新技術をビジネスや日常生活の場面でどんな使い方をするかを具体的に紹介いただけたことと、AIの進化が人間の価値をどう変えるかのようなお話を聞けたことです。興味があるトピックの時はまた参加したいです。
- 共催
-

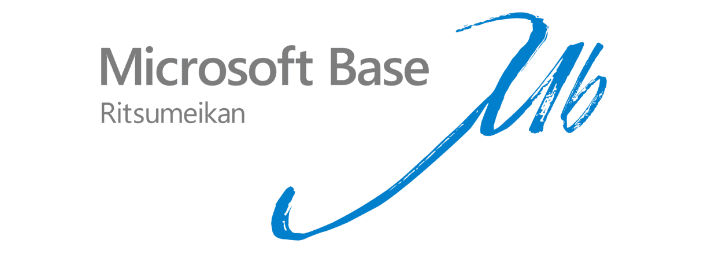

キーワード
- #Microsoft Base Ritsumeikan
- #人材育成
- #自己啓発支援
- #スキルアップ
- #トレンド
- #就活
- #ビジネスチャレンジ
- #学生グループ
- #スタートアップ
- #イノベーション
- #人脈形成
- #Copilot