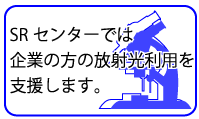Home > 成果報告(Published Papers)
- >最新の論文
- >最近の連絡のあった学会発表
- >受賞
最新の論文(Published Papers)
横浜国立大学にAshraf Abdel Haleem助教、光島重徳教授、京都大学の内本喜晴教授らと立命館大学生命科学部の折笠有基教授の共研究グループが当センターBL-11を利用した成果をACS Applied Materials & Interfacesに発表されました。
Accelerated Durability Assessment and a Proposed Degradation Mechanism of NiCoOx OER Catalysts under Simulated Intermittent Renewable Power: Insights from XAS
Abdel Haleem, A.; Enjoji, H.; Gu, K.; Miwa, T.; Kuroda, Y.; Orikasa, Y.; Uchiyama, T.; Uchimoto, Y.; Mitsushima, S.,
ACS Appl Mater Interfaces 2025.DOI:10.1021/acsami.5c10518
本研究は、太陽光や風力といった再生可能エネルギー源(RES)の本質的な間欠性がもたらす課題に対応し、効率的なエネルギーキャリアであるグリーン水素の製造を促進することを目的に行われました。グリーン水素製造において広く用いられるアルカリ水電解(AWE)システムでは、電力供給の変動が電極の耐久性低下と寿命短縮を引き起こすため、動的運転条件下での電極の長期安定性確保が極めて重要です。そこで、より現実的な新しい加速劣化試験プロトコルの開発し、現実の劣化過程を再現することに成功しました。電気化学的測定とX線吸収分光法(XAS)を組み合わせたところ、触媒劣化の主なメカニズムは、Niが主要な活性サイトとして機能する一方で、Coイオンの優先的な溶出と、それに続く表面構造再構成および基板からの剥離であることを明らかにしました。この研究により次世代電極材料の開発指針を提供することができました。
立命館大学総合科学技術研究機構SRセンターではBL-11 軟X線ビームラインが使われ、Ni,CoのL吸収端を同時測定することで、Coが優先的に溶出していることを明らかにしました。
ACS Applied Energy Materials に山口大学大学院創成科学研究科の中山 雅晴教授らのグループ、大阪大学産業科学研究所の片山 祐准教授らのグループそしてファインセラミックセンターの桑原 彰秀主席研究員らの研究グループが、電気自動車用革新型蓄電池開発Rising3のプロジェクトで、当センターBL3を利用した成果を発表されました。当センターでは、入澤 明典准教授、朝倉 清高教授が研究に参加し、協力しました。
An Fe3+-Responsive MnO2/Mn2+Cathode for Zinc-Ion Batteries: Fe3+ Incorporated into MnO2 during Charging Accelerates its Dissolution during Discharging
Koki Obuchi, Jin Kitamura, Misaki Ando, Kota Kamo, Kota Nakamura, Eiki Mukayabu, Tomohiko Utsunomiya, Yasuyuki Kondo, Yuki Sasaki, Kaname Yoshida, Yuki Yamada, Akinori Irizawa, Akihide Kuwabara, Wataru Yoshida, Kiyotaka Asakura, Yu Katayama, Masaharu Nakayama
ACS Applied Energy Materials (DOI:10.1021/acsaem.5c01923)
本論文は、穏やかな酸性酢酸緩衝液を用いた亜鉛イオン電池向けのFe3+応答型MnO2/Mn2+カソードシステムを提案したものです。充電中にMnO2マトリックスへFe3+が組み込まれ、これが固相レドックスメディエーターとして機能し、放電時に生成する不活性なMn3+中間相の完全な溶解を促進することがわかりました。この新規メカニズムは、自己放電を抑制しつつ、909 Wh kg-1の高いエネルギー密度と優れた可逆性(5 mAh cm-2の高面積容量)を達成することができました。立命館SRセンターは、シンクロトロン放射光を利用し、BL-3でX線吸収スペクトル(XAS)を透過モードで取得しました。これにより、電極上の充電・放電中のマンガンの酸化状態や溶解量を分析を行いました。
Applied Surface Scienceに本学理工学部の村田順二教授と滝沢優教授らの研究グループが当センターBL-7,BL-13 を利用した共同研究を発表されました。
Liquid-free electrochemical approach for direct patterning of ITO films with polymer electrolyte stamps for flexible transparent electrodes
Shimpei Hayakawa, Masaru Takizawa, Daishi Hakozaki, Junji Murata
Applied Surface Science,716(2026)164674: DOI:10.1016/j.apsusc.2025.164674
柔軟で透明な電極に不可欠なITO(酸化インジウムスズ)膜に対し、液体フリーの固相電気化学的還元に基づいた直接的なパターニング手法を提案しました。高分子電解質膜 (PEM) スタンプを用いてITO膜(陰極)を直接エッチングする新しい方法です。フォトリソグラフィや液体電解質を用いた従来の方法に比べ、低コスト、低環境負荷で、室温でマスクレスかつ直接的にパターン形成を可能とした方法です。特に、酸化物材料(ITO)の電気化学的エッチング(還元)に基づくパターニングを固相—固相界面で実現した初の方法です。当研究センターでは、BL-7で表面処理後の表面化学分析がXPSを用いて行われ、BL‐13で行われたXANES測定により負のバイアス(還元処理)を受けたITO表面において、酸化インジウムが金属状態に還元されていることを明確に実証することができました。
ACS Applied Energy Materials に奈良女子大学の原田雅史先生らの研究グループが当センターBL-11 を利用したCoMnスピネル酸化物電極反応の研究(S21001, S22005, S22018)を発表されました。
In Situ Observations of Catalytically Active Sites of Cobalt-Manganese Spinel Oxides as Efficient Bifunctional Electrocatalysts for Oxygen Evolution and Reduction Reactions
Harada Masafumi; Saito Ayumi; Nakahira Honoka; Mori Yuki; Kawaguchi Shogo
ACS Appl. Energy Mater.(2025)DOI: 10.1021/acsaem.5c01571
原田雅史先生らの研究グループはコバルト-マンガン(CoMn)スピネル酸化物 電極触媒をマイクロ波アシスト合成とそれに続く低温焼成によって調製されました。先進的なエネルギー変換技術を開発するためには、電気化学条件下での酸素発生反応 (OER) および酸素還元反応 (ORR) の触媒活性サイトを特定する必要があります。本研究では、最先端放射光を用いた粉末X線回折、軟X線および硬X線吸収分光法 (XAS)、および異なる印加電位下でのin situ XAS測定が行われ、電極触媒作用中のこれらの触媒活性サイトの構造変化が調べられました。OERの活性サイトはORRのそれとは異なり、OERはCo-OOH、ORRはMn-OOHが重要活性種と判明しました。当センターのBL-11でMn,CoのL23吸収端、OのK吸収端のXAFSがTEYモードで測定され、ORR条件下では、Mn L2,3の約643.1 eVに新しい強いピークが出現し、また、O K-XAFSでは、0.30 Vの印加電位で531.5 eVにピークが観察され、これによりMn−OOH活性種の存在が示唆されました。
Journal of American Chemical Society に横浜国立大学藪内直明教授の研究グループが当センターBL13を利用した共同研究(成果公開型S22003)の成果を発表しました。当センターでは、柴田大輔助教、入澤 明典准教授、太田俊明上席研究員が研究グループに参加し、協力しました。
Activation of Anionic Redox for Stoichiometric and Li-Excess Metal Sulfides through Structural Disordering: Joint Experimental and Theoretical Study
Shinoda, M.; Matsunoshita, K.; Nakayama, M.; Hiroi, S.; Ohara, K.; Abe, M.; Ishiguro, N.; Takahashi, Y.; Hasegawa, G.; Kuwata, N.; Iwama, T.; Masuda, T.; Suzuki, K.; Ishii, H.; Shao, Y. C.; Shibata, D.; Irizawa, A.; Ohta, T.; Konuma, I.; Ohno, T.; Ugata, Y.; Yabuuchi, N.
J. Am. Chem. Soc., (2025) DOI: 10.1021/jacs.5c04018
2次電池の高性能化は電気自動車普及のための喫緊の課題です。従来の酸化物型に変わる硫化物型を利用したリチウム電池では、アニオンレドックスが進行しやすいことが期待されます。酸化物型と異なり、硫化物型では、層状構造では性能を示さず、無秩序型構造が高い性能を示すことがわかっています。研究チームは、in situ XRD, HAXPES,XAFS,PDF解析, Li-NMR, SQUID,DFTを駆使し、無秩序型構造が高活性になる要因を明らかにしました。この成果はアニオンレドックスを活用した高エネルギー密度正極材料の開発に有用な指針となると期待されます。当研究センターは、BL13において、SとTiのK吸収端XAFS測定を実施し、成果に貢献いたしました。
Journal of Power Sourcesに京都大学大学院エネルギー科学研究科の黄 珍光助教、松本 一彦教授、立命館大学生命化学研究部 折笠 有基教授、当センター 家路 豊成准教授らが当センターを利用した共同研究(成果公開型 S23023)の成果を発表されました
Overlooked issues on oxidation state analysis in electrode materials by X-ray photoelectron spectroscopy
Shaoning Zhang, Jinkwang Hwang, Keisuke Murakami, Chengchao Zhong, Toyonari Yaji, Yuki Orikasa, Kazuhiko Matsumoto;
Journal of Power Sources 644 237093 (2025) DOI: 10.1016/j.jpowsour.2025.237093
XPSは物質中の化学種の化学状態を知ることができる有力な手法ですが,表面の情報に敏感であり,不純物等に影響を受けます.そこで,表面を清浄化する目的でスパッタリングが良く行われます.研究グループはNb2O5を活物質とする電池電極をXPSで調べました.Arスパッタリングをすると,電極に含まれる活物質の状態が変化し,誤った結論を導く可能性があることをこの論文では指摘し,広く警鐘を鳴らしました.研究グループはこれに代わる手法として,XANES法やArクラスタースパッタリングという温和な清浄法を提案しました.当センターは,NbのL3 吸収端測定で貢献いたしました.
Beilstein Journal of Nanotechnologyに量子科学技術研究開発機構の圓谷志郎上席研究員と立命館大学理工学部の滝沢優教授らが、当センターを利用した共同研究(成果公開型S18026,S20009)の成果を発表されました
Single-layer graphene oxide film grown on α-Al2O3(0001) for use as an adsorbent
Entani, Shiro; Honda, Mitsunori; Takizawa, Masaru; Kohda, Makoto
Beilstein Journal of Nanotechnology 16 1082-1087 (2025) DOI: 10.3762/bjnano.16.79
酸化グラフェンは高表面積を有し、放射性同位元素を含む様々な金属イオンを吸着する素材として注目されています。酸化グラフェンそれ自体は、凝集したりして吸着過程を調べるのに適していませんでした。筆者らは、単結晶Al2O3(0001)面に酸化グラフェンを成長させ、その表面をキャラクタリゼーションし、Cs+の吸着挙動を調べたところ、高い吸着能を示し、吸着サイトは、水酸基やカルボキシル基などの酸素官能基でプロトンとのイオン交換で吸着することを明らかにしました。当センターでCとOのK端XAFS測定が行われ、532.7eVにCs-Oに由来するピークを観測しました。さらにそのCs-O結合が酸化グラフェンシートに対してやや立った構造であることを明らかにしました。この研究は今後のCsの除去プロセスの効率化につながり、放射性廃棄物の環境への影響を軽減することにつながると期待されます。
Materials Advances のオンライン版に 理工学部 村田順二先生、滝沢優先生らによる 当センターを利用した共同研究の成果が掲載されました
Maskless soft lithography for fabricating micro- and nanoscale Ag structures via solid-state electrochemical etching using a polymer electrolyte membrane for optoelectronic and sensing applications
Tatsuya Fujii , Daishi Hakozaki , Atsuki Tsuji , Masaru Takizawa and Junji Murata
Materials Advances (2025) DOI: 10.1039/D5MA00218D
マイクロ/ナノ構造を持つ銀(Ag)表面は、透明導電膜や高感度プラズモニックセンサーの有望な候補とされています。本研究では、ポリマー電解質膜(PEM)スタンプを用いた固体電気分解により、直接的で、簡便かつ低コストなパターニング手法を開発しました。形成されたパターン表面は光透過性が向上しており、フレキシブルな透明導電膜や表面増強ラマン分光法(SERS)基板への応用が期待されます。
当センターでは、BL7によるXSP測定とBL13によるXAS測定により、出来上がったAgナノパターンの状態が金属状であること。ポリマー電解質が不純物として表面に残らないことを明らかにしました。
J.Amer. Ceram. Soc. のオンライン版に滋賀県立大学山田明寛先生、松岡純先生らと当研究センター 柴田大輔先生の共同研究が掲載されました
Synthesis and structure of anisotropic borosilicate glasses under differential stress at high pressure and temperature
Taniguchi Shingo , Yamada Akihiro , Tomohiro Ohuchi , Koji Ohara , Daisuke Shibata , Mizuki Nishiwaki , Jun Matsuoka
Journal of the American Ceramic Society (2025) DOI:10.1111/jace.70040
高圧下で、ガラス転移点以下の温度域においてガラスに差応力を加えることで、大きな複屈折を示すホウケイ酸塩ガラスの合成に成功した。また、当研究センターで測定したB K-edge吸収スペクトルの解析により、平面三角形配位のホウ素が差応力によって配向することで、ガラス内部に高い異方性が生じていることが明らかとなった。
Gels誌に京都府立医科大学の足立哲也先生、当センターの家路 豊成先生との共同研究論文が掲載されました
Spectroscopic Analysis of the Extracellular Matrix in Naked Mole-Rat Temporomandibular Joints
Tetsuya Adach, Hayata Imamura,Toyonari Yaji, Kentaro Mochizuki , Wenliang Zhu , Satoru Shindo ,Shunichi Shibata , Keiji Adachi ,Toshiro Yamamoto , Fumishige Oseko , Osam Mazda , Kyoko Miura ,Toshihisa Kawai and Giuseppe Pezzotti
Gels 11(6) 414 (2025).
ハダカデバネズミは最大寿命が37歳と非常に長寿のげっ歯類であり、細胞の老化や組織の老化はほとんど見られません。本研究では、ハダカデバネズミの顎関節の細胞外マトリックスを分子レベルで解析し、老化防止に関与する分子とその局在を探りました。様々な分光学的手法と人工知能(AI)を用いて、ハダカデバネズミの関節円板(顎の開け閉めをスムーズにするクッション)は、ヒアルロン酸とコラーゲン線維が様々な方向性を持つ軟骨様組織で構成されていることを発見し、これが機械的応力を緩和し、下顎頭を保護していると考えています。本センターにある放射光を利用したFT-IR mappingにより、ハダカデバネズミの関節円板にグリコサミングリカンの一種であるヒアルロン酸が存在することを明らかにしました。今回の発見は、顎関節症(口を大きく開けられなくなる症状)の治療法や予防法の開発に役立つと期待されています。
Optical Materials のJournal Pre-Proof に鈴鹿高専の和田憲幸先生、当センターの家路豊成先生、小島一男先生、新居浜高専の朝日太郎先生との共同研究論文が掲載されました
Glass compositional dependence of In+-center concentration and fluorescence spectral properties in In3+-doped and Mn2+-co-doped phosphate glasses
Noriyuki Wada, Kaito Akiyama, You Yamashita, Toyonari Yaji, Kazuo Kojima, Taro Asahi
Optical Materials 165 (2025) 117165.
リン酸塩ガラスのMnは紫外光により赤色発光します。本論文は活性化助剤として働くIn+を高濃度に含むリン酸塩ガラスの組成を検討されたものです。本センターのBL10を用いて、Inの局所構造が調べました。
Journal of Physical Chemistry CのWeb版に当センターの朝倉清高センター長が 北海道大学、名古屋大学、ICUとの共同研究の論文が掲載されました
3D Precise Structure Determination of Single-Atom Cu Species on TiO2 Using Polarization-Dependent Total Reflection Fluorescent X-ray Absorption Fine Structure Empowered by Chemically Constrained Micro Reverse Monte Carlo and Density Functional Theory
Yunli Lin, Kai Oshiro, Jun-ya Hasegawa, Satoru Takakusagi, Wang-Jae Chun, Masao Tabuchi, and Kiyotaka Asakura
The Journal of Physical Chemistry C 129 8193-8205.
担体上の単原子で高分散した単原子触媒は100%原子効率を示す触媒として注目されていますが、その立体構造を精密に決める手段はありません。この研究では、単結晶酸化物担体をThiophene Carbonic Acidで修飾することで、Cuの単原子触媒を調製し、その3次元立体構造を偏光全反射蛍光XAFSスペクトルを、新たに開発した化学構造拘束条件マイクロ逆モンテカルロ(CC-MRMC)法により解析し、さらに密度汎関数法を併用することで、長距離構造も含めて、精密に決定することができました。この手法を用いることで、他の単原子触媒の精密な立体構造決定に応用できるものと期待されます。
Angewante Chemie International Edition 誌に生命科学部小林洋一教授、理工学部今田真教授、本センター入澤明典准教授、柴田大輔客員助教の論文が掲載されました
Photochromic Color Tuning of Copper-Doped Zinc Sulfide Nanocrystals by Control of Local Dopant Environments
Mayu Kimura, Daisuke Yoshioka, Dr. I-Ya Chang, Dr. Akinori Irizawa, Daisuke Shibata, Prof. Shin Imada, Prof. Yoichi Kobayashi
Angew. Chem. Int. Ed. (2025) 64 e202423776.
フォトクロミック材料は、光照射によって可逆的に色や透明度が変化する物質です。無機フォトクロミック材料は、有機化合物よりも比較的安価で、熱安定性が高いなど、いくつかの利点があります。しかし、同じ成分でその色を調整することは、依然として大きな課題となっています。本研究では、CuドープZnSナノ結晶(NC)のフォトクロミック色を、チオール配位子および非チオール配位子を用いて制御したZnとSの表面化学量論を調整することにより、光照射前は淡黄色であるフォトクロミック色を灰色から褐色に調整できることを実証しました。本センターの軟X線Beam Line BL11 において、Cu L 吸収端を測定し、1価のCuに特徴的なスペクトルを得ることができました。さらに、SA-1で測定したXPSでも1価のCuであることと矛盾しない結果が得られました。本研究成果は、無機ナノ粒子におけるフォトクロミック反応の多様性を拡大し、さらなる高度なフォトクロミックナノ材料の開発に向けた重要な一歩となると期待されます。
ACS Applied Materials & Interfaces 誌に関西大学の石川正司先生が当センターとの共同研究成果を発表されました
Oxygen Functional Groups Regulating Sulfur Distribution in Carbon Micropores to Enhance Solid-Phase Conversion Reactions for Lithium–Sulfur Batteries
Luna Yoshida, Takashi Hakari, Yukiko Matsui, Yuki Orikasa, and Masashi Ishikawa
ACS Applied Materials & Interfaces (2025) 17 22822-22830.
次世代Liイオンバッテリーとして注目を集めるLi硫黄電池の硫黄を、酸素で修飾したカーボンナノ細孔に閉じ込めることで、性能が大きく向上することがわかっていたが、その性能向上メカニズムは未解明であった。本研究では、STEM-EELS測定、O K-edge XANES測定といった最先端分析手法を駆使することで、カーボンナノ細孔に存在する酸素官能基が充放電に伴う細孔内部での硫黄の移動およびそれに伴う局在化を抑制することを明らかにした。当研究センターを利用した O K-edge スペクトル測定により、カーボンナノ細孔の内部および表面の酸素官能基が充放電後も残存していることが証明された。こうした知見は今後のLi硫黄電池開発に役立つものと期待される。
最近の連絡のあった学会発表
受賞
令和7年9月 立命館大学大学院生命科学部応用化学科の東亜紗花さん(M2, 指導教員 稲田康宏先生)が第28回XAFS討論会(KEK-IMSS-PF、つくば、2025.9.14-9.16)で学生奨励賞を受賞されました。心からお祝い申し上げます。
ご受賞講演のタイトルは、シリカ担持酸化マンガンの昇温脱酸素過程の in situ XAFS解析 です。
ご研究はSRセンターBL-3を使われて行われました。

指導教員 稲田康宏先生、東亜紗花さん
令和7年4月 京都大学大学院理学研究科化学専攻の中村雅史さん(D2, 指導教員 北川宏先生)が日本化学会第105回春季年会で学生講演賞を受賞されました。心からお祝い申し上げます。
ご受賞講演のタイトルは、X線分光と第一原理計算による多元素合金触媒の電子構造–物性相関の定量評価 です。
2023年度の成果公開型S23028の成果が一部貢献しております。