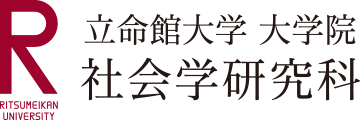先生は、どのような経緯から現在の研究テーマを設定されたのでしょうか。
学部の2回生頃から精神分析学や精神医学分野に関心を持ち始めて自分なりの勉強を開始し、それは現在も続いているのですが、学部3回生の頃、偶然も手伝って社会学(社会学史)を研究活動のメインフィールドにすることにしました。そこで、P.L.バーガーの社会学理論の批判的検討を経て、4回生の春頃、「近代社会の自己認識」を自称する社会学のコアを知るべく、E.デュルケムの社会学思想と学説の研究に取り掛かりました。10年間ほどしゃにむに取り組んだ末にようやく把握したのは、E.デュルケムの独特の社会認識でした。それは、いわゆる「前近代」と「近代」を截然と分離するのではなく、「前近代」はなお社会的価値の源泉として「近代」を生み出し支える形で存在し続けるという社会認識でした。大枠を言えばそれは、「前近代」と「近代」の二重構造として現実の社会は形作られている、という認識です。『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』などを通じ、「前近代」から「近代」への逆説を孕んだ不可逆的な歴史的転換を明らかにしようとしたM.ウェーバーの歴史・社会像と並んで、社会学における二大社会像だと言ってよいと思います。
ここから、もともと現代日本における社会的諸問題に関心があったので、歴史を貫く「心性」の研究を切り開いたアナール学派を横に睨みながら、日本独特の近代社会の構造やその成立過程において伝統的習俗や制度的慣習がいかなる役割を果たしてきているのかという問題への関心が生じ、民俗学や世間論を含む日本研究そして組織論の研究にも触手を伸ばしています。
他方で、デュルケムの社会学思想から公共性や公性の問題圏へ展開することを目指して、地域社会学や比較的新しい学問分野である公益学、そして長く厚い蓄積のある社会教育学などの勉強を始めています。現在は、地元京都の中山間地域の地域振興活動を具体的な取り組みにしながら、少子高齢化や急速な限界集落化など諸課題を抱えて模索の続く地域社会においていかなる公共性や公益のあり方が構想・実現されねばならないのかという課題を立て、新たな高等教育活動の開発と絡めながら、仲間とともに研究しています。
いろいろな分野やテーマに拡散しているように見えると思うのですが、これら多様な分野への関心には、もちろん根本的な問題意識があります。それは、人間が社会的次元において遂行する個人的および共同的な創造活動のありようとその可能性・条件、また反対にその阻害要因を、実践的および理論的に解明することです。
先生は、これまで研究上の大きな困難にぶつかったことがおありでしょうか。
また、その場合どのようにしてそれを克服されましたか。
もちろん、何度も壁にぶつかってきました。自分の力量やある分野の限界に突き当たって動きがつかず、新たな展開に着手するまで数年を要したこともあります。そうした経験から学んだ、研究上の困難を克服する私なりのコツは、自分の恣意を棚上げして、研究対象がそれ自体で持っている潜在的な展開可能性を徹底的に追求し、発見し、それを形にすることでした。研究対象に据えている物事がそれ自体で持っている力と可能性を信頼し、それを発掘し顕在化させるのが研究活動であるし、それこそが研究活動が持つことできる創造性だと、私は考えています。社会科学の世界が“科学”を自称する以上、研究者の側の恣意にではなく客観的事実の側にこそ、さまざまな現実的可能性が見いだされねばならないと、私は思います。
そうしたスタンスから、社会的諸問題に応答することのできる学問分野を探し、それに学ぼうとしてきましたし、それは今も今後も変わりません。壁を乗り越えてきたと言えるとすれば、隣接分野や関連領域へ展開するという経過をたどるなかで、新たな方法や知見を入手するという形で、乗り越えて来られているのだと思います。
特定の学問分野や問題に忠義立てする必要なんて、実は全くありません。自分と社会的・歴史的現実との結節点に研究活動を置き、自分と社会的・歴史的現実の双方にメリットを生むことを目指しながら、その結節のあり方を豊饒化することを求めればいいだけのことだと、私は思います。
2年間の修士課程を終えて社会に出ていく院生に対して、大学院時代の成果をどのように実社会で活かしていくか、アドバイスをお願いします。
研究活動というのは、既存の知識を「正解」として頭にインプットすることをひたすら求める中学や高校の「勉強」と違って、それ自体が何ほどか新しい“知”を創造する活動です。ですから、大学院で幾ばくか専門的な研究活動を経験したということは、専門的な学術の世界の中で、またそれを通じて、一種の創造活動を経験したということに他なりません。これはとても重要なことです。
冷戦終結後から激しい社会変動が続く中、ready madeの「正解」が使える世の中はとうに終わりを告げています。卒業後それぞれが仕事をしていく「現場」で、その「現場」の経緯や状況に即した“ローカルな最適解”を創造し発信する力こそが、これからますます重要になります。「現場」に呑まれるのではなく、「現場」にありながら「現場」に創造的変化 ―― つまりイノベーション―― をもたらす知的・実践的能力がますます重要になります。“Think globally, act locally”と言われるように、視野の広さと具体的な実動能力こそが、これからますます力を発揮する技法になります。知性と五感を、そして具体的な実践能力をフル稼働させて“ローカルな最適解”を生み出し、「現場」に創造的変化を巻き起こし、誇りを持ってそれぞれの「現場」を豊かなものにしていってください。
将来研究職を目指す院生が早い段階から取り組んでおくべき課題があるとすれば、それは何でしょう。
社会科学分野における研究活動は、社会学が「近代社会の自己認識」を標榜するように、さまざまなアプローチによる社会の自己認識です。研究活動というのはまた、それ自体が社会的・集団的行為ですから、社会科学分野における研究活動とは本来的に、“研究者集団を通じて行われる社会の自己認識活動”ということになります。これは、まさしく集団的・社会的な「メタ認識」活動に他なりません。社会科学においては研究者自身も社会的世界の一部ですから、認識のあり方は、自然科学的に研究対象と研究主体を分離することはできず、当事者的メタ認識の形態をとります。社会科学分野における「理論」と呼ばれるものは、すべてこうした当事者的メタ認識を体系化したものに他なりません。
研究活動を支え維持させるものが、研究者の側が抱く何らかの意味で切実な研究関心であることは確かですし、それがなければとりわけ社会学という一種独特の学術世界は成立し得ません。しかし、個人的な興味関心だけで学術活動が成立するわけではありませんし、学術的成果を創造することができるわけでもありません。時空を超えて妥当する「真理」を捉えようとする客観主義的諸分野とは異なり、いわば「主観的にリアルな同時代の客観的真実」を捉えようとする社会学研究は、研究者の側にかかる負荷が実はむしろ高いのです。同時代的な客観的真実を捉えることのできる力量を備えた当事者的主観性を、社会学研究者は持たねばならないからです。
というわけで、社会科学分野とりわけ社会学という独特の分野での研究活動を目指す上で、その基礎的かつ本質的なトレーニングは、大きくは2つあることになります。一方では、専門的知識を頭の中にただ集積するのではなく、たとえばすぐれた古典を読むことを通じてメタ認識能力を磨くことです。具体的な問題や事例やテキストに即しながら「認識」と「メタ認識」の往還ができるようになることを目指して思考を訓練することが、「勉強」から「研究」への転換を実現し、あなたを独断から解放し、「素人」から「玄人」にしてくれます。
そして他方、同時代的諸問題や諸課題に直接的・間接的に触れることをも通じて、有意義な研究成果を生み出すことのできる自らの当事者的主観性を、鍛え育むことです。これによって、研究活動が個人的恣意や衒学に堕落する過ちが未然に防がれ、あなたの仕事に唯一無二の“アウラ”が宿ることになります。自分自身の「暗黙知」を自覚化し、さらにそれを育てるというのはなかなか大変なことですが、これを通じてのみ、「研究者」が誕生します。