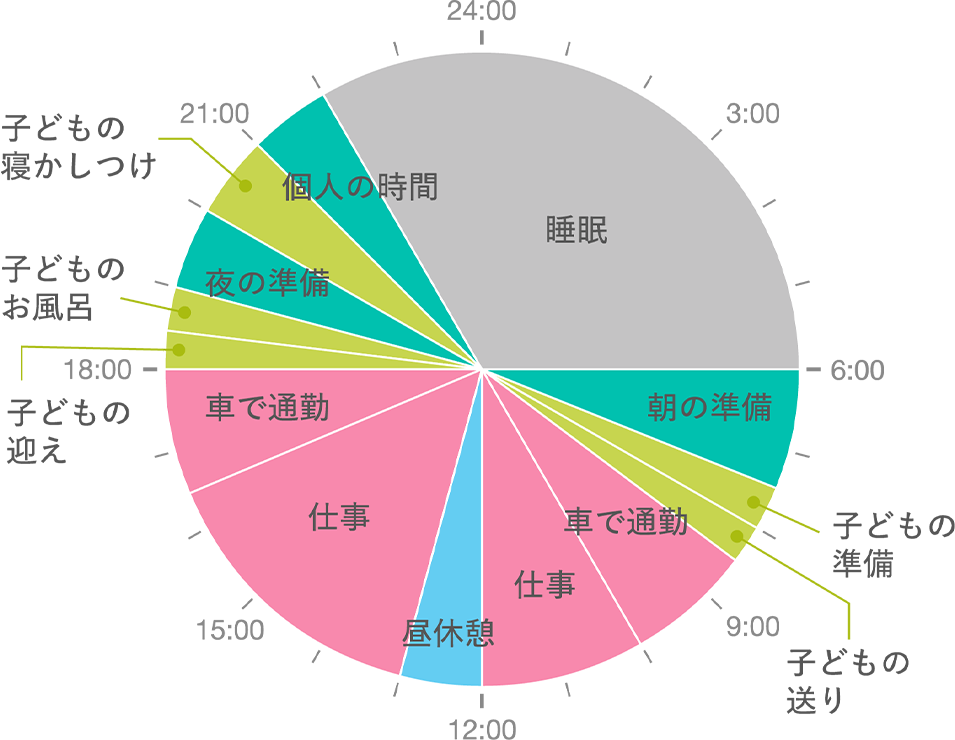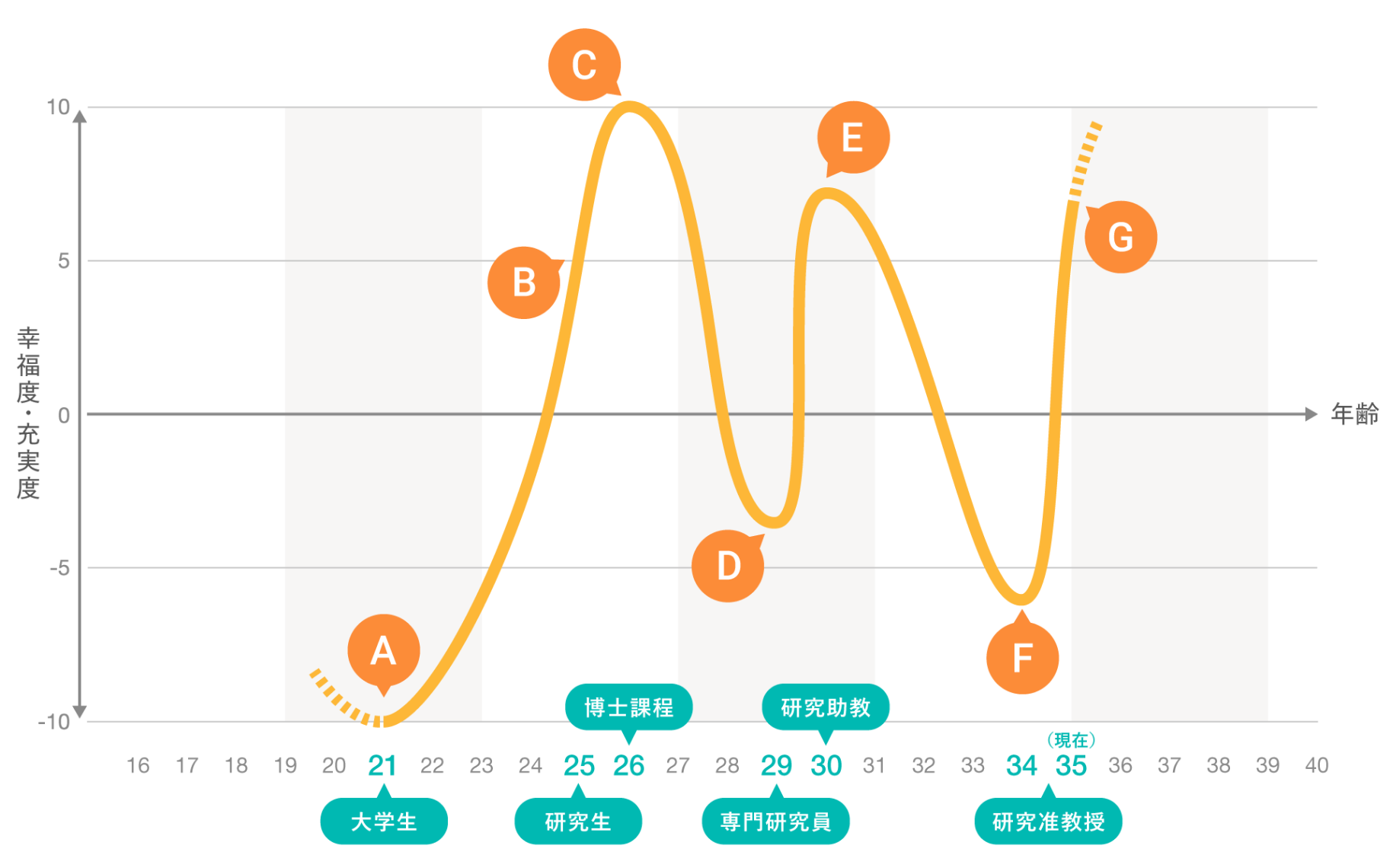ロボットコンテストでの出会いが
就職の転機に
来日後はロボティクス研究室に所属し、新たな研究をスタートさせました。当初苦労したのは、日本人学生とのコミュニケーションです。日本人学生は、豊富な知識と高いスキルを持っているにもかかわらず、教授の指示に従うだけで、主体的に行動したり、自分のアイデアを提案したりしないことに、最初は戸惑いを覚えました。本音が見えないために、親しくなる糸口をつかめず、寂しい思いをすることもありました。
研究では、眼の角膜に投影される画像を認識し、ヒトが見ているものを捉えるという新しい視線追跡システムの構築を試みました。角膜に映る画像は非常に粗いため、そのままでは何が映っているのか認識できません。そこでディープラーニングを使って、画像を認識する手法を考案しました。
また研究室の大学院生とチームを組み、それぞれの専門を活かしてロボットを製作し、国際的なロボットコンテストにも出場しました。転機は2017年、愛知県で開催された世界大会「Amazon Robotics Challenge」に出場した時、立命館大学情報理工学部の谷口忠大先生(当時)と出会ったことです。谷口先生にお誘いいただき、立命館グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO)のプロジェクトに専門研究員として加わることになり、立命館大学に赴任しました。