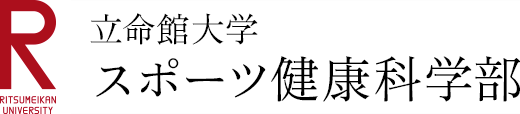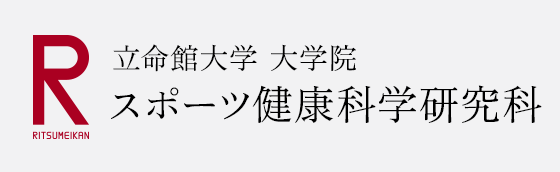2021.06.25 education
専門演習Ⅲ:ロシアのスポーツビジネス
ロシアのスポーツ業界は、知らないことばかりで、また3カ国語を操るエンジェさん自身に対しても、驚きにも近い多くのことを教えていただきました。エンジェさんにとっては、日本語でのご講義は英語よりも負担になります。そのため、ゼミ生たちに事前の質問や講義後のコメントに英語を用いることを提案したところ、(大変ながらも)多くの学生が英語での記述にチャレンジをしてくれました。
長く続くコロナ禍において、海外への留学が難しくなっていますが、既に海外で学んでいる留学生たちもまた、帰国がしにくいという困難を抱えています。そのような状況であっても日本で学び続けるエンジェさんのご講義は、ゼミ生たちにとって新しい経験や気づきを与えてくださるものでした。
エンジェさんには、ご講義の前後にも「エンジェ先生、エンジェ先生」と呼ぶゼミ生たちと多くの交流をしていただきました。
LATYPOVA Endzheさん、ありがとうございました。
Note:1) PEST分析は、Political(政治的)、Economical(経済的)、Social/Cultural(社会文化的)、Technological(技術的)の視点を用いたマクロ環境分析です。スポーツマーケティング論でも学ぶフレームワークです。