02

文学部
遠藤 英樹 教授
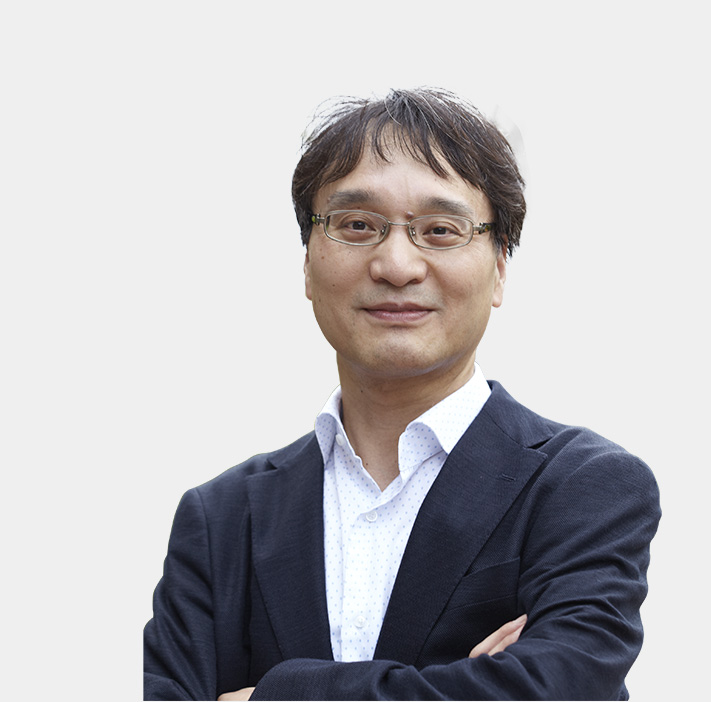
Contents
コロナ禍で生活は
どう変わったか?
コロナ禍での授業は
どのように進めていましたか。
オンライン授業に移行するため、普段の3~5倍の時間をかけて準備に取り組みました。大講義の授業については、これまで対面で話していた内容を文字に書き起こして資料を作成しました。ただ、それだけでは学生にモチベーションを維持してもらいにくいので、資料には余談や冗談も盛り込んだり、公式的なものであれば動画のリンクを適宜貼ったりするようにしています。どの授業も課題が出され、学生たちは忙しい毎日を送っていますから、学修の興味を持続させるような授業が大事だと思っています。
今年4月に入学した学生は
戸惑うこともあったのでしょうか。
本来であれば、先輩や友達との会話を通して自然とわかってくるような大学のルールや授業の仕組みなどがあると思いますが、それも知る機会が少ないようです。授業の終わりに記入する振り返りシートが評価の対象になると知らなかった学生もいました。
そのため、できる限り授業の受け方や仕組みといった基本的なことについても、丁寧に情報発信するよう心がけています。
学生の様子はいかがですか。
急な変化で大変な状況だと思いますが、皆さんやる気をもって授業を受けてくれています。直接顔を合わせる機会が少ない分、一人ひとりの通信環境を確認したり、ゼミを欠席した学生にLINEで連絡を入れたりと、できうる限り細かなフォローを行なおうと心がけています。大講義でも、「皆さんのことをちゃんと見守っていますよ」というメッセージが伝わるようにと授業を進めているつもりです。
アフターコロナの
観光産業はどうなる?
コロナ禍により、
現在も国内外への移動が
一部制限されています。
今後、観光産業は
どうなるのでしょうか。
向こう1~2年は、3密を避けた国内旅行が中心となり、「マイクロツーリズム」に力を入れていくことになるでしょう。マイクロツーリズムとは、地元の人が近場のホテルや宿に宿泊し、地元を楽しむ移動範囲の小さい旅行です。
とにかく、これから必要になるのは、「何かを見に来てもらう」旅行ではなく、「コンテンツとして魅せる」旅行を生み出すことです。今まで掘り起こされていなかった地元の文化や自然を再発見し、人々を楽しませるものとして観光をコンテンツ化していくことが求められると思います。

「観光のコンテンツ化」とは
どういうことですか。
例えば、ある観光地では、かつて都があった様子をVR(Virtual Reality)やMR(Mixed Reality)で体感できるサービスを提供しているところがあります。そんな風にリアルとバーチャルを上手く組み合わせて、地域の魅力をコンテンツ化して観光客に楽しんでもらえる仕組みができると面白いと思うのです。リアルからバーチャルに完全移行するのは難しい。でも、これまでのリアルな観光とメディアコンテンツをかけ合わせると、観光の可能性がもっと広がるのではないかと考えています。
地域の魅力を再発見し楽しませる
コンテンツづくりは、
地域の活性化にもつながりそう
です。
では、今後ツーリスト側に
求められることは何でしょうか。
もてなされる側として観光を楽しむだけではなく、ツーリスト側からのもてなしを考えることでしょう。例えば、現地の文化を大切にする、環境にやさしい移動方法を採るなどが挙げられます。私は「観光を通して、この世界に『もてなし(hospitality)』をギフトする」と言っているのですが、一方的にサービスを受けるのではなく、自分の楽しみと観光地の環境・文化のバランスをうまく保ちながら旅行することが重要になってきています。これは「モビリティ・ジャスティス=移動の公正さ」といい、今後ますます求められる考え方です。地域の暮らし・自然・文化を大切にしながら観光を楽しむことで、地域とサステイナブルな関係性を築いていかなければなりません。
今後、移動制限は
緩和されていくと思いますが、
日本社会には
何が求められるのでしょうか。
人の移動をどのような形で元に戻していくかを考えなければなりません。3密になりにくい社会設計をすることは重要になるでしょう。観光のアーキテクチャーです。例えば電車の座席にくぼみをつければ、くぼみのあるところにしか人は座りません。これを利用すれば自然と距離を取れる環境を作ることができますよね。このようなアフターコロナを見据えた社会設計が求められると思います。
「夢見るようなリアリスト」が可能性を切り拓く
アフターコロナの世界で、
私たちはどう生きるべき
でしょうか。
キーワードは「夢見るようにリアリストたれ」です。「リアリスト=現実主義者」には、現実を受け入れるだけの「現状追認型」と、現実の向こう側にある可能性を切り拓く「リアル開拓型」の2種類があります。皆さんにはぜひ後者のリアリストになってもらいたい。ただ夢を見るのでもなく、ただ現状を追認するのでもない。現状を知り、その先を考える。今は誰も見えていなくても、そして人からは「夢想家」と思われても、現実の中に確かに存在する新たなつぼみをしっかりとらえ、それを信じて進むこと。それができれば、アフターコロナの世界も、豊かな可能性に満ち溢れた新たなかたちで現れてくることでしょう。
そのためにはまず、現状を
知ることが大事なのでしょうか?
現状を知り、問いを持ち、それを手放さないことです。これは学生たちに常々言っていることですが、「自分のこだわりのある問いを持つ」ことを意識してほしいと思います。その問いが人から笑われようと構わないのです。人から笑われるような問いであっても、自分が大切に思う問いだけは決して手放さない。そういう人だけが、未来を切り拓くことができるのです。私も若い頃、社会学の領域で観光を研究しようとしたときに、「研究で観光地に調査に行くなんて気楽なもんだね」と笑われた経験があります。でも気にしませんでした。何事も、やり続けると形になっていくものです。
「問いを持つ」とは、
とても難しそうなのですが。
「問い」は案外、何気ない日常の中にあるものです。見逃してしまいそうなところにこそ、深い問いがあったりします。「ライアー・ライアー」という映画をご存知ですか?嘘つきの弁護士が、ある日、嘘がつけなくなってしまい、社会生活が崩壊していくというコメディなのですが、私はこれをみて「嘘と、嘘でないものの境目とは何なのだろう?」と考えました。これもひとつの「問い」です。すこし丁寧な視線をもって映画を見るだけで、さまざまな問いが生まれてきます。コロナ禍について見つめ直すのも、社会に対するさまざまな問いを見つけるきっかけになるのではないでしょうか。
Message
Profile
Other articles






