■「後方支援スタッフ派遣」第7便 活動報告
災害復興支援室では、中長期的支援が求められる東北の被災地へ学生を継続的に派遣する企画
「後方支援スタッフ派遣」を、サービスラーニングとは異なる位置づけで実施中です。
今回は、宮古市観光協会が岩手県宮古市田老地区開催する津波被害に関する学習会に参加の後、
宮古市災害ボランティアセンターからの派遣による被災した海岸の清掃、および写真修復作業、
また、現地で依頼を受けボランティアマップの作成を行いました。


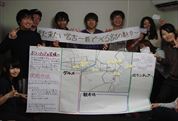
【第7便の概要】
参加人数:学生12名、職員4名
日 程:2012年5月2日(水)から5月7(月)
宿泊場所:宮古市災害ボランティアセンター・生活復興支援センター ボランティア宿泊スペース
活動場所:宮古市内応急仮設住宅、集会所内集会所等
活動内容:津波被害・防災学習会への参加、仮設住宅生活支援、被災した海岸のがれき掃除、
ランティアマップ作成
<スケジュール>
5/2(水) 夜 京都駅出発
5/3(木) 岩手県宮古市へ、田老地区の津波被害説明「学ぶ防災」に参加
5/4(金) 仮設住宅生活支援活動、マップ作成等
5/5(土) 海岸での清掃、宮古災害FM見学等
5/6(日) 宿舎清掃、観光(仙台市内)、帰路
5/7(月) 朝 京都着
<参加学生のコメント(終了後のアンケートより一部抜粋)>
■遠くからボランティアに行くことの意味
地震や津波の被害についてニュースなどでは見ていましたが、実際にその現場に立ち、その力の凄さを
改めて理解しました。また「遠くからボランティアにいくことは、はたして意味があるのか。私たちの
ような活動は必要なのか。」という疑問を前から抱いていたのですが、その思いが解決しました。
現地のかたに言われた「県外の人の力はとても刺激になる。」という言葉から、『県外だからこそ、
学生だからこそ、京都だからこそできるボランティア』を考えていく必要があるなと気づきました。
<産業社会学部 3回生>
■がれきという言葉に込められた現実
海岸清掃に参加した際の、「“がれき”という言葉でひとくくりにされてしまうそれらは
元々は家でり、日常品でり、財産なんだ」という話が一番印象に残っています。
この話を聞くまで、“瓦礫”とは処理に困っている厄介なものという認識でしたが、本当は思い出の品が
流されてしまったものと気付き、海岸清掃で大量に拾い集めた貝殻も、養殖していた漁師さんたちの
大切な財産だったと分かり、とても悲しい気持ちになりました。
今回の活動で気付くことができたことは、とても良い経験だったと感じています。今後できるだけ多くの
学生に、このような経験をしてほしいと思いました。
<理工学部 2回生>
※引率職員より
今回の第7便において、過去の派遣便に参加したボランティアのリピーターがいた。その影響もあってか
学生が現地に複数回足を運ぶことについての重要性を感じている学生が複数見受けられ、今回の経験を
通じ宮古や被災地に対しての親近感が湧き、今後連携を増やしたいと考えている学生もいた。
今後は複数回現地に足を運ぶ学生「学生リーダー制度」をつくり、職員と事前に現地の行程等の確認や
先方との調整を一部行うことが学生自身の更なる学びに繋がると感じている。
<スポーツ健康科学部事務室 職員>
「後方支援スタッフ派遣」を、サービスラーニングとは異なる位置づけで実施中です。
今回は、宮古市観光協会が岩手県宮古市田老地区開催する津波被害に関する学習会に参加の後、
宮古市災害ボランティアセンターからの派遣による被災した海岸の清掃、および写真修復作業、
また、現地で依頼を受けボランティアマップの作成を行いました。
【第7便の概要】
参加人数:学生12名、職員4名
日 程:2012年5月2日(水)から5月7(月)
宿泊場所:宮古市災害ボランティアセンター・生活復興支援センター ボランティア宿泊スペース
活動場所:宮古市内応急仮設住宅、集会所内集会所等
活動内容:津波被害・防災学習会への参加、仮設住宅生活支援、被災した海岸のがれき掃除、
ランティアマップ作成
<スケジュール>
5/2(水) 夜 京都駅出発
5/3(木) 岩手県宮古市へ、田老地区の津波被害説明「学ぶ防災」に参加
5/4(金) 仮設住宅生活支援活動、マップ作成等
5/5(土) 海岸での清掃、宮古災害FM見学等
5/6(日) 宿舎清掃、観光(仙台市内)、帰路
5/7(月) 朝 京都着
<参加学生のコメント(終了後のアンケートより一部抜粋)>
■遠くからボランティアに行くことの意味
地震や津波の被害についてニュースなどでは見ていましたが、実際にその現場に立ち、その力の凄さを
改めて理解しました。また「遠くからボランティアにいくことは、はたして意味があるのか。私たちの
ような活動は必要なのか。」という疑問を前から抱いていたのですが、その思いが解決しました。
現地のかたに言われた「県外の人の力はとても刺激になる。」という言葉から、『県外だからこそ、
学生だからこそ、京都だからこそできるボランティア』を考えていく必要があるなと気づきました。
<産業社会学部 3回生>
■がれきという言葉に込められた現実
海岸清掃に参加した際の、「“がれき”という言葉でひとくくりにされてしまうそれらは
元々は家でり、日常品でり、財産なんだ」という話が一番印象に残っています。
この話を聞くまで、“瓦礫”とは処理に困っている厄介なものという認識でしたが、本当は思い出の品が
流されてしまったものと気付き、海岸清掃で大量に拾い集めた貝殻も、養殖していた漁師さんたちの
大切な財産だったと分かり、とても悲しい気持ちになりました。
今回の活動で気付くことができたことは、とても良い経験だったと感じています。今後できるだけ多くの
学生に、このような経験をしてほしいと思いました。
<理工学部 2回生>
※引率職員より
今回の第7便において、過去の派遣便に参加したボランティアのリピーターがいた。その影響もあってか
学生が現地に複数回足を運ぶことについての重要性を感じている学生が複数見受けられ、今回の経験を
通じ宮古や被災地に対しての親近感が湧き、今後連携を増やしたいと考えている学生もいた。
今後は複数回現地に足を運ぶ学生「学生リーダー制度」をつくり、職員と事前に現地の行程等の確認や
先方との調整を一部行うことが学生自身の更なる学びに繋がると感じている。
<スポーツ健康科学部事務室 職員>
