学生インタビュー
INTERVIEW

INTERVIEW 01
飲食店運営や商品開発に挑戦し、実践から「食」と「経営」を学ぶ。
藤原 光希 さん
食マネジメント学部 食マネジメント学科
兵庫県・神戸大学附属中等教育学校出身
INTERVIEW
01
⼤好きな「⾷」。特に、飲⾷店の「経営」を学べるところに惹かれて⾷マネジメント学部を志望しました。⾷マネジメント学部の魅⼒は、正課での学びを社会で実践する機会が充実していることです。課外プログラム「カフェの学校」では、カフェのメニュー設計から店舗運営までを実践。仲間と試⾏錯誤しながら、飲⾷店を⼀から創り上げていく中で得た「⽣きた知識」は、将来⾷産業で働く上で、きっと強みになると思います。その他にも、琵琶湖の漁師さんと連携して湖⿂を使ったお⼟産の開発に取り組みました。頭に思い描いたものが商品として形になり、お客様に⼿に取ってもらえた時の感動は忘れられません。元々、新しいことに挑戦することへ苦⼿意識がありましたが、⼤学での様々な挑戦を通じて、「やってみたい!」という気持ちに向き合い、それを実現する喜びを実感しました。次は就職する飲料メーカーで「100年後も愛され続ける酒ブランド創り」に挑戦します。

INTERVIEW 02
外食企業との共同研究、農業体験の団体設立。正課・課外で食を追求。
長谷川 梨香 さん
食マネジメント学部 食マネジメント学科
茨城県・土浦日本大学中等教育学校出身
INTERVIEW
02
高校時代は料理人になりたいと思っていました。料理だけでなく「食」を総合的に学べるところに魅力を感じ、食マネジメント学部に進学しました。印象に残っているのが3回生の時に受講した「総合講義(起業)」で、外食産業の大手企業・株式会社サイゼリアの創業者の講義を聴いたこと。これをきっかけに、1年にわたって株式会社サイゼリアとの共同研究に挑戦しました。社員の方々へのインタビュー調査、店舗で活用されているマニュアルの分析、店舗施設などを行い、大手企業のノウハウをまちの個人経営の飲食店に生かすにはどうしたらいいかを考えました。また課外では、友人と一緒に学生団体「カノール」を創設。農業体験を通じて生産者と学生をつなげる活動に取り組んでいます。活動を通じて実感したのが「リーダーシップ」の重要性。現在、これをテーマに卒業論文を執筆中です。自分がかなえたい夢を信じ切る。そんな勇気が湧く卒論を書きたいと思っています。

INTERVIEW 03
イタリア実習を通じて食の文化や歴史に関心が広がった。
萩原 千夏 さん
食マネジメント学部 食マネジメント学科
千葉県立成田国際高校出身
INTERVIEW
03
高校時代のムスリムの友人との出会いをきっかけに、文化や宗教の違いを超えて共に食事を楽しむ方法を学びたいと思うようになりました。食マネジメント学部では、マネジメント・カルチャー・テクノロジーの3つの領域から「食」について学べることに加え、食業界で活躍している方からリアルな話を聞く機会が数多くあります。特に印象に残っている授業は、「GSPⅠ※」でのイタリア実習です。イタリア各地で食関連の企業や施設を見学し、ワクワクが止まらない2週間でした。実習を経て、誰かと一緒に食事をすることを大切にするイタリアの食文化に関心が高まり、帰国後は、イタリアの食が形成するアイデンティティや食の歴史について学びを深めています。また「学生団体BohNo」に所属し、地域の小学生を対象に食育活動に取り組むなど、課外でも食の大切さを学びました。4年間の学びを糧に、将来はバックグラウンドに関係なく、誰もが笑顔で暮らせる社会の実現に貢献したいと思っています。
※ GSPⅠ:ガストロノミックスタディプロジェクトⅠ
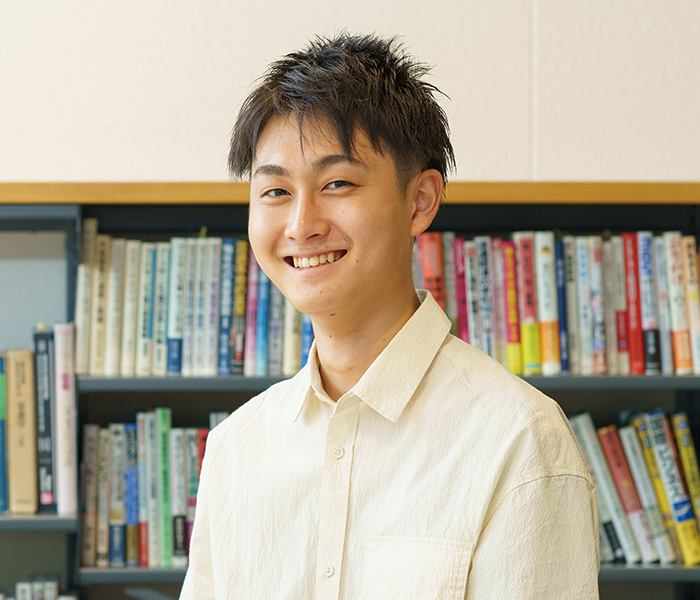
INTERVIEW 04
ビジネス、文化人類学、栄養学、調理への挑戦、「食」を切り口に幅広い分野を学んだ。
石崎 宏太朗 さん
食マネジメント学部 食マネジメント学科
東京都・青稜高校出身
INTERVIEW
04
「食」についてカルチャー、マネジメント、テクノロジーとさまざまな側面から学べるところに興味を持ち、食マネジメント学部を志望しました。心が惹きつけられた授業の一つが「総合講義」です。食ビジネスの現場で働く方や、世界中の料理を食べてきた方など多様なゲスト講師の講義を聴いて、視野が大きく広がりました。また課外プログラムである「グローバル・カリナリーアーツ・アンド・マネジメント・プログラム」に参加し、「ル・コルドン・ブルー」の先生に教わりながら調理に挑戦。その中で時間通りに仕事をやり遂げるマネジメントスキルを磨くことができました。文化人類学やマーケティング、栄養学など幅広い分野を専門にする先生から学べるのが本学部の魅力です。また学業だけでなく、学生団体「ぎゅっと滋賀」に入り、お土産の開発を通して滋賀県の魅力を知ってもらう活動にも力を注ぎました。多様なバックグラウンドや考え方を持つ学生と友達になり、自分自身の考え方も成長したと感じています。
