学べること
自分の探求したいテーマを持ち、さまざまな分野の知識を得て、社会で実践していく学びを用意しています。
-
CASE 01
食を通じて人に
感動してもらいたい食は、栄養を摂るという生活基盤としての役割のほかにも、人々の生活に喜びや感動をもたらし、人生のさまざまな場面に彩を添える、大切な役目を持ちます。食の付加価値を多面的に理解して、食のもつ価値を消費者に伝え届けることで感動を生む。そのようなことができる人になるために、食マネジメント学部では必要な学びを準備しています。
- おいしさについての
科学的な知識 - サービスを
マーケティングする視点 - 食ビジネスの現状を
分析する力
-
学び 01
食と認知科学
人間の食行動と認知プロセスの関係を探究します。味覚・嗅覚だけでなく視覚や触覚、ブランドイメージなど多様な要因が食認知に影響する仕組みを学び、複雑な食行動のメカニズムを科学的に理解します。これにより、人間の食に関わる意思決定や行動の法則性を見出す力を養います。

-
学び 02
官能評価学
食品や飲料を開発するためには、物理的・化学的な技術とともに、人の感覚や嗜好の多様な側面についての知識が必要です。官能評価に必要な幅広い知識を身につけ、さらに他の品質分析方法も学びながら、人の感度や嗜好との関係を理解します。

-
学び 03
食と先端技術
認知科学や情報工学をはじめ、分子生物学や工学などの最先端技術が発展する中で生まれた「フードテック」について学びます。フードテックは、科学技術の理解なしには語れません。そこで、認知科学などの基礎知識を学びつつ、フードテックの様々な話題を紹介します。これにより、食に最新技術を活用する力を身につけます。

-
学び 04
総合講義Ⅱ(食ビジネスの現在)
食ビジネスは、今後の国際経済の中においても、最も成長が見込まれる産業です。そこでは日々技術革新が行われ、厳しい競争が行われています。授業では、実際の食ビジネスで活躍する実務者を招いて、食ビジネスの実態と課題についてのリアルな講義も受けていきます。
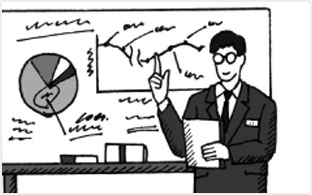
-
-
CASE 02
食で暮らしやすい社会を
築きたい世界では食の不均衡が起きており、日本にも不平等や貧困といった課題が存在しています。課題解決に向けた取り組みの一例として、地域の大人が子どもたちのための食事を提供する動きも広がっています。このような活動をどのようにして維持発展していけるか。そこに求められるマネジメントの知識と実践、全体を見渡せる視野を身につけていきます。
- 社会の課題と
食とをつなげる視点 - 物事を総合的・相対的に
捉える力 - ソーシャル
イノベーションの素養
-
学び 01
フードデザインマネジメント論
フードデザインとは、形や色、味覚といった物質的側面に加えて、企業価値、製品価値を含めて、収益の向上を目ざして全方位で検討されるべき概念です。デザインという概念を用いる事で、収益構造やビジネスモデル、オペレーションや意匠などを統合的に理解します。

-
学び 02
食のクロスカルチュラル・スタディ
食に関わる異文化間理解とその応用を扱います。地域・国境・民族・宗教等の境界線を越えた食理解や、食を通して異文化を背景にした人々がつながる術を発展させることを考えます。

-
学び 03
食と健康
健康管理の視点からとらえた食生活のあり方について学びます。例えば、栄養や食生活と健康との関係、健康や栄養に関する情報、食に関するリスクの正しいとらえ方を理解します。さらには高齢化社会で期待される健康に関わる食産業についても考えます。
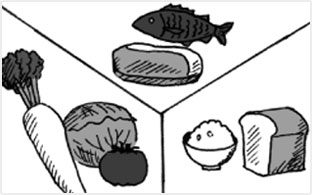
-
学び 04
総合講義Ⅲ(食サービスの経営)
食ビジネスは、企業家が生み出すイノベーションや、新業態の起業によって成長してきました。この科目では、多様な知識を結びつけて新しいものを生み出す方法や、実際の起業に関する知識を様々な視点から扱います。そして、新しいビジネスのアイデアの元を生み出すための思考力を養います。

-
-
CASE 03
食で地域を活性化したい
いま日本は、世界でも屈指の少子高齢化によって、急速に変化していく社会になっています。地域の持っている可能性を最大限に発揮し、地域を元気にしていくための切り口として、食は大きな意味を持っています。食というツールを使って地域を活性化するプロデューサーとして活躍するために必要な学びを、食マネジメント学部では用意しています。
- 人やモノ等の流れを
読み解く視点 - 食品の加工・調理に
ついての知識 - 地域の魅力を使って
協働できる力
-
学び 01
流通論
届けるという活動には、ただモノを送るだけではなく、情報やお金の流れなど様々な活動も含まれます。流通は、生産と販売を結び、消費者の手元までモノを届ける活動全体を指し、食に関わる経済活動で重要な役割を果たします。広い視野で食の流通の全体像を学びます。
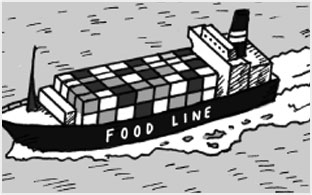
-
学び 02
食の地理学
地理学の「地図上で考える」という方法と考え方のもとに、地図を使って食を考察します。食を通じて、文化や、農業・食品企業等の経済活動だけでなく、それをとりまく自然環境や社会環境、政治や国際関係、食べるという行為そのものと価値観の関連も検討します。
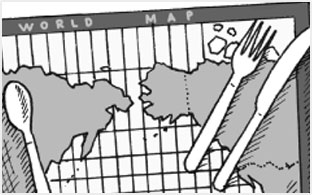
-
学び 03
食品機能評価学
食品中の含まれる様々な成分の基礎知識をもとに、さらに詳細な化学的な構造や性質、分離分析法などについて学びます。そして、成分が品質に与える影響を学習したうえで、食品の貯蔵・加工・調理を通じて起こる食品成分の変化や食品品質への影響を理解します。

-
学び 04
食と地域振興
地域づくりにおける食の役割は多岐にわたります。農業や漁業の振興は、耕作放棄地の減少や移住の促進に寄与し、地元の食材を活かした料理は観光にも役立ちます。これにより地域内の経済循環が促進されます。具体的な事例を通じて、地域経済やコミュニティ再生における食の重要性を学び、その土地独自のガストロノミー資源を活用した地域振興の効果や実践方法について理解を深めます。

-
-
CASE 04
食で日本の魅力を
海外に伝えたい日本食の世界的なブームが続いています。一方で、食材など日本食を支えている様々なものは、海外で生産され輸入されていたりします。日本と海外とをつなぐ仕事に就いたり、海外で活躍していくために必要な、食を通じて地域の文化や宗教、ビジネスの慣習などについての幅広い知識と教養を学んでいきます。
- 異文化理解と
コミュニケーション力 - 文化を国際経済から
読み解く視点 - 食事と国際ビジネスを
考える力
-
学び 01
国際経済学
国際経済の基礎理論と諸問題の理解と分析をしたうえで、食の生産・消費における国際取引の果たす役割やその広がりを学びます。貿易や企業の国際活動、資金の国際間取引、為替など、食を含んだモノ・サービス・資金の国際的な流れを理解し分析します。
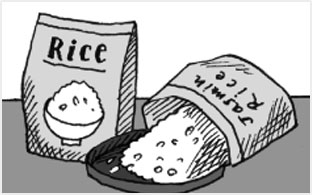
-
学び 02
マーケティングマネジメント論
マスマーケティングや市場細分化、ブランド管理など、マーケティングマネジメントの基本的な考え方と理論を学びます。実在する企業が直面する事例から理論と実践を結びつけて、現実に即したマーケティング管理の知識を身につけます。

-
学び 03
総合講義Ⅰ(日本の食と経済)
日本の食文化のあり方を経済という視点から考えます。「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録された背後には、自然を尊ぶ日本人の食に関する習わしが評価された一方で、米食の普及、和食の海外普及といった文化現象の経済化という問題も見えてきます。食と経済に関する事実と現象を、総合的に考察します。

-
学び 04
総合講義Ⅱ(グローバル化と食ビジネス)
この講義では、広範なフードシステムと国際経済学を基に、国際ビジネスと食関連企業の分類を学びます。国際展開には、国内外でのビジネスや取引、外国の影響を受ける国内企業も含まれます。多様な企業の講師を招き、農業から消費者までの食の流れや食の安全性に関する知識も深めます。これにより、グローバル化した社会での食ビジネスを広く理解し、実際の社会課題と結び付けて学ぶことを目指します。
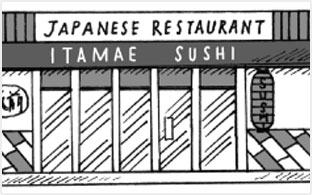
-












