Updatesニュース
最新のニュース
2018年度 立命館西園寺塾 1月12日講義「朝鮮半島をどう見るか:変化する北東アジアの国際環境を考える」を実施
2019年1月12日(土)
・13:00~14:40 講演
講師:神戸大学大学院国際協力研究科教授
木村 幹
・15:00~17:00 質疑応答
【指定文献】
『日韓歴史認識問題とは何か』木村幹【著】ミネルヴァ書房




・13:00~14:40 講演
講師:神戸大学大学院国際協力研究科教授
木村 幹
・15:00~17:00 質疑応答
【指定文献】
『日韓歴史認識問題とは何か』木村幹【著】ミネルヴァ書房
『だまされないための「韓国」』浅羽祐樹、木村幹、安田峰俊【著】講談社
2019年度 立命館西園寺塾 塾生募集要項を公開
2018年度 立命館西園寺塾 福島フィールドワークを実施
12月22日(土)~23日(日)、福島県においてフィールドワークを
実施しました。概要は、以下のとおりです。
【概要】
12月22日(土)
小高町・浪江町・富岡町周辺 見学
回転寿しアトム・殉職警察官慰霊碑などの見学
東京電力廃炉資料館 見学・質疑応答
12月23日(日)
Jヴィレッジ・天神岬(洋上風力・火力発電)・ここなら笑店街
みんなの交流館ならはCANvasなどの見学
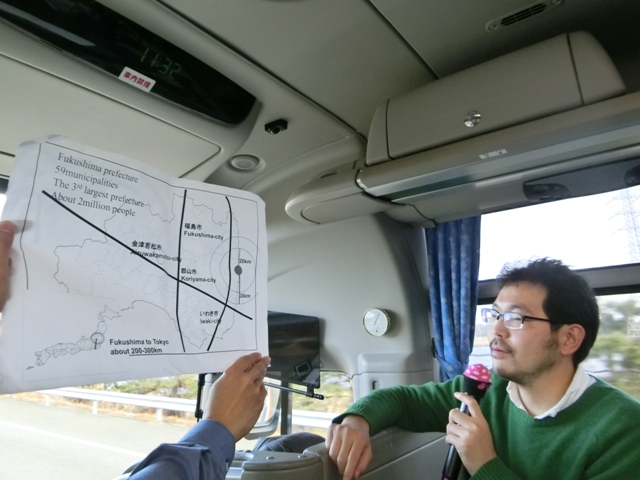










実施しました。概要は、以下のとおりです。
【概要】
12月22日(土)
小高町・浪江町・富岡町周辺 見学
回転寿しアトム・殉職警察官慰霊碑などの見学
東京電力廃炉資料館 見学・質疑応答
12月23日(日)
Jヴィレッジ・天神岬(洋上風力・火力発電)・ここなら笑店街
みんなの交流館ならはCANvasなどの見学
いわき・ら・ら・ミュウ 展示見学
2018年度 立命館西園寺塾 12月15日講義「イスラームのとらえ方―穏健イスラームに注目して―」を実施
2018年12月15日(土)
・13:00~14:40 講義
講師:京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授
東長 靖
・15:00~16:10 質疑応答
・16:10~17:00 グループワーク
【指定文献】
『イスラームのとらえ方』東長靖【著】 山川出版社
『イスラーム神秘思想の輝き―愛と知の探求』東長靖・今松泰【著】*1
*1:前半部分にある東長先生部分(序章~第3章)のみ
『スーフィー ― イスラームの神秘主義者たち』


・13:00~14:40 講義
講師:京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授
東長 靖
・15:00~16:10 質疑応答
・16:10~17:00 グループワーク
【指定文献】
『イスラームのとらえ方』東長靖【著】 山川出版社
『イスラーム神秘思想の輝き―愛と知の探求』東長靖・今松泰【著】*1
*1:前半部分にある東長先生部分(序章~第3章)のみ
『スーフィー ― イスラームの神秘主義者たち』
ティエリー・ザルコンヌ【著】東長靖【編】遠藤 ゆかり【訳】創元社
2018年度 立命館西園寺塾 12月1日講義「近代日本とアジア」を実施
2018年12月1日(土)
・13:00~15:00 講義(前半)
・15:15~16:15 講義(後半)
講師:東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授
中島 岳志
・16:15~17:00 質疑応答
【指定文献】
『ナショナリズム ― その神話と論理』 橋川 文三【著】ちくま学芸文庫

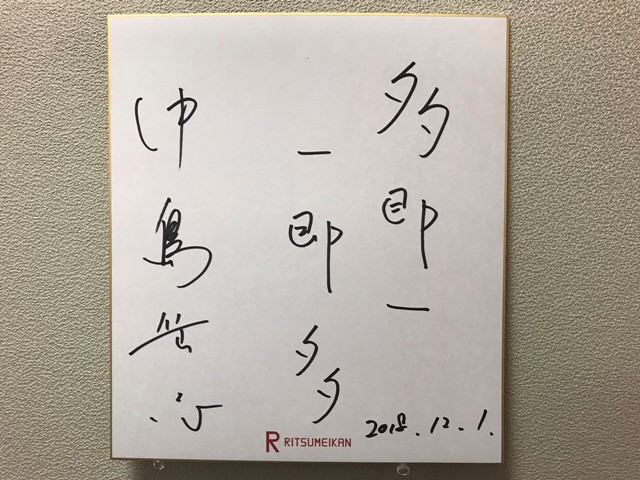
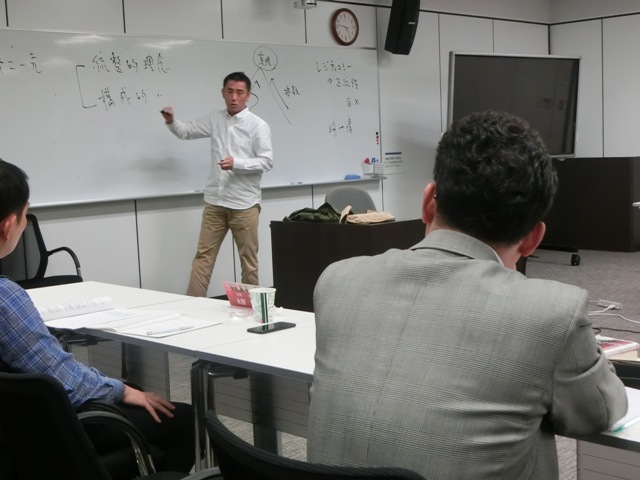

・13:00~15:00 講義(前半)
・15:15~16:15 講義(後半)
講師:東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授
中島 岳志
・16:15~17:00 質疑応答
【指定文献】
『ナショナリズム ― その神話と論理』 橋川 文三【著】ちくま学芸文庫
『アジア主義 西郷隆盛から石原莞爾へ』 中島 岳志【著】潮文庫
2018年度 立命館西園寺塾 京都フィールドワークを実施
11月23日(金・祝)~25日(日)、京都市においてフィールドワークを
実施しました。概要は、以下のとおりです。
【概要】
11月23日(金・祝)
午後:・上賀茂神社 参拝・拝観
・西本願寺 特別拝観
解説:立命館大学文学部教授 本郷真紹
11月24日(土)
午前:・光悦寺 拝観
・六角堂およびいけばな資料館 見学
・講義および華道体験
講師:華道家元池坊次期家元 池坊専好
午後:・講義および組香体験「お香の楽しみ方」
講師:株式会社松栄堂 専務取締役 畑元章
・高台寺 拝観
11月25日(日)
午前:・臨済宗建仁寺塔頭 霊源院 座禅体験および法話
講師:雲林院宗碩
・平安神宮 拝観およびお庭の説明
講師:植治 次期十二代 小川勝章
午後:・講義およびお茶席







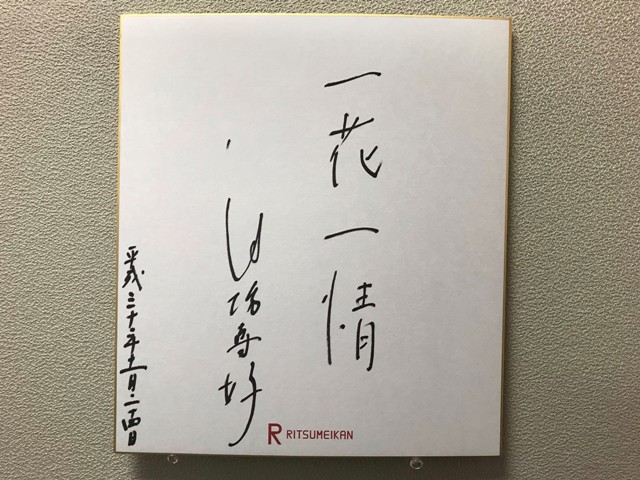

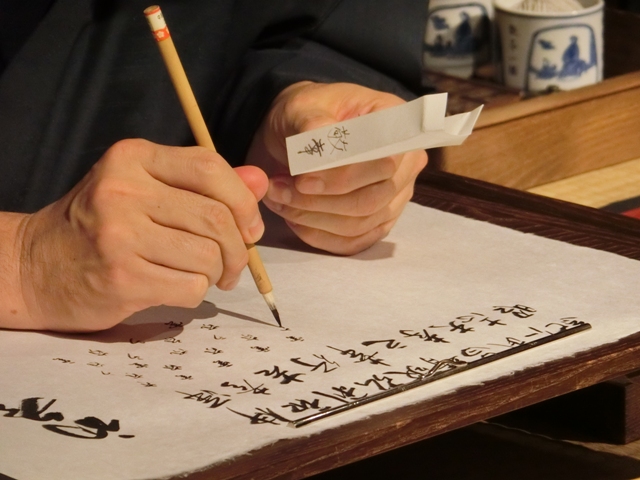


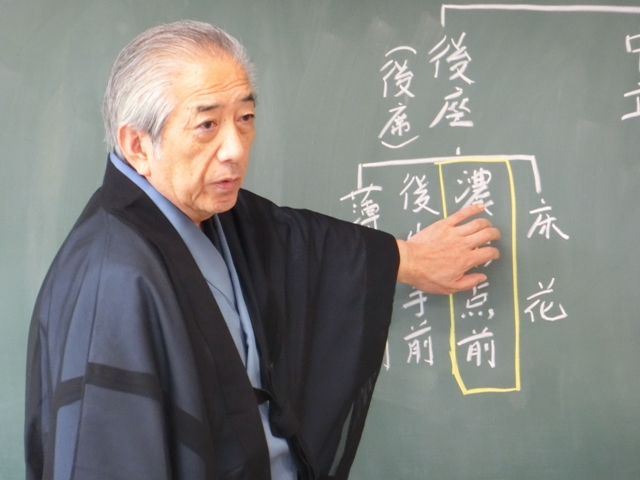

実施しました。概要は、以下のとおりです。
【概要】
11月23日(金・祝)
午後:・上賀茂神社 参拝・拝観
・西本願寺 特別拝観
解説:立命館大学文学部教授 本郷真紹
11月24日(土)
午前:・光悦寺 拝観
・六角堂およびいけばな資料館 見学
・講義および華道体験
講師:華道家元池坊次期家元 池坊専好
午後:・講義および組香体験「お香の楽しみ方」
講師:株式会社松栄堂 専務取締役 畑元章
・高台寺 拝観
11月25日(日)
午前:・臨済宗建仁寺塔頭 霊源院 座禅体験および法話
講師:雲林院宗碩
・平安神宮 拝観およびお庭の説明
講師:植治 次期十二代 小川勝章
午後:・講義およびお茶席
講師:裏千家 今日庵業躰 倉斗宗覚
上賀茂神社
西本願寺 いけばな資料館
池坊 専好 先生
畑 元章 先生
雲林院 宗碩 先生 小川 勝章 先生
倉斗 宗覚 先生
2018年度 立命館西園寺塾 11月17日講義「文明(科学技術)はなぜ発展するのか?」を実施
2018年11月17日(土)
・14:00~15:30 講義1
・15:45~17:15 講義2
講師:千葉工業大学惑星探査研究センター 所長
【指定文献】
『文明は<見えない世界>がつくる』松井孝典【著】岩波新書

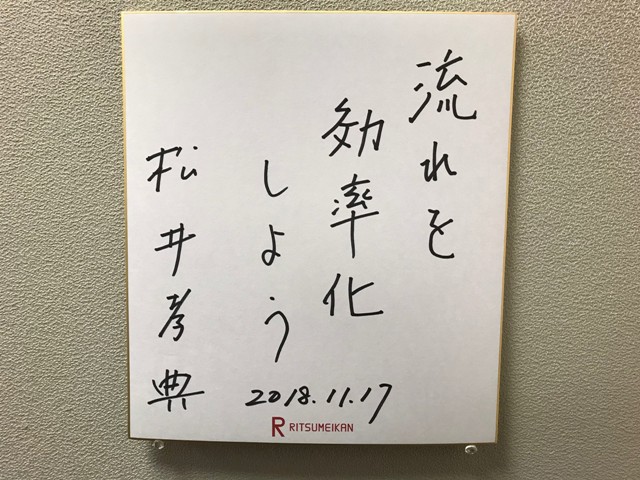


・14:00~15:30 講義1
・15:45~17:15 講義2
講師:千葉工業大学惑星探査研究センター 所長
東京大学 名誉教授
松井孝典
・17:15~18:00 質疑応答【指定文献】
『文明は<見えない世界>がつくる』松井孝典【著】岩波新書
2018年度 立命館西園寺塾 11月10日講義「古気候学が映し出す未来 -人類は気候の激動期をどう生きたか-」を実施
2018年11月10日(土)
・13:00~14:40 講義
講師:立命館大学総合科学技術研究機構 教授
・15:20~16:00 ディスカッション
・16:00~17:00 質疑応答
【指定文献】
『禁断の市場フラクタルでみるリスクとリターン』
ベノワ・B・マンデルブロ、リチャード・L・ハドソン【共著】東洋経済新報社
『チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る』 大河内 直彦【著】岩波現代文庫

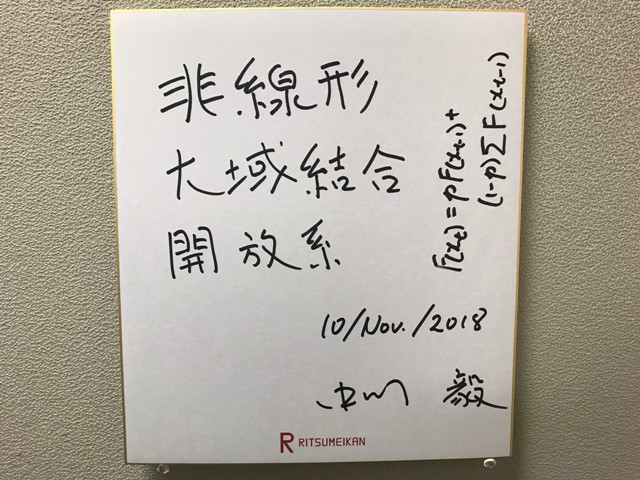
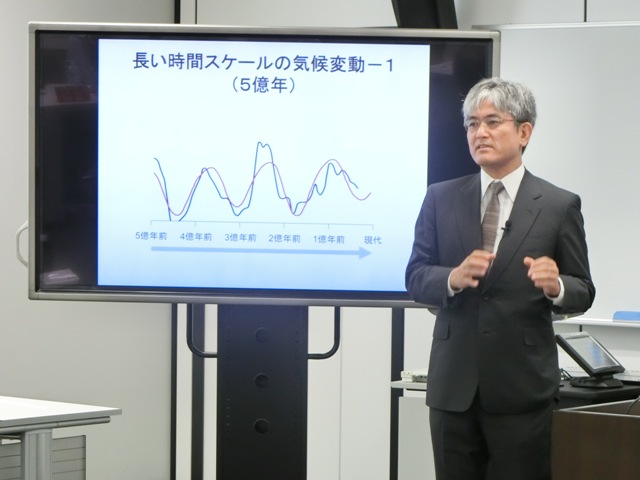

・13:00~14:40 講義
講師:立命館大学総合科学技術研究機構 教授
古気候学研究センター長
中川 毅
・14:55~15:20 質疑応答・15:20~16:00 ディスカッション
・16:00~17:00 質疑応答
【指定文献】
『禁断の市場フラクタルでみるリスクとリターン』
ベノワ・B・マンデルブロ、リチャード・L・ハドソン【共著】東洋経済新報社
『チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る』 大河内 直彦【著】岩波現代文庫
2018年度 立命館西園寺塾 10月27日講義「文明の海洋史観」を実施
2018年10月27日(土)
・13:00~17:00 講義
講師:静岡県知事
川勝 平太
【指定文献】
『文明の海洋史観』 川勝 平太【著】中公文庫

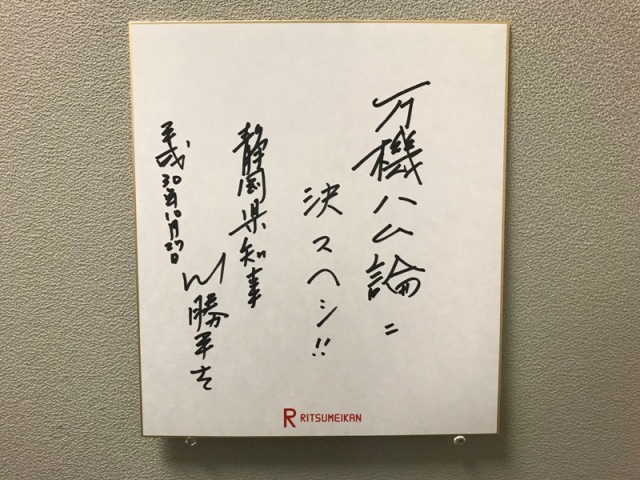


・13:00~17:00 講義
講師:静岡県知事
川勝 平太
【指定文献】
『文明の海洋史観』 川勝 平太【著】中公文庫
『日本思想の古層』 梅原 猛、川勝 平太【共著】藤原書店
2018年度 立命館西園寺塾 10月13日講義「ビジネスにおけるアートとサイエンスのリバランス」を実施
2018年10月13日(土)
・13:00~17:00 講演・ディスカッション
講師:コーン・フェリー・ヘイグループ シニア・パートナー
山口 周
【事後課題】
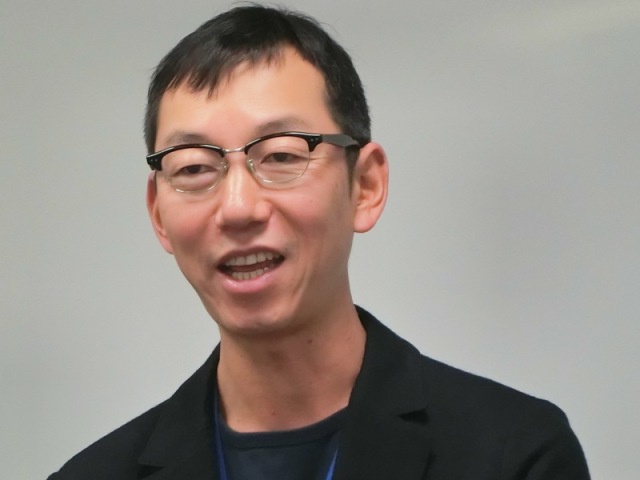
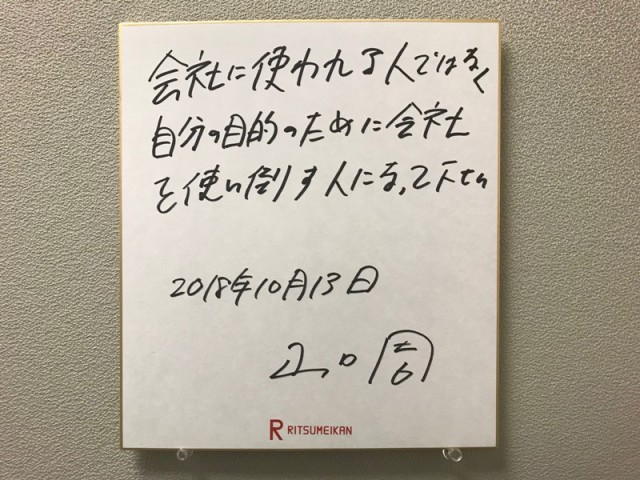


・13:00~17:00 講演・ディスカッション
講師:コーン・フェリー・ヘイグループ シニア・パートナー
山口 周
【事後課題】
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』山口周【著】光文社
Archive
- Home
- ニュース
