Updatesニュース
最新のニュース
2018年度 立命館西園寺塾 8月4日講義「JAL再生と意識改革の必要性」を実施
2018年8月4日(土)
・13:00~14:00 講演
講師:元 京セラ株式会社取締役執行役員常務
大田 嘉仁
・14:15~17:00 ディスカッション
【指定文献】
『JAL再生―高収益企業への転換』引頭麻実【編】日本経済新聞出版社
『稲盛和夫の実学―経営と会計』稲盛和夫【著】日本経済新聞出版社

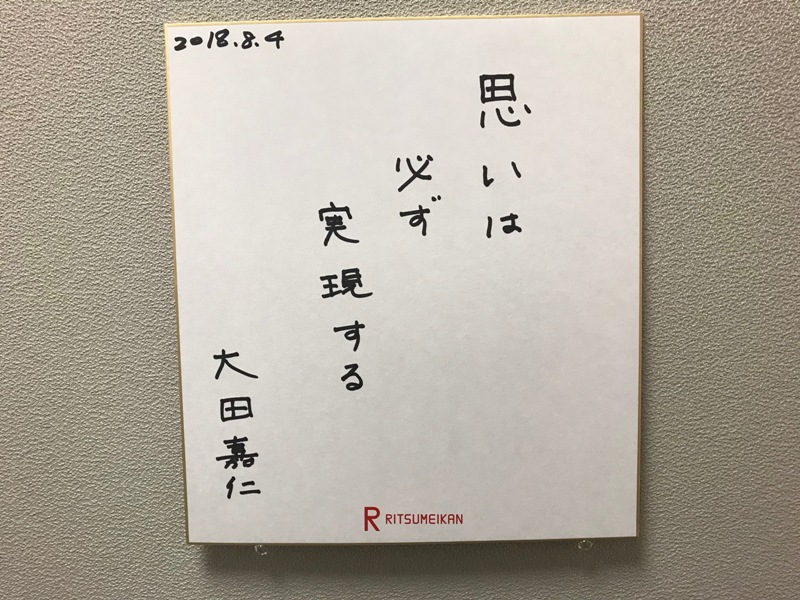


・13:00~14:00 講演
講師:元 京セラ株式会社取締役執行役員常務
大田 嘉仁
・14:15~17:00 ディスカッション
【指定文献】
『JAL再生―高収益企業への転換』引頭麻実【編】日本経済新聞出版社
『稲盛和夫の実学―経営と会計』稲盛和夫【著】日本経済新聞出版社
『心を高める、経営を伸ばす』稲盛和夫【著】PHP研究所; 新装版
2018年度 立命館西園寺塾 7月28日講義を実施
2018年7月28日(土)
・13:00~14:45 講演
講師:株式会社三越伊勢丹ホールディングス 特別顧問
石塚 邦雄
・15:00~17:00 ディスカッション
【指定文献】
『自由からの逃走』 エーリッヒ・フロム 【著】日高六郎【訳】東京創元社
『人工知能の核心』羽生善治【著】NHK出版
『日の名残り』カズオ・イシグロ【著】土屋政雄【訳】中央公論社

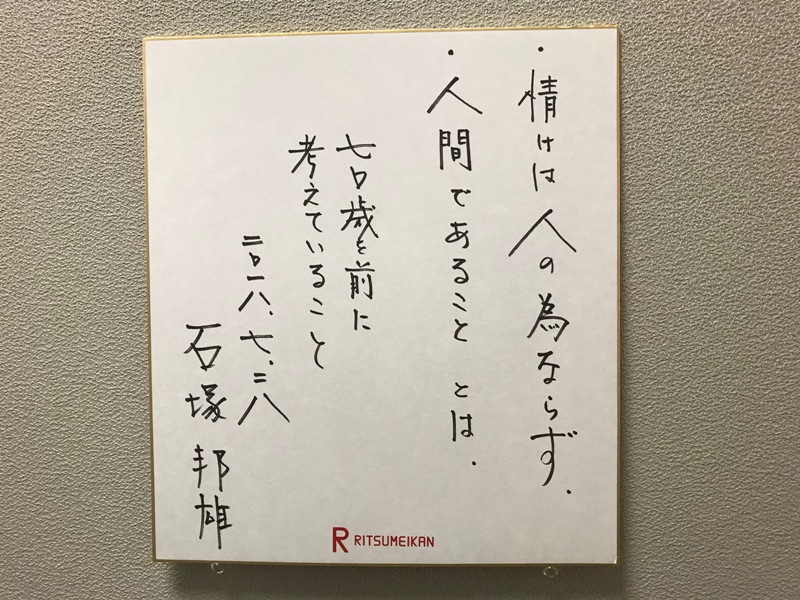


・13:00~14:45 講演
講師:株式会社三越伊勢丹ホールディングス 特別顧問
石塚 邦雄
・15:00~17:00 ディスカッション
【指定文献】
『自由からの逃走』 エーリッヒ・フロム 【著】日高六郎【訳】東京創元社
『人工知能の核心』羽生善治【著】NHK出版
『日の名残り』カズオ・イシグロ【著】土屋政雄【訳】中央公論社
『われ敗れたり- コンピュータ棋戦のすべてを語る』米長邦雄【著】中央公論新社
2018年度 立命館西園寺塾 7月21日講義「実戦リーダーシップの鍛え方」を実施
2018年7月21日(土)
入交 昭一郎
・14:40~17:00 ディスカッション
【指定文献】

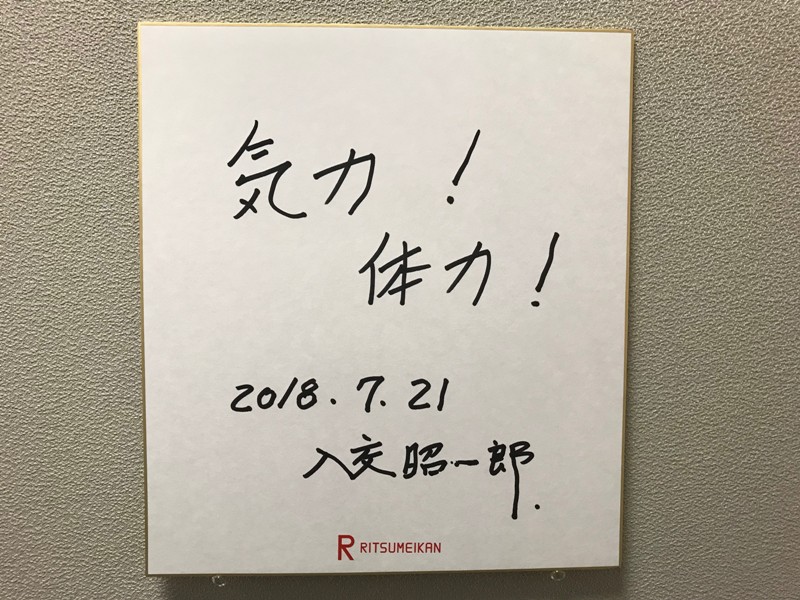


・13:00~14:35 講演
講師:有限会社入交昭一郎 代表取締役入交 昭一郎
・14:40~17:00 ディスカッション
【指定文献】
『リーダーシップの旅 ―見えないものを見る』野田智義・金井壽宏【著】光文社新書
2018年度 立命館西園寺塾 九州フィールドワークを実施
7月13日(金)~15日(日)、宮崎県および大分県においてフィールドワークを実施しました。
概要は、以下のとおりです。
【概要】
7月13日(金)
・木花神社、みそぎ池 見学
・黒木本店工場、農業生産法人「よみがえる大地の会」、尾鈴山蒸留所 見学
講師:株式会社黒木本店 代表取締役 黒木 敏之
7月14日(土)
・天岩戸神社、天安河原、荒立神社、高千穂神社、高千穂峡 見学
7月15日(日)
・立命館アジア太平洋大学(APU)の概要説明、役職者との懇談会
立命館アジア太平洋大学 学長 出口治明
立命館アジア太平洋大学 副学長 横山研治
・APUの国内学生および国際学生との懇談会






概要は、以下のとおりです。
【概要】
7月13日(金)
・木花神社、みそぎ池 見学
・黒木本店工場、農業生産法人「よみがえる大地の会」、尾鈴山蒸留所 見学
講師:株式会社黒木本店 代表取締役 黒木 敏之
7月14日(土)
・天岩戸神社、天安河原、荒立神社、高千穂神社、高千穂峡 見学
7月15日(日)
・立命館アジア太平洋大学(APU)の概要説明、役職者との懇談会
立命館アジア太平洋大学 学長 出口治明
立命館アジア太平洋大学 副学長 横山研治
・APUの国内学生および国際学生との懇談会
・学生によるキャンパスツアー
【指定文献】
『極上の酒を生む土と人 大地を醸す』山同 敦子【著】講談社
『混ぜる教育 -80カ国の学生が学ぶ立命館アジア太平洋大学APUの秘密』
崎谷 実穂・柳瀬 博一【著】日経BP社
『混ぜる教育 -80カ国の学生が学ぶ立命館アジア太平洋大学APUの秘密』
崎谷 実穂・柳瀬 博一【著】日経BP社
2018年度 立命館西園寺塾 7月7日講義「バリアバリュー~障害を価値に変える~」を実施
2018年7月7日(土)
・12:30~14:30 講義・質疑応答
講師:株式会社ミライロ 代表取締役社長
日本ユニバーサルマナー協会 代表理事
2020東京大会組織委員会 アドバイザー
垣内 俊哉
・14:45~15:30 高齢者体験 実技講習
・15:40~17:40 ユニバーサルマナー検定(3級)

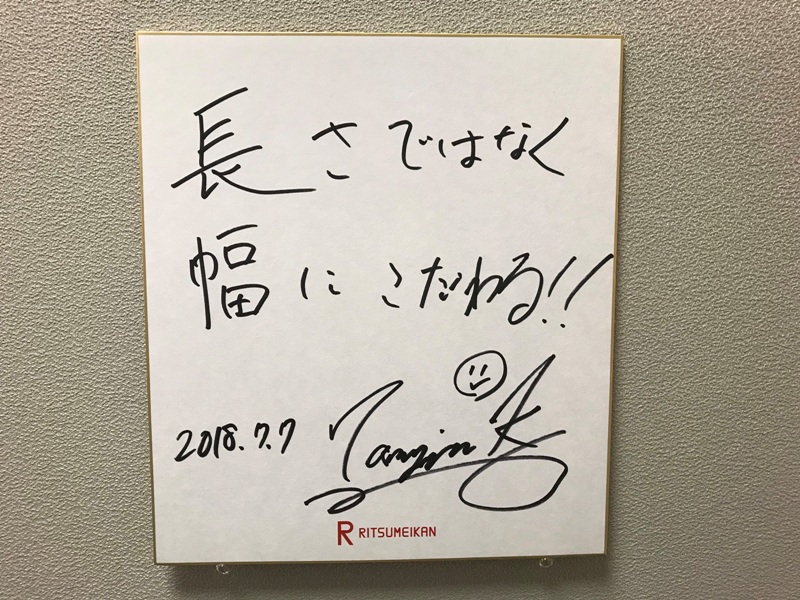




・12:30~14:30 講義・質疑応答
講師:株式会社ミライロ 代表取締役社長
日本ユニバーサルマナー協会 代表理事
2020東京大会組織委員会 アドバイザー
垣内 俊哉
・14:45~15:30 高齢者体験 実技講習
・15:40~17:40 ユニバーサルマナー検定(3級)
【指定文献】
2018年度 立命館西園寺塾 6月30日講義「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。」を実施
2018年6月30日(土)
【指定文献】
『経営学』小倉昌男【著】日経BP社
『ムハマド・ユヌス 自伝 上・下』ムハマド・ユヌス/アラン・ジョリ【著】
猪熊弘子【訳】早川書房
『ロケットボーイズ 上・下』ホーマー・ヒッカム・ジュニア【著】
武者圭子【訳】草思社
※参考:映画「遠い空の向こうに」ジョー・ジョンストン【監督】
(原作『ロケットボーイズ』)
・12:30~13:30 特別講義「九州フィールドワークに向けて」
講師:立命館大学文学部教授・立命館西園寺塾コーディネーター
本郷 真紹
・13:45~15:15 講義
講師:株式会社ユーグレナ 代表取締役社長
出雲 充
・15:30~17:00 ディスカッション
【指定文献】
『経営学』小倉昌男【著】日経BP社
『ムハマド・ユヌス 自伝 上・下』ムハマド・ユヌス/アラン・ジョリ【著】
猪熊弘子【訳】早川書房
『ロケットボーイズ 上・下』ホーマー・ヒッカム・ジュニア【著】
武者圭子【訳】草思社
※参考:映画「遠い空の向こうに」ジョー・ジョンストン【監督】
(原作『ロケットボーイズ』)
2018年度 立命館西園寺塾 6月23日講義「目指すべき社会を考える」を実施
2018年6月23日(土)
堂目 卓生
・14:45~15:00 質疑応答
【指定文献】
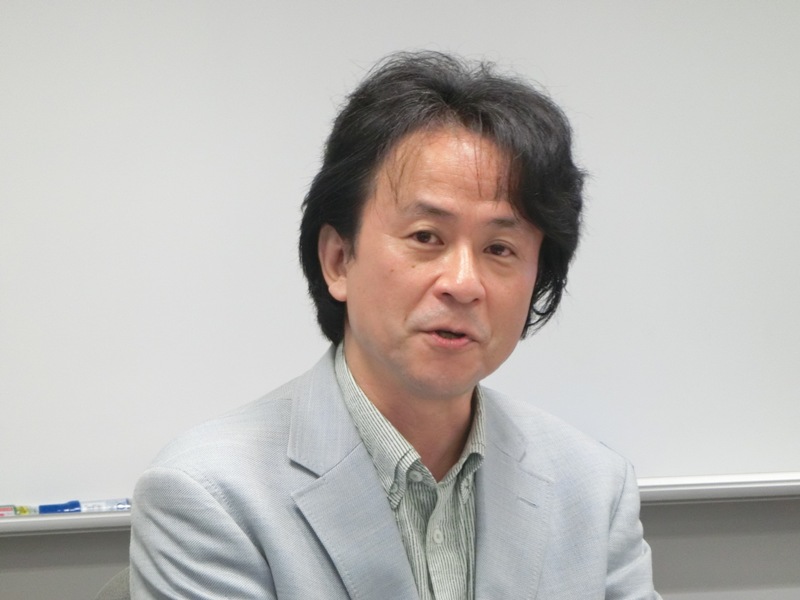
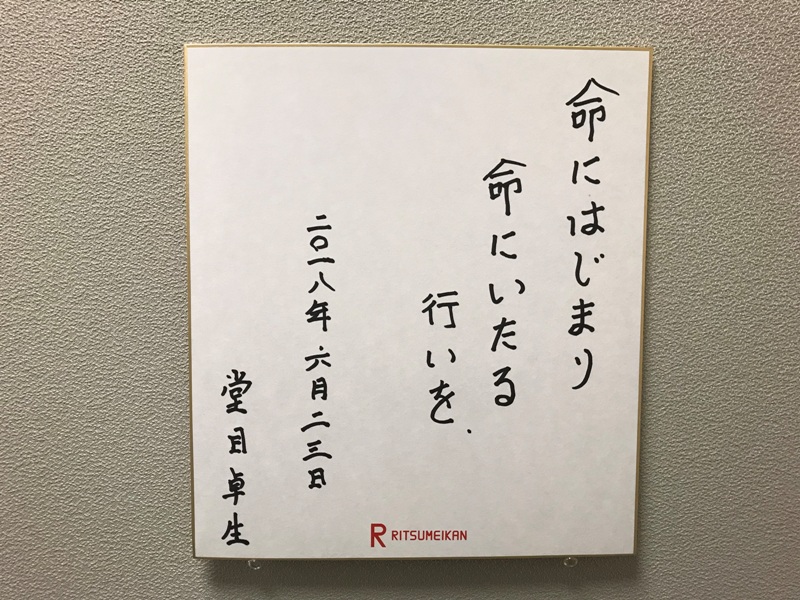

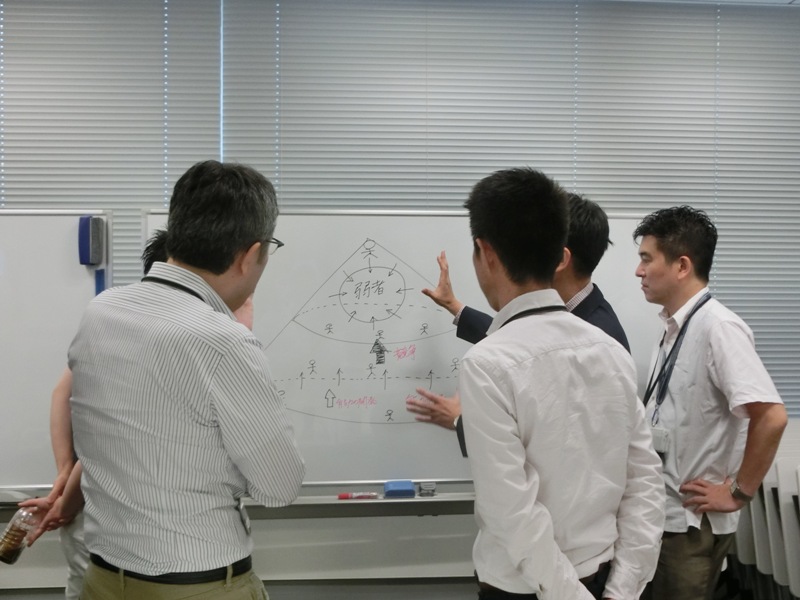
・13:30~14:45 講演
講師:大阪大学大学院経済学研究科 教授堂目 卓生
・14:45~15:00 質疑応答
・15:15~17:15 グループワーク
・17:15~17:45 ディスカッション
・17:45~18:00 統括
【指定文献】
『アダム・スミス―「道徳感情論」と「国富論」の世界』 堂目卓生【著】中公新書
2018年度 立命館西園寺塾 6月16日講義「その日暮らしの生き方と働き方」を実施
2018年6月16日(土)
・13:00~14:30 講義
講師:立命館大学大学院先端総合学術研究科 副研究科長
小川 さやか
・14:40~17:30 ディスカッション
【指定文献】
『実践日々のアナキズム ―世界に抗う土着の秩序の作り方』
ジェームズ・C.スコット【著】清水展・日下渉・中溝和弥【訳】岩波書店
『「その日暮らし」の人類学 ―もう一つの資本主義経済』小川さやか【著】光文社

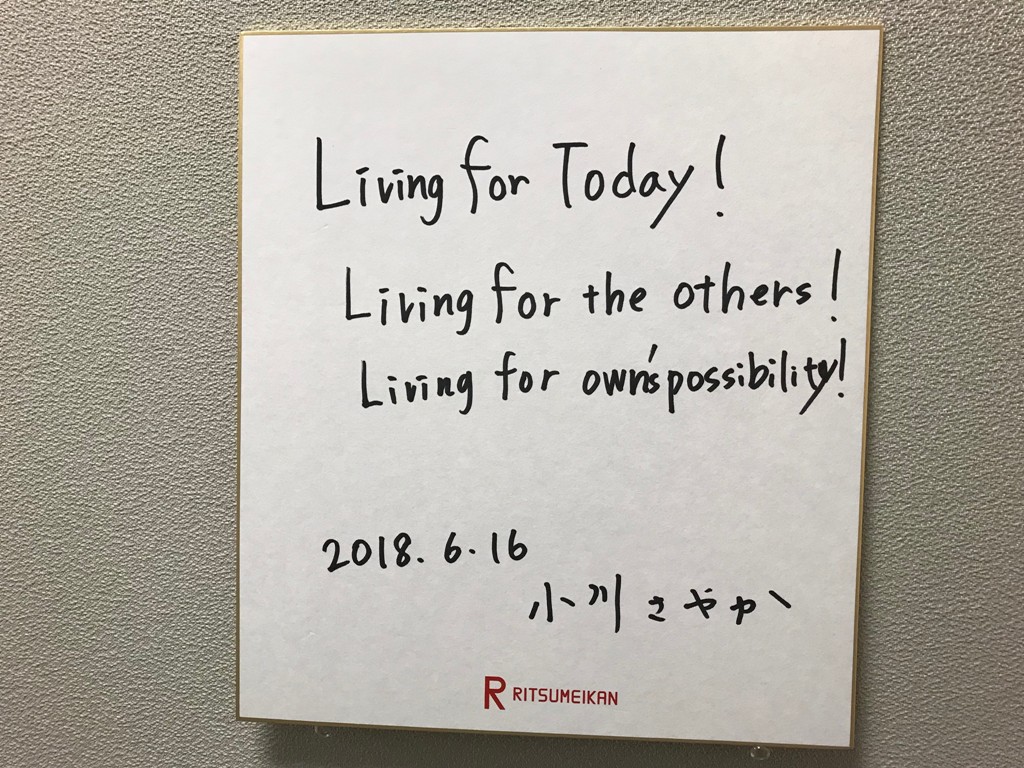
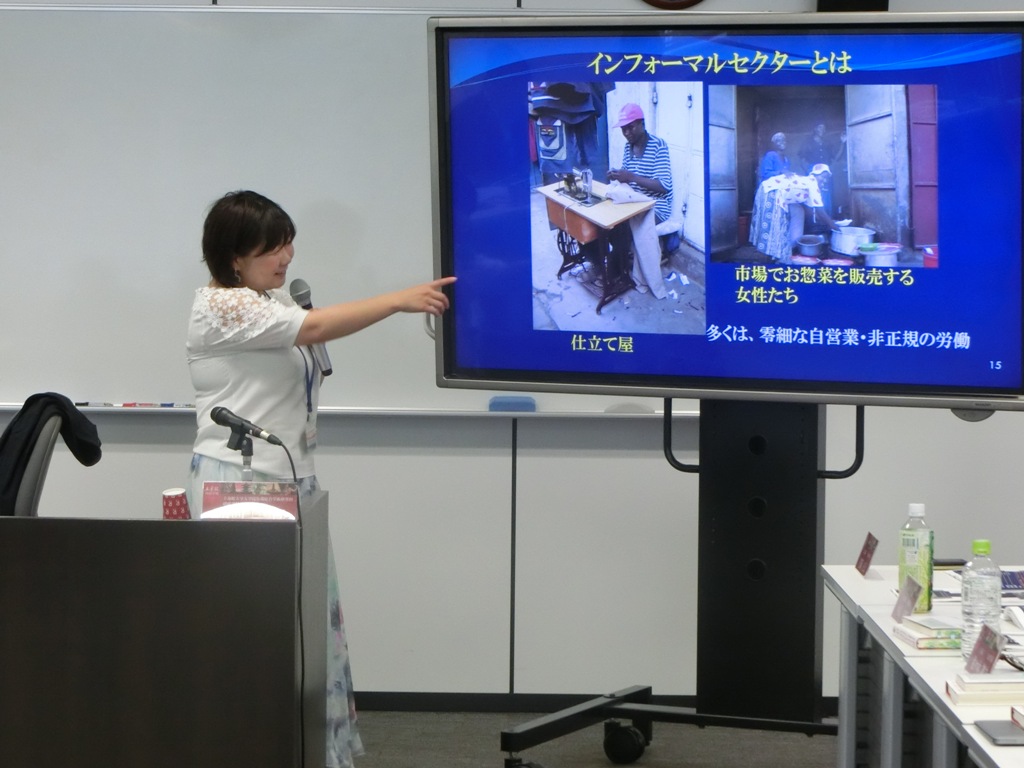

・13:00~14:30 講義
講師:立命館大学大学院先端総合学術研究科 副研究科長
小川 さやか
・14:40~17:30 ディスカッション
【指定文献】
『実践日々のアナキズム ―世界に抗う土着の秩序の作り方』
ジェームズ・C.スコット【著】清水展・日下渉・中溝和弥【訳】岩波書店
『「その日暮らし」の人類学 ―もう一つの資本主義経済』小川さやか【著】光文社
2018年度 立命館西園寺塾 6月2日講義「緊迫する国際情勢と日本」を実施
2018年6月2日(土)
・13:30~15:30 1~5期生合同講義(前半)
講師:立命館大学国際関係学部 客員教授
薮中 三十二
・15:45~17:00 1~5期生合同講義(後半)
・17:30~19:30 1~5期生合同懇親会
【指定文献】
『日本の針路―ヒントは交隣外交の歴史にあり』 薮中三十二【著】岩波書店

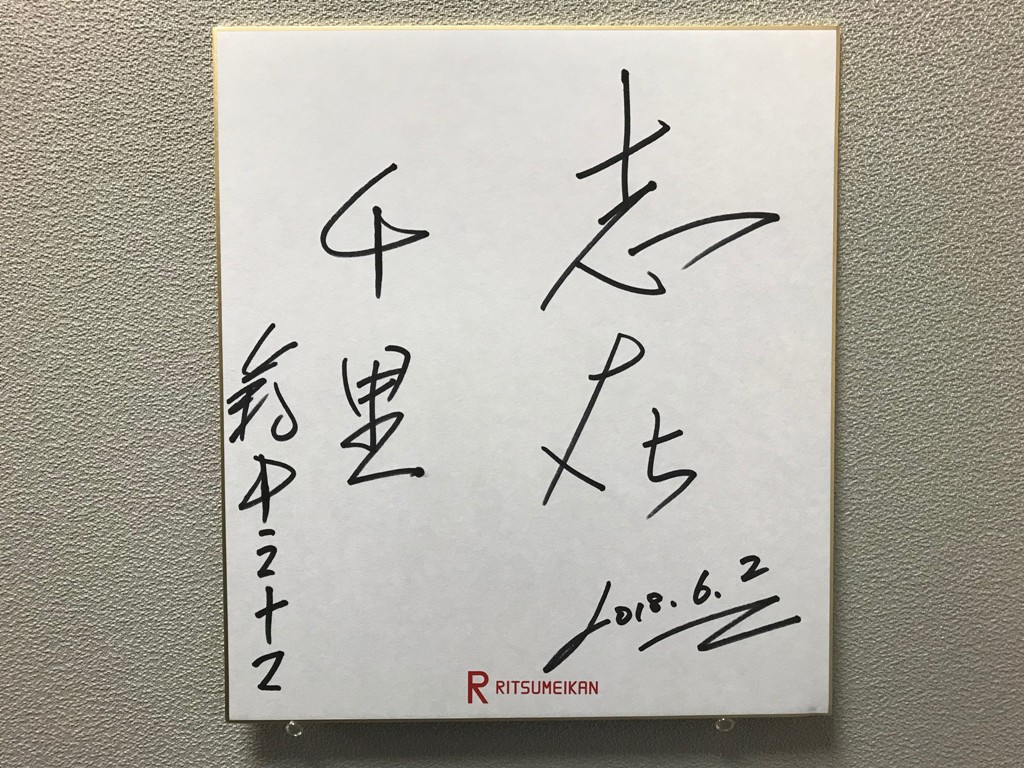

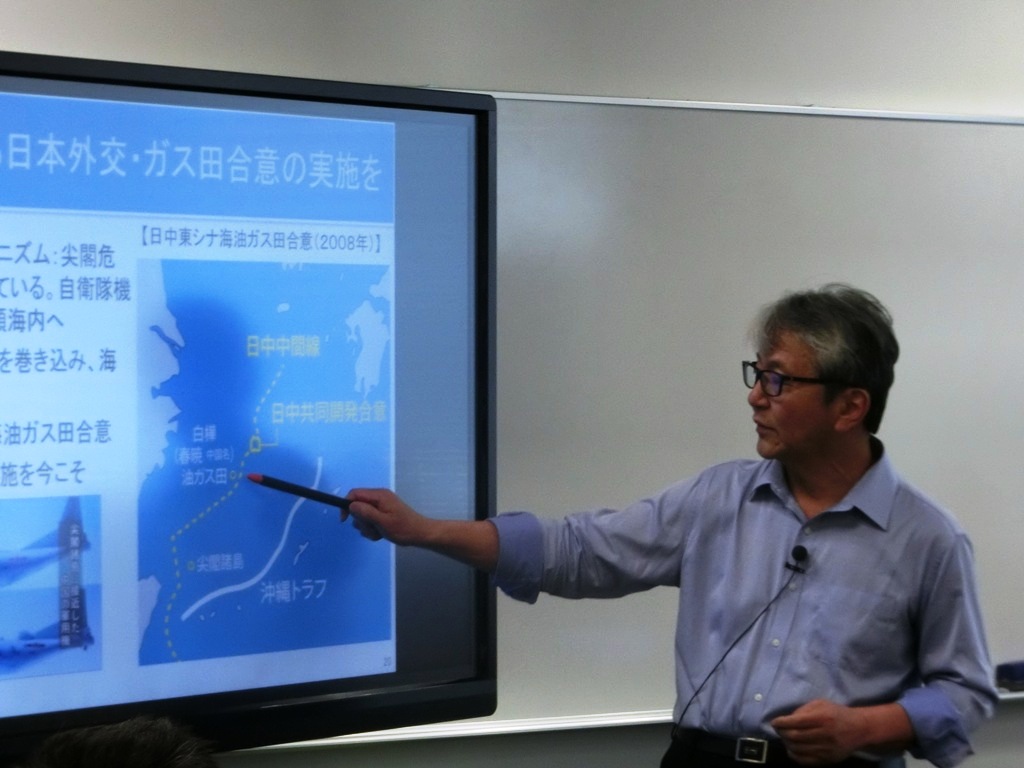
・13:30~15:30 1~5期生合同講義(前半)
講師:立命館大学国際関係学部 客員教授
薮中 三十二
・15:45~17:00 1~5期生合同講義(後半)
・17:30~19:30 1~5期生合同懇親会
【指定文献】
『日本の針路―ヒントは交隣外交の歴史にあり』 薮中三十二【著】岩波書店
2018年度 立命館西園寺塾 5月26日講義「資本主義の行方とアートとしての経済学」を実施
2018年5月26日(土)
・13:00~15:00 講義1-資本主義の行方
講師:大阪大学大学院経済学研究科 准教授
安田 洋祐
・15:15~16:50 講義2-資本主義の行方
・17:00~18:00 講義3-アートとしての経済学
【指定文献】
『資本の世界史 資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか』
ウルリケ・ヘルマン【著】太田出版
『ゲーム理論はアート 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学』
松島斉【著】日本評論社
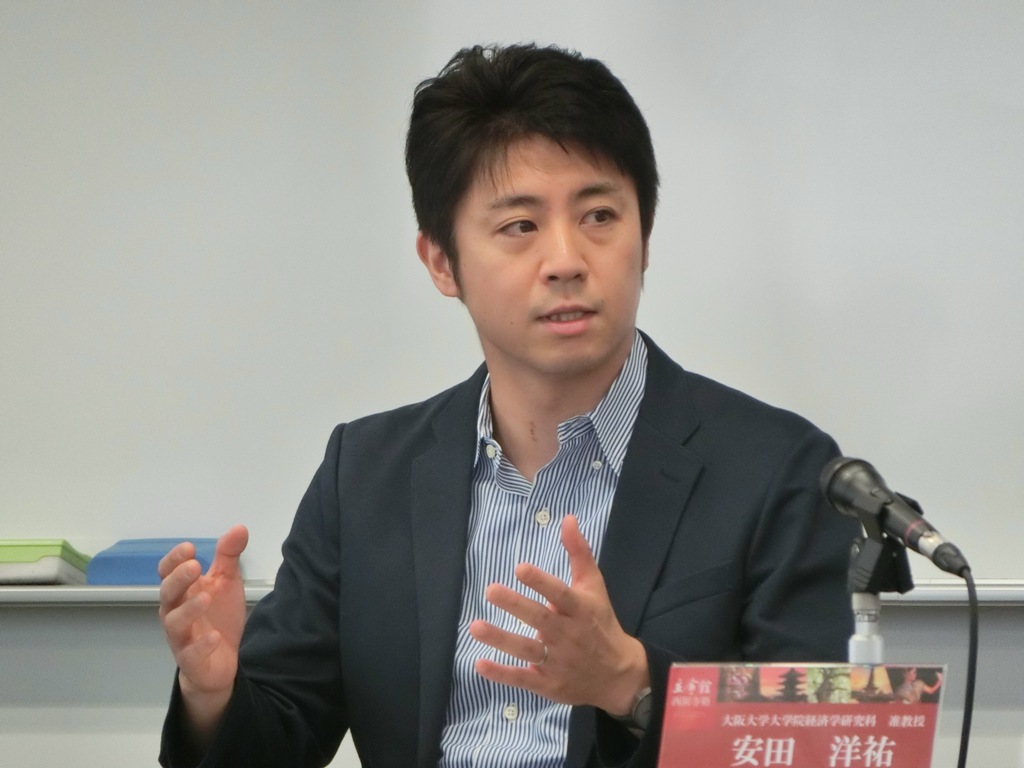
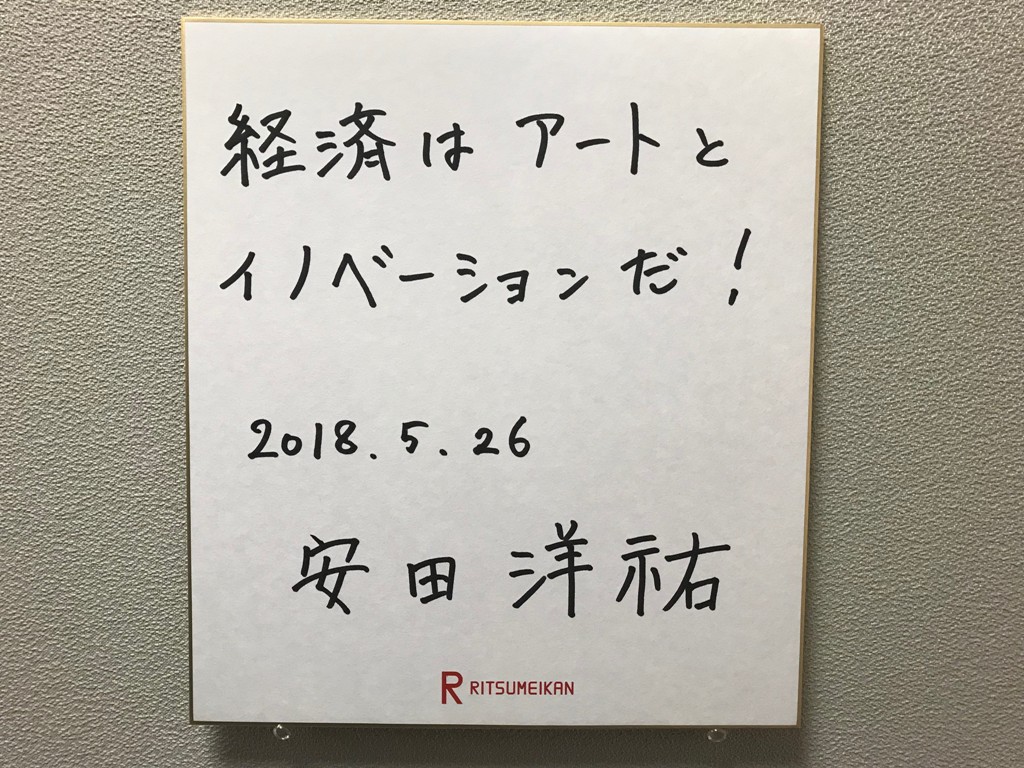
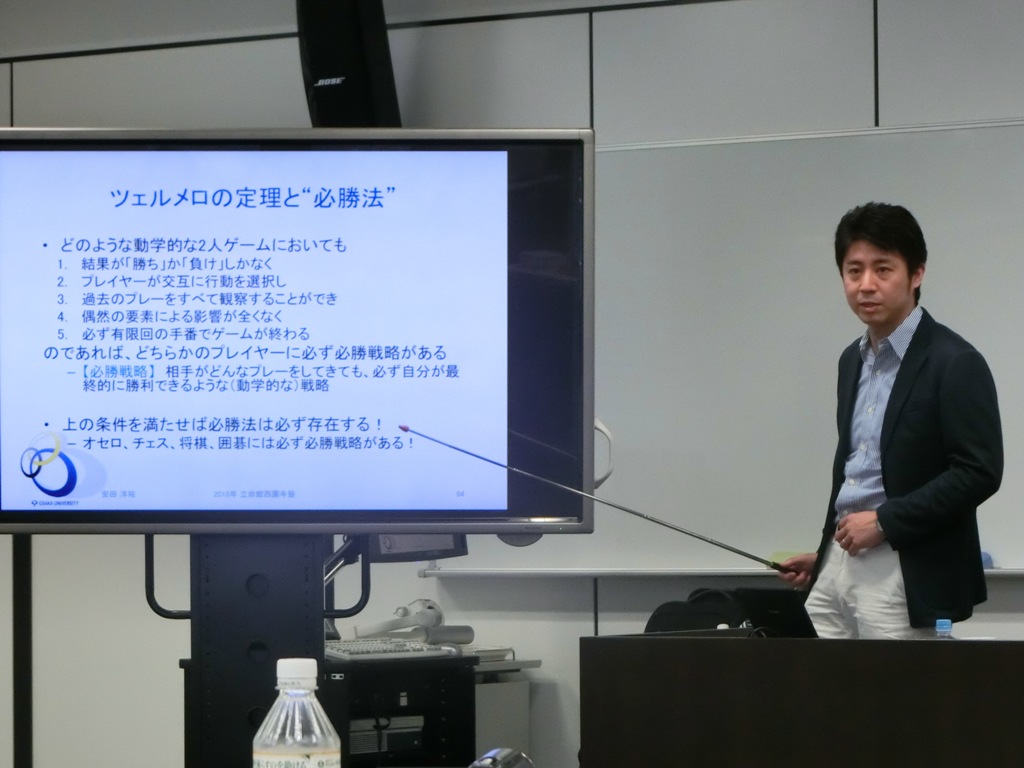

・13:00~15:00 講義1-資本主義の行方
講師:大阪大学大学院経済学研究科 准教授
安田 洋祐
・15:15~16:50 講義2-資本主義の行方
・17:00~18:00 講義3-アートとしての経済学
【指定文献】
『資本の世界史 資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか』
ウルリケ・ヘルマン【著】太田出版
『ゲーム理論はアート 社会のしくみを思いつくための繊細な哲学』
松島斉【著】日本評論社
Archive
- Home
- ニュース
