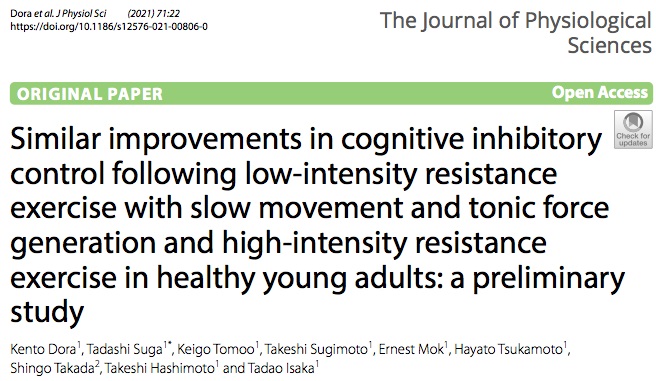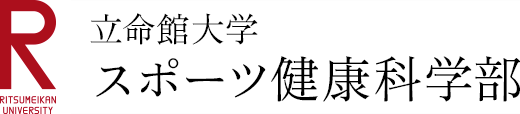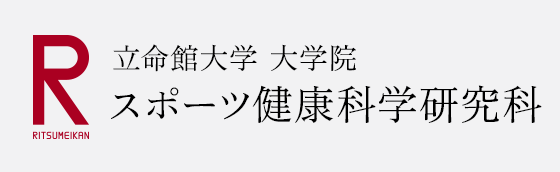スポーツ健康科学研究科博士課程前期課程2回生 道羅絢斗さんが, 総合科学技術研究機構菅唯志准教授,スポーツ健康科学部・同研究科, 塚本敏人助教,橋本健志教授, 伊坂忠夫教授, 北翔大学・生涯スポーツ学部高田真吾講師と共同で取り組まれた研究論文が「The
Journal of Physiological Sciences」に原著論文として掲載されました.
近年,運動により人々が健康的な生活を送るために重要な認知機能を向上・改善できることが明らかにされています.これまで本研究グループは,一過性のレジスタンス運動後に認知実行機能が亢進することを報告しています(Dora et al., Heliyon, 2021;Tsukamoto et al., PLoS One, 2017;Tomoo et al., Physiol Rep, 2021)。また、このようなレジスタンス運動誘発性の認知実行機能の亢進程度は, 低強度運動に比べて高強度運動において大きいことを報告しています(Tsukamoto
et al. PLoS One, 2017).しかしながら,高強度レジスタンス運動は,高齢者や有疾患者に施行することがしばしば困難です.一方,スロートレーニングと呼ばれるレジスタンス運動は,高齢者や慢性疾患者でも安全に実施できる効果的なレジスタンス運動法として期待されています.
スロートレーニングは、低速度で運動を実施するため,筋骨格系や心血管系にかかる負荷が比較的小さいとされています.また,低速度で運動を行い,筋発揮張力を維持することでトレーニング効果を高めます.実際に,低強度レジスタンス運動であってもスロートレーニングを用いることで高強度レジスタンス運動と同等の筋肥大・筋力増強効果を得られることが明らかにされています.本研究では,一般的な運動速度(拳上局面1秒, 下降局面, 脱力局面1秒)での高強度レジスタンス運動(最大挙上重量の80%)とスロートレーニング(拳上局面3秒, 下降局面, 1秒維持)を用いた低強度レジスタンス運動(最大挙上重量の50%)をそれぞれ実施した後の認知実行機能を比較しました.その結果,両条件とも認知実行機能は亢進しました.さらに,この認知実行機能の亢進程度は両条件で同様でした.したがって,本研究の結果から,スロートレーニングを用いた低強度レジスタンス運動は,高強度レジスタンス運動と同様に筋機能および脳機能の双方を効果的かつ効率的に向上させることができ,且つ幅広い人々が実施可能な汎用性の高い運動処方となりうる可能性を示唆しました.
https://jps.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12576-021-00806-0
https://jps.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12576-021-00806-0.pdf