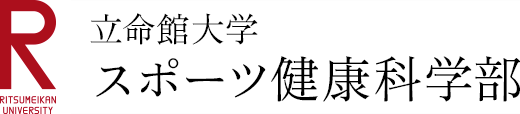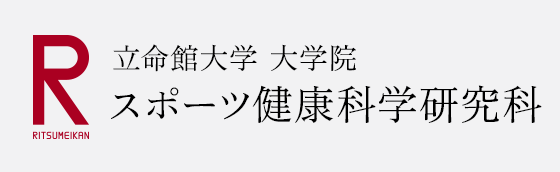2022.06.28
生涯スポーツ論 特別講義 「多様な性 スポーツ界は:キャスター・セメンヤの問題を軸に」
速水 徹氏(一般社団法人子ども未来・スポーツ社会文化研究所主席研究員・立命館大学客員教授)
去る2022年6月23日における生涯スポーツ論の授業にて、元朝日新聞論説委員で、現在、一般社団法人子ども未来・スポーツ社会文化研究所主席研究員であり、本学客員教授でもある速水徹氏から「多様な性 スポーツ界は」というタイトルで、特別講義をしていただきました。
速水氏は、法的整備をはじめ、LGBTQといった多様な性が認められる社会において、「男性」と「女性」とが明確に区別されているものは、「トイレ」「公衆浴場」、そして「トップレベルのスポーツ」くらいではないかと学生に問いを投げかけられました。公正な競技運営を施す上で、様々なルールや規定は確かに重要であるものの、染色体で「区別」することが可能であった性において、心身の様々な発達が「性分化疾患(Disorders of Sex Development:DSD)」の規定を困難している状況について説明されました。とりわけ、2012年ロンドン五輪と2016年リオデジャネイロ五輪において、女子800mで2大会連続の金メダリストに輝いた南アフリカ共和国のキャスター・セメンヤ選手のDSDを巡る問題とスポーツ仲裁裁判所(CAS)の裁定について紹介されました。
セメンヤ選手は、男性における主要な性ホルモンの1つであるテストステロンが、平均的な女性よりも、値が高いため、国際陸上競技連盟(現在、ワールドアスレティックス)は、テストステロンに関する新たな規定を定め、セメンヤ選手の出場資格を制限しようとしました。セメンヤ選手と南アフリカ共和国陸上競技連盟は、この規定の無効を求めて、CASに訴えましたが、CASは国際陸上競技連盟の新規定を容認し、セメンヤ選手らの訴えを退けました。つまり、セメンヤ選手が今後、国際陸上競技連盟が主催する大会に出場するには、テストステロン値を下げる薬を服用しなければならなくなったという経緯について説明されました。
速水氏は、女性アスリートに対する参加資格の厳格化やLGBTQといった多様な性の在り方、またそれらに対するスポーツ界の対応がスポーツそのものの発展にどのような影響をもたらすのかについて、学生に問いかけながら、講義を進められました。また速水氏は、「スポーツ健康科学」を学ぶ学生に対し、公平性の名のもとに、男女二元性を堅持し続けるスポーツ界において、新たな制度設計やマイノリティの権利の保護などにどのように向き合うべきなのか、「問い」を立てて、考え続けてほしいというメッセージを残されました。