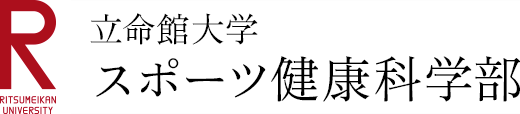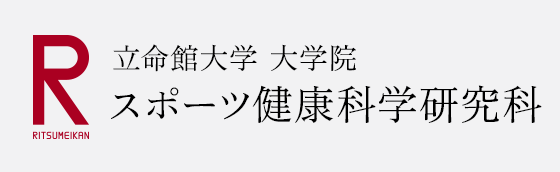2018.12.17 research
本学部助教 寺田 昌史先生がケンタッキー大学大学院健康科学・リハビリテーション学研究科Phillip A. Gribble先生らと共同で取り組まれた研究が、「Motor control」に原著論文として掲載されました。
本学部助教 寺田 昌史先生がケンタッキー大学大学院健康科学・リハビリテーション学研究科Phillip A. Gribble先生らと共同で取り組まれた研究が、「Motor
control」に原著論文として掲載されました。
この研究論文は、足圧中心軌跡の非線形時系列解析による評価から慢性足関節不安定症(CAI)の立位姿勢制御の特徴を探りました。
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30318988
Dr. Terada, Assistant Professor in College of Sport and Health Science, published a research manuscript in Motor Control, co-authored with Dr. Gribble, Dr. Beard, Ms. Carey, Dr. Pfile, Dr. Pietrosimone, Dr. Rullestad, and Ms. Whitaker. This study assessed static postural control performance in individuals with chronic ankle instability, lateral ankle sprain copers, and healthy controls using nonlinear dynamic measures
Terada M, Beard M, Carey S, Pfile K, Pietrosimone B, Rullestad E, Whitaker H, Gribble P. Nonlinear Dynamic Measures for Evaluating Postural Control in Individuals with and without Chronic Ankle Instability. Motor Control. 2018;13:1-19.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30318988