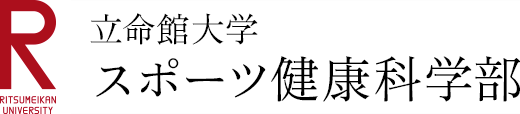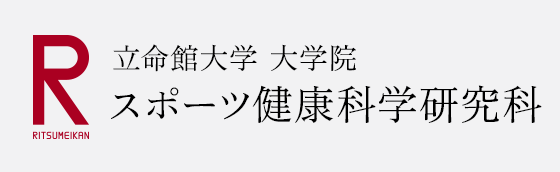2017.04.14 research
2017/04/14 スポーツ健康科学研究科博士課程前期課程2回生の堀居 直希さんが同研究科教授、家光素行先生、教授橋本健志先生、教授田畑泉先生、助教内田昌隆先生と共同で取り組まれた研究が、「Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol」に原著論文として掲載されました。
スポーツ健康科学研究科博士課程前期課程2回生の堀居 直希さんが同研究科教授、家光素行先生、教授橋本健志先生、教授田畑泉先生、助教内田昌隆先生と共同で取り組まれた研究が、「Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol」に原著論文として掲載されました。
この研究論文では、6週間の間欠的短時間高強度運動とクロレラ摂取の併用が運動パフォーマンスと骨格筋のエネルギー代謝をそれぞれ単独よりも加算的に亢進させることを明らかにしました。
Horii N, Hasegawa N, Fujie S, Uchida M, Miyamoto-Mikami E, Hashimoto T, Tabata I, Iemitsu M. High-intensity intermittent exercise training with chlorella intake accelerates exercise performance and muscle glycolytic and oxidative capacity in rats. (2017) Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 312(4): R520-R528.