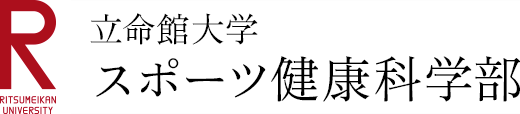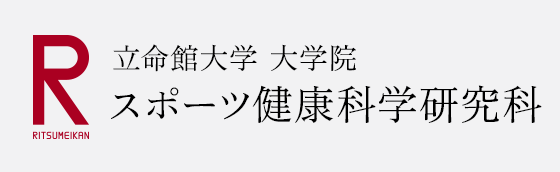2016.10.14 research
ニュース
researchのニュース
2016/10/21 立命館大学×順天堂大学『スポーツ健康科学研究交流セミナー』を開催します。
2016.10.06 research
2016/10/6 本研究科博士課程後期課程1回生水野沙洸さんの研究が、国際誌「International Journal of Sports Medicine」に原著論文として掲載されました。
スポーツ健康科学研究科博士課程後期課程1回生水野 沙洸さんがスポーツ健康科学部准教授 後藤 一成先生と共同で取り組まれた研究内容が、「International Journal of Sports Medicine」に原著論文として掲載されました。
本研究論文では、成人男性18名を対象に、持久性運動終了後におけるコンプレッションウェアの着用が運動パフォーマンスおよび筋損傷・炎症反応に及ぼす影響を、筋損傷の程度の差異に着目して検討を行いました。その結果、持久性運動終了後におけるコンプレッションウェアの着用は、運動パフォーマンスの回復を促進すること、またその効果は運動誘発性筋損傷が大きい場合にみられることが明らかとなりました。
Sahiro Mizuno, Ikuhiro Morii, Yoshifumi Tsuchiya and Kazushige Goto. International Journal of Sports Medicine, 2016; 37:870-877
2016.09.16 research
2016/9/12-14 第24回日本バイオメカニクス学会において、宇宙飛行士で立命館大学スポーツ健康科学部客員教授の山崎直子先生に特別講演を行っていただきました。
2016年9月12日に立命館大学びわこくさつキャンパスにて行われました第24回日本バイオメカニクス学会において「宇宙から考える未来のバイオメカニクス」というタイトルで、山崎直子先生に講演していただきました。
無重力環境にある宇宙では、人の身体は、歩かなくても良いので筋力が減る、胴体が2~5センチ伸びる、上のほうに血液が行くので脳が身体全体の体液が増えたと勘違いし尿の量が増え体重が減る、骨密度が骨粗しょう症の患者の10倍の速さで減る、などの様々な変化が現れるそうです。
人の身体は、ジョギングなどの運動のように、重力を感じながら身体を動かすことが大切で、この重力について考えることが、高齢化社会における予防医学に役立つのではないかとのことでした。
また現在、国際宇宙ステーションでは、骨粗しょう症の薬の開発・対処法、製薬会社による創薬の基礎実験、また、iPS細胞を用いた立体臓器培養実験等が行われているそうです。また自然科学分野だけでなく芸術分野の研究も行われているそうです。
①生命の持つ可能性、②1G重力下で進化してきた地球上の生命、③テクノロジー の3つを組み合わせることが、未来のバイオメカニクスの発展につながるとのことでした。
講演の最後に、質疑応答の時間が設けられ、障害者の障害の多くが重力によって生まれているのではないかとの質問に対して、たとえ足が不自由でも、宇宙では指1本で移動出来るので、障害が障害でなくなる、我々が持っている日頃の価値観が覆る、というお話が印象的でした。
2016.09.13 research
2016/9/20 立命館大学が目指す 次世代ICT×健康医療の融合に関するシンポジウムを開催します。

2016.07.19 research
2016/07/14 総合科学技術研究機構プロジェクト研究員の福谷充輝先生の研究が「PLOS ONE」に原著論文として掲載されました。
総合科学技術研究機構プロジェクト研究員である福谷充輝先生が、大学院生の御前純さん、伊坂忠夫教授と共同で研究を実施し、その成果が「PLoS ONE」に原著論文として掲載されました。この研究論文では、反動動作に伴う力発揮能力増強は、予備緊張、および筋線維の伸長に伴う力発揮能力増強によって生じていることを確認しました。反動動作に伴う力発揮能力増強のメカニズムを明らかにすることで、より効果的にスポーツパフォーマンスを向上させる策略を立てることが出来るようになる可能性があります。
Fukutani A, Misaki J, Isaka T. (2016). Effect of Preactivation on Torque Enhancement by the Stretch-Shortening Cycle in Knee Extensors. PLoS ONE 11(7): e0159058. doi:10.1371/journal.pone.0159058.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0159058
2016.07.14 research
2015/05/03 本究科博士課程前期課程1回生田中大智さんの研究が「International Journal of Sports Medicine」に原著論文として掲載されました。
本研究科博士課程前期課程1回生田中大智さんが本研究科教授伊坂忠夫先生、本学部助教菅唯志先生と共同で取り組まれた研究が、「International Journal of Sports Medicine」に原著論文として掲載されました。
これまでの先行研究(例えばKido et al. Physiol Rep, 2015) において、全身性の持久運動に先立って運動肢に短時間の虚血/再還流を複数回繰り返す虚血プレコンディショニング(IPC)を実施することで、骨格筋機能が高まることに関連して、運動持久力が増加することが示唆されていましたが、全身性の持久運動の場合は、IPCによる効果が心臓の適応を介して生じる可能性を除外できません。この研究論文では、局所運動においてもIPCを実施することで、骨格筋における酸素化動態が促進することに関連して、筋持久力が増加することを明らかにしました。したがって、IPCの効果機序は、骨格筋機能の増加を生理的基盤としている可能性が強く示唆されました。
Tanaka D, Suga T, Tanaka T, Kido K, Honjo T, Fujita S, Hamaoka T, Isaka T (2015). Ischemic preconditioning enhances muscle endurance during sustained isometric exercise. Int J Sports Med, Vol. 37: pp614-618.
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0035-1565141
2016.06.21 research
2016/06/18 本学部助教の寺田昌史先生の研究が「PM & R : the journal of injury, function, and rehabilitation」に原著論文として掲載されました。
本学部助教 寺田 昌史先生がケンタッキー大学大学院健康科学・リハビリテーション学研究科准教授 Phillip A. Gribble先生、ノースカロライナ大学シャーロット校キネシオロジー学部助教 Abbey Thomas先生、ノースカロライナ大学スポーツ運動科学部助教Brian Pietrosimone先生、シドニー大学健康科学部教授Clair Hiller 先生、ケントステイト大学のSamantha Bowkerさんと共同で取り組まれた研究が、「PM & R : the journal of injury, function, and rehabilitation」に原著論文として掲載されました。
この研究論文は、慢性足関節不安定症(CAI)と中枢神経における機能低下の関連性を検証するため、 経頭蓋磁気刺激(TMS)を用いてCAI患者のヒラメ筋の大脳皮質脊髄路興奮性および抑制性を評価しました。 CAI症例におけるヒラメ筋の大脳皮質脊髄路興奮性と抑制性のバランスが崩れていることが明らかになりました。これらの結果は、CAIの病態を理解するために重要な知見となり、中枢神経機能に対してリハビリテーション介入を行うことが,CAI患者の足関節安定性向上するために有用であると推測されます。
Terada M, Bowker S, Thomas AC, Pietrosimone B, Hiller CE, Gribble PA. (2016). Corticospinal excitability and inhibition of the soleus in individuals with chronic ankle instability. PM R. [Epub ahead of print].
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934148216301150
2016.06.21 research
2016/06/18 本学部助教の寺田昌史先生の研究が「Scandinavian journal of medicine & science in sports」に原著論文として掲載されました。
本学部助教 寺田 昌史先生がケンタッキー大学大学院健康科学・リハビリテーション学研究科准教授 Phillip A. Gribble先生、ノースカロライナ大学シャーロット校キネシオロジー学部助教 Abbey Thomas先生、ノースカロライナ大学スポーツ運動科学部助教Brian Pietrosimone先生、シドニー大学健康科学部教授Clair Hiller 先生、ケントステイト大学のSamantha Bowkerさんと共同で取り組まれた研究が、「Scandinavian journal of medicine & science in sports」に原著論文として掲載されました。
この研究論文は、慢性足関節不安定症(CAI)における主観症状の程度によって3つの病態モデルに分類し、様々な測定方法を用いてCAIの病態モデルの特徴を評価しています。CAIの病態はheterogenousと考えられ、CAIの原因をしっかりと見極めることがCAIに対してより効果的な予防・治療戦略の立案において最重要であることが示唆されました。これらの結果は、CAIの病態を理解するために重要な知見となるものです。
Terada M, Bowker S, Hiller CE, Thomas AC, Pietrosimone B, Gribble PA. (2016). Quantifying levels of function between different subgroups of chronic ankle instability. Scand J Med Sci Sports. doi: 10.1111/sms.12712.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.12712/abstract;jsessionid=F1C16096C94615585F6493165A2F4C72.f04t04
2016.06.21 research
2016/06/18 本学部助教の寺田昌史先生の研究が「Medicine & Science in Sport & Exercise」に原著論文として掲載されました。
本学部助教 寺田 昌史先生がケンタッキー大学大学院健康科学・リハビリテーション学研究科准教授 Phillip A. Gribble先生、同研究科の博士課程後期4回生のKyle Kosik さんとRyan McCannさんと共同で取り組まれた研究が、「Medicine & Science in Sport & Exercise」に原著論文として掲載されました。
この研究論文は、慢性足関節不安定症(CAI)が足関節だけでなく全身の機能に影響を及ぼすという観点から、CAIが横隔膜の機能に与える影響を検討しています。CAI患者の左横隔膜の収縮率が低下していること(左横隔膜が呼吸筋として活発に動いてないこと)を明らかにしました。これらの結果は、足関節捻挫後の安定性の再獲得および向上に有効な治療プログラムを開発するうえで重要な知見となるものです。
Terada M, Kosik KB, McCann RS, Gribble PA. (2016). Diaphragm Contractility in Individuals with Chronic Ankle Instability. Med Sci Sports Exerc. 2016. [Epub ahead of print].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27232242
2016.05.23 research
2016/05/20 本研究科助教・大塚光雄先生の研究が「SpringerPlus」に原著論文として掲載されました
本研究科助教・大塚光雄先生が、本研究科教授・伊坂忠夫先生、同研究科修了生・伊藤太祐さん、防衛大学校助教本城豊之先生との共同研究の上、 その研究内容がSpringerPlusに原著論文として掲載されました。このスプリント走に関する研究では、特殊なテーピング法を用いて肩甲骨回りの関節可動域を下げた結果、スプリント走時において下肢のキック動作が制限され、疾走速度の生成能力が低下することが明らかとなりました。つまり、肩甲骨回りの関節の活動は疾走パフォーマンスと関連があることが示唆されました。
Otsuka M., Ito T., Isaka T. (2016) Scapula behavior associates with fast sprinting in first accelerated running. SpringerPlus. 5: 1-9.
2016.04.28 research
016/04/28本研究科博士課程後期課程1回生水野沙洸さんの研究が、国際誌「SpringerPlus」に原著論文として掲載されました。
スポーツ健康科学研究科博士課程後期課程1回生、水野 沙洸さんの研究がスポーツ健康科学部准教授、後藤 一成先生と共同で取り組まれた研究内容が、「SpringerPlus」に原著論文として掲載されました。
本研究論文では、成人男性7名を対象に、サッカーをシミュレーションした90分間のランニング時における異なるタイミングでの糖質摂取が、運動パフォーマンスおよび筋損傷・炎症反応に及ぼす影響を検討しました。その結果、糖質摂取のタイミングの相違は、運動パフォーマンスや筋損傷・炎症反応の動態に影響を及ぼさないことが明らかとなりました。
Sahiro Mizuno, Chihiro Kojima and Kazushige Goto. Timing of carbohydrate ingestion did not affect inflammatory response and exercise performance during prolonged intermittent running. SpringerPlus 5(1): 1-8, 2016.
2016.04.07 research
2016/03/29 本研究科博士課程後期課程1回生 塚本敏人さん(日本学術振興会 特別研究員(DC1))の研究が「Physiology & Behavior」に原著論文として掲載されました。
本研究科博士課程後期課程1回生の塚本敏人さん(日本学術振興会 特別研究員(DC1))が同研究科准教授 橋本健志先生、東洋大学理工学部教授 小河繁彦先生らと共同で取り組まれた研究が、「Physiology & Behavior」に原著論文として掲載されました。
この研究論文は、高強度運動を間断的に繰り返し実施する高強度間欠的運動を、1時間の休息を挟んで2回実施すると、1回目の運動と比較して2回目の運動による乳酸産生量が少なくなることを明らかにしました。さらに、前回の我々の報告(2016/01/01のニュース参照(Tsukamoto H et al. Physiol Behav, 2016))では、高強度間欠的運動が、運動後の認知機能の亢進をより長い時間持続させることを報告しましたが、同じ運動強度、実施時間、運動様式の運動であるにもかかわらず、2回目の高強度間欠的運動のように乳酸産生量が少なくなると、亢進した認知機能の持続性が損なわれてしまうことを明らかにしました。この研究により、運動による認知機能亢進の持続性に、運動誘発性の乳酸産生量が重要な役割を担っている可能性が示されました。競技性スポーツなどで、競技開始直後および競技終盤に頻繁に見受けられる認知機能の低下には、乳酸が関与している可能性が考えられますが、脳の乳酸代謝と認知機能の直接的な関係については更なる検証が必要です。
Tsukamoto H, Suga T, Takenaka S, Tanaka D, Takeuchi T, Hamaoka T, Isaka T, Ogoh S, and Hashimoto T (2016). Repeated high-intensity interval exercise shortens the positive effect on executive function during post-exercise recovery in healthy young males. Physiol Behav, Vol.160: pp 26-34.
/file.jsp?id=2552952016.04.06 research
2016/04/04 本研究科博士課程後期課程2回生 塚本敏人さん(日本学術振興会 特別研究員(DC1))が21st annual Congress of the European College of Sport Scienceで「Nutrition Award Travel Grant」を受賞しました。
本研究科博士課程後期課程2回生の塚本敏人さん(日本学術振興会 特別研究員(DC1))が、今夏にウィーン(オーストリア)で開催される21st annual Congress of the European College of Sport Science(第21回ヨーロッパスポーツ科学会議)において、本研究科准教授 橋本健志先生、本研究科教授 伊坂忠夫先生、本研究科助教 菅唯志先生と共同で取り組まれた口頭発表予定の下記演題が、「GSSI Nutrition Award Travel Grant 2016」を受賞しました。
Tsukamoto H, Suga T, Ishibashi A, Takenaka S, Goto K, Ebi K, Isaka T, and Hashimoto T.
A COMBINATION OF ACUTE DYNAMIC EXERCISE AND FLAVANOL-RICH COCOA CONSUMPTION ADDITIVELY IMPROVE EXECUTIVE FUNCTION IN HUMAN
なお、塚本さんは2016年7月6日18時からのOpening ceremony (incl. Aspetar & GSSI award ceremony)にて表彰される予定です。
2016.04.06 research
2016/4 日本学術振興会特別研究員・PD(平成26年度スポーツ健康科学研究科修了)の森嶋琢真さんの研究が「Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism」に原著論文として掲載されました.
日本学術振興会特別研究員・PD(平成26年度スポーツ健康科学研究科修了、研究従事機関:筑波大学および米国ミズーリ州立大学)の森嶋琢真さんが本学准教授、後藤一成先生と共同で取り組まれた研究が,「Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism」に原著論文として掲載されました.
この研究論文は,通常(酸素濃度 20.9 %)よりも酸素濃度が低い低酸素環境(酸素濃度 15.0 %)への7時間の曝露が食後における食欲に関連するホルモンの分泌応答や主観的食欲の変化に及ぼす影響を検討したものです.
Takuma Morishima and Kazushige Goto. (2016). Ghrelin, GLP-1 and Leptin Responses during Exposure to Moderate Hypoxia. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 41(4): 375-381.
2016.04.04 research
2016/3/23本研究科博士課程後期課程1回生の石橋彩さんの研究が「体力科学」に原著論文として掲載されました。
スポーツ健康科学研究科博士課程後期課程1回生の石橋彩さんが同研究科 海老久美子教授、後藤一成准教授と共同で取り組まれた研究が、「体力科学」に原著論文として掲載されました。
この研究論文は、運動習慣のある成人男性に対する 4 週間のn-3系脂肪酸の摂取が長時間運動時の脂質代謝および 5 kmタイムトライアルにおけるパフォーマンスに及ぼす影響を検討しました。
その結果、4 週間のn-3系脂肪酸の摂取は60分間の長時間運動時の脂肪分解および脂肪利用をいずれも亢進させる可能性を示唆しました。
石橋 彩,佐々木 裕人,松宮 さおり,池戸 葵,海崎 彩,浜岡 隆文,後藤 一成,海老 久美子 (2016).4週間のn-3系多価不飽和脂肪酸摂取が運動時の脂質代謝に及ぼす影響.体力科学,65 (2)p.225-235.
2016.03.24 research
2016/3/24 本学部4回生の堀居 直希さんが同学部 家光素行教授と共同で取り組まれた研究が、「Hormone and Metabolic Research」に原著論文として掲載されました。
この研究論文では、肥満により低下した骨格筋の脂質代謝制御因子が6週間の有酸素性トレーニングおよび性ステロイドホルモン投与により改善し、その機序には血液中の性ステロイドホルモン濃度の増大が関連していることを明らかにしました。
Horii N, Sato K, Mesaki N, Iemitsu M. DHEA Administration Activates Transcription of Muscular Lipid Metabolic Enzymes via PPARα and PPARδ in Obese Rats. (2016). Horm Metab Res 48(3):207-212, 2016.
2016.03.18 research
2016/03/13本研究科博士課程前期課程1回生の鳥取伸彬さんが、京都滋賀体育学会第145回大会で若手研究最優秀奨励賞を受賞しました。
2015/03/13 本研究科博士課程前期課程1回生の鳥取伸彬さんが、京都の同志社大学で開催された京都滋賀体育学会第145回大会において、本学部教授 藤田聡先生、同研究科 貴船創一さんとの共同研究としてまとめた下記の発表演題が若手研究最優秀奨励賞を受賞しました。
「小学生の疾走能力に及ぼす体力因子の検討」
鳥取伸彬、貴船創一、藤田聡(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科)
2016.03.15 research
2016/03/11 第24回NS研究会αが開催されました。
NS研究会α第24回定例会にて、生藤大典(いけふじ だいすけ)先生(立命館大学大学院 情報理工学研究科 博士課程後期課程 3回生)と藤井慶輔先生(名古屋大学 総合保険体育科学センター 日本学術振興会特別研究員(PD))をお招きし、ご講演頂きました。
生藤先生には「局面・多面体超音波スピーカーを用いた高音質な3次元音場再生」というテーマで、お話頂きました。先生が開発されたスピーカーは音の周波数特性を利用し、狙ったところだけ音が聞こえるようになっています。講演では、実際にスピーカーから音を聞かせて頂き、技術の発展に感銘を受けました。また、超音波スピーカーを用いて、投手にだけ的確な指示を与えることや、空間シェアリングを行うなど、スポーツ・健康運動にも応用することができるという興味深いお話もして頂きました。
藤井先生には「集団スポーツの動きに関する仕組みと振る舞い、あるいは部分と全体」というテーマでお話を頂きました。生命は「仕組みを研究すること」と、「実際の振る舞いを研究すること」の2つの過程について説明することができるそうですが、この2つを含めた全体の生命過程については研究されていないそうです。藤井先生はバスケットボールにおける、オフェンスとディフェンスの動きに着目し、シュートの成功に影響している要因について、わかりやすくご説明頂きました。この研究は、大変難しいというお話もいただき、この難しい問題に取り組まれている姿勢に大変刺激を受けました。
お二人の先生に大変興味深いお話を頂き、講演後の質疑応答・議論も大変活発に行われ、たくさんの新しいアイデアが生まれる非常に有意義な定例会となりました。
2016.03.11 research
2016/03/10 本学部助教の藤本雅大先生の研究が「Gait & Posture」に原著論文として掲載されました。
本学部助教 藤本 雅大先生がオレゴン大学生理学部教授 Li-Shan Chou先生と共同で取り組まれた研究が、「Gait & Posture」に原著論文として掲載されました。
この研究論文では、歩行の安定性を速度と加速度の観点から評価しています。歩行速度が同じであっても、加速度による速度のコントロールは若年者と高齢者とでは異なること、そして転倒経験のある高齢者は安定性をより重視した保守的な歩行動作をとることを明らかにしています。これらの結果は、高齢者の歩行の不安定性や転倒の原因を解明するうえで重要な知見となるものです。
Fujimoto M and Chou L-S. (2016). Sagittal plane momentum control during walking in elderly fallers. Gait & Posture, 45: 121-126.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636216000102
2016.03.10 research
2016/03/04 第23回NS研究会αが開催されました。
NS研究会α第23回定例会にて、橘由里香先生(鹿児島大学 共同獣医学部付属動物病院 特任助教)、進矢正宏先生(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻生命環境科学系 認知行動科学講座 助教)をお招きし、ご講演いただきました。
橘先生は、「人はなぜ馬に乗るのか」というテーマについて、馬の診療に関わられ、馬術選手としてもご活躍されている立場から詳細に説明されていました。人が馬に乗る理由としては、乗ることに適した大きさ・背部の形態、優れた体力、そしてコミュニケーションをとれることが挙げられていました。また、馬術競技においてアスリートとして活躍する馬についてもお話いただき、蹄鉄の固定釘を2ミリ出すだけでスプリントパフォーマンスが向上した事例など、興味深い内容をご紹介いただきました。
進矢先生には、「ヒトの反射的姿勢制御における予測の役割」についてご紹介いただきました。我々は自分の運動を「意識的に予測・制御している」と感じていますが、実際には無意識的な予測・反射的な制御が働いているそうです。ご講演では、落とし穴のあるコースを歩行させる「踏み外し実験」など、新規的な実験デザインを用いたご自身の研究データをご紹介いただき、ヒトの反射的な姿勢制御における意識的・無意識的な予測の役割について、理解を深めることができました。講演の終盤には、研究の展望についても述べられており、今後も研究が大いに発展していくことが感じられました。