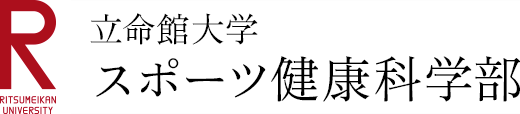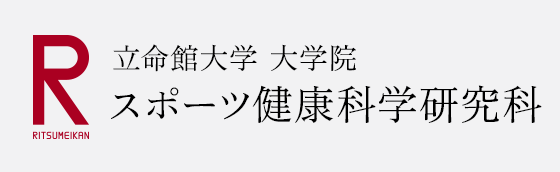2016.03.03 research
2016/02/24 本研究科特任助教・大塚光雄先生の研究が「Journal of Strength and Conditioning Research」に原著論文として掲載されました.
本研究科特任助教 大塚光雄先生が,本研究科教授 伊坂忠夫先生,同学部卒業生 川原泰祐さんとの共同研究の上, その研究内容がJournal of Strength and Conditioning Researchに原著論文として掲載されました.この短距離走選手を対象とした研究では,トレーニング時におけるスプリント走の足跡データと試合におけるスプリント走の足跡データを比較しました.その結果,トレーニング時と比較して,試合時では短距離走選手のステップ頻度は増加し,その結果,疾走速度も高まることが明らかとなりました. つまり,たとえ練習時では全力疾走をしていたとしても,試合時でスプリント走では,さらに高い強度となることが示唆されました.
Otsuka M., Kawahara T., Isaka T. (2016) Acute Response of Well-Trained Sprinters to a 100-m Race: Higher Sprinting Velocity Achieved With Increased Step Rate Compared With Speed Training. Journal of Strength and Conditioning Research. 30(3): 635-642.