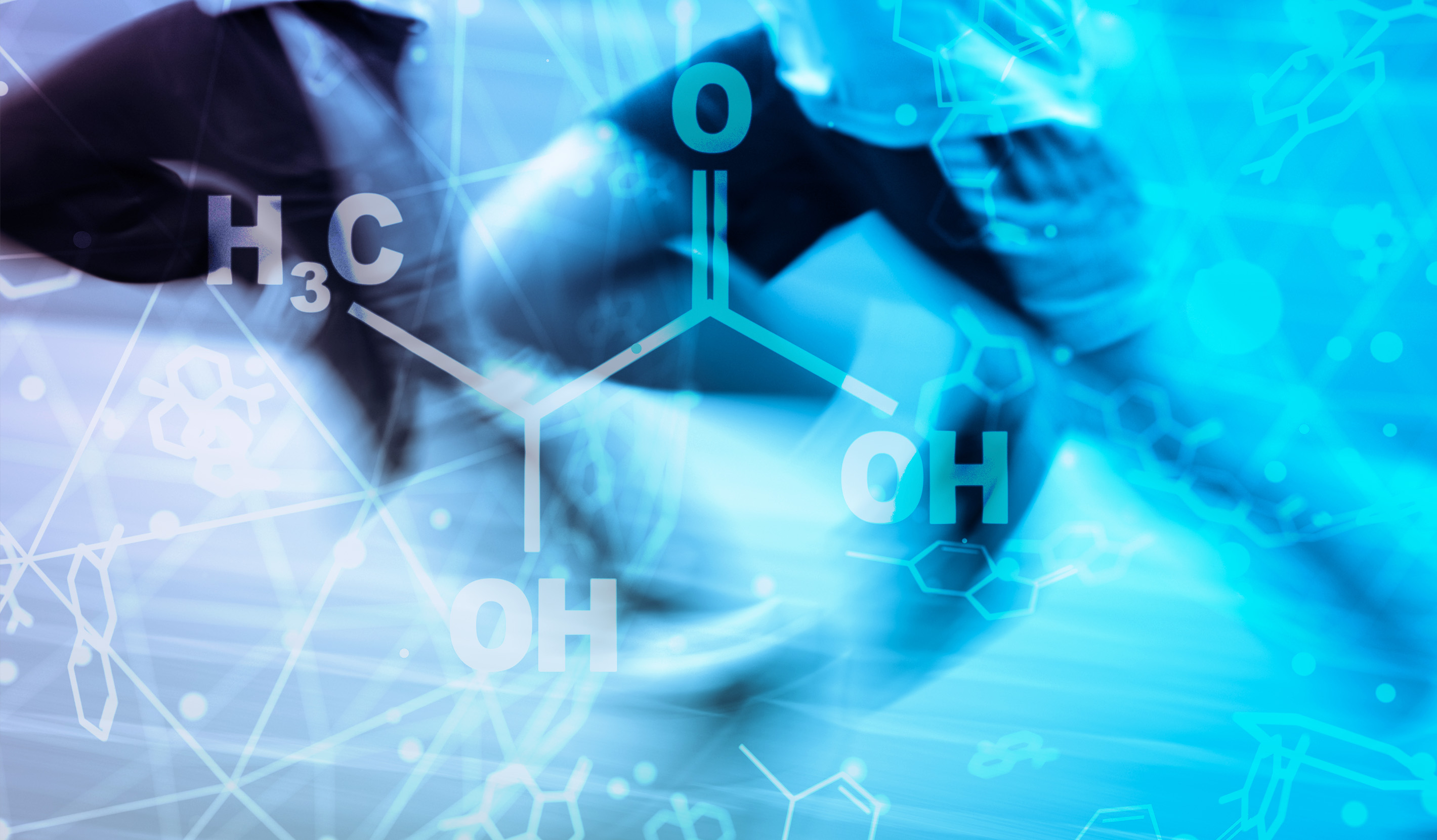「スポーツ」と「健康」を横断し学際的に学ぶ
理学・工学・保健衛生学・医学・体育学・教育学・経済学・経営学・栄養学など総合的・学際的な領域から、 スポーツ健康科学を幅広く学びます。学びの領域から、学びのイメージをつかんでください。
トップアスリートが、酸素濃度の薄い高地でトレーニングを行うことは多くの人が知っているでしょう。低酸素環境での運動が、体内でエネルギーを作り出す能力や持久力を高めるからです。しかし最近の研究で、低酸素の環境は、そこにいるだけで体重や体脂肪が減ったり、血糖値が下がったり、動脈硬化を防いだり、誰にとっても有益な健康効果がある可能性が注目されています。スポーツジム、オフィス、学校、いずれは家庭でも。低酸素環境下で生活するだけで健康になれる日は来るのでしょうか。さまざまな企業と協力しながら研究を進める後藤一成先生に聞きました。
学校に行く機会に恵まれない児童生徒も多い開発途上国では、他教科に比べて体育は軽視されがちだといいます。しかし、体育の授業には、目標を達成するためチームで協力し合ったり、本気で人を応援したり、試合の後にチームで振り返ったことを発表し合ったり、社会でも活きるさまざまな学びがあったことを、日本で教育を受けた人なら実感しているのではないでしょうか。環境や道具の整わない開発途上国で、地域の文化や状況に合った体育科教育を行い、将来につながる子どもたちの力を伸ばすにはどうすればよいのでしょう。カンボジアやペルーでフィールドワークを続けながら、開発途上国の体育科教育について研究する山平芳美先生に聞きました。
スポーツ選手にとって、チームの雰囲気やチームメイトとの人間関係は、競技へのモチベーションや技術の向上、精神的安定にも関わるものではないでしょうか。そして、それらを左右するのが、チームをリードする監督やキャプテンの存在です。 今の時代、どんなリーダーが、どんなリーダーシップを発揮することが、個人の成長を促し、チームとしての高い成果にもつなげられるのでしょうか?関係性リーダーシップとチーム力向上に関する心理学研究を行う山浦一保先生に聞きました。
子どもの体力低下が叫ばれて久しい今、水泳やサッカーなどの教室に早くから子どもを通わせなければと思う人がいるかもしれません。しかし、競技に特化したトレーニングだけでは身につかず、しかも10代前半までに鍛えなければどんな競技に進んでも高いパフォーマンスが発揮できないとされる神経系の能力があることを知っていますか? 一生の運動センスを左右する「動作コオーディネーション能力」。スポーツタレント発掘・育成の場でも重要視されつつあるその能力とはどのようなものでしょう?子どもの体力や運動能力の向上に関する研究を続ける上田憲嗣先生に聞きました。
普段スポーツをしない人でも「乳酸」という物質の名前は聞いたことがあるでしょう。疲労物質、あるいは筋肉痛の原因物質だと思っている人がいるかもしれません。しかし、それは大いなる誤解であり、乳酸はむしろ身体や脳に良い影響を与えてくれていることが最近の研究によって明らかになってきました。
乳酸が身体に与える影響とはどのようなものなのでしょう?運動と栄養が身体へ及ぼす作用の解明を通して健康増進や競技力向上をサポートする橋本健志先生に、最新の知見を聞きました。
陸上競技の長距離トップ選手が多く履いている厚底のシューズ。高いパフォーマンスが期待できるものの、脚部への負荷は大きくなるといいます。一方で、薄底のシューズはアキレス腱への負荷が大きくなります。どちらを選ぶべきなのでしょう?シューズの底厚によって何がどのように違ってくるのでしょう? 現在、ランニングシューズの底の素材・形状とランニング時の負荷の関係について研究している長野明紀先生に、スポーツ健康科学部の施設で行われている調査の内容について聞きました。