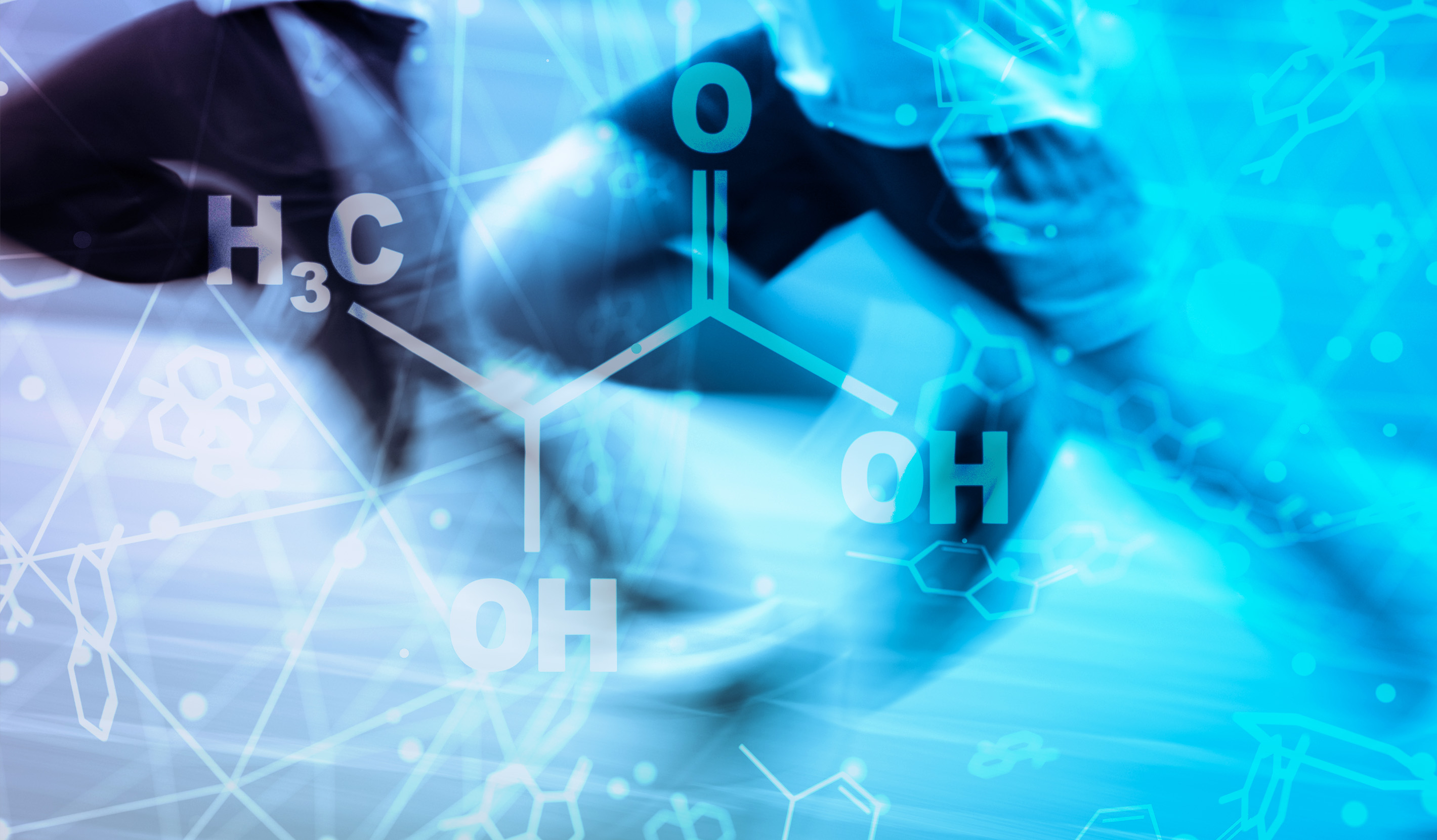海外の体育から考える日本の体育の特徴とは?
開発途上国の文化・環境に応じた体育授業を探求し
社会課題の解決にもつなげる。
山平 芳美 准教授 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科
Question
学校に行く機会に恵まれない児童生徒も多い開発途上国では、他教科に比べて体育は軽視されがちだといいます。しかし、体育の授業には、目標を達成するためチームで協力し合ったり、本気で人を応援したり、試合の後にチームで振り返ったことを発表し合ったり、社会でも活きるさまざまな学びがあったことを、日本で教育を受けた人なら実感しているのではないでしょうか。環境や道具の整わない開発途上国で、地域の文化や状況に合った体育科教育を行い、将来につながる子どもたちの力を伸ばすにはどうすればよいのでしょう。カンボジアやペルーでフィールドワークを続けながら、開発途上国の体育科教育について研究する山平芳美先生に聞きました。

体育を通して子どもたちの将来に活きる力を育む
それぞれの国に合った体育授業、教師教育を検討
私は、大学時代に授業でカンボジアに行き、現地の高校生に球技を指導したことがきっかけで、開発途上国の体育科教育に関心を持ちました。スポーツをしたくても日本に比べて環境も整わず、練習メニューも限定的、そもそも学校に通える児童生徒は限られている…社会課題が明確な地で体育科教育に携わることに魅力を感じたのです。
世界的に、国語や数学などの科目と比べて体育が重要視されていないことは、ユネスコのデータでも示されています。例えばドイツの体育を見ても、サッカーやホッケーを楽しむ時間が中心になっています。一方、日本では、小学校から高等学校までの体育を通して、体つくり運動、器械運動、陸上競技、水泳、球技、武道、ダンスなど多くの種目を経験できます。また、チームで勝つための作戦を話し合ったり、試合中に協力し合ったり、試合後に振り返りをして全体でシェアするといった経験は、共感性、優しい気持ちを向ける力、目標に対する忍耐力、ストレスに柔軟に対応する力、目標へ向かう情熱など「非認知能力」とよばれる将来に活きる力を育むと考えられます。体育的行事としての運動会で、チーム一体となって応援したり、みんなでゴールを目指したりすることも同様です。
私は、環境や道具が整わない開発途上国でも、体育の授業によってこのような力を養うことは国の発展においても重要であることを伝え、質の高い体育の授業を実施できるようにしたいと考えています。そのために、現地でのフィールドワークも続けながら、それぞれの国の文化や環境に合った体育の授業の実施方法や教師教育を検討し、効果をデータとして提示できるよう研究しています。
カンボジアではお正月行事で綱引きをする習慣があるため、運動会の種目として「引く」動きの綱引きを取り入れてみたところ、大人気となりました。玉入れは道具が必要なので、すべての学校で実施することはできませんが、「投げる」動きとして取り入れたところ人気です。勝敗を競うため争いとなる恐れもありますが、運動会の目的に即してみんな真剣に取り組み、はっきり順位が決まることをとても楽しんでくれています。国ごとに用意できる道具や習慣が違うので、それぞれに合ったものができるようにしていきたいと考えています。


日本で100年前に生まれた研修システムは
開発途上国の体育授業の質を高めるか
数年前から、開発途上国での教師の研修システムに関する研究も行っています。授業に他校の先生が大勢で見学に来られたという記憶はありませんか?それが、日本で約100年前に生まれた「授業研究(レッスンスタディ)」と呼ばれる研修です。教師が共同で指導案を作成して授業を実施し、授業後には振り返りを行って改善につなげるというもので、1990年代になって世界的に注目されるようになりました。この研修を開発途上国の体育科教育に導入することによって、どのように体育授業の質が高まるのかを調査しています。現地の先生方が、自分たちで話し合って作成した指導案に基づいて授業を行い、自分たちで振り返って改善点を話し合い、また次の計画をする。プールや体育館がないなど環境が整っていなくても、体育授業を良くしていくための研修システムとして認識してもらえるようにしたいと考えています。
スポーツは、言葉を必要としない優れたコミュニケーションツールだと思います。一緒にスポーツするだけで、言語の壁を越えて「楽しかったね」「負けてくやしかったね」という気分を一緒に味わうことができます。熱中してわーっとハグしたりすることもあるでしょう。体育・スポーツには、民族間の誤解をといたり、社会の経済発展に寄与したりするなど、社会課題を解決させる力があるということを、より多くの人に知ってほしいと願っています。

「先進的」なのは、日本よりカンボジアの方だった?
諸外国の学校で体育の授業に関わっていると、日本の体育の良さや課題がよく見えてきます。今、日本の教育では、男女共習や、障がいの有無や多様な違いがあってもすべての児童生徒が同じ環境で学ぶインクルーシブ教育が重要視されていますが、カンボジアでは、何も言わなくても大学生の男女が一緒に楽しそうにスポーツをしている様子が見られたり、けがした児童、障害のある児童のことも自主的にサポートし合っています。女の子の列にどう見ても男の子らしい子がいたので「列が違うんじゃない?」と言うと、ある児童が「この子はこっちでいいんだよ」と教えてくれたこともありました。カリキュラムに示す必要のない、ことさら「一緒に仲良く」「多様性を尊重して」などと指導する必要のない環境があったのです。他国を見て自国を知る。そのことの面白さと、自身の信念を問い直す重要性を感じています。

スポーツ国際開発学の分野に興味がある人へ
身近な社会課題に目を向け
体育・スポーツにできることはないかを考えよう
世界にも、日本にも、まだまだ社会が抱える課題があります。皆さんには、体育・スポーツで社会課題にアプローチできる分野があるということを知ってほしいと思います。まずは社会課題に目を向けてください。ジェンダー、教育、貧困、紛争…身近なところにも、性自認で悩んでいたり、もしかしたら体育が苦手で困っている人がいるかもしれません。それらに対して、自分が好きな体育・スポーツで貢献できることはないだろうかという考え方をしてみてください。
私は、開発途上国の社会課題解決の一環として体育科教育に関わり続けています。さまざまな困難を乗り越えて実施されている体育授業で、楽しそうに運動している児童生徒の姿を見たり、それを見て喜んでいる教師の姿を見たりすることが大きな喜びです。国内の研究者はまだ少なく、先行研究も少ない領域ですが、関心のある人は、スポーツ健康科学部で一緒に学び、実践して、考えていきましょう。

山平 芳美 准教授
広島大学大学院教育学研究科修了。博士(教育学)。国際武道大学体育学部、広島市立大学国際学部を経て2024年より現職。専門分野はスポーツ国際開発学、スポーツ教育学。カンボジアで定期的にフィールドワークを実施しながら、開発途上国の教員養成や体育の授業研究に関する研究、スポーツを通じた開発に関する研究に取り組んでいる。
先生のおすすめカルチャー
-
 映画
映画『小学校~それは小さな社会~』 監督:山崎エマ
東京都の公立小学校に1年間密着し、児童と教師の日常生活をありのままに記録した映画です。給食当番や掃除当番など、日本では当たり前のように行われている文化が協調性や責任感などを育んでいく様子が描かれ、海外でも大きな反響がありました。教育大国と言われるフィンランドでロングランヒットを記録しています。日本の体育科教育に関しても、このように広く認識されるようになるといいなと思います。
-
 映画
映画『インビクタス/負けざる者たち』 監督:クリント・イーストウッド
アパルトヘイト(人種隔離政策)の影響が残る南アフリカでの実話に基づく映画です。当時のネルソン・マンデラ大統領が、ラグビーW杯の開催を通して、人種対立の壁を乗り越えて国民を一つに導く姿を描いたもの。スポーツが社会課題を解決するという意味でも、とても好きな映画です。
-
 漫画
漫画『SLAM DUNK』 井上雄彦 著
大会での優勝に向けて熱くまとまっていく仲間の物語。起業を目指す若者たちと同じような熱を感じます。悩んでいる高校生に対し、安西先生という指導者が、いいタイミングでいい一言を言うんですよね。保健体育教師を目指す人や、スポーツのコーチングに興味がある人にとっても、とても勉強になる内容だと思います。
-
スポーツサイエンス領域
普通に生活するだけで体脂肪も血糖値も下がる。
アスリートの競技能力を向上させてきた
低酸素の環境を利用して、すべての人を健康に。後藤 一成 教授
-
スポーツ教育学領域
海外の体育から考える日本の体育の特徴とは?
開発途上国の文化・環境に応じた体育授業を探求し
社会課題の解決にもつなげる。山平 芳美 准教授
-
スポーツマネジメント領域
引っ張る?サポートする?
個人が成長し、チームとしても
高い成果を上げるためのリーダーシップとは?山浦 一保 教授
-
スポーツ教育学領域
一生ものの運動センス
10代前半までに鍛えておくべき
「動作コオーディネーション能力」とは?上田 憲嗣 教授
-
健康運動科学領域
「乳酸は疲労物質」はもう古い
筋肉や脳のエネルギー源
競技力アップにもつながる「乳酸」の話橋本 健志 教授
-
スポーツサイエンス領域
厚底シューズはなぜ人気?
最新のテクノロジーで解明する
ランニングフォームと身体への負荷の関係長野 明紀 教授