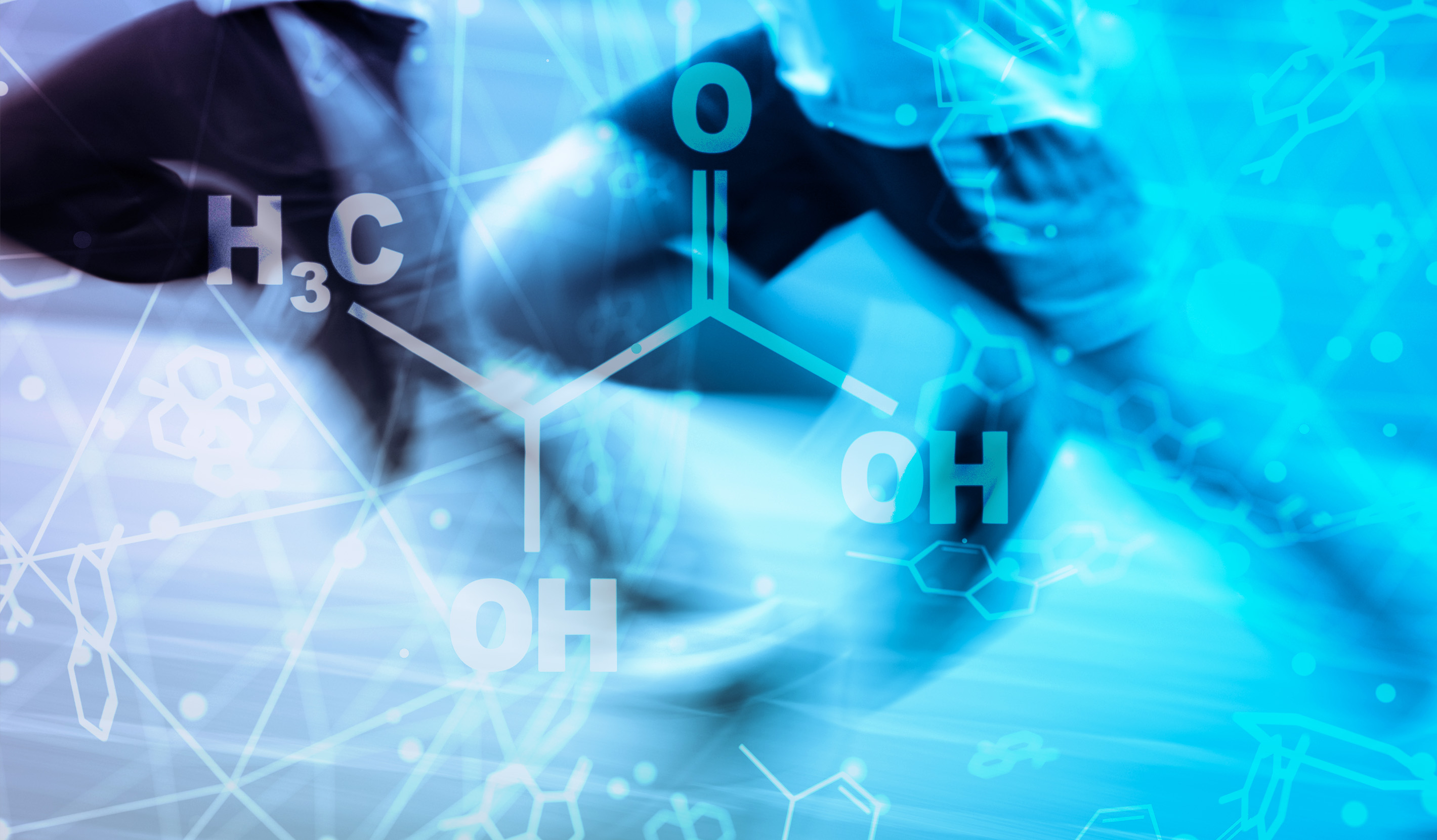普通に生活するだけで体脂肪も血糖値も下がる。
アスリートの競技能力を向上させてきた
低酸素の環境を利用して、すべての人を健康に。
後藤 一成 教授 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科
Question
トップアスリートが、酸素濃度の薄い高地でトレーニングを行うことは多くの人が知っているでしょう。低酸素環境での運動が、体内でエネルギーを作り出す能力や持久力を高めるからです。しかし最近の研究で、低酸素の環境は、そこにいるだけで体重や体脂肪が減ったり、血糖値が下がったり、動脈硬化を防いだり、誰にとっても有益な健康効果がある可能性が注目されています。スポーツジム、オフィス、学校、いずれは家庭でも。低酸素環境下で生活するだけで健康になれる日は来るのでしょうか。さまざまな企業と協力しながら研究を進める後藤一成先生に聞きました。
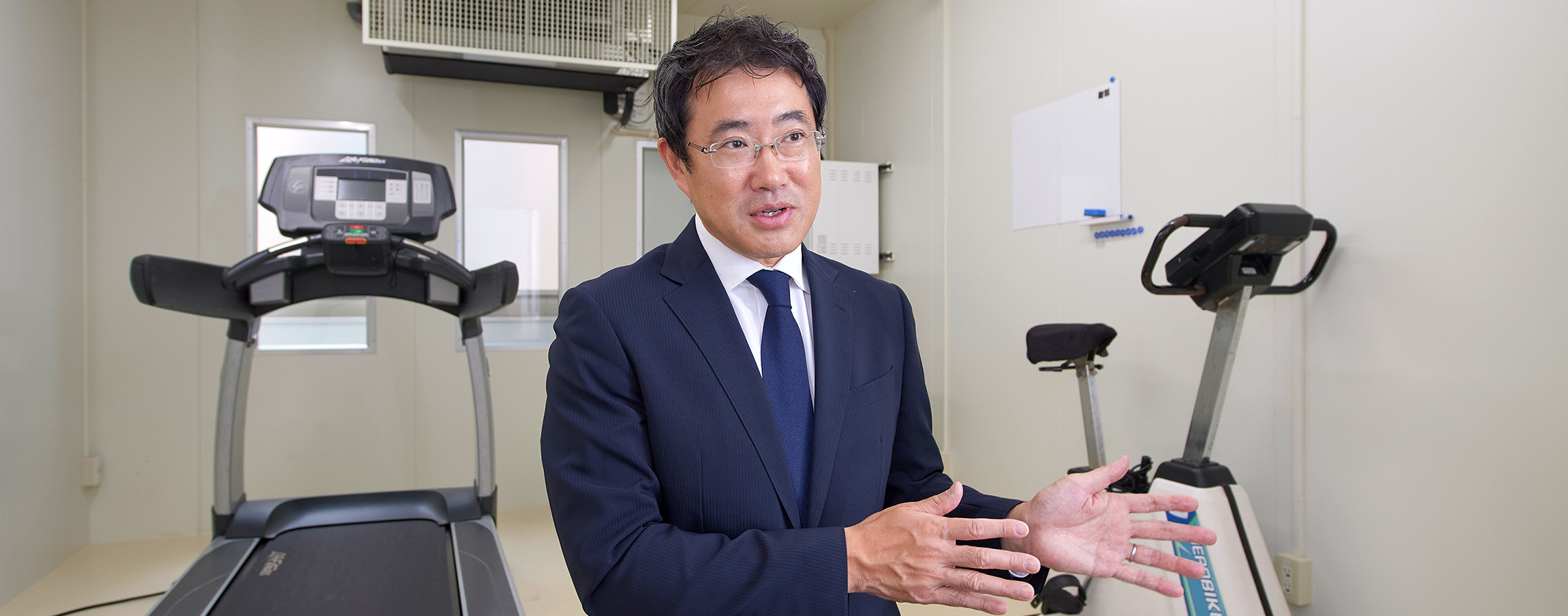
忙しくて運動できないなら、発想を転換して
生活の中で健康を維持できる環境を作る
低酸素環境でのトレーニングは、ひと昔前までは長距離ランナーが持久力を高める目的で行うものでした。しかし今は、短距離ランナーや球技の選手などの競技力向上にも有効だということがわかっています。低酸素の環境で運動すると、無酸素でエネルギーを生産する能力が向上するため、強い運動を長く続けられるようになるからです。本学の実験室でも、これまでオリンピックやパラリンピックの日本代表選手が低酸素の環境でトレーニングを行ってきました。
同時に、低酸素の環境は、一般の人の健康増進にも有効であることが明らかになってきました。低酸素環境で軽いトレーニングをするだけで、あるいは椅子に座ったり立ったりといった日常的な身体動作だけでも、体重の減少、体脂肪の減少、血糖値の低下、動脈硬化症の抑制といった生活習慣病の予防に有効である可能性が注目されています。例えば、低酸素の環境下では、血管の壁から一酸化窒素という物質が産生されます。これが血管を拡張して血圧を下げ、血管も柔らかくなるのです。低酸素の環境で過ごすだけで、健康を維持、増進させることができるかもしれません。
これまでのスポーツ科学は、運動による健康増進効果をうたってきました。もちろん運動することが理想ではありますが、実際に運動する人はなかなか増えていません。理由として一番に挙げられるのは忙しくて時間がとれないことなので、思い切って発想の転換を行い、時間がなくても、運動できなくても、生活の中で健康を維持できる環境を作ることも大切なのではと考えるようになりました。


5年後の実用化を目指して実証実験中
将来は、AIが個人の低酸素メニューを提示?
今は、低酸素環境のアスリートへの効果に関する研究もしつつ、あらゆる人が、生活の中に低酸素を取り入れて健康増進できる社会を作るための研究も行っています。体温、脂質代謝、性周期などさまざまな面から低酸素環境の効果を調べると共に、酸素が薄くなったことに気づくことなく効果を得られる酸素濃度、1日の中でどのくらいの時間を低酸素の環境にするのが良いかの最適値も探っています。息苦しくなったり、眠くなったり、活性酸素が増えたりしないかなどの検証も必要です。私が懸念していたのは、脳への酸素供給量が低下することによる認知機能の低下、それによる生産性低下でした。しかし最近の研究では、低酸素の空気と通常量の酸素を含む空気を交互に吸入すると、脳へ供給される血液量が逆に増えるというデータも出てきています。将来は、低酸素と高酸素を交互に使い分けて脳の血流を良くし、集中力を高められるようになるかもしれません。リラックス状態につながる副交感神経の働きを高め、質の良い睡眠がとれるようになることにも期待しています。睡眠はメンタルヘルスにも直結するもの。忙しい社会人も、メンタルが整えば、運動をする気持ちが生まれることもあるでしょう。
現在、パートナー企業や自治体と連携し、被験者の方々の協力もいただいて、実際の施設や自宅での実証実験を進めると共に、その成果をどのように社会実装するかの研究も行っています。積み上げたデータをもとに、5年以内には社会で活用できるようなものを提供したいと考えています。低酸素の環境を作れるオフィスが実現すれば、特に意識をせずに社員の健康増進を図ることができるかもしれません。さらに将来は、低酸素発生装置を備えた健康住宅が当たり前になったり、個人の状態をモニタリングして、一人ひとりにとって適切な酸素濃度(低酸素や高酸素)をAIが提示してくれるような日が来るかもしれません。

センシング技術の進歩が
トレーニング科学の研究を支えている
低酸素の実証実験では、被験者の体温、呼吸、心拍、血圧など身体の状態を示す数値に加え、血糖値や筋肉中の酸素量などの1日の変化、数カ月単位の変化を計測します。それが可能になったのは、センシング技術の急速な進歩です。ボタン大のウエラブルセンサを身体に貼り、普通に生活していただくだけで、Bluetoothによってクラウド上にデータが上がり、研究室からリアルタイムに解析ができるようになりました。 この研究には、低酸素の空気の発生装置を開発する空調機メーカー、それを備える施設を作る企業、最先端のセンシング技術を持つ企業など、研究の意義を理解し、協力してくださっているパートナー企業との連携が欠かせません。ゼミ生にとっても、研究を通した企業の方とのやり取り自体が大きな経験になるのはもちろん、スポーツとは一見関係のない企業への関心が深まることから、就職先の幅が大きく広がるようになりました。

トレーニング科学の分野に興味がある人へ
人生をかけてやりたいことを見つけよう
今の得意不得意で進路を狭めるのはもったいない
研究とは、高校で取り組む探究学習の延長にあるものです。探究学習の中でさまざまな調べごとをしたり、グループワークをしたりすることが、実はもう研究です。探求学習を面白がりながら一生懸命やることが、大学や大学院での研究につながっていきます。
スポーツ科学は文系、理系というくくりで分けることのできない文理融合の分野です。私は長年、実験から得られた数値データを解析し、血液中に含まれるホルモン濃度を生化学的に解析する研究に取り組んでいます。一方で、高校生の頃は数学、物理、化学よりも、歴史や現代文、理科の生物など文系寄りの科目が好きでした。理系科目に苦手意識があっても、興味があるなら、この分野にどんどん入ってきてもらいたいと思います。数学が苦手だから、英語が苦手だからこの道に行くしかない、と得意科目や不得意科目で進路を狭めてしまうのはもったいないことです。
まずは自分のやりたいこと、興味のあることを見つけてください。自分の人生をかけてやりたいことに出会うと、人間は本気で頑張れるものです。夢に向かって進む中で、必要なことを勉強すれば良いのです。それが、進路選択に当たっての私からのアドバイスです。
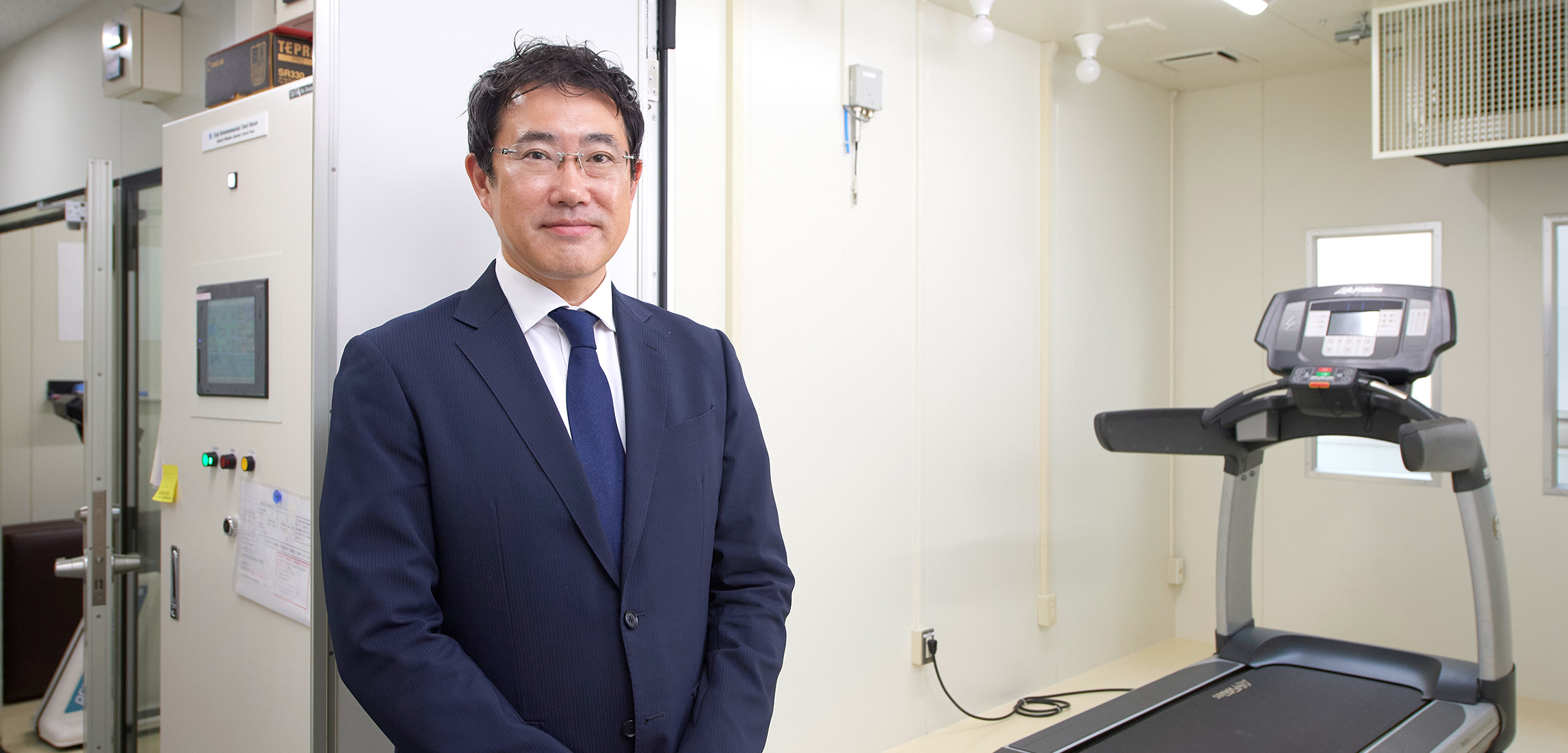
後藤 一成 教授
筑波大学体育科学研究科博士課程修了。博士(体育科学)。日本学術振興会特別研究員、早稲田大学スポーツ科学学術院助教、立命館大学スポーツ健康科学部准教授を経て2017年より現職。健康増進およびスポーツの競技力向上に資するトレーニングや栄養法、疲労回復法などの開発に関する研究を行っている。
先生のおすすめカルチャー
-
 書籍
書籍『最新のスポーツ科学で強くなる!』 後藤一成 著
最新の研究成果をもとに、効果的に身体を鍛え、競技力向上に活かすためのトレーニング、コンディショニング、栄養補給について誰にでも分かるように書いた本です。スポーツ健康科学部、なかでも私の専門であるトレーニング科学の分野でどんなことを学ぶことができるかはこの本の中にすべて入っています。この分野の幅広さや面白さをお分かりいただけると思います。
-
 漫画
漫画『はたらく細胞』 清水茜 著
あまり漫画は読まないのですが、これは、白血球の話とか血小板の話とか、すごく面白かったですね。体の中に何が起きているのか、免疫とは何なのか、小中学生でも分かるように書かれているので、子どもと一緒によく読んでいました。
-
スポーツサイエンス領域
普通に生活するだけで体脂肪も血糖値も下がる。
アスリートの競技能力を向上させてきた
低酸素の環境を利用して、すべての人を健康に。後藤 一成 教授
-
スポーツ教育学領域
海外の体育から考える日本の体育の特徴とは?
開発途上国の文化・環境に応じた体育授業を探求し
社会課題の解決にもつなげる。山平 芳美 准教授
-
スポーツマネジメント領域
引っ張る?サポートする?
個人が成長し、チームとしても
高い成果を上げるためのリーダーシップとは?山浦 一保 教授
-
スポーツ教育学領域
一生ものの運動センス
10代前半までに鍛えておくべき
「動作コオーディネーション能力」とは?上田 憲嗣 教授
-
健康運動科学領域
「乳酸は疲労物質」はもう古い
筋肉や脳のエネルギー源
競技力アップにもつながる「乳酸」の話橋本 健志 教授
-
スポーツサイエンス領域
厚底シューズはなぜ人気?
最新のテクノロジーで解明する
ランニングフォームと身体への負荷の関係長野 明紀 教授