専修概要
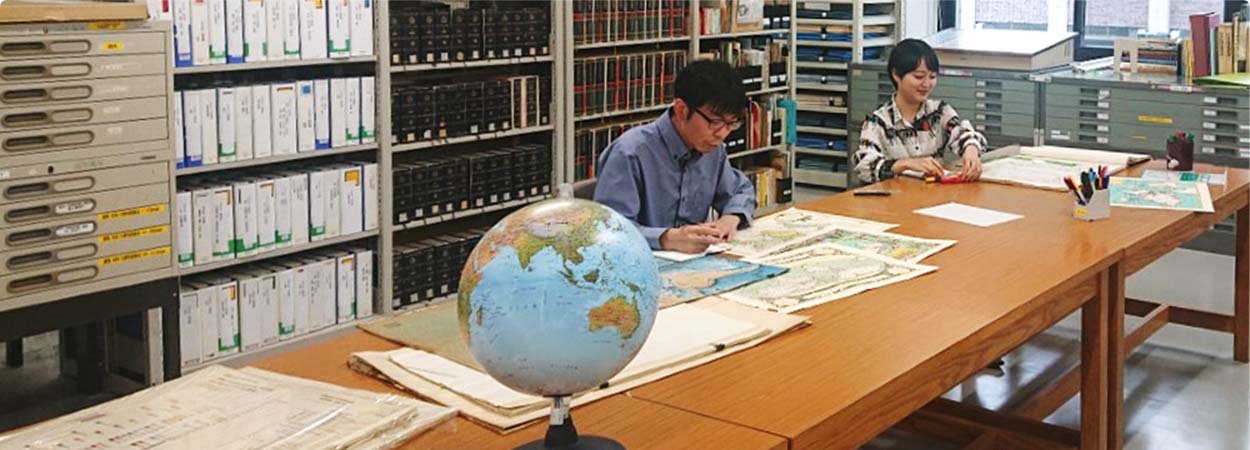
地理学・地域観光学専修
ようこそ。「地理学」と「地域観光学」における教育・研究の世界拠点へ。
「地理学・地域観光学専修」は、1935年、西日本の私学においてはじめて、地理学教室が設立されたことに始まります。文学研究科に地理学専攻が設置されたのが1954年のことです。それ以降、当教室は研究者を養成し続け、多数の修了生がいまも全国の大学や研究機関に勤務しています。
「地理学・地域観光学専修」は、「研究一貫コース」と「高度探究コース」2つのコースのもと、空間的視座から地球上の多様な現象を解明する「地理学」と、地理学を軸としつつ社会学・文化人類学等の知見を取り入れた学際的視座から観光現象を解明する「地域観光学」に関し、質の高い教育・研究を展開しています。
「研究一貫コース」は、主に研究者の育成を目的としたコースです。本専修は、自然地理学から人文地理学にわたる地理学の広い領域を扱っており、GISについても先端的な研究を行なうなど、世界中から注目される研究拠点となっています。そのことは、観光学の分野でも同様で、国内はもちろん、海外の研究者から多くの注目を集める観光学の拠点となっています。こうした研究拠点をベースにして、地理学・地域観光学の研究者・調査者を養成し続けています。
「高度探究コース」では、地理学・地域観光学に関する専門教育をうけた多くの修了生が、中学・高校の教員として教育現場において即戦力として採用されています。もちろん、教員に採用されているだけではなく、都市計画コンサルティング企業に勤務するGISの専門家、観光や地域・都市政策に携わる公務員、観光産業従事者、大学職員など、様々な分野に採用され、活躍し続けています。
本専修修了生の全国各地での活躍により、「立命の地理学」「立命の観光学」は、学界、教育界、産業界などで高い評価を得ています。
過去の修士論文・博士論文タイトル(例)
修士論文
- 日本における中国人のコンテンツツーリズム―安倍晴明に関する「聖地巡礼」を事例に―
- ゲストハウス(簡易宿所)に対するツーリストと地域住民の反応―京都市西陣地域を中心にした考察―
- パフォーマティブに体験される文化の真正性―京都観光における着物体験を事例として
- ごみ排出量とリサイクル率に影響を与える地域の社会経済特性 ―影響の地理的・経年的差異の一般化―
- 中学校社会科における絵図資料の活用―群馬県浅間山の災害学習を事例に―
博士論文
- 近代〈軽井沢〉の成立に関する歴史地理学的研究―別荘地の拡大による「季節的な都市」の誕生―
- 近世京都における名所見物の歴史地理学的研究―旅日記の分析を中心に―
- 両大戦間期における陸上貨物輸送の変容―近畿地方の大都市を中心として―
- 2000 年代以降の外食産業再編期における飲食店の立地動向に関する研究―京阪神大都市圏を中心に―
- 中近世京都の祭礼における空間構造 ―今宮祭と六斎念仏を事例として―
