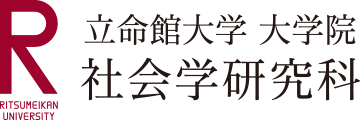藤本 ヨシタカさん 修了生
博士課程後期課程 2015年3月修了
現職
大学等非常勤講師
社会学研究科では、どのようなテーマを研究されましたか。
博士論文のタイトルは、「黎明期家族臨床研究をめぐる認識論的意義とその応用可能性―Bateson、Laing & Esterson、そしてアダルト・チルドレンを通じて―」です。
大学院では、「心的外傷(トラウマ)」と呼ばれる複雑な出来事をいかに把握すべきか、という認識学的テーマを掲げ、理論的ないし思想的な側面から追究しました。とりわけ、家族関係における外傷体験に関心があったため、「家族療法」と呼ばれる分野でいかなる認識学的な議論がなされてきたかに着目しました。そこでは主に、〈直線的因果律〉すなわち被害‐加害関係に代表されるような単線的な因果連関を強調する立場と、〈円環的認識〉すなわち単線的な因果連関を超えた自己回帰的でシステム論的な認識を強調する立場とが、互いに相容れないものとして想定されてきました。しかしながら、現実の複雑かつ多様な背景を有する外傷的な出来事を考えると、そうした二者択一的な立場の取り方ではやや限界があるように思えます。そこで私は、家族療法の黎明期(1950~60年代)を支えたG.ベイトソンやR.D.レイン、A.エスターソンの研究に着目し、その中から、上記二つの立場を統合したより緻密な認識学的議論の萌芽を探ろうと試みました。この研究課題は現在も継続中です。
研究を進めていく上でご苦労されたことはありましたか。また、それをどのように乗り越えていかれましたか。
研究は苦労の連続でした。特に、この研究が最終的にどこに行き着くのか、また誰のために役立てられるべきかという点で、頭ではぼんやり浮かびつつもなかなか言葉にできない苦しさをずっと抱えていました(今もそうかもしれません)。私の場合、「(外傷的出来事という)ある現実の社会的事象をいかに把握すべきか」といった認識学的テーマに取り組んだため、たとえば外傷体験に現に苦しんでいる当事者の方々に対し、ただちに治療的効果を望めるわけではありません。また、臨床活動に携わる専門家の人々に対しても、私自身の関心が理論的ないし思想的な側面が強いこともあり、なかなか理解が得られ辛いのではないかと思います。そうした根本的なもどかしさを抱えつつも、粘り強く研究成果を発信し続けることで、様々な立場、関心、方法を超えて共通のテーマに取り組む意義を見出すこと――こうした意識をもって研究に臨むことが、重要ではないかと考えています。
院生時代の研究が、今のお仕事にどのように活かされていますか。
現在は、非常勤講師という形ではありますが、いくつかの大学・専門学校で教える機会に恵まれています。そこでは、断片的ではありますが研究成果について話をすることもありますし、論文の読み書きや資料収集、調査手順といった具体的な研究手法について話をすることもあります。これらはすべて、大学院を通じて実践し得られた賜物に他なりません。教わる側から教える側へと急激に立場が変わり、戸惑うことも多いですが、「研究(者)」と「教育(者)」という二つのスキルが相互に高め合えるような仕事をしていきたいと考えています。
いま社会学研究科で学び研究する院生たちに、なにかアドバイスがありましたらお願いします。
研究に打ち込める時間は限られています。そのため、自らの手に負える範囲を見定め、ある程度の結論を想定しつつ計画的に事を進めることが、どうしても求められます。でもその一方で、まったく想定していなかった結論に導かれ動揺したり、今まで知らなかった生活世界に触れ驚愕したりすることも、研究の質を高めるうえでたいへん重要な要素となります。「発見的驚き」と呼べるかもしれません。
私もそうでしたが、限られた時間内で成果を出そうとすればするほど、自らの生活世界や馴染みのある思考回路に閉じこもりがちになり、外的世界の多様性や重層性といったものに盲目的になります。社会学という学問は何よりそうした多様性や重層性に敏感であるべきにもかかわらず、かえって“自己愛的に”社会に向き合うといった本末転倒な事態になりがちです。そうならないためにも、絶えず研究対象に固有の思考や論理に寄り添う中で「発見的驚き」を見出し、自己愛的ではない開かれた研究を進めていくことが重要だと思います。勇気をもって他の分野・領域に飛び込むのもいいでしょう。
そうして「計画性」と「意外性」とをバランスよく行き来すること。難しいかもしれませんが、これが私からのアドバイスです。
キャンパスライフ