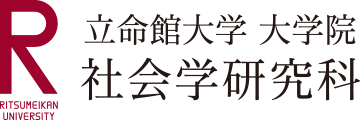先生は、どのような経緯から現在の研究テーマを設定されたのでしょうか。
なぜスポーツは世界各地で広まり、世間で支持を獲得しているか。端的に言うと、この素朴なナゾからスポーツの存在理由を理解したいからです。もっとも、こんな大それたテーマを正面切ってやれる力はありませんし、唯一の答えもないと思っているので、とりあえずラグビーという種目を選んでその生成と拡大、変容を時代や社会との関わりの中で明らかにしようと取り組んでいます。よく「なぜラグビーなのか」と聞かれるのですが、率直にいって自分がやっていたからという以上の理由はないんですよね。
もちろん、ラグビーやスポーツには色々と問題が指摘されていますし、現在の私もそれなりに課題を見いだすようにはなったのですが、もともとスポーツになにか不満があって研究をはじめたわけではありません。むしろ、私にとっての問題は、「スポーツのここが問題だ」「スポーツ振興はこうあるべき」「スポーツにはこんな力がある」というように、スポーツの問題やあるべき姿、(不)有用論、改善策などを説き、それを強いてくる人々、あるいはそんな社会そのものでした。その世界にひどく疲れ、不自由さを感じるくせに、自分も他人のことはいえず、忌み嫌う世界にどっぷり漬かっている。
この難題は今なお私をつかんで離しませんが、社会学研究科に進学して社会学に触れるなかで徐々に、スポーツは、ある時代に、ある場所で、ある組織や人びとに、様々に意味づけられ、色々と使われてきたからこそ、日常に「当たり前」に存在しているのかもしれないと思うようになりました。とてつもなく平凡な発想で恥ずかしいのですが、同じ世界を俯瞰的に見られるようになったのは大きかったです。それからは指導性をキーワードに、スポーツがこの世界でいかに正統性を獲得していったのか、世界はスポーツをどう使ったのか、またそこではなにが排除や忘却されたか、といった事柄を知ることに魅力を感じるようになり、現在に至っています。
先生は、これまで研究上の大きな困難にぶつかったことがおありでしょうか。
また、その場合どのようにしてそれを克服されましたか。
研究と実践の関係、研究の応用可能性といったこともそうですし、自分の力不足には辟易しています。ただ、研究上の困難というと、やはりテーマの設定です。
学部生のときは経営学やスポーツサイエンスを学んでいたので、社会学との付き合いは本学の社会学研究科に進学してからになります。社会学は、必ずしも物事を成し遂げたり、問題をスムーズに解決したりする理論や方法の構築を目指しませんし、なぜ研究するのかという前提も人によってまちまちですから、これまでの環境とのギャップにかなり戸惑いました。修士論文もアメリカのスポーツ哲学の理論研究だったので、紆余曲折してやっと、博士課程の途中から現在のテーマが朧気ながら見えてきた感じです。もがいていた、と言えば聞こえはいいですが、迷走ですよね(苦笑)。
どう乗り越えたかということですが、学内外の先生や院生、論文や書籍上でしか会えない人々との出会いや交流のなかで、粘り強く自分の研究をデザインしようとしていたとしか言いようがないです。過去の英知に触れ、社会学やスポーツ社会学の研究はもちろん、隣接する歴史学、人類学、政策学などはどういうものかを探り、事あるごとにテーマや手法、内容を問われ、批判される…。辛く苦しいことも少なくないのですが、その只中において自分の問いはなにか、どのような論文を書くか等を地道に考えることで、自らの研究が組み立てられていくのだと思います。
実のところ、今も同じ悩みを抱えていますけど、研究をする以上、逃れられないことですし「意味は後からついてくる」という気持ちでやっているので、それほど困難とは思わないようになりました。最後に余暇を研究する者の端くれとしては、たまには大いに遊び、日常から逃げるということもお勧めします。
2年間の修士課程を終えて社会に出ていく院生に対して、大学院時代の成果をどのように実社会で生かしていくか、アドバイスをお願いします。
大学院時代の成果といえば、修士論文でしょうか。ひとつは論文を書き上げる過程で培われるスキルや能力は、企業であれ行政であれ、仕事で活かすことができると思います。例えば、なにが取り組むべき課題かを選び取り、その背景や原因などをきちんと探り、それに基づいて適切な見通しや解決策を作り、相手を説得することは、どんな仕事でも求められます。また、その活動は不適切な方針や計画、取り組みを見直すことも繋がりますから、その精度が高ければ高いほど、評価されることでしょう。
もちろん、修士課程は2年間と限られ、まして就職活動との両立を考えると、個人の力量をどれほど高められるのかという点に疑問を持たれるかもしれませんが、その訓練をちゃんとつんでいるかどうかは長いスパンで着実に効いてきます。
加えて、現代社会の問題や困りごとは極めて複雑ですから、複眼的な視点や総合的な思考・対応が求められます。本学の社会学研究科は、産業社会学部の特長つまり社会学をベースにした学際性を高度化させた場といえますから、多彩な分野の知識や視点を獲得したり、人間の多様な生きざまに触れたりできるという意味で、より一層皆さんの公私にわたる営みに役立つことでしょう。
むしろ、社会学を学んだ成果は、仕事だけではなく、日常のいたるところで活かすことできますし、そうあって欲しいと願っています。例えば、危機や災難、不幸を目の当たりにしたとき、人々の痛みを深く理解したり、過去の教訓から希望を紡ぎだしたり、これまでの常識や社会の在り方を相対化することなどは、そう簡単にできることではありません。
将来研究職を目指す院生が早い段階から取り組んでおくべき課題があるとすれば、それは何でしょう。
後悔や反省ばかりなので、たくさんありますが、まず大学教員だけが研究職ではありませんので、自分が研究をしながらどうすれば生活していけるか将来ビジョンを幾つか描いてみることですね。コメンテーターとして業界で引っ張りダコということだってありえます。
ともあれ、これから研究を仕事にしようという皆さんは、かなり厳しい競争社会に置かれていると思います。国際的な活躍、インパクトファクターの高い雑誌での掲載、学振特別研究員の地位や競争的獲得資金の獲得など、自分の知らないところで歩むべき道がどんどん整備され、その路線に乗って「当たり前」という空気が作られ、そこから外れてしまう怖さも膨れ上がっているのではないでしょうか。そのため、この路線に乗る、あるいは勝ち抜くために必要なこと、例えば語学力の向上、自分の研究に関連する国内外のトレンドをキャッチすること、研究活動や成果を社会に還元することなどについては、積極的におこなっていくことをお勧めします。もはやスポーツと変わりませんから、大変です。
でも、私が忘れてはいけないと思うのは、研究とは個人的な営みであり、本当に世の中の役に立つかどうかなんてわからないということです。自分の研究分野が無くなることもあるだろうし、いまは見向きもされないけど、遠い将来、人の成長に不可欠な知を与えることになるかもしれない。自分の研究が、いつか、どこかで、なにかのためになる。そんな保障なんてないことを知りつつも、そう信じているところが研究職の性分ではないかと思っています。その自覚さえあれば、知らないうちに目の前に立ちふさがるハードルにひるむことなく、それを飛び越えたり避けたりしながら、比較的自由に走ることができるのではないでしょうか。あとは気合と根性です(笑)。
キャンパスライフ