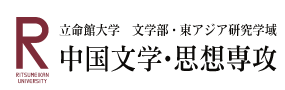研究会・総会の報告
2025年
4月20日(日) 『學林』第79号合評会および研究会が立命館大学清心館206号教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 今場正美 陶淵明「飲酒」其五について
- 張 志偉 「夢窓詞」における詞調と宮調の関係について
- 萩原正樹 武井見龍とその周邊人物の詞について
2024年
12月22日(日) 第43回総会が立命館大学清心館206教室およびオンラインで行われました。
11月17日(日) 『學林』第78号合評会および研究会が立命館大学清心館206号教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 萩原正樹 大阪天滿宮所藏(近藤元粹舊藏)の『草堂詩餘』について
9月21日(土) 研究会が立命館大学清心館206号教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 陳 銘 『説文解字』部首の配列について――「鬲」部の位置問題
- 許 暁璐 『捜神記』にみる死後復生
- 王 愷珺 田能村竹田詞研究:『閉門』と『旅窓』
4月27日(土) 『學林』第77号合評会および研究会が立命館大学末川記念会館第二会議室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 嘉瀬達男 『法言』の主題と楊雄の思想
- 尾崎順一郎 高攀龍の顕彰活動とその思想史的意義
また、博士前期課程の新入生による自己紹介と簡単な研究発表が行われました。
2023年
12月2日(土) 『學林』第76号合評会および研究会が立命館大学学而館310教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 陳 銘 『説文解字』部首配列の規則について――字形に基づいての部首接続の三つの段階とそれぞれの表現
また、研究会終了後は同会場にて第42回総会が行われました。
9月24日(日) 研究会が立命館大学啓明館305教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 高島敏夫 《宗周鐘(㝬鐘)》再考
- 萩原正樹 晏殊と柳永の豔情詞
- 詹 斐雯 高橋玉蕉の詠物詩と江戸後期女性文人の風雅な日常情景
7月15日(土) 研究会が立命館大学清心館206教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 許 暁璐 漢代の尸解仙のあり方
- 唐 鈺 「桃花源記」中の理想郷の所在――洞天思想との結びつき
- 鄭 玲玉 毛維瞻の生涯について
- 詹 斐雯 高橋玉蕉の社交詩について
4月23日(日) 『學林』第75号合評会が立命館大学啓明館302教室およびオンラインで行われました。
2022年
9月18日(日) 『學林』第74号合評会及び研究会が立命館大学清心館206教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 許 暁璐 自然災害や疫病から見る『列仙傳』の服藥を推奬する理由
- 詹 斐雯 高橋玉蕉の詠物詩の「和の趣味」について
7月31日(日) 研究会が立命館大学清心館206教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 許 暁璐 『列仙傳』の服藥を推奬する理由――漢代の神仙術との對照
- 宮本紗代 『神仙傳』と六朝までの神仙・神人・眞人・仙人像の對比——超自然現象を中心として——
- 髙井 龍 『李遠詩集』考
- 唐 鈺 唐代小説の中の詩の機能――「鄭德璘傳」を例として
- 鄭 玲玉 蘇轍の後半生における仕官・隱棲に對する考え方について
- 今場正美 三好達治「雪」をめぐる斷想
4月24日(日) 『學林』第73号合評会及び研究会が立命館大学清心館206教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 萩原正樹 「集曲名詞」考論
2021年
11月13日(土) 『學林』第72号合評会及び研究会が立命館大学敬学館206教室およびオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 廣澤裕介 白話小説を構成するもの~地理情報が語るもの~
8月29日(日) 研究会がオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 唐 鈺 プロットなどの組み合わせによる唐代伝奇小説の書き方―「霊応伝」を例として
- 鄭 玲玉 蘇轍の仕官・隠棲に対する考え方について――元祐時期以降
- 詹 斐雯 江戸時代後期女流文人の社交について―高橋玉蕉を中心に
- 靳 春雨 明治文壇における高青邱詩の受容―長三洲と近藤元粋の次韻詩を中心に
4月25日(日) 『學林』第71号合評会及び研究会がオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 髙井 龍 敦煌文獻「佛圖澄和尚因緣記」の基礎研究
- 靳 春雨 元好問詩文の刊行と受容
- 萩原正樹 詞牌「迎仙客」について
2020年
12月27日(日) 『學林』第70号合評会及び研究会がオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 許 暁璐 『列仙伝』の作者のイメージ及び仙人実在の裏付けについて
- 唐 鈺 唐代伝奇小説の中の類話群―細部描写による虚構の一つの体現として
- 鄭 玲玉 蘇轍の仕官・隠棲に対する考え方について
- 詹 斐雯 商家の娘から女儒へ―江戸後期女流学者高橋玉蕉の伝記研究
7月26日(日) 『學林』第69号合評会及び研究会がオンラインで行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 草野友子 北大秦簡『教女』について
- 富 嘉吟 石経山房本『陶淵明文集』の刊行について
- 時信和佳 『史記』「管晏列伝」に関する考察
- 許 暁璐 『列仙伝』の中の仙人になる方法
- 靳 春雨 『詞綜』と日本の知識人たち―その旧蔵者をめぐって
2019年
12月7日(土) 第38回総会が、京都市中京区の「酒菜柚家」において開催されました。
10月27日(日) 『學林』第68号合評会及び研究会が立命館大学学而館313号教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 銀雀山漢簡「將義」篇に見る將の要件
- 萩原正樹 浦川源吾の『支那歴代純文學選』について
6月16日(日) 研究会が立命館大学学而館307号教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 許 曉璐 漢代『太平經』における天人關係
- 宮本紗代 『列仙傳』と『神仙傳』の神仙・神人・真人・仙人
- 芳村弘道 古筆切の李善注本《文選》について
- 今場正美 高適の「酬裴員外以詩代書」詩について
- 田中 京 『高適集』版本について
- 靳 春雨 立命館大学図書館西園寺文庫所蔵の『詞綜』について
- 詹 斐雯 商家の娘から女儒へー江戸後期女流漢詩人高橋玉蕉の伝記研究ー
3月24日(日) 『學林』第67号合評会及び研究会が立命館大学末川記念会館第3会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 富嘉吟・唐鈺 『苑詩類選』について
- 詹 千慧 王鵬運《梁苑集》校讀及相關問題討論
2018年
12月15日(土) 第37回総会が、京都市左京区下鴨の料亭「照月」において開催されました。
8月11日(土) 『學林』第66号合評会及び研究会が立命館大学敬学館106教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 王 睿 日本新見三種《類編草堂詩餘》考
- 萩原正樹 小泉盗泉とその詞について
6月23日(土) 研究会が立命館大学学而館312教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 富 嘉吟 官版『又玄集』とその周辺
- 詹 斐雯 中日抒情美学比較研究――唐宋令詞の情景交融と平安短歌の物の哀──
- 谷口義介 善妙考
- 唐 元 黃周星傳記綜考
- 李 日康 從樂章到詞壇――清初朝野間的詞學互動,兼論《詞律》成書的現實契機
3月3日(土) 『學林』第65号合評会及び研究会が立命館大学敬学館232教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 富 嘉吟 尾張明倫堂刊本『唐丞相曲江張先生文集』について
- 楊 月英 法學家的情感困境――從董康《書舶庸譚》中的一段苦澀戀情說起
- 萩原正樹 詞牌「鵲橋仙」について
2017年
11月25日(土) 第36回総会が、京都市左京区下鴨の料亭「照月」において開催されました。
10月15日(日) 研究会が立命館大学末川記念会館第二会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 田中 京 高適の辺塞詩―封丘尉の職を辞すまでの辺塞詩
高適の薊北の地での辺塞詩の特徴はどうして形成されたか
- 富 嘉吟 『白氏文公年譜』所収の「旧譜」について
- 萩原正樹 『和晏叔原小山樂府』をめぐって
7月22日(土) 『學林』第64号合評会及び研究会が立命館大学敬学館232教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 銀雀山漢墓竹簡「地典」譯注補
- 宮本紗代 『列仙傳』と『神仙傳』の中の仙人像
- 萩原正樹 鶚軒文庫所藏「森川竹磎詩稿」について
3月26日(日) 『學林』第63号合評会及び研究会が立命館大学末川記念会館第二会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 村田 進 漢簡『反淫』にみえる道家思想について
- 今場正美 江淹の「効阮公詩」について
- 廣澤裕介 明代白話小説「蘇知縣羅衫再合」の関連作品について
- 金 菊園 梁德繩續補《再生縁全傳》説獻疑
1月29日(日) 研究会が立命館大学末川記念会館第二会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 田中 京 盛唐の辺塞詩における望郷の詩について
- 靳 春雨 詹騤について
- 金 菊園 劉弘毅與《少微通鑑》
2016年
12月10日(土) 第35回総会が、京都市左京区下鴨の料亭「照月」において開催されました。
9月3日(土) 研究会が立命館大学敬学館232号室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 高井 龍 「伍子胥変文(擬)」写本研究
- 劉 宏輝 詩論《楽府補題》的文本流伝
5月22日(日) 『學林』第62号合評会及び研究会が立命館大学末川記念会館第二会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 富 嘉吟 天王寺屋市郎兵衛刊本唐人詩集二種について
- 靳 春雨 曹冠の生平について
- 劉 宏輝 東洋文庫本劉履芬『鷗夢詞』について
- 萩原正樹 王国維年譜補訂二則
2月11日(木) 『學林』第61号合評会及び研究会が立命館大学末川記念会館第二会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 村田 進 北京大学蔵漢簡『周馴』について
- 富 嘉吟 『天宝集』について
- 芳村弘道 【資料紹介】中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書館所蔵の稿本『銭注杜詩』
- 萩原正樹 戈載『詞律訂』について
2015年
12月12日(土) 第34回総会が、京都市下京区の料亭「ト一」において開催されました。
9月5日(土) 研究会が立命館大学末川記念会館第三会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 富 嘉吟 『文苑英華』及び校記に於ける『白氏文集』諸本の利用状況
- 今場正美 滁州時代の韋応物の境地
- 萩原正樹 『厲評詞律』について
- 富 嘉吟 顧陶『唐詩類選』について
6月21日(日) 『學林』第60号合評会及び研究会が立命館大学末川記念会館第二会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 宮本紗代 『列仙傳』の中の仙人像
- 横尾聡美 『全唐詩』中の「かんざし」表現と女性像
- 千代延暁子 『公孫龍子』の認識論と正名思想
- 田中 京 盛唐の離別詩 公的離別詩と私的離別詩
3月1日(日) 『學林』第59号合評会及び研究会が立命館大学清心館542教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 谷口義介 河清瑞兆説と凶兆説
- 芳村弘道 明鈔本『新刊古今歳時雑詠』について
- 萩原正樹 『增續陸放翁詩選』所收「詞十九首」と村瀨栲亭
2014年
12月13日(土) 第33回総会が、京都市上京区の広東料理店「糸仙」において開催されました。
11月2日(日) 研究会が立命館大学諒友館831教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 今場正美 韋応物の隠逸について
- 富 嘉吟 『江談抄』に於ける白氏詩文の考察
- 芳村弘道 再訪復旦所見録(続)と朝鮮本『選賦抄評註解刪補』の紹介
7月27日(日) 研究会が末川記念会館会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 銀雀山漢墓竹簡残簡の整理についての一考察
- 萩原正樹 尾道の漢詩人・栗田鶴渚と『別天地』
- 芳村弘道 再訪復旦所見書録
4月27日(日) 『學林』第58号合評会及び研究会が末川記念会館会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 千代延暁子 『公孫龍子』の思想的特徴
- 富 嘉吟 陶淵明「歸去來辭」の異文の一考察
- 靳 春雨 李清照の「失節」について
- 廣澤裕介 『全相平話』の「全相」と上圖下文スタイルについて――『三國志平話』を中心に
2013年
12月14日(土) 第32回総会が、朱雀キャンパス7Fのレストラン「Tawawa二条店」において開催されました。
9月15日(日) 研究会が末川記念会館会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 村田 進 北大漢簡『老子』と嚴本『老子』について
- 季 忠平 易縣龍興觀唐玄宗注《道德經》幢諱校平議
- 路 璐 内閣文庫蔵五山版『新刊五百家註音辯唐柳先生文集』の書き入れについて
――卷四十二・四十三「古今詩」を手掛かりとして
- 池田智幸 蘇軾「江神子」詞諸篇の受容と評價について
8月18日(日) 研究会が国際平和ミュージアム二階会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 『六韜』諸本と銀雀山殘簡
- 池田智幸 蘇軾「江神子(乙卯正月二十日夜記夢)」詞の受容と評價について
4月14日(日) 『學林』第56号合評会及び研究会が国際平和ミュージアム二階会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 片野朱夏 左思の詠史詩について
- 田中 京 杜甫の交友
- 靳 春雨 李清照詞の研究
- 谷口義介 馮夢竜と黄圖珌のあいだ─白蛇傳變遷史(四)─
- 萩原正樹 「中調」「長調」考
2012年
12月9日(日) 第31回総会が、京都市上京区の広東料理店「糸仙」において開催されました。
11月4日(日) 研究会が立命館大学研心館642教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 高石和典 『藝文類聚』における『初學記』からの竄入に關して
- 芳村弘道 『乾隆四庫全書無板本』所收『江湖集』の鮑廷博校宋本識語について
- 井上枝里子 『太平廣記』から見る胡人イメージについて―異人論の視点から
- 谷口義介 黄圖珌『雷峰塔傳奇』にみえる西湖の水屬―白蛇傳變遷史(三)―
- 萩原正樹 國内所藏稀見『詩餘圖譜』三種について
8月1日(水) 『學林』第55号合評会及び研究会が立命館大学研心館642教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 布谷達朗 『世説新語』及び『晉書』から見る王羲之の人物像と『蘭亭序』について
- 高石和典 『藝文類聚』の採録文に関する検討
- 吉村 遼 唐代傳奇小説『鶯鶯傳』の主題について
- 小泉太郎 歐陽脩の夷陵時代 ―歐陽脩詩における夷陵時代の意義―
2月12日(日) 『學林』第53・54号合評会及び研究会が立命館大学清心館501教室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 董 偉華 浙刊宋版『廣韻』の版本系統について
- 岡本淳子 日本に於ける三國志受容と周瑜像について
- 谷口義介 白夫人と法海―もう一つの白蛇傳變遷史―
2011年
12月11日(日) 第30回総会が、京都市下京区の料亭「田ごと」において開催されました。
9月25日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 谷口義介 白夫人と靑靑―ひとつの白蛇傳變遷史―
- 鈴木俊哉 『采菽堂古詩選』における七子批判
7月24日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 高島敏夫 甲骨文の誕生 原論
- 芳村弘道 『選詩演義』攷異―『選詩演義』の『文選』版本上の問題―
- 萩原正樹 森川竹磎年譜稿
- 金 程宇 中村不折舊藏「月令」殘卷について
4月24日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 篠原健二 建安詩壇形成の一場面
- 井上枝里子 唐代文学における胡人について
- 劉 暢 薛濤とその詩の魅力について
- 渡部玄太 三つのテクストにおける太公望像の比較
- 和泉 遼 沈従文と自殺概念の関連性
- 路 璐 柳宗元作品の研究―柳州時代を中心として―
- 鈴木俊哉 『采菽堂古詩選』編纂と七子派批判との関係性
3月20日(日) 『學林』第52号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 董 偉華 四庫全書原本『廣韻』の底本
- 廣澤裕介 明代短篇白話小説「范知縣羅衫再合」について ~明代を描くこと~
- 辛 文 晋唐書風及び和様書道 ―粘葉本『和漢朗詠集』を中心にして
- 萩原正樹 巖谷小波と森川竹磎
2010年
12月12日(日) 第29回総会が、京都市上京区の広東料理店「糸仙」において開催されました。
10月16日(土) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 今場正美 陳祚明の沈約評價
- 董 偉華 顧炎武刊廣韻の明經廠本廣韻に對しての改變 ―文字・反切・韻目の改變を中心に
8月5日(木) 『學林』第51号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 『銀雀山漢墓竹簡(貳)』と『銀雀山漢簡釋文』の相違
- 池田智幸 蘇軾「江神子(密州出獵)」詞の受容と評価をめぐって
- 鈴木俊哉 陸時雍『詩鏡』について ―『四庫提要』の内容檢討を中心として―
4月4日(日) 『學林』第50号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 張 丹鳳 杜甫の詩に現れる二畳語の擬声語・擬態語について
- 萩原正樹 明・周瑛編『詞學筌蹄』について
2009年
12月6日(日) 第28回総会が、京都市上京区の広東料理店「糸仙」において開催されました。
10月25日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 村田 進 敦煌寫本『老子義』殘卷の思想特色
- 今場正美 「白蛇記」と「白蛇伝」―説話の構造における比較―
- 廣澤裕介 明代を舞臺にした短篇白話小説の中の科擧
- 萩原正樹 國内現藏詞譜版本考
8月7日(金) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 銀雀山漢簡殘簡について
- 村田 進 敦煌唐冩本『老子義』殘卷について
- 鈴木俊哉 陳祚明『采菽堂古詩選』の採録とその文學觀
- 芳村弘道 胡適が青木正兒先生に獻呈した『章氏遺書』の紹介 ―白川靜文庫の一善本―
3月1日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 高島敏夫 春秋時代における「天命」と「大命」
―「天令(命)」と「大令(命)」の意義変遷が示すもの(二) - 岡本淳子 周瑜評価の変遷について
- 平塚順良 沈義甫(沈義父)の生平について
- 芳村弘道 留滬半年経眼書録抄
2008年
12月14日(日) 第27回総会が、京都市上京区の料亭「繁なり」において開催されました。
7月13日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 鈴木俊哉 阮籍『詠懷詩』における憂い解消について
- 洪 玉芳 唐詩の隱喩と詩人の認知
- 池田智幸 宋代『青玉案』詞考
- 谷口義介 義湘・善妙説話の成立
- 董 偉華 現代中國語の諸方言における入聲韻の體母音の差異
1月20日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 張家山漢簡『蓋廬』についての一考察
- 山内 貴 太初改暦 ─暦術甲子篇と八十一分律暦の再検討─
- 今場正美 樂廣の夢説をめぐる後代の諸説
- 岡本淳子 關羽の靑龍偃月刀、別名「冷艷鋸」についての一考察
2007年
12月16日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 中嶋篤實 中國における蝙蝠のイメージ
- 平塚順良 元代北曲【一半兒】から明代南曲【駐雲飛】へ
- 芳村弘道 孤本朝鮮本『選詩演義』初探
11月25日(日) 第26回総会が、京都市下京区のホテル日航プリンセス京都において開催されました。
9月23日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 村田 進 『老子』三十九章「萬物得一以生」句をめぐって
- 今場正美 樂廣の「因」「想」の説について―占夢の歴史の中で―
- 萩原正樹 中國における日本詞研究
4月22日(日) 『學林』第44号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 高島敏夫 殷末先周期の殷周關係―周原甲骨の歴史的位相
- 村田 進 『老子指歸』における「氣」
- 今場正美 二人同夢 ―志怪・傳奇における夢の役割―
2006年
12月17日(日) 第25回総会が、京都市下京区の料亭「ト一」において開催されました。
8月27日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 阪谷昭弘 卜辭に見える「伊尹」の呼稱に關する試論
- 山内 貴 太初暦制定の背景
- 村田 進 『老子指歸』と『老子』河上公注
- 堀口育子 郭象と『論語』
6月18日(日) 『學林』第43号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 福岡千穗 物語の中の二郞神―『封神演義』を中心に―
- 山口眞貴 マキャヴェリについて
- 高井 龍 『賢愚經』「波斯匿王女金剛品」と「降六師品」との比較研究
- 今場正美 王符『潛夫論』夢列篇の夢解釋
- 堀口育子 『列子』註中の「郭象曰」と「向秀曰」について
2005年
12月18日(日) 第24回総会が、京都市上京区の広東料理店「糸仙」において開催されました。
8月7日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 阪谷昭弘 卜辭に見える高妣某の再檢討
- 岡本淳子 白話小説中の「詩」「詞」より見られる文學的特徴 ―胡曾の詠史詩を手掛かりとして―
- 平塚順良 汪廷訥『獅吼記』について
- 奥井美絵 『故事新編』誕生に關する一考察 ―魯迅と芥川龍之介―
6月5日(日) 『學林』第41号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 高石和典 六朝志怪小説に見る怪異について
- 堀尾由貴代 蘇軾と出版文化
- 堀口育子 郭象『荘子註』の典故について(逍遙游から人間世篇まで)
- 芳村弘道 靜嘉堂文庫所藏古鈔無注本『文選』卷十殘卷の紹介
3月6日(日) 『學林』第40号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 村田 進 嚴遵撰『老子指歸』の眞偽について
- 嘉瀬達男 諸子としての『史記』―『漢書』成立までの『史記』評論と撰續―
- 今場正美 傅正谷著『中國夢文學史』
2004年
11月23日(火) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 澁澤 尚 『列子』の華胥について
- 尾崎 裕 唐代傳奇の視點に關する物語論的研究
- 芳村弘道 「梁山伯祝英臺傳」と「梁叔故事」説唱諸作品との繋がり
- 上野隆三 州の三義宮について
また、引き続き第23回総会が、京都市下京区の料亭「ト一」において開催されました。
7月25日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 岡本淳子 『三国志演義』における武器について
- 平塚順良 猪八戒の武器について
- 谷口義介 蛇捕り名人の戴先生-白蛇伝形成史の一要素-
- 奥井美絵 「一件小事」に見る魯迅の希望
5月16日(日) 『學林』第39号合評会及び研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 近藤聖史 周王朝の君臣関係について-賜與形式金文を中心として-
- 山内 貴 太初暦小考
- 堀口育子 郭象と『論語』
2003年
11月30日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 近藤聖史 西周前期の「?邑」について
- 清水凱夫 『金樓子』自序篇の「不閑什一」「大寛小急」について
- 尾崎 裕 唐代傳奇の語りと視點
また、引き続き第22回総会が、京都市下京区の料亭「ト一」において開催されました。
7月6日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 矢崎文有子 中庸思想について
- 川津康弘 體驗的直觀について-老莊思想・禪宗等における認識論-
- 芳村弘道 朝鮮本『夾注名十抄詩』について-『全唐詩』の佚詩の紹介-
- 池田智幸 宋代『六州歌頭』考
- 豐後宏記 平話における“但見/只見”と駢語との關係
- 前田 惠 關羽の顔はなぜ赤いのか-神聖化との關わり-
2002年
11月3日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 阪谷昭弘 有扈討伐における禹と啓
- 近藤聖史 西周金文中に見える某祖・某考の用法について
- 澁澤 尚 『列子』の楽園説話について
また、引き続き第21回総会が開催されました。
9月29日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 『孫子』虚実篇と軍争篇
- 村田 進 『春秋繁露』にみえる身国論について
- 堀口育子 郭象の経世済民思想-死生観を通して
- 尾崎 裕 唐代伝奇における語り手の介入について
- 谷口義介 西湖三塔記の時代性と深層
6月16日(日) 『學林』第35号合評会および研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 清水凱夫 文選李善注の性質
- 佃 隆志 王安石の「萬言書」の理念
- 池田智幸 賀鋳詞における楽府文学の影響
4月7日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 近藤聖史 『尚書』文侯之命について文侯の策命とその賜與の方式-
- 山内 貴 太初改暦 ~太初暦採用の真意~
- 伊崎孝幸 李賀と古楽府
1月27日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 石井真美子 『孫子』勢篇と銀雀山漢簡「奇正篇」について
- 村田 進 『淮南子』における身國一致説
- 谷口義介 『西湖三塔記』の成立
2001年
11月18日(日) 第20回総会が開催されました。
7月29日(日) 研究会が立命館大学文学部中国文学専攻共同研究室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 岡由岐子 『三徑』(陶淵明と王維と蕪村の三徑について
- 嘉瀬達男 『法言』の人物評
- 谷口義介 雷峰塔基壇の調査
4月1日(日) 『學林』第33号合評会及び研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 阪谷昭弘 感生帝説の再檢討(殷の始祖傳説を中心として)
- 村田 進 『淮南子』の身國一致説について
2000年
12月17日(日) 研究会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて行われました。発表者と発表内容は以下の通り。
- 谷口義介 西周終末期の政治と詩篇
- 今場正美 東陽太守時代の沈約-「獨往」の實踐
- 尾崎 裕 「枕中記」と「南柯太守傳」-その《枠》を手がかりに-
11月23日(祝) 第19回総会が立命館大学国際平和ミュージアム会議室にて開催されました。