概要
今日の人類の営みと発展は多くの自然の恵み(生態系サービス)を享受することによって成り立っています。生態系サービスによる人類の経済活動は年間44兆米ドル*1に上るとされ、これは世界の総GDPの半分以上にあたります。
しかし、地球の生物多様性は1970年から2016年の間に平均68%減少*2しており、人類が持続可能な社会を目指す上で、生物多様性を守り、生態系サービスを維持することは必須の課題です。
こうした生物多様性の危機的状況を踏まえ、2021年のG7イギリス・コーンウォールサミットでの「30by30」の合意を皮切りに、2022年に開催されたCOP15(第15回国連生物多様性条約締約国会議)において、新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。
ここでは、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全する(30by30)ほか、23の目標が合意され、生物多様性の損失を食い止め、反転させること(ネイチャー・ポジティブ)を目標として、各国間で約束されました。
日本では30by30の達成に向けて、環境省主導のもと、有志の企業・自治体等による組織「生物多様性のための30by30アライアンス」が結成され、本学は2023年に加盟を行いました。
立命館はネイチャー・ポジティブへの貢献を図るべく、生物多様性保全に向けた研究・教育、社会連携活動を推進しています。
- *1 世界経済フォーラム(WEF) , Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and Economy , 2019
- *2 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES) , 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書 , 2020
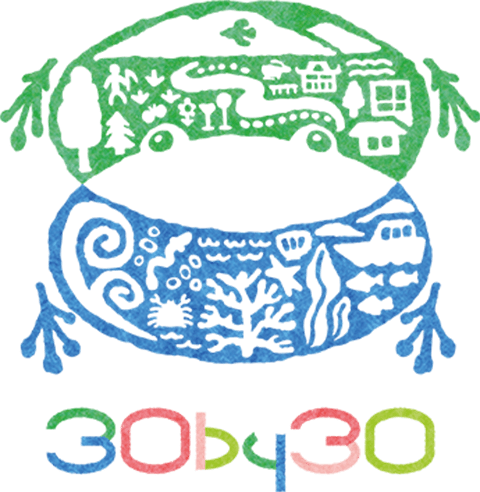
立命館の取り組み
キャンパス・附属校の取り組み
-
-
・嵐電沿線フジバカマプロジェクト
立命館大学の教職員・学生と衣笠キャンパス近隣の地域住民、地域を走る嵐電(京福電気鉄道)の社員が協働し、京都府の絶滅寸前種に指定されている「フジバカマ」の保全活動に取り組むプロジェクトで、2021年5月に活動をスタートしました。フジバカマは秋の七草のひとつで、日本書紀や万葉集、源氏物語などの古典文学にも多く登場する植物です。古来より人々の生活に馴染み深い植物ではありますが、近年絶滅が危惧される状況にあります。
挿し芽によって増やした種苗を衣笠キャンパス内で育成し、秋の開花期には嵐電北野線各駅に設置するほか、嵐電嵐山駅でフジバカマの花や葉を香料に用いた期間限定の足湯イベントの開催を行っています。沿線地域に保全活動を浸透させるとともに、フジバカマの花蜜を好む希少種アサギマダラが飛来する地域としてのブランド化や、地域へのSDGsの普及・啓発、生物多様性保全に貢献しています。


-
-
-
・BKC自然緑地


-
・BKCいきものマップ


-
-
-
・OIC育てる里山プロジェクト


-
-
-
・ホタルを別府の川へ
―APUと地域をつなぐ環境保全活動―APUの環境保護サークル「ECOS(Environmental Community Organization for Sustainability)」と「亀川の自然環境を守る会」の主催で、別府市内で唯一温泉が流れ込まない川、「冷川(ひやかわ)」において、清掃などの環境保全を行いながら、流域の生態系を守る活動を行っています。環境の変化や汚染などの影響でホタルが見られなくなったことを受けて、ホタルが飛ぶ美しい環境を維持するため、「ECOS」と地元の「亀川の自然環境を守る会」が協力して活動しています。毎年6月のホタル観賞会では数百匹のホタルが飛翔する姿を学生や別府市民と楽しんでいます。
学生団体の活動から始まり、10年以上継続しているこの取り組みは、地域社会と大学の連携、そして学生の積極的な参加によって成り立っています。APUの学生たちは実際の環境保全活動に参加することで、地域社会に貢献し、その一員として力を発揮しています。地域の人々や子供たちは環境保護の重要性を学ぶことができ、地域の自然の美しさに気が付くきっかけになっています。
-
- Home
- Nature Positive