2021.10.04 activity
スポーツ健康科学部 2018年卒業生の谷山大季さん(伊坂ゼミ)がGATプログラムで修士号を取り ATCの資格も取得されました!
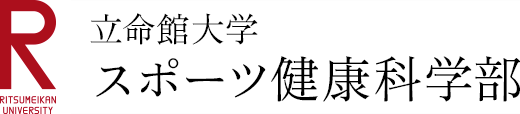
ニュース
2021.10.04 activity
2021.09.30 education
2021.09.30 research
2021.09.24 education
コロナ感染第○波、1日の感染者数○人、緊急事態宣言、自粛、ワクチン摂取率といった類の言葉を、皆さんは、この1年半以上もの歳月で何度耳にしたことでしょうか?延長されている緊急事態宣言は、9月末に解除が検討されているようですが、立命館大学は、「BCP(行動指針)レベル3」で秋セメスターを迎え、当面は、オンライン授業やハイブリッド授業、また教室収容定員50%以下での対面授業などで、「学びの場」を形成することになります。専門家によれば、コロナ禍が終息するまでには、あと2~3年は要するとの見解が示されていますが、コロナ禍であるか否かの如何を問わず、秋セメスターを迎えるにあたり、「大学で学ぶ」ことの意味について、改めて皆さんに考えてもらいたいと思います。
「学生」という言葉は、英語で“student”と表現されますが、この言葉は、「熱中する・努力する」という意味を持つラテン語の“studeo”に由来するそうです。ちなみに、勉強や勉学を意味する“study”という言葉は、「熱意・情熱」を意味するラテン語の“studium”がルーツのようです。この“student”を日本語にする場合、私たちは、中学生や高校生のことを「生徒」と表現し、大学生のことを「学生」と表現して、両者を使い分けています。それは、生徒のことを、「学校などで教育を受ける者」という、受け身的な立場にある者だと認識し、その一方で、学生に対しては、「学業を修める者」という、学修者としての主体性や自律性が求められる存在であると認識しているからです。“student”や“study”の言葉の由来と言葉の意味合いを踏まえれば、熱中したり、努力したり、熱意や情熱を持ったりすることは、学修者としての前提条件であり、皆さんには、学修者としての主体性や自律性をより強く発揮してもらいたいと思います。
オンライン授業が続くと、「授業料に見合った学びができているのか?」という疑念が湧くことは理解しています。漫然と通学し、半ば義務的に授業に出席していることにも疑問を抱くのならば、このような主張は、ある意味、健全だと思います。一方で、現在では、ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)、また日本でも東京大学や京都大学、もちろん、立命館大学でも“MOOC(Massive Open Online Course)”と呼ばれる仕組みを用いて、大学の授業を公開し、在学生だけでなく、誰もが様々な大学の授業をインターネット上で受講できるようにしています。それは、そもそも大学が「知」を創出し、人々にそれを伝授する場であるからに他なりません。言い換えれば、大学は、真理を探究するために必要な考え方や様々なスキルを学生に学んでもらいながら、まだ明らかにされていない事象や現象を解明し、「新しい知」を生み出すところだといえます。同時に、様々な知や情報は、いわば世界の「共有財産」であり、特定の個人や集団が囲い込むものではなく、できる限り知や情報はオープンにして、社会の健全な発展に活用されるべきです。
恐らく皆さんは、なぜ、私たちは授業料を払っているのに?と感じるかも知れません。「大学で学ぶ」ことの意味は、もはや「どこで学ぶのか?」という場所に規定されるものではありません。誤解を恐れずにいえば、「何を学ぶのか?」というコンテンツに左右されるものでもないのかもしれません。「大学で学ぶ」ことの意味は、場所や内容以上に、「誰と学ぶのか?」ということがより一層、重視されるようになります。皆さんは、興味を持ったこと、疑問に思ったことを友だちと一緒に考えたり、議論したりするような機会を創っていますか?あるいは、直接、教員と対話するような機会を創っていますか?皆さんに学修者の主体性と自律性を問うのは、自分自身で問いを立て、「学びの出発点」を自ら創り出さなければ、大学で「知」をプロデュースするという行為に辿り着かなくなるからです。授業中のみならず、日常生活の様々な場面で、「なぜ?」「どうしてだろう?」「本当なのか?」といったことを感じることが多々あると思います。それが「問いを立てる」ことや「思考を巡らす」ことにつながり、「学びの出発点」が生まれます。その「学びの出発点」をもとに、友だちや教職員と大いに対話し、「知」をプロデュースして下さい。しかもできる限り、異なる分野や異なる考え方を持つ人たちと対話を重ねて、身の回りにある事象や現象を多角的に見つめる眼差しを磨いてほしいと思います。
扉は、皆さんに開かれています。どうか、大学という知をプロデュースする世界へと漕ぎ出すはじめの一歩を…
長積 仁
2021.09.21 research
スポーツ健康科学部でリーダーシップ論などを担当している山浦一保先生が、この度、ダイヤモンド社より『武器としての組織心理学』を出版されました。
この分野の最先端研究のエビデンスをふんだんに取り入れながらも、初学者やビジネスパーソンにも分かりやすく、読みやすくまとめてあります。
スポーツ健康科学部は、「グローバルな視野とリーダーシップを備えて、スポーツ健康科学の理解をもって社会に貢献する人材育成」を目指しており、その基盤となる「リーダーシップ」についての専門的な知識、実践的な研究を学生、院生、関係する先生方、企業の方などと積み上げられてきた山浦先生が、この間の英知を一般書としてまとめられました。
<<同僚教員の感想>>
この本は、単なるビジネス書ではない。山浦先生が、授業、講演などで独自のスタイルとして大事にされている、「最新研究によるエビデンス、客観的データにもとづいた豊富な専門的知識を、現場の声、社会の声と紡ぎ語る」ことで、現場感覚を持ちながらも深い理解に導いてくれる著作である。本書の内容は、人間関係に悩む方にはもちろんのこと、組織のリーダー、部下の双方が抱える関係性の悩みを解決する多くの糸口がある。
組織には、それぞれに達成すべき目標、ミッションがあり、その達成に向けて組織内の人間関係の良否は極めて重要な要件となる。人と人の間の数だけ、人間関係は生じ、その「間」の取り方、「関係」の紡ぎ方を、本書は今一度振り返らせてくれる。人類は、原始のころより共同生活することで繁栄してきた。コミュニティ、組織の中で良好な関係を築くことは人生そのものの価値を輝かせてくれる。多様化する社会の中で、良好な人間関係を築くための理論的背景を理解し、明日から実践する知恵を身につけるためにも一読を勧めたい。同時に、座右において、時間とともに変化する関係性を適宜振り返られるときの参考書にしてもらいたい。
2021.09.20 research
先般、告知させていただいた「スポ健の博士力」の展開企画として、本学部の教員によるシンポジウムを10・11月に4週連続で開催します。
そのシンポジウムの告知第2弾として、シンポジウムに登壇する本学部の教員によるショートプレゼンテーション(自身の研究内容・シンポジウムの概要)の動画コンテンツを公開しました。
ぜひご覧いただき、10月・11月に開催するシンポジウムへもご参加いただければ幸いです。
【笹塲育子】心をトレーニングするとは?
【長谷川夏輝】体脂肪から見た健康管理と運動効果
【藤江隼平】運動による健康な血管の未来予測
【塚本敏人】運動をすると脳が変化する?
シンポジウムの詳細については後日、情報公開させていただきます。
2021.09.16 research
先般、スポーツ健康科学部・研究科10周年記念のひとつとして、「スポ健の博士力」の冊子を発刊、ならびにHPに掲載しました。
その「スポ健の博士力」から生み出される研究成果・社会共生価値がどのようなものであるのかについて、本学部の教員であり、「スポ健の博士力」に掲載されている若手研究者によるシンポジウムとして10・11月に4週連続で開催します。
そのシンポジウムに向けた序曲として、本学部の若手研究者が語る「スポ健のCREA」「研究の魅力」についての動画コンテンツの第1弾を公開しました。
ぜひご覧いただき、10月・11月に開催するシンポジウムへもご参加いただければ幸いです。
【座談会1】若手研究者が語るスポ健のCREA(創造)
【座談会2】若手研究者が語る研究の魅力
シンポジウムの詳細については後日、情報公開させていただきます。
また、近日、第2弾の動画コンテンツも公開しますので、お楽しみにしていてください。
2021.09.13 education
2021.09.09 research
2021年8月20日、21日にオンラインにて開催された第29回日本運動生理学会大会にて、スポーツ健康科学研究科博士課程前期課程1回生の内野崇雅さんが同研究科教授 家光素行先生の指導の下で行われた研究発表で、若手奨励賞を受賞しました。
発表演題は、「一過性運動による唾液IgAの分泌応答に運動様式の差異が及ぼす影響」です。
2021.09.03 research
2021.09.01 education
去る2021年8月26日の超創人財育成プログラム「スポーツ健康科学特論(健康ビジネス演習)」において、ラプソード・シンガポール本社に勤務されている宇野冠章氏をお招きし、「産学連携による新産業の創出 『Sports‐Tech ( Sports × Technology ) 』とは」というテーマで、現地のシンガポールからzoomによる特別講義をしていただきました。
講義では、ご自身の海外での多彩なキャリアのお話も踏まえながら、スポーツ不毛の地と言われるシンガポールにおいて、産学連携によってどのようにスポーツ界で新しい産業を創出しているのかということを、『Sports‐Tech ( Sports × Technology ) の観点から話をされました。具体的には、リトルシリコンバレーである都市国家シンガポールの現状と、その発展を支える政府や高等教育機関、民間企業の取り組み、さらには、野球などを中心に、移動する物体を追跡する技術の1つであるトラッキングシステムを用いて、ピッチングやバッティングのデータを分析し、米メジャーリーグ(MLB)や日本プロ野球(NPB)の球団に最先端システムを提供するラプソード社の事業事例を、ご自身の事業提案書に基づくPDCA分析などを踏まえながらご紹介くださいました。
中でも、技術革新によるスポーツ指導現場の改革について、ラプソード社が新たに導き出せるようになった科学的データが、様々な指導場面において、どのように有効であるのかを、「コーチング」および「学術」面で具体事例を挙げながら、受講者と活発な議論を交わしました。また、「科学的データ」という客観的根拠と、経験則に基づいた主観的指導とのギャップをどのように埋めていくか、というバランスさせていく難しさなども述べられました。受講者からは「量的研究による可視化や汎用化と、個人特性のギャップをどう捉えるか」「スポーツテック導入後の効果検証はどのような項目が適切か」など、質の高い質問や議論を交え、学生の目線に合わせて、意義深いお話をしていただきました。
2021年10月21日CNBC局放送分
2021.08.31 activity
2020年にスポ健は10周年を迎え、スポ健で学び成長した卒業生が様々な分野で活躍しています。
そんな卒業生たちに「現在の挑戦、Challenge your mind. Change our future.」をインタビューしました。第一回はスポーツ健康科学部1期生、小学校教諭として活動している三島優人さんにお話しを伺いました。
あいコアCaféでご紹介しています。
https://www.ritsumei.ac.jp/shs/cafe/
是非ご覧ください!
2021.08.27 research
スポーツ健康科学研究科・博士課程後期課程5回生 前田哲史さんが、スポーツ健康科学部教授 橋本健志先生、2019年度学部卒業生 山岸真綸さん、順天堂大学 専任准教授 宮本直和先生、国立健康・栄養研究所 特別研究員 山田陽介先生、八戸学院大学 講師 有光琢磨先生、ふくだ内科クリニック 院長 福田正博先生、サントリーウエルネス株式会社 健康科学研究所と共同で取り組まれた研究論文「Characteristics of the Passive Muscle Stiffness of the Vastus Lateralis: A Feasibility Study to Assess Muscle Fibrosis」が、「International Journal of Environmental Research and Public Health」に原著論文として掲載されることが決定しました。
https://doi.org/10.3390/ijerph18178947
骨格筋の線維化(細胞外マトリクスの過剰蓄積)は加齢とともに進行し、筋肉の機能(e.g., 筋スティフネスの増加)に影響することで生活の質(QOL; Quality of life)を低下させることが示唆されています。近年、非侵襲的に筋スティフネスを測定することが可能な超音波剪断波エラストグラフィー(SWE)を用いた研究が活発に行われており、剪断弾性率を算出することで骨格筋の線維化を評価することが可能であることが示唆されます
本研究では、30歳から79歳までの男女86名を対象に、SWEを用いて大腿部の剪断弾性率を測定し、加齢による骨格筋の線維化を検討しました。
膝の角度が異なる3つの姿勢(完全伸展、90度屈曲、完全屈曲)で、外側広筋の剪断弾性率を測定したところ、外側広筋が伸長した状態である完全屈曲時の測定において、女性よりも男性で高く、また、年齢が上がるとともに高くなることが示されました。特に年齢においては、47.9歳という比較的若い時から、剪断弾性率が高くなる、すなわち骨格筋の線維化が起こり始めている可能性があることが、初めて明らかになりました。
本研究の結果は、加齢による筋肉の機能低下によるQOL低下を抑制するためには、従来認識されている骨格筋の萎縮に対する予防だけでなく、40歳代後半からの骨格筋の線維化に対する効果的なケアやプログラムを開発することが重要であることを示しています。
2021.08.26 research
2021.08.24 research
2021.08.17 career
スポ健在学生から受験生へのVIDEOメッセージ企画です。
授業の様子、他にはない学びやこの学部の魅力、そして受験生へのエールを動画にしてお届けします。
第四弾は在学生が、スポーツマネジメントコースでの学びや、課外で頑張っていることをお送りします。
あいコアCaféでご紹介しています。
https://www.ritsumei.ac.jp/shs/cafe/
是非ご覧ください!
2021.08.06 research
2021.07.30 career
スポ健在学生から受験生へのVIDEOメッセージ企画です。
授業の様子、他にはない学びやこの学部の魅力、そして受験生へのエールを動画にしてお届けします。
第三弾は在学生が、スポ健の学生の特徴やスポーツマネジメントコースでの学びの魅力をお送りします。
(コロナ禍以前に撮影した動画が含まれるため、一部マスク着用のない場面があります。)
あいコアCaféでご紹介しています。
https://www.ritsumei.ac.jp/shs/cafe/
是非ご覧ください!
2021.07.29 career
2021.07.29 education
スポーツ健康科学部の授業を体感することができる模擬講義動画を公開しました。
スポーツ科学コースからは長野 明紀 教授が【ランニングのバイオメカニクス:動作解析で何がわかる?】をお届けします。
https://www.youtube.com/watch?v=v8iSNZdOThQ
【内容】
模擬講義【ランニングのバイオメカニクス:動作解析で何がわかる?】
競技として、あるいはレクリエーションや健康増進のために、ランニングに取り組む方が多くいらっしゃいます。ランニングの時に身体にはどの様な負荷がかかっているのでしょうか?今回はバイオメカニクスの知識と技術を使ってそれを明らかにしていきます。ランニング中の動作と力のデータに基づいて考えてみま しょう。
スポーツ健康科学部オープンキャンパスサイト(https://www.ritsumei.ac.jp/shs/opencampus)で他の模擬講義動画も公開中です。
また、8/1(日)に対面・LIVE配信でオープンキャンパスを開催します。
模擬講義・施設紹介でスポーツ健康科学部の空気を肌で感じましょう!
参加申込はこちら
https://opencampus.ritsumei.ac.jp/open/