2021.05.01 education
スポーツ健康科学部・研究科10周年サイトが開設
立命館大学スポーツ健康科学部・研究科は2020年に10周年を迎えました。
10周年サイトでは、これまでの軌跡や学生、卒業生の様子を掲載しております。また、記念式典の情報を更新していく予定です。是非ご覧ください。
立命館大学スポーツ健康科学部・研究科10周年サイトはこちら https://www.ritsumei.ac.jp/shs/10th/
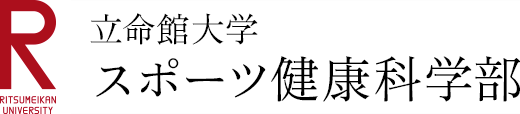
ニュース
2021.05.01 education
立命館大学スポーツ健康科学部・研究科は2020年に10周年を迎えました。
10周年サイトでは、これまでの軌跡や学生、卒業生の様子を掲載しております。また、記念式典の情報を更新していく予定です。是非ご覧ください。
立命館大学スポーツ健康科学部・研究科10周年サイトはこちら https://www.ritsumei.ac.jp/shs/10th/
2021.12.20 education
2021年12月18日の1限、「運動生理学」の授業に、中京大学准教授の森嶋琢真先生を招聘し、「これまでの研究紹介」と題して、先生が精力的にされている血管内皮機能に関する運動生理学について講義いただきました。
森嶋先生は本研究科の1期生です。
https://www.ritsumei.ac.jp/shs/hakaseryoku/pdf/Hakushiryoku_Part3.pdf
本研究科在学中は、「低酸素環境での運動と健康増進」について研究を進められました。学位取得後、米国に留学され、本講義内容に繋がる研究を開始されました。
運動不足は不健康だと認識されていますが、さて、「座りすぎ」ということがどれほど疾患リスクを孕んでいるか、考えたことがあるでしょうか。
日常生活において、皆さんはどれくらい座位行動をとっているでしょうか。
そして、私たち日本人は、諸外国と比べてどれくらい座位行動を愛してしまっているか、ご存知でしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/000656521.pdf
森嶋先生は、座りすぎの悪影響に触れながら、なかでも心血管疾患リスクを高めること、その理由に血管内皮機能の低下が示唆されること、その打開策として、いわゆる「貧乏ゆすり」の効果を実験的に証明した研究成果をご紹介くださいました(写真参照)。
この血管内皮機能は、運動習慣によって高まること、ただし運動の種類(例えば有酸素運動かレジスタンス運動か)や、運動中の血圧応答の影響を大きく受けることを解説してくださいました。特に、血圧上昇を来すレジスタンス運動は一過的な血管内皮機能の低下のみならず、恒常的な動脈硬化にも関わりますので、可能な限り血管内皮機能を維持しつつトレーニング効果が期待できるような運動様式を模索しているとのことです。そのひとつが、レジスタンス運動後に有酸素運動を10minでいいので実施することが挙げられていました。
さらには、血管内皮機能の向上が期待できる栄養素の紹介もされておりました。
こうした生理的応答に対して、想定されるメカニズムにも触れながら、大変有意義な講義をしていただきました。
また、最後に本研究科(大学院)で学ぶことの素晴らしさ、どっぷり「青春を謳歌」できることを力強く語ってくださりもしました。
愉しくてあっという間に時間が過ぎた1コマでした。
森嶋先生、ありがとうございました!
2021.12.17 education
去る2021年12月2日に組織マネジメント論の授業において、尼崎市理事であり、特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティ顧問の能島裕介氏に、「ボランティア組織のマネジメント」というテーマで特別講義をしていただきました。
能島氏は、1994年、関西学院大学在学中に学友とともに、家庭教師サークル「関学学習指導会」を設立されました。この組織を設立した翌年に、阪神淡路大震災によって被災され、学習指導会のメンバーも震災後、様々な苦労をされたようでした。そして、被災地などでの様子を目の当たりにし、学習活動のみならず、被災した子どもたちが少しでも生き生きと過ごすことができないものかと考え、設立された関学学習指導会のメンバーがボランティアで学習支援やキャンプなどのレクリエーション活動などを被災地の子どもたちを中心に展開されたとのことでした。当時は、200人以上ものボランティアが集まり、活動を進めていたとのことです。その後、大学を卒業し、一旦、就職されたものの、被災後から関学学習指導会が展開していた様々な活動を、持続的な事業化を図るために、法人を設立するということになり、就職した企業の職を辞して、学生が主体となって活動を進める特定非営利活動法人では日本初となるNPO法人Brain Humanityを設立されました。
NPO法人Brain Humanityは、「子どもたちに多様な価値を提供し、子どもたちが多様な選択肢を持つ社会をつくる」ということをミッションに掲げ、現在でも学生を主体とした経営を続けており、950人を超えるボランティアを束ねる大所帯となったようです。ユニークなのは、定款に定められているとのことですが、過半数の理事は学生であり、学生が職員の採用や雇用を担うということです。大学生を主体とする組織であるため、4年間でほとんどの構成員が入れ替わってしまうため、経験に基づく、知識とスキルの蓄積が困難であるという課題を抱えているとのことですが、このような組織特性を踏まえて、NPO法人Brain Humanityでは、組織をマネジメントするにあたり、様々な工夫が凝らされています。例えば、学生主体の組織であるため、事業の構造を理解させるために、毎週、学生理事による定例の役員会が開催され、職員の採用や事務局長の選任といった人事案件から様々な事業企画や予算編成などについて、審議、議決が繰り返されているとのことです。とりわけ、ユニークな取り組みは、「徹底した文書化と記録化」を図り、短期間で組織が刷新されていく組織特性を踏まえて、ルールやマニュアルを作成するに余念がなく、このような文書化や記録化された、ある種、形式知化する作業によって、事業運営や活動の遂行に支障を来さないような工夫を施していることです。事務所には、過去14年間にわたる役員会の議事録を誰もが閲覧可能な状態にしてあり、学生が新規事業の企画や事業運営の手がかりとして活用できるようにしているとのことでした。またアクティビティを志向する学生の気質を踏まえて、彼らのモチベーションを維持するために、活動後の「評価」を重視し、学生の取り組みにどのような意味があったのか、それが子どもたちの成長にどのように貢献していたのかを頻繁にフィードバックするとのことでした。つまり、学生の活動を、認め、讃え、そして報いるという連鎖を繰り返しながら、学生に明確なキャリアパスを示しながら、役割や業務を変化させて、活動に対するモチベーションの維持を図っているとのことでした。
学生を主体としたボランティア組織であるが故に、事業運営や活動を安定的に維持するためには、バックアップ機能を構築する必要があるものの、そのような組織体制を強化することが、逆に学生の主体性や責任感を脆弱にさせてしまうというジレンマも抱えているとのことでした。つまり、「その人にしかできない→自分がいないといけない」という責任感を醸成する一方で、各々の負担が大きくなり、バーンアウトに陥れば、事業運営に支障を来してしまう。そのため、バックアップ機能を構築するようにしているものの、それが逆に、「誰にでもできる→自分がいなくても大丈夫」という役割意識や責任感を低下させてしまうという事態も招いているとおっしゃっていました。学生を主体とした組織であるが故に、学生とどうのように向き合い、支援することが、学生の自律性と主体性を促しながら、責任を持って活動に取り組むのかは、難しい課題だとおっしゃっていました。
あっという間に時間が経ち、前のめりであった学生、とりわけ、課外活動で中核的な役割を果たし始める3回生にとっては、タイムリーな話題であり、多くの学生から質問が寄せられ、大盛況のうちに特別講義は終わりました。
2021.12.16 education
2021.12.16 activity
2021年12月14日(火)、2021年度秋学期立命館大学西園寺記念奨学金(成績優秀者枠)及び+R学部奨学金給付証書授与式を開催しました。スポーツ健康科学部では、今年度秋学期は、西園寺記念奨学金15名(1~3回生)、+R学部奨学金15名の計30名が奨学生として表彰されました。
学部生のロールモデルとして、奨学生の皆さんのますますの活躍を期待します。
なお、スポーツ健康科学部・大学院スポーツ健康科学研究科のFacebookページ(https://www.facebook.com/rits.spoken/)にて、奨学生自身の学びやチャレンジ、日々感じていることなどをリレーブログとして配信予定ですので、是非ご覧ください。
■奨学生の決意表明一覧
約束
自分との約束を守る
チャレンジしない方がわがまま。
Stay hungry, stay foolish
失敗を糧に
伝える
不撓不屈
心堅石穿
Believe in my potential
生きとし生けるものへの畏敬の念
一点一画もゆるがせにしない
進取果敢
歳月不待
温己知新
canではなくdoを求める
諦めない人間力
常に前進
容易い道に意味はない
Lose my self
My way is on your way
不昧不落
迷ったらGO
初志貫徹
So life is fun
「なぜ」をつきつめる
理解
学びの先にあるもの
信念と報恩
2021.12.09 activity
2020年にスポ健は10周年を迎え、スポ健で学び成長した卒業生が様々な分野で活躍しています。
そんな卒業生たちに「現在の挑戦、Challenge your mind. Change our future.」をインタビューしました。第4回は損害保険ジャパン株式会社にて、中小企業向けに支援をされている中村寿太郎さんにお話しを伺いました。
中村寿太郎さんのインタビューはあいコアCaféで紹介しています。
是非こちらをご覧ください!
2021.12.06 research
スポーツ健康科学部・同研究科の橋本健志教授が、塚本敏人助教、電気通信大学の安藤創一准教授、東洋大学の小河繁彦教授と共同で「Metabolites」に総説を公表しました(Title: Effect of Exercise on Brain Health: The Potential Role of Lactate as a Myokine)。
https://www.mdpi.com/2218-1989/11/12/813
「Exercise is the real polypill」といわれるように、運動が健康増進に対して万能薬の働きをすることに異論はないでしょう。近年深刻な問題となっている認知症に対しても、運動は有効な対抗策であるとされています。
実行機能をはじめとした認知機能は、習慣的な有酸素運動やレジスタンス運動によって向上し、運動習慣などの環境変化に対して可逆的に変化することが示唆されています。また、精神疾患に対しても運動効果が認められています。しかしながら、背後の生理学的なメカニズムについて未解明な部分が多く、ブレインヘルス向上のためのより効果的な方法論の確立は途上です。運動習慣は、一過性の運動の繰り返しです。そして、一過性の運動も脳機能を高めること、一過性あるいは慢性の運動効果の作用機序の共通点と相違点が整理されていないことが、統合的理解を阻んでいるのです。
私たちは、一過性の運動が認知機能を高める効果において精力的に研究を進め、効果的・効率的に認知機能を亢進させる運動強度、時間、様式を整理してきました。興味深いことに、乳酸産生を促すような様式の運動(筋収縮)が効果的に認知機能を亢進することが明らかとなり、それは脳の乳酸取り込みとその利用が関係している可能性が示唆されたのです。本総説は、そうした私たちの一連の知見に基づき、ブレインヘルス向上にとっての広義のマイオカイン(骨格筋由来の生理活性物質)としての『乳酸の役割』について、その他の考慮すべき分子とともに検討する機会としたいと願う、渾身の記事となっております。
Hashimoto, T.; Tsukamoto, H.; Ando, S.; Ogoh, S. Effect of Exercise on Brain Health: The Potential Role of Lactate as a Myokine. Metabolites 2021, 11, 813.
https://doi.org/10.3390/metabo11120813
2021.12.03 education
2021.12.01 activity
7月28日に行われた立命館×カシオ・アシックスのビジネスアイデア創出イベント「スポーツと健康をサービスにする力」について、参加学生が広報部SNSに記事を投稿しました。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.instagram.com/ritsumeikan_sports/
2021.11.30 education
2021.11.19 research
2021.11.16 activity
2020年にスポ健は10周年を迎え、スポ健で学び成長した卒業生が様々な分野で活躍しています。
そんな卒業生たちに「現在の挑戦、Challenge your mind. Change our future.」をインタビューしました。
第3回はパーソナルルトレーニング等で活躍されている西川亜沙美さんにお話しを伺いました。
西川亜沙美さんのインタビューはあいコアCaféで紹介しています。
是非こちらの記事をご覧ください!
2021.11.22 research
本学部4回生友尾圭吾さんが、総合科学技術研究機構菅 唯志准教授、スポーツ健康科学部・同研究科塚本敏人助教、橋本健志教授、伊坂忠夫教授、北翔大学生涯スポーツ学部高田真吾講師と共同で取り組まれた研究論文が「Frontiers in Physiology」に原著論文として掲載されました。
本研究は、低強度レジスタンス運動であっても、運動セット間の休息時間を短縮させることで、効果的に運動後の認知実行機能を亢進させられることを明らかにしました。
近年、運動により人々が健康的な生活を送るために重要な認知機能を向上・改善できることが明らかにされています。これまで、本研究グループは、一過性のレジスタンス運動後に認知実行機能が亢進することを報告しています(Tomoo et al. Physiol Rep, 2020; Tsukamoto et al. PLoS One, 2017; Dora et al. Heliyon, 2021; Dora et al. J Physiol Sci, 2021)。また、このようなレジスタンス運動誘発性の認知実行機能の亢進程度は、低強度運動と比較して高強度運動において大きいことを報告しています(Tsukamoto et al. PLoS One, 2017)。しかしながら、高強度レジスタンス運動は、高齢者や有疾患者に施行することがしばしば困難です。したがって、本研究が明らかにしたような、低強度運動であっても認知実行機能を亢進できる知見は、脳機能の維持・改善に効果的な運動処方を開発する上で重要であると考えられます。
Tomoo, K., Suga, T., Dora, K., Sugimoto, T., Mok, E., Tsukamoto, H., Takada, S., Hashimoto, T., & Isaka, T. (2021). Impact of Inter-Set Short Rest Interval Length on Inhibitory Control Improvements Following Low-Intensity Resistance Exercise in Healthy Young Males. Fronters in Physiology, 12, 741966.
https://doi.org/10.3389/fphys.2021.741966
2021.11.11 research
2021年11月6-7日に順天堂大学さくらキャンパスにて開催された「第27回日本バイオメカニクス学会大会」にて博士前期課程M2の桜井洸くんが若手奨励賞(1位)を受賞しました!
発表演題:
2021.11.08 education
Cerebral Autoregulation Research Network(CARNet)は、脳循環代謝・認知機能研究の将来を担う若手研究者をスピーカーとして「Cerebral Blood Flow Virtual Seminar Series 2021」を毎月主催し、世界最先端の研究・トピックを発信しています。CARNetは、11月回で“Nutrition and Cerebral Blood Flow(栄養と脳血流)”を企画し、本学部助教の塚本敏人先生をスピーカーとして招待しました。実施されるセミナーの詳細は以下の通りです。
<2021年11月22日午後10時開始(日本時間)>
1. Catarina Rendeiro, MSc, PhD. (Lecturer, University of Birmingham, UK) “Food for thought: Can plant flavonoids modulate cerebral vascular function?”
「レンデイロ・カタリーナ博士,バーミンガム大学・講師(イギリス)“フラボノイドは脳血管機能を調節し得るか?”」
2. Hayato Tsukamoto, MSc, PhD. (Assistant Professor, Ritsumeikan University, Japan) “Cerebral blood flow regulation following breakfast”
「塚本敏人博士,立命館大学・助教(日本)“朝食後の脳循環調節”」
3. Gabriella Rossetti, PhD. (Research Fellow, University of Reading, UK) “Dietary nitrate supplementation and neurovascular function”
「ロゼッティ・ガブリエラ博士,レディング大学・研究員(イギリス)“硝酸サプリメント(一酸化窒素)と神経血管機能”」
4. Kamila Pollin, PhD. (Research Scientist, Washington DC VA Medical Center, USA) “The impact of dietary sodium on cerebral blood flow regulation in healthy adults”
「ポリン・カミラ博士,ワシントンDC退役軍人医療センター・研究員(アメリカ合衆国)“脳循環調節に対するナトリウム摂取の効果”」
日本時間22時開始と、遅い時間に開始されるセミナーですが、脳循環代謝・認知機能分野における将来を、栄養生理学の視座から築く世界中の研究者が集い議論する貴重なセミナーになっております。この機会に是非、ご参加ください。
登録はこちらからできます。
2021.10.27 research
2021.10.26. 読売新聞全国版「フレイル講座」にて、スポーツ健康科学部教員によるフレイル予防のための早期のサルコペニア対策についての記事が掲載されました。
<記事引用>
加齢などで筋肉量が減った状態を「サルコペニア」と呼びます。サルコペニアは、フレイルの引き金になると言われています。筋肉を構成する筋繊維の本数が減ったり、筋肉が細くなったりし始めるのは40歳頃から。ですから、この頃から、筋トレをして筋肉量を維持することが、フレイル予防に効果的なのです。
2021.11.10 education
日時
2021年12月10日(金)16:30~17:30
プログラム
16:30~17:00 前大先生のライトニングトーク
17:00~17:30 参加者を交えたディスカッション
開催形式・定員
①京都リサーチパーク 東地区 KISTIC 2階「イノベーションルーム」:
5名
②オンライン(ZOOMによる開催):20名程度(増席決定)
詳細や申し込みはこちらから。
2021.10.11 research
第10回日本アスレティックトレーニング学会学術大会(オンライン開催)にて、スポーツ健康科学部 伊坂忠夫教授が、特別講演を行いました。
一般公開(10月末まで)されていますので、どなたでもご覧いただけます。
第10回日本アスレティックトレーニング学会学術大会
特別講演(一般公開)
『ポスト・コロナ時代におけるスポーツの価値とアスレティックトレーニングの貢献可能性』
動画視聴はこちらから!
講師:伊坂忠夫(立命館大学)
座長:倉持梨恵子(中京大学)2021.10.08 activity
2020年にスポ健は10周年を迎え、スポ健で学び成長した卒業生が様々な分野で活躍しています。
そんな卒業生たちに「現在の挑戦、Challenge your mind. Change our future.」をインタビューしました。第2回は教員として生徒指導を行なう傍ら、甲子園出場に向け、野球部監督として活動している西純平さんにお話しを伺いました。
西純平さんのインタビューはあいコアCaféで紹介しています。
是非こちらの記事をご覧ください!
2021.10.06 research