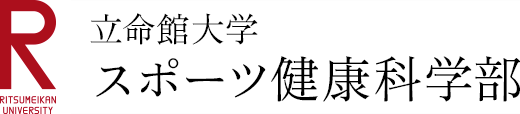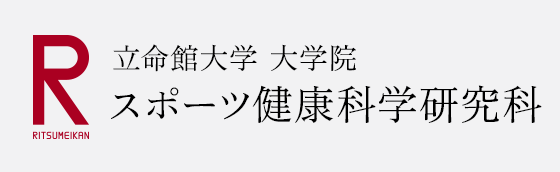今年10月より設置されます東京大学、立命館大学を中心とした
健康・スポーツ・ウェルフェアをテーマとした研究の成果を社会実装までつなげる
アクティブライフ共創コンソーシアム設立記念シンポジウム開催のご案内です。
アクティブライフ共創コンソーシアム設立記念シンポジウム
「世界水準の研究成果による地域・社会課題の解決に向けて」
★詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=548250
日 程 : 2022年9月29日(木)
15:00 ~ 17:30
現 地 : 立命館大学びわこ・くさつキャンパス ローム記念館 5F 大会議室
形 式 :オンライン(zoom)とのハイブリッド
詳 細 : 以下内のURLからお申込みください。
https://bit.ly/activelife0929
【タイムスケジュール】
15:05 開会挨拶 田畑 泉(立命館大学スポーツ健康科学部 教授)
15:10 来賓挨拶1 室伏 広治氏 (スポーツ庁長官)*ビデオメッセージ
15:15 来賓挨拶2 三日月大造氏 (滋賀県知事) *ビデオメッセージ
15:20 コンソーシアム概要紹介
15:35 基調講演 「パラリンピックブレインーアスリート研究から迫る人間の未知なる可能性―」
中澤 公孝 (東京大学大学院総合文化研究科 教授)
16:25 休憩
16:35 若手研究者によるディスカッション
「アクティブライフ社会実現に向けた次世代のスポーツ健康科学研究」
パネリスト:
鎌田 真光(東京大学大学院医学系研究科 講師)
金子 直嗣(東京大学大学院総合文化研究科 助教)
前大 純朗(立命館大学スポーツ健康科学部 助教)
坂上 友介(立命館グローバル・イノベーション研究機構 助教)
モデレーター:
伊坂 忠夫(立命館大学スポーツ健康科学部 教授/立命館大学副学長)
17:25 閉会挨拶 伊坂 忠夫(立命館大学スポーツ健康科学部 教授/立命館大学副学長)
主 催 : アクティブライフ共創コンソーシアム
お時間許す限りで結構ですので、ご興味のある方々につきましては
是非ご参加いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
【アクティブライフ共創コンソーシアムについて】
従来までのコンソーシアムと大きく違う点としては、企業の皆さまにも参加型のコンソーシアムであることです。
プロジェクト立ち上げのお打ち合わせからご参加いただき、各企業、団体、地域の皆さまの課題解決をディスカッションしながら
研究推進する形を目指しております。
コンソーシアム会員のメリットとしては
・ほかの企業や団体、研究機関と連携できること
・「最近の研究動向や業界情報が入手可能
・自社のビジネスチャンスを拡大
・社会に貢献
などが挙げられております。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.activelife.design/
アクティブライフ共創コンソーシアムWEBページ
↑↑↑
こちらから入会フォームに入っていただけます。
■お問合わせ先
アクティブライフ共創コンソーシアム事務局 担当者:成瀬・森
(立命館大学研究部BKCリサーチオフィス)
メール: actvlife@st.ritsumei.ac.jp
電話 : 077-561-2802