2014.06.23
2014/06/19 留学なんでも相談会開催!
カリフォルニア大学デービス校「サイエンス&テクノロジー」プログラムについての個別説明会を実施しました。
当日は和気あいあいとした雰囲気の中、昨年度の参加者より、ガイダンスだけでは分からない「リアル」な留学体験を熱くかつ魅力的に語られました。
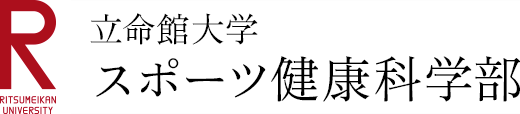
ニュース
2014.06.23
2014.06.20
この研究論文は、インスリン分泌不能の1型糖尿病モデルラットに急性に性ステロイドホルモン合成促進する栄養成分であるジオスゲニンを投与した結果、骨格筋の糖代謝調節経路の亢進を介して高血糖を改善すること、また、高血糖改善に骨格筋内の性ステロイドホルモンが関与している事を明らかにしました。
Sato K, Fujita S, Iemitsu M. (2014). Acute administration of diosgenin or dioscorea improves hyperglycemia with increases muscular steroidogenesis in STZ-induced type 1 diabetic rats. J Steroid Biochem and Molecu Biol, 143: 152-159.
2014.06.20
スポーツ健康科学部助教の 佐藤 幸治先生が同学部教授、家光素行先生、藤田聡先生、浜岡隆文先生、助教、栗原俊之先生と共同で取り組まれた研究が、「The FASEB Journal」に原著論文として掲載されました。
この研究論文は、加齢により低下している血液、骨格筋内の性ステロイドホルモンが1週間の筋力トレーニングにより高齢者の血液、骨格筋の性ステロイドホルモンが増加すること、さらに、骨格筋内の性ステロイド代謝および濃度の亢進が筋力、筋量の増加に関連していることを明らかにしました。
Sato K, Iemitsu M, Matsutani K, Kurihara T, Hamaoka T, Fujita S. (2014). Resistance exercise improves age-related declines in muscle steroidogenesis in older men. FASEB J, 28: 1891-1897.
2014.06.20
2014年6月19日3限目:基礎生理学に川崎医療福祉大学 健康体育学科 准教授 矢野博巳先生を外部講師として「免疫学」について授業をして頂きました。免疫系は複雑な調節機構により生体内で機能するが、できるだけわかり易く説明をして頂きました。
授業内容としては、免疫系の主役である白血球の説明があり、好中球、好酸球、好塩基球、単球、NK細胞、マクロファージ、Bリンパ球、Tリンパ球のそれぞれ階級や役割分担について解説しました。例えば、Tリンパ球は他の白血球を操作する司令塔的な役割を担っています。エイズなどはこのTリンパ球に攻撃するため、免疫系が破綻することから、免疫不全となります。
また、運動でも関係することに関しても説明がありました。運動後に起こる筋肉痛には免疫による筋の修復が行われます。しかしながら、壊れた筋細胞だけでは、マクロファージは動かない、ところが、正常な筋と壊れた筋があれば、壊れた筋を察知した正常な筋からマクロファージを呼び寄せています。ただし、この免疫機能はメタボな人の場合、マクロファージの働きは鈍くなります。一方、運動を習慣的に実施している人はマクロファージの動きは非常に優れています。
さらに、「運動をやりすぎると風邪をひきやすくなる」という仮説、「Jカーブモデル」についても説明がありました。その機序には、激運動後に免疫機能が一過性に低下させたことから、「オープンウィンドウ説」が現在では提唱されています。
しかし、実施にはその中で練習をしなければならない場合、どうすればいいのか?練習後の免疫機能の低下をどのくらいケアが必要なのか?それは、実験結果から、運動6時間後くらいまでは免疫機能が低下しているので、感染リスクを低下させるには、運動後6時間までは、コンディショニングをコントロールする必要があります。激運動練習後には、うがいや手洗い、着替えなど、からだや環境を清潔にしておくことがコンディショニングづくりに重要かもしれないなどの説明がありました。
新しい運動と免疫に関する情報も含め、スポーツ健康科学を学ぶ学生にとって有益な情報が盛りだくさんでした。
2014.06.20
2014.06.18
2014.06.18
2014.06.18
2014.06.16
2014.06.13
2014.06.13
2014.06.06
キャリア形成科目「スポーツ健康科学セミナーⅡ」の授業で、京都府教育庁保健体育課の前課長で、現在、京都府立乙訓高等学校の学校長を務められている川合英之先生に、「保健体育科教員に求められるもの」というタイトルで特別講義をしていただきました。
川合先生は、教育委員会に勤務される前は、京都府立鳥羽高等学校で保健体育科教員として教鞭を執られる傍ら、水泳部(水球)の顧問として課外活動の指導も担当され、国体やインターハイでの優勝経験のみならず、日本代表チームのヘッドコーチを歴任され、世界選手権で5位という成績も収められた経歴の持ち主です。
お話は、「保健体育科教員としてのポリシーを確立するために」「教科指導・部活動で考えるべきこと」「保健体育科教員になるために」といった内容で、ご自身の経験を交えながら、わかりやすく紹介されました。
例えば…
「目的」と「目標」の違いは?
「育てる」と「鍛える」の違いは?
「愉しむ」と「楽しむ」の違いは?
中でも、印象に残ったのは、「育てる」と「鍛える」の違い…
「鍛える」は、外側から刺激と与えるだけ…ということに対して、「育てる」というのは、内側から養分を吸い上げる、つまり、生徒自身が「自主的・主体的に行動する力を身につけ、そして自分で判断できる力を養うこと」という点に違いがあると説明されました。
また学習指導要領に定められているように、「態度、思考・判断」は目的的内容で、「技能、知識・理解」が目標的内容、つまり、保健体育科教員は、運動やスポーツのやり方や技術だけでなく、協力・責任・公正・尊敬といった社会性の伸長と、健康・感動・挑戦といった自己の伸長を意識し、「運動やスポーツで“何を”教えるのか」という視座と信念が必要だと述べられました。
2014.06.04
2014年5月28日、生涯スポーツ論の特別講師として、トランスインサイト株式会社代表取締役の鈴木友也氏をお招きし、「スポーツは“超える”-米国の生涯スポーツを支える日本との4つの違い-」と題した講演会を行いました。
鈴木さんは、日経ビジネスの「米国スポーツビジネス最前線」を連載し、アメリカと日本のスポーツビジネスの橋渡しをなされる第一人者です。
今回は、スポーツビジネスのお話しがメインではなく、スポーツが人々からどのように捉えられているのか、また人々は、スポーツに対してどのような価値観を抱いているのかを、日本とアメリカの文化や社会構造の違いから論じていただきました。
日本とアメリカのスポーツに対する価値や捉え方の違いを、「スポーツは“競技”を超える」「スポーツは“言葉”を超える」「スポーツは“人間”を超える」「スポーツは“スポーツ”を超える」という4つの「超える」という視点から話をされました。
「スポーツは“競技”を超える」では、1つの競技に専念することが基本となっている日本の部活動のカルチャーとシーズン制で複数種目のスポーツに親しむアメリカとの違いは、人とスポーツとのかかわりにおいて、生涯スポーツへの選択肢が狭められるだけでなく、競技レベルの低下やスポーツビジネスの市場規模にまで影響を及ぼすことを説明されました。
「スポーツは“言葉”を超える」では、日本語でも「彼の“ピンチヒッター”として、その仕事を担当する」というように、アメリカでもスポーツは、言葉で説明するよりもわかりやすいメタファー(隠喩)として日常的に用いられることを、また「スポーツは“人間”を超える」では、自由を自らの手で獲得したアメリカと、敗戦によって自由を“規定”され、与えられた日本とにおける民主主義の成熟度の違いがスポーツ観戦という行為の自由度に影響することを、さらには、「スポーツは“スポーツ”を超える」では、読書の大切さや、スポーツマンシップ、また様々な国々や人々との交流の大切さなどを教えるというNBAを事例に取り上げ、スポーツにおける社会的責任の話をされました。
2014.06.02
5月31日(土)4限目に、スポーツバイオメカニクス論のゲスト講師として、藤井慶輔先生(学振PD、名古屋大学)に、「対人スポーツのバイオメカニクス」について講義してもらいました。
藤井先生は、今年の3月に、京都大学より博士学位を取得された新進気鋭の若手研究者です。
講義の冒頭は、学生へ向けて次のように研究の進め方について話をしてもらいました。
「どうして研究していくのか」
1.何をしりたいのか(何が面白いのか)?を絞り込む
2.どんなデータを取りたいか(取れるか)?を考える
3.実際に実験→分析→論文
研究の進め方の説明の後、ご自身のテーマとして、『スポーツが上手とは?』について球技選手の対人プレイについて研究を進められました。これまでのバイオメカニクス研究では、個人の動作を対象とするものが多く、よりパフォーマンスに近づけた形で研究するため、「相手がいる状況」に着目して、バスケットボールのディフェンスについて研究を進めてこられています。
丁寧なデータ解析の結果、防御側選手が、攻撃選手との攻防の決定的場面で、どちからの足に大きく加重させられると抜かれ、逆に左右バランス良く体重をかけられていると防御成功することを明らかにしました。その理由として、バランスの良い体重のかけ方により、動き出しが良くなり、移動速度が速くなることも明らかにしています。
講義の締めくくりに、「スポーツパフォーマンスはプロセスが複雑で、要素と全体の結びつきが明らかになっていないのが難しい。一方でそこが魅力的である」と学生にメッセージしていただきました。
今後、対人スポーツのバイオメカニクスという新しい分野を切り開かれることが感じられた非常に興味深い講義でした。
2014.06.02
5月31日(土)1限目に、基礎機能解剖論のゲスト講師として、藤谷 亮先生(滋賀医療技術専門学校)に、「基礎機能解剖の理解とスポーツパフォーマンス」について講義してもらいました。
藤谷先生は、今年の3月に、立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科の博士前期課程を修了されて、現職の滋賀医療技術専門学校に勤めておられます。研究科入学前は、理学療法士としてクリニックで働いておられました。
今回の講義では、外骨格型の昆虫と内骨格型の人を比べながら、人のパフォーマンスを向上させるためにはどのようにするべきかを話してもらいました。
人は内骨格型ではあるが、筋肉を固くして外骨格化することもできる。そうすることで安定させるこができる。一方で、パンチをだすような動作の時に、関節が硬くなるような筋肉の使い方をすると早く動くことはできない。ということは、外骨格化、内骨格化を使い分けることで、その環境や行為に適した状態にすることは可能である。
特に身体構造が多関節である人は、その多関節の動きを考慮しておく必要がある。座位姿勢を長時間とると胸を反らすような姿勢、猫背の姿勢になりやすい。このような姿勢では、深層筋の活動が低下し、骨盤の前傾、後傾により脊柱に負担がかかる。その影響は腰部にとどまらず、膝、肩にもつながっていくことを解説してもらいました。
日常の何気ない姿勢がパフォーマンス、傷害につながることを身体も使いながら理解させていただきました。
2014.06.02
5月21日 生涯スポーツ論(長積教授担当)のゲストスピーカーとして、佐々木秀幸先生をお招きし講演していただきました。
講演のタイトルは、
「スポーツ強化・振興 ―次世代を担うあなたたちへのメッセージ―」
講演の内容は、1スポーツとは、2現代日本のスポーツの目標、3プレイヤーと指導者(選手とコーチ)、4スポーツイベントの構築(創り方)でした。
スポーツのもつ力、スポーツの神髄は何かへの問いかけは、古代ローマオリンピックから遡って検証され、現在の日本のスポーツ強化、振興の到達点と今後の課題を示していただきました。また、ご自身も多くのオリンピック選手を輩出されるとともに、連盟の組織強化ならびに競技力向上へ携わられた経験も踏まえた指導論は大いに若い世代の参考となりました。
講演テーマにありますように、『次世代』を託す若者へ、『伝道師』の立場から分かりやすくご講演いただきました。
【佐々木秀幸先生プロフィール】
スポーツ解説者、指導者。早稲田大学教育学部卒業。学生時代は跳躍の選手として活躍。東洋大学並びに早稲田大学教授。その間には日本陸上競技連盟 のコーチ、役員としてオリンピックに参加したほか、専務理事として組織の強化に奔走。現在も地元の中学校陸上部指導員として指導。陸上競技の教本・テキストの著書多数。
2014.05.28
2014.05.01
2014.04.17
2014.04.08