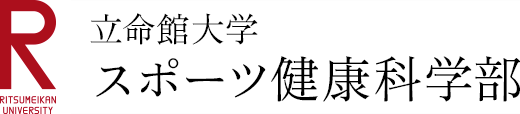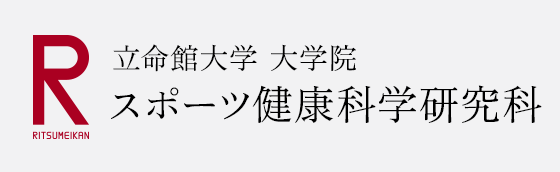2017年12月12日(火)、2017年度後期立命館大学西園寺育英奨学金(成績優秀者枠)及び+R Challenge奨学金給付証書授与式を開催しました。スポーツ健康科学部では、今年度前期は、西園寺育英奨学金12名(1~3回生)、+R Challenge奨学金6名(1回生)の計18名が奨学生として表彰されました。

授与式では、給付証書の授与に加え、回生を交えたグループ懇談にて、【今までに取り組んできたこと】、【これから実践したいこと】、【将来の目標】などをテーマに語り合い、1人ずつ決意表明を行ってもらいました。各学生とも力強い、頼もしいスピーチで、奨学生同士、お互い刺激を与え合うことができました。
学部生のロールモデルとして、奨学生の皆さんのますますの活躍を期待します。

なお、学部Facebookページにて、奨学生が、自身の学びやチャレンジの内容、日々感じていることなどを綴っているブログ記事も掲載していますので、是非ご覧ください(現在は前期受給者のブログを配信中です)!
https://www.facebook.com/rits.spoken/
また、+R Challenge奨学金受給者については、2018年5月に報告会を実施する予定です。奨学生の活躍を励みに、是非皆さんも次年度の受給を目指して頑張ってください。
■奨学生の決意表明一覧
「感謝と努力 自分らしく」、「取捨選択」、「文武両道」、「子どもと共に成長できる体育教師」、「トライアスロンの発展」、「世界基準を日本の『現場』へ」、「?」、「今の自分を越える」、「視野を広げる」、「とにかく挑戦する」、「何事にも全力で」、「常に高みへ」、「幅広い知識と発展」、「将来について真剣に考える」、「根性」、「高校保健体育教員」、「研究内容を深める」
※奨学生全員の決意表明は、立命館大学びわこくさつキャンパス インテグレーションコア 2階に掲示予定です。
「立命館大学西園寺育英奨学金(成績優秀者枠)」
学部での正課の学習において努力し、優れた成績を修め学生を「学びの立命館モデル」の趣旨にそって褒賞し、周囲の学生の学びと成長の模範となることを奨励することを目的とした奨学金制度
「立命館大学+R Challenge奨学金」
学部において正課の成績が良好であり、学部の専門学習、全学共通教育(教職教育・教養教育・外国語教育など)、留学や国際的な学習を通して、問題意識を持ち、それを発展させて学習テーマを追求しようとする学生の学習プロセスを支援することにより、周囲の学生の学びと成長の模範となることを奨励することを目的とした奨学金制度