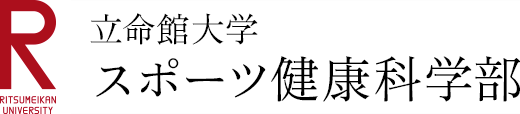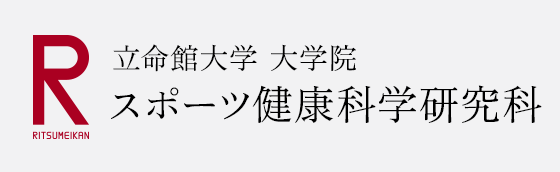2019年6月13日の1,2限、専門演習I, IIの授業に、筑波大学体育系助教の國部雅大先生を招聘し、「スポーツパフォーマンスに関連する注視および注意のはたらき」について講義いただきました。國部先生のご専門は体育・スポーツ心理学、実験心理学です。たとえば、「どうすれば運動がうまくなるのか?」「運動中、どこに注意を向ければいいのか?」「うまく運動を行うにはどこを見ればいいか?」といった疑問に対して、反応時間や眼球運動の解析、身体動作解析などの手法を用いて実験的に検証されております。
先生は、ご自身がバレーボール選手であったので、その際相手選手の動きを見てプレーする際に視覚情報の重要性を感じられたことが研究の発端になったということです。また、バレエもされており、その際は自身の身体の動きに注意を払い、そうした固有感覚の重要性を感じられた。つまり、視覚(外受容感覚)と固有感覚(内受容感覚)のバランス、相互作用といったものがこの分野の興味となったということです。
講義では、学生に実際に視覚情報について体験させるかたちの、非常に楽しい授業を展開していただきました。
たとえば、腕を伸ばして親指を突き上げ、それを左右に少しずつずらしながら中心視と周辺視を確認させたり(図1)、

図1 中心視と周辺視の確認
上方に投げた消しゴム、あるいは対峙した相手が投げた消しゴムを片目でキャッチすることの困難さを示したり(図2)、


図2 片目での消しゴムキャッチ(みな床に消しゴムを落としています)
ビジョントレーニングを紹介したり(図3)、

図3 フォーカスを前方の指、後方の指と交互に変えていきます
学生も楽しく体感しておりました。
他にも、バスケットボールのフリースローでの、熟練者と初心者の注視点の違いや、野球のキャッチャーがフィールドでの指示(バント処理など)をどのタイミングで行っているか、上級者の特徴付けなど、興味深い研究報告をしていただきました。
お話のなかで、運動能力を技能(ソフトウェア)と体力(ハードウェア)に分けて構造・構成要素を捉える、ということがありました。これは私たちの分野の課題で、これまで運動体力(エネルギー代謝機能や筋力、呼吸・循環機能など)を指標に、トレーニング効果などを評価・検証してきました。一方、運動技能に関わる知覚機能であったり中枢神経系の機能は評価が難しく、まだまだ課題も多いわけです。その分、興味深いわけですが。。
特に、当方では運動が認知機能に及ぼす影響について研究しており、スポーツにおける状況判断能力(例えばパスを出すかシュートに持ち込むかなど)に関わる高次脳機能に興味を持っております。実験的研究としては実験室(ラボ)で実施することが多いのですが、実際のフィールドでの「認知パフォーマンス」との整合性については検証できておらず、課題として掲げております。そんななか、ラボ実験とフィールド実験の齟齬を示した報告をいくつか紹介いただき、また、フィールド実験においてこそ抽出できるパフォーマンスの解析例などもご紹介いただき、とても興味深いものでした。ゼミ生も卒業研究に大変参考になったと言っておりました。
國部先生、ありがとうございました。