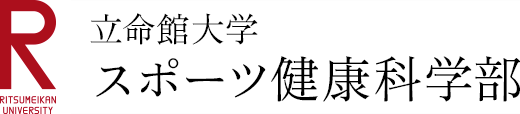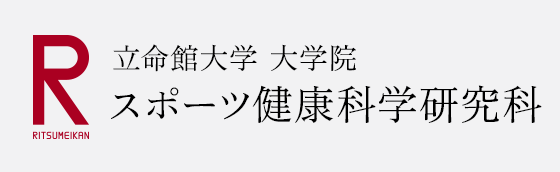2017年5月30日に、筑波大学・鬼頭朋見先生を、お招きして文理融合セミナーを開催しました。
ご存じのように、スポーツ健康科学は、遺伝子から組織/社会までを扱う学問で、自然科学、人文科学、社会科学を総合的・学際的に扱う学問です。そのため、文理融合を常に意識しており、分野を越えた教員同士のコラボが活発です。
今回、鬼頭先生をお招きしたのは、鬼頭先生のキャリア自体が文理融合を体現されていたこと、ならびに現在の研究アプローチそのものが学際領域であることでした。鬼頭先生は、学部から博士課程修了までは、ロボット工学の分野で研究され、その後、オックスフォード大学のビジネススクールで、ロボット工学で学ばれた解析手法を活用した研究を進められ、現在は経営学の分野で活躍しておられます。
現在の研究については、次の講演テーマでお話し頂きました。
『社会・産業の持続的発展のための領域融合的研究:ビッグデータ+ネットワーク科学アプローチ』
お話は非常に面白く、かつ多岐にわたりますので全て紹介できませんが、いくつかを紹介します。
その一つは、複雑創発システムという考え方です。このシステムは、複数の要素間の関係性、相互作用から複雑な全体が組織化され、個々の要素の振る舞いからは予測できないような現象・秩序・機能が現れる系、というものです。一つの事例としては、車を製造するということを考えた場合に、自動車メーカーにはそれぞれに部品を納入するサプライヤー、取引先企業、さらにはそれぞれの拠点国などがあり、これらが複雑にリンクを張りながら、自動車製造ということで一つの秩序が成り立っている。ただし、メーカーごとにリンクの張り方、関連度合いも違うこともあり、それぞれの置かれた環境にも影響を受ける、というものです。
もう一つは、ネットワーク科学+ビッグデータについてです。これからの時代、IoTといわれるように、多くのもの、コトがネットワークにつながり、ビックデータが形成されます。そのようなビックデータをどのように使われるのか?
ネットワーク科学では、タンパク合成、インターネットのつながり、飛行機のルートマップ、FBの人間関係などが解析されます。このようなネットワーク科学とビックデータを活用すると、エボラが発症したとき、ネットワーク科学者は、ネットワークを解析してどのような感染するのかの予測。限られたワクチンをどのように投与すれば効果があるのかを考えるのもネットワーク科学の仕事。
さらには、ネットワーク間のつながりの強さ、弱さを分析してみると、意外と近くで強いネットワーク(リンク)よりも離れたコミュニティと弱い紐帯(リンク)がある方が、イノベーション(創発)を起こしやすい、ということもデータを活用した研究から明らかにされているようです。
参加した先生方からは、多方面から活発な質問が出され、まさに鬼頭先生の刺激に創発をうけたセミナーでした。