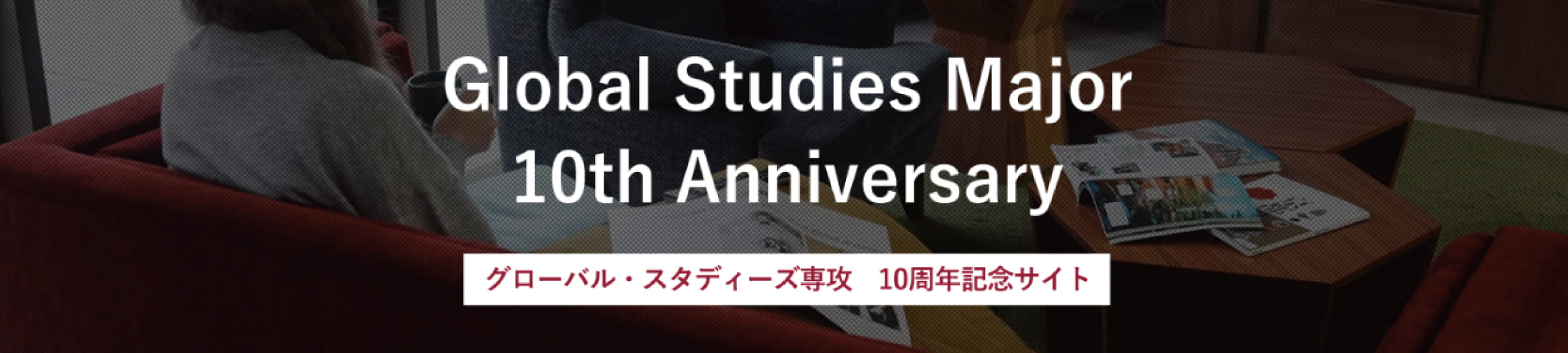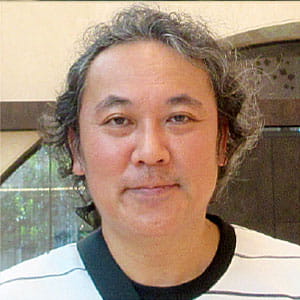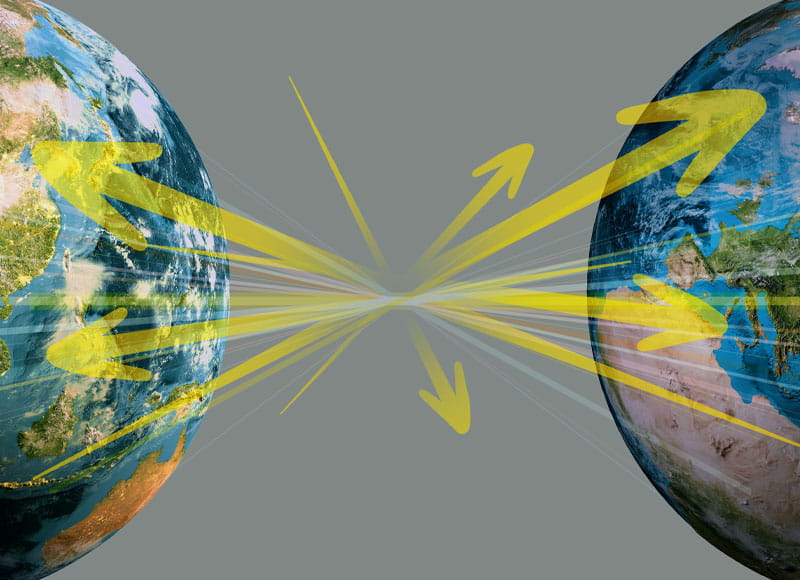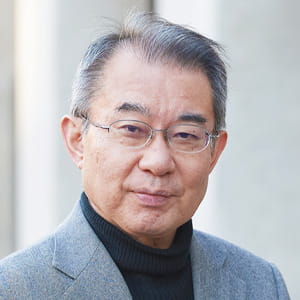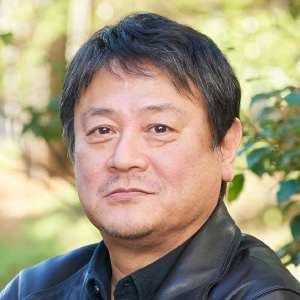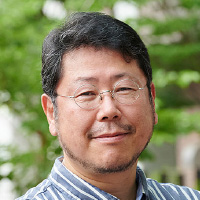国際関係学を学ぶ3つのアプローチ
国際秩序平和
国際社会の
ダイナミズムを学び、
新しい国際秩序のあり方を探る
国際秩序の歴史と現在、そして新時代の展望を、国際政治・国際関係論・国際法・国際政治経済、国際ジャーナリズム論などの分野から綜合的に学修。戦争・平和・人権から、紛争や経済摩擦まで、幅広い問題を解決するための新たな手法を探ります。
国際協力開発
持続的な社会と
経済発展を両立する
国際協力・開発援助の
あり方を学ぶ
途上国の現状や国際協力・援助など、国際的な社会・経済発展の条件や貧富の格差の問題を実践的に学修。政府や国際機関による国際協力だけでなく、企業やNGOなどの活動も視野に入れながら諸問題の解決策を探ります。
国際文化理解
高度な異文化理解力を
身につけ、
共生社会の実現にアプローチ
グローバル化が進む現代において、多様な文化や価値観を尊重しあい、共生社会を育てて行くことは重要なテーマです。さまざまな文化や社会を比較考察し、多文化共生の道を探ります。
国際関係学科IR専攻国際公務プログラム
国際関係の学びを
国内外の行政キャリアへと繋ぐ少人数教育
外交官をはじめとする国家公務員や国連職員、地域を支える地方公務員など、行政を担うキャリアをめざす学生が切磋琢磨しながら、グローバルな公共政策や国内外の行政に関する実務と理論を学びます。
TOPICS
池田 淑子教授の「退職記念講義」を1月14日(水) に開催します
11月に開催した「オープンゼミナール大会」当日の様子を収録した動画を公開しました。
国連・国際機関で働きたい人のためのセミナーを1月26日に開催します(対面+Zoom開催:要事前予約:本学部の卒業生が登壇)
ゲスト講義実施報告「憎しみの連鎖をほどく挑戦-日本から生み出す新たなアプローチ-」(NPO法人アクセプト・インターナショナル代表理事 永井 陽右様)
オープンゼミナール2025【もうええでしょう】「食い尽くし系夫」は何故食い尽くしをやめられないのか?(鳥山ゼミ インタビュー)
元外務事務次官 薮中三十二客員教授による特別講演と外務省を目指す学生へ向けた「キャリア・トークセッション」を開催しました
2025年度春セメスターの成績優秀者を対象とした「西園寺記念奨学金」の授与式を行いました
ゲスト講義実施報告(ジャーナリスト 安藤 優子様)

再入学
2026年度立命館大学【学部】再入学試験について
ゲスト講義実施報告(元世界銀行・IMF開発委員会幹事 小寺 清様)
ゲスト講義実施報告「アフガニスタン支援:20年間の成果と今後の課題」(元 JICA国際協力機構南アジア部長 中原 正孝様)
体操部の主将としての活動と学部の学びの両立。ゼミの海外フィールドワークが国連職員になりたいという夢に挑戦する勇気をくれました(3回生 吉田 誇太郎さん)
数字で見る国際関係学部
開設年度
1988年
卒業生
9000名以上
学生数
1500名以上
在学中の留学生数
370名以上
留学生受入れ国・地域
30ヵ国・地域
英語開講科目数
100科目以上
国際関係学部開講科目全体の
30%を占める
海外留学生数
年間160名以上
外国人教員数
18名以上
外国人教員の国籍
12ヵ国・地域
2025年5月時点の実績を掲載しています。