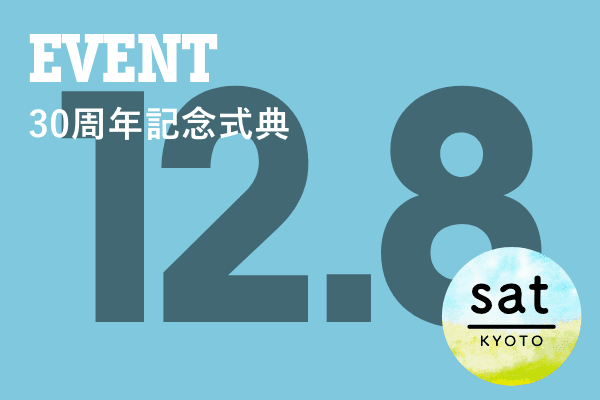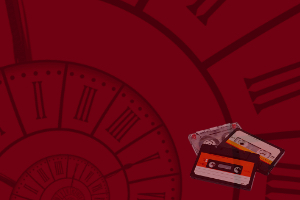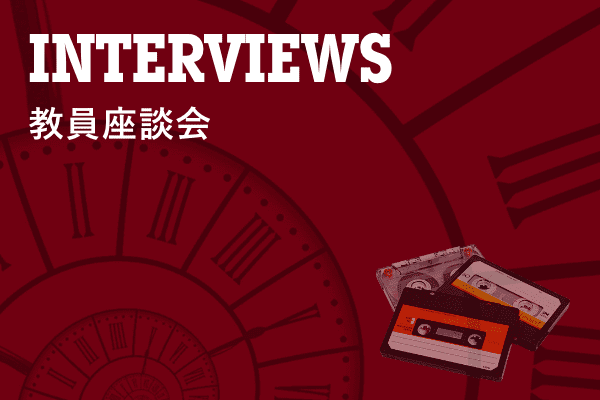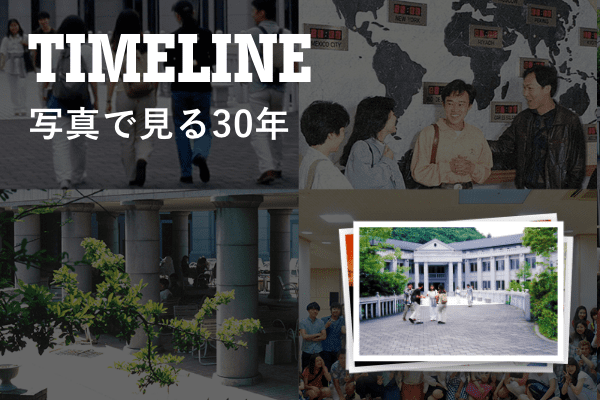世界でグローバル化が進展する中、国際関係学部は次々と新機軸を打ち出し、立命館大学の国際化をけん引しました。
国際関係学部草創期に学部長を務めたお三方が激動の時代を振り返りました。
語り手:朝日稔先生、奥田宏司先生、小木裕文先生
聞き手:君島東彦(学部長)、中川涼司(教学担当副学部長)
2018年7月31日
言語×理論×地域を柱に据えた
これまでにない国際関係学部をつくった
君島 国際関係学部の草創期に学部長を務められたお三方は、生まれたばかりの学部をどのようにつくっていったのか、まず最も先輩である朝日先生からお聞かせください。

学部開設準備から関わり、草創期のカリキュラム構想やダブル・ディグリープログラムの開発に携わる。学部長(1994~1995年度)、学部主事、研究科長も務めた。
専門は世界経済論、多国籍企業、貿易摩擦、国際政治経済学
朝日 最も苦労したのは、学部長になるより以前、国際関係学部を創設するにあたって学部の方針や教学の基本的な考え方をつくる過程でした。当時、全国に私立大学の国際系学部は明治学院大学と大東文化大学、そして日本大学の三つしかなく、ほとんど参考にするもののない中、ゼロから新しい学部をつくらなければなりませんでした。
まずは「『ディシプリン中心』ではない学部をどうつくるべきか」という議論から始めました。とりわけ難航したのは、「学際性」と「総合性」をいかに学問の中に織り込んでいくか。当初は教員の多くを他学部から招いて構成していたため、多様なディシプリンの専門教員、さらに語学教員の意見をまとめ、一緒に教学をつくっていくのは至難の業でした。
議論を尽くした末に、政治学、法学、経済学、経営学といった既存ディシプリンを揃えた理論系科目と現実に即した新たな「語学教育」、そして「地域研究」の三つの要素を教学の柱としてカリキュラムを編成しました。
君島 現在国際関係学部は「言語×理論×地域」を教育の三本柱に据えていますが、これは開設時につくられて以来、一貫して変わらないのですね。この三つ中で特に難しいのは、「地域研究」を教学に位置づけることです。教員人事においてもディシプリンを基準に採用してきたため、ともすればカリキュラムがディシプリン中心になってしまうのが現在の課題です。
朝日 「地域研究」の弱さは当時から今に残された「宿題」ですね。新学部をつくる際、本学ならでの独自性を打ち出せないかと考え、あえて「地域研究」を入れました。とはいえ限られた財政の中で、各ディシプリンに語学、さらに地域研究と全分野に教員を配置できるわけではありません。そこで各ディシプリンを専門とする教員が地域研究も兼ねることですべての科目を網羅しようと考えました。それが今日の教員人事にも引き継がれています。それでも「学生1学年160名に対し約40名もの教員を擁するのは多すぎる」と当時全学から批判を受けたものです。
それ以外にも、他大学の国際系学部とは一線を画す新たな機軸も次々と打ち出しました。海外の大学との共同学位プログラムDUDP(Dual Undergraduate Degree Program)もその一つです。二つ目には、大学院を開設。そして三つ目として学生を積極的に海外留学に送り出す一方、海外からも多くの留学生を受け入れ、国際的な学部を志向しました。
開設後も現実に即して改革は続きました。一つには、カリキュラムの見直しです。「学際性」と「総合性」をうたったものの、そこで学ぶ学生たちの専門分野は何なのか、学生自身が自覚できないことが課題となり、新たにコース制を導入しました。またゼミナール大会や国際インスティテュート、大学院への飛び級制度など、新たな試みを果敢に取り入れた結果、非常に先進的な学部をつくることができたと思っています。
教員が企業を回り、大学院設立の意義を訴えた
君島 奥田先生も創設当初から国際関係学部で教えられ、新学部の草創期をつくりあげた教員のお一人ですね。
奥田 大学院を設立した時のことはよく覚えています。1992年のことでした。最初に構想したのは、160名規模の学部の先にある大学院ではなく、他学部の教員も招聘し、100名規模の教員を有する独立大学院でした。今では想像できないでしょうが、それを実現させるため、教員自ら企業を回って立命館大学国際関係学部に大学院をつくる意義を説明し、賛同のサインをお願いしたんです。それを「これだけ社会的なニーズがあるのだ」という傍証として申請書類と一緒に文部省に提出しました。
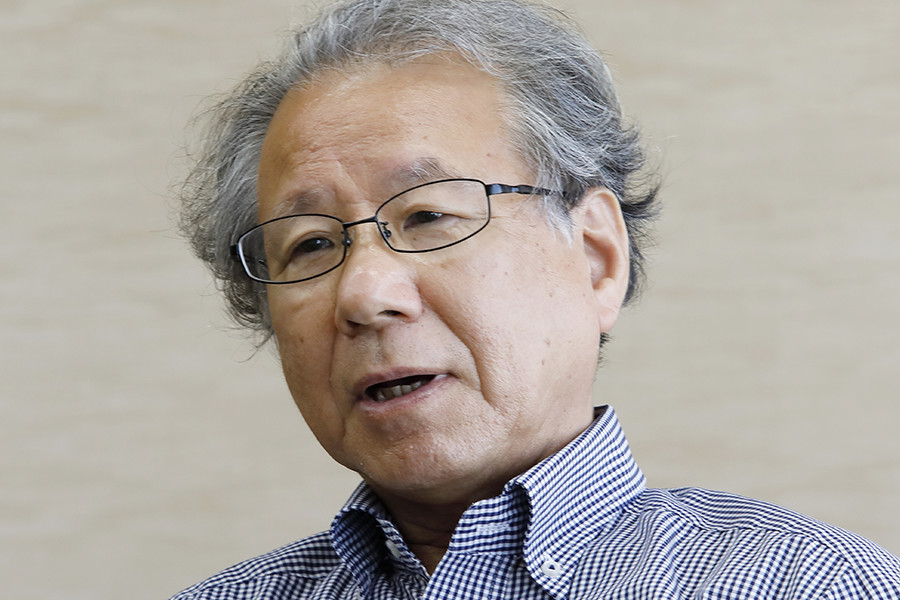
学部創設期より教学プログラムやインターンシップ・プログラムの開発に携わる。学部長(2001~2003年度)、学部主事、研究科主事、調査委員長も務めた。専門は国際金融論、国際経済学
君島 各企業にはどのような主旨で賛同を得たのですか。
朝日 主に出口問題(=学生の就職問題)です。企業が修士課程修了者に期待するのは専門性です。語学力だけでは評価されないので、「マルチディシプリンを修めた学生を育てたい」と訴えました。
奥田 我々も正直なところ最初は「就職は大丈夫かな」と危惧していましたが、企業を回って一定の賛同を得られたことが自信になりました。加えて、JICAをはじめ国内外の国際機関と協定を結べたことも大きな財産になりましたね。
その後、1995年度からいわゆる「97年改革」に向けての議論が始まりました。特に問題になったのは、各コースが法律・政治、経済・経営、文化・社会といったディシプリンで分かれていたことでした。「これではいけないだろう」と議論を重ねた結果が、今日の教学システムの基礎になっています。97年改革ではその他にも、立命館大学から「外交官を輩出したい」といった要望もあり、キャリア形成についてもずいぶん議論しました。
国際関係学部が全学の先陣を切った数々の取り組み
君島 2000年9月に国際関係学部が西園寺記念館から衣笠キャンパスの恒心館に移転したことについてお聞かせください。
奥田 当時衣笠キャンパスで国際インスティテュートを展開しようという話が持ち上がりました。依然として学生数に対して教員が多いことが批判の的になっていたため、他学部から学生を受け入れることで国際関係学部の学生定員数を抑えつつ、立命館大学全体の国際化にも貢献しようと考えたのです。しかし前例のないことに最初は受け入れられず、何度も各学部と折衝しましたね。
小木 奥田先生の後を引き継いだ私が学部長在任中に、国際インスティテュートの学生定員を増やす案が出され、カリキュラムを増やしました。その際には、各学部から教員を割り当ててくれるなど、「立命館大学の国際化に役立つなら」と全学が後押ししてくれました。
朝日 国際関係学部の取り組みが立命館大学の常識を覆し、当たり前のように踏襲されてきた体制を変えた例は少なくありません。例えば当時基礎演習は全学横並びで一クラス40名で行われていました。我々は「少人数教育を謳いながら40名は多い」と訴えましたが、定員を減らす許可は得られませんでした。そこで国際関係学部独自に20名ずつの二クラスに割り、それぞれに教員を割り当てて基礎演習を実施しました。当然増えた教員分の手当てはありません。それでも手弁当で20名の少人数教育を続けました。
その他、インターンシップなど今では当たり前になっている立命館大学の取り組みについても、国際関係学部が先陣を切ってきました。
小木 インターンシップを導入する際、当初3ヵ月間のインターンシップを単位認定することは文部省(現・文部科学省)に認められませんでしたね。そこで教職員がインターンシップを受け入れてくださる協定企業・機関を一つひとつ開拓し、ようやく認可されたのです。その時の教員たちの情熱・行動力は我ながら「すごいな」と思いましたよ。
君島 当時の教員の方々はそれだけ強い意気込みと覚悟を持って取り組んでおられたのですね。
国際関係学部が開拓した多様な進路
小木 学生のキャリア形成に関しても皆熱意を持っていました。就職支援のために教員が企業回りを行ったのもその一つです。総合商社など、それまで立命館大学の卒業生があまり就職していない業界・企業を中心にずいぶん足を運んだ覚えがあります。その甲斐あって企業に立命館大学国際関係学部の認知度が高まり、就職先が広がっていきました。
朝日 学部だけでなく大学院についても国際機関などに積極的に働きかけ、就職の間口を広げましたね。今では当たり前になっている全学のキャリア支援は、先駆けて国際関係学部が成功体験をつくってきた結果だと自負しています。
奥田 しかし大学全体として就職支援を強化するようになって以降、次第に学部としてキャリア支援に取り組まなくなった結果、それまで培ってきた企業や国際機関などとのつながりが希薄になってしまった点については、課題が残ったと思います。
君島 1990年代の国際関係学部には、大学の中でも社会的にも「いかに認知してもらうか」という危機感・緊張感があったと思います。偏差値が高くなった頃からそうした高い意識が薄れていったのかもしれません。
学部が一丸となって厳しい時代を乗り越えていく
君島 現在の国際関係学部、教職員に対し、先達としてぜひ率直に注文を聞かせてください。
小木 「国際関係学部が日本、そして世界に貢献する人材を育てる」という気持ちを全教員が持ち、皆で協力する体制をつくることが重要ではないかと思います。内に籠っていては山積する課題を解決できません。教員が大学の教育現場はもちろん、学外の企業やさまざまな機関、社会と関わって知見を得て、それを大学にフィードバックする仕組みがあればいいですね。

学部長(2004~2006年度)、学生主事、研究科主事、副学部長を務める。学生のキャリア支援から卒業後のネットワーク構築に貢献。
専門は華文文学、東南アジア華人社会論
朝日 振り返ると、国際関係学部をつくった時には原点に据えたことが三つありました。一つは、長期目標を持つこと。二つ目には他の大学や学部にない独自性を発揮すること。そして三つ目に、何事も協働で進める気風をつくることです。時代や人は変わっても、この三つは変わらず重要だと思います。
受験生に、「立命館大学に行きたい」というより「立命館の国際関係学部で学びたい」と思われる学部であることが大切です。教職員の方々には「日本有数の国際関係学部である」という気概を持ってほしいですね。
奥田 教員だけでなく、職員との関係も重要です。現在も教職協働に注力していますが、「教員と職員、そして学生が一体である」という意識を持って取り組んでほしいですね。
国際系学部のパラダイムとして
君島 国際関係学部が開設されて30年、いまや日本中、国際系学部のない大学の方が少ないほどあらゆる大学に「国際」と名がつく学部ができています。そうした中で、国際系学部の標準化とそのための基準を設定することが課題となっていると考えています。我々は、立命館大学国際関係学部こそが国際系学部の「パラダイム=範型」だと自負し、それも踏まえて2016年、学部、大学院ともに専門分野別外部評価を受けました。こうした国際系学部の基準設定・標準化についてお考えはありますか。
朝日 難しい問題ですね。というのもそれぞれの学部の性格があまりにも違うからです。例えば世界的に見ると、国際関係学部といってもアメリカ型とヨーロッパ型は違います。アメリカ型は世界の覇権国として他国に影響を及ぼすという立場から国際関係学部がつくられましたが、ヨーロッパの場合は、文字通り隣接する国々との関係を考える学部として成り立っています。そして日本の国際関係学部はそのどちらとも異なります。本学の国際関係学部を創設した当時はまだ世界に貢献するという意識は希薄で、経済成長を遂げていくことを志向していた背景があります。こうした成り立ちの異なる学部を標準化する基準をつくるのは、容易ではないと思います。
君島 加えて、全国にある国際系学部とヨコのネットワークをつくれないかという点も課題であると感じています。
奥田 学部設立当初も全国的に連携する動きはありましたが、結局はうまくいきませんでした。学部同士でつながるよりも、まずは学生同士が交流することを考えてはいかがでしょうか。
君島 確かに考えられますね。立命館大学で全国の国際系学部を招いてゼミナール大会を実施するのもいいかもしれません。
朝日 産業界からも協力を得ることを検討するのも一手です。さらに高等学校も含めて考えていくと良いと思います。
小木 開設から30年が過ぎた今では、世界中の企業や国際機関、外務省などさまざまなところで卒業生が活躍しています。そうした卒業生の活躍ぶりを学生に伝えられれば、学びの励みになるのではないでしょうか。
朝日 研究者として活躍する卒業生が多いことも誇るべきことだと思います。「ホームカミングデー」を開催するのもいい。卒業生の多様なネットワークをつくり、「母校のために貢献したい」という気風を育てることも大切だと思います。
奥田 学部1回生から博士後期課程の院生までいるということが立命国関の強さですよ。教員のためにも学生のためにもそうだと思う。後期課程の院生を確保することもしないといけないと思いますね。
君島・中川 きょうは貴重なお話をどうもありがとうございました