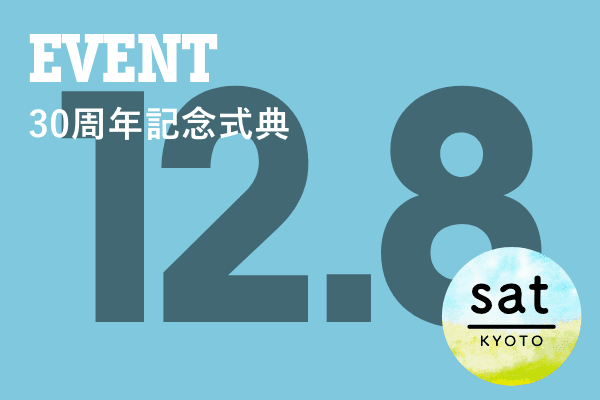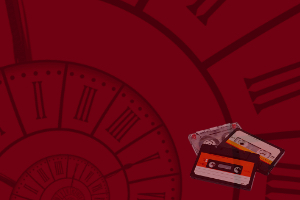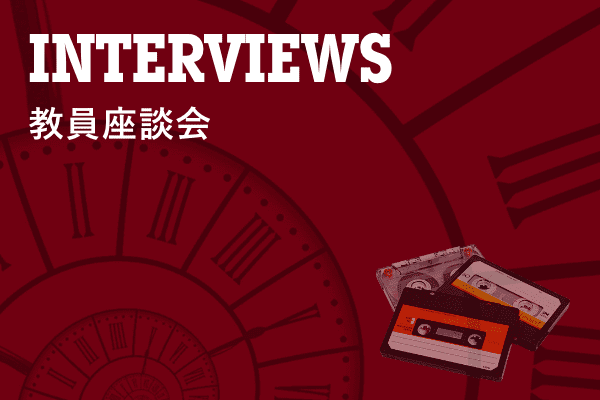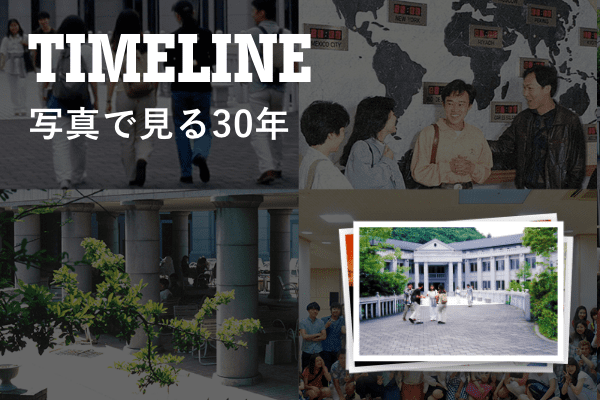草創期に勤務し、教育・研究を支えた先生方に、
過去の経験から現在を分析し、国際関係学部の未来を展望していただきました。
語り手:佐藤誠先生、加藤恒彦先生、竹内隆夫先生
聞き手:君島東彦(学部長)、中川涼司(教学担当副学部長)
2018年7月31日
「永続革命」の学部として、
絶えず新たにつくっていく学部
君島 国際関係学部の草創期からの発展を目の当たりにしてきた皆さんは、現在の国際関係学部をどのようにご覧になっていますか。課題として感じられることなどをお聞かせください。

英国留学後、学部発足時教員の一人に。特に90年代以降、日本のODA政策拡大に伴い、国際貢献・開発分野の教学に貢献。専門は開発学、地域研究(アフリカ)
佐藤 我々が認識しなければならない最も大切なことは、国際関係学部は「永続革命」の学部だということです。例えば法学部は、歴史的に見てもまた他大学を見ても、民法、刑法、憲法といった科目構成や教育内容はほとんど変わりませんが、国際関係学部にはそうした普遍的な枠組みがないため、絶えずつくっていかなければなりません。その意味では私たちの経験をそのまま生かすことはできないでしょう。
私は立命館大学に赴任するまで民間企業で働いてきて、教師になること自体が初めてでしたが、国際関係学部もまさにゼロからのスタートでした。悪戦苦闘する中で実感したのは、現状に甘んじることなく社会や大学の状況に合わせて絶えず変化していかなければならないということです。というのも国際関係学部は、他の学問分野以上に社会の動向の影響を受けるからです。
思い出すのは、1990年代後半から2000年代前半にかけて、ひと際ゼミの応募者が多く、優秀な学生が揃った時期があったことです。今思えばこれには当時の日本の社会状況が大きく影響していました。1989年から2000年まで日本のODA援助額は世界一でした。バブル経済が崩壊した後もしばらくは社会に余裕があり、「世界に貢献する」という意識が若者に浸透していたことから、多くの学生が国際関係学部の門を叩いたのだと思います。そう考えると、これからの国際関係学部の方向性を決める上でも、今そして今後の社会情勢をどう捉えるかが重要になるでしょう。
これからも絶えず新しい学部をつくり続けていく。今の先生方にもその覚悟が問われていると思います。
君島 国際関係学部が設立された1988年から今日までの国際的、政治的、経済的な変化はすさまじいものでした。それをどのように捉えて分析するか。国際関係学部の教員として、一人ひとりの力量が問われた30年間でしたね。
加藤 時代の変化を見通すのは簡単ではありません。ソビエトを例にとってみても、国際関係学部ができたのと同じ頃にゴルバチョフが登場した時、誰も今日のプーチン政権にたどり着くとは予想だにしなかったでしょう。また当時、南アフリカ共和国の変遷も国際的に大きな注目を集めました。長く続いたアパルトヘイトに対してANC(African National Congress、アフリカ民族会議)が犠牲をものともせずに反政府活動を繰り広げた時、国際社会には、ANCの指導のもとで南アが変わっていくのではないかという期待がありました。しかし1994年にマンデラが大統領になったのを頂点に、やがて新政府で腐敗が横行し、その期待は裏切られていくことになります。同じようにインドなどヨーロッパ諸国の植民地だった国々が独立を果たしましたが、南アと同様、問題をかかえた国家へと変質していきました。こうした世界の国々の変化を見通せたかと問われると、難しいところです。
危機感を原動力に国際関係学部が切り拓いた新たな世界
加藤 そもそも国際関係学部をつくる原動力となったのは、全学的な危機意識でした。本学は1960年代の大学紛争の最中、「平和と民主主義」という理念のもとで徹底した大学の民主化を行い、「全構成員自治」という日本の大学として例を見ない成果を挙げました。しかし次第に地盤沈下を起こし、後を追いかけてくる他の関西の私立大学との距離が次第に縮まりつつあることに対し、大学全体が危機感を共有していました。それを打破するべく、国際関係学部はつくられたのです。
もう一つ見過ごしてはならないのが、立命館大学が危機打開の方向としていち早く「国際化」を見出した点です。1970年代の終わりから80年代にかけて日本はものづくりの分野で世界の先頭を走る国になりました。自動車産業においても質の高さと安さで本場アメリカを圧倒し、大きな反発を買うことになります。本学が「国際化」を打ち出したのは、まさに日本の国際化が不可避となりつつある時期でした。国際関係学部の設立は、世界の中で日本経済や日本の大学の置かれた状況を考え、全学的に極めて先見的な判断を下した結果だったのです。
竹内 学部が開設されて3年目に私が国際関係学部に赴任した時、大きな問題となっていたのが学生の進路でした。当時は我々教員も企業を回り、本学部や卒業生の可能性について訴えたものです。しかし最初は「実績がない」との理由で多くの企業に「採用しません」とはっきり言われました。数年間苦戦が続いた後、転機になったのは、初めて総合商社に卒業生を輩出したことです。それを境にそれまで立命館大学生があまり採用されていなかった企業にも国際関係学部の卒業生が就職するようになったのです。長年立命館大学が切り拓けなかった進路を国際関係学部が短期間で開拓したことで、本学部に対する全学的な見方や期待も変わりましたね。
また立命館大学全体が国際社会に目を向ける出発点をつくったという点でも国際関係学部の貢献は大きいと思います。例えばインターンシップを最初に始めたのも本学部でした。また海外の大学との共同学位プログラムDUDP(Dual Undergraduate Degree Program)や国際インスティテュートなどをつくり、他学部も巻き込んで国際化を進めてきました。
世界をどう捉え、「地域研究」をどう位置づけるかが課題
君島 国際関係学部では「言語×理論×地域」を教育の三本柱としていますが、教員の採用においてはディシプリンを基準としてきたため、教育の主軸の一つであるにもかかわらず、「地域研究」の体系が確立されていないという課題があります。それについてどのようにお考えですか。
竹内 国際関係学部のカリキュラムは最初から確立されていたわけではありませんでした。開設間もない頃は、母体となるディシプリンを基礎とした上で、「国際関係学」をどのように科目に取り込んでいくかが課題でした。加えて地域研究科目については、どの教員がどの地域の科目を担当するか、ずいぶん議論が交わされました。もちろんすべての地域を網羅することはできません。どの地域を科目に選ぶかは教員の有無により、学部として明確な方針はなかったように思います。そのため当初アラブ世界に関する科目はほとんどなかったし、ロシアや南アジア地域もそれほど強くありませんでした。開設から10年余りは教員が講義を担当できる地域のバランスを考えて、新たな教員を採用していましたが、21世紀に入って以降、そうした地域研究科目に対する意識が薄れ、似た地域を担当する教員が多くなっているように感じます。
君島 現在も絶えず地域のバランスを見ながら教員体制を整えていますが、「地域研究」の優先順位は高くないのが実情です。人事の際にどこまで地域について意識すべきかは、今後検討すべき課題かもしれません。
加藤 学部として常に新しい動向を把握し、それをもとに必要な専門分野、教員について議論し、合意を形成していくような柔軟な体制が必要だと思います。そのために最新の研究情勢や教育課題について議論や意見交換を行う研究プロジェクトをつくっても良いのではないでしょうか。

本学部教学のあらゆる基礎となる英語教育の開発を通じ、その発展に寄与。国際教育センター副センター長(2004~2007年度)を務める。専門はアメリカ、イギリス黒人文学、インド英語文学
実際の英語のカリキュラム作りでは、まず1回生で短期集中的に語学を教え込もうと考え、「英語Ⅰ」から「英語Ⅲ」まで設定しました。具体的には「英語Ⅰ」と「英語Ⅲ」を日本人教員が担当し、英語の論理構造を中心に英語の読み方を教えます。授業では、環境問題や異文化コミュニケーションなどいわゆるグローバルイシューを扱った多様な文献を徹底的に読ませる「多読」を心がけました。他方「英語Ⅱ」は外国人教員が受け持ち、「スピーキング」を中心に教えました。授業中はすべて英語ですから、学生は英語で考える力が鍛えられたと思います。より長い文章のライティングを中心とする「英語Ⅳ」は、2回生に設定。ここでは「環境問題」や「開発問題」などについて英語でエッセイを書き、ネイティブ教員が添削。よくできたエッセイを精選し、エッセイ集も作っていました。こうしたこれまでにない取り組みは他学部にも波及。政策科学部や経済学部でも、英語でのエッセイ作文集が出されました。さらにスピーチコンテストを開催したり、全学部を対象としたディベート大会の口火を切ったのも、国際関係学部でした。
「日本の国際関係学」をつくる

インターンシップの展開や就職委員長を務め、学部のキャリア支援の充実と教学発展に貢献。その他にも研究科主事、副学部長、国際インスティテュート委員長、入学センター要職も務める。専門は社会学、東南アジア社会研究
君島 私は、立命館大学国際関係学部こそ「日本の国際関係学」をつくっていく責任があり、またそれができると考えています。「日本の国際関係学」が英米の国際関係学の翻訳だけではあまりに不本意です。今年開設したアメリカン大学とのジョイント・ディグリー・プログラム(アメリカン大学・立命館大学国際連携学科)の学位の名称である「グローバル国際関係学(Global International Relations、Global IR)」こそ、日本の国際関係学が目指すべき方向ではないかと思っています。それは今までのパックス・ブリタニカとかパックス・アメリカーナといった、かつての覇権国がつくる世界秩序を肯定的に見るのではなく、むしろ日本をはじめとした非西洋の側から世界をどう捉え、どのような世界秩序をつくるかを考える国際関係学です。そこに「日本の国際関係学」すなわち立命館大学の国際関係学のアイデンティティはあるのではないか。こうしたことを今後学部の教員間でも議論したいと考えています。
卒業生が自分の子どもを入学させたい学部になれるか
竹内 あと10年もすれば、第一期生たちはそれぞれの企業でかなり高い役職につく年齢になります。国際関係学部の社会的な評価も、そうした卒業生の立ち位置に左右されることになるでしょう。
もう一つ気がかりなのは、卒業生たちが「自分の子どもたちに立命館大学国際関係学部で学んでもらいたい」と思ってくれるかということです。「自分の卒業した国際関係学部はこうなってしまっているのか」と失望され、「こんな学部では子どもを学ばせたくない」と思われない学部にしなければなりません。今後、二世代目が喜んで来てくれるような学部にしていくために、今の教員の方々がどのような努力をしてくださるのか、期待しています。
佐藤 考えてみれば私たちが勤めていた頃は、もっと頻繁にこうした議論を行っていたように思います。理想像は皆それぞれ違うと思いますが、それでも議論を重ねることで共通項をつくり出していく努力をこれからも続けてほしいと願っています。
君島・中川 貴重なメッセージをどうもありがとうございました。重く受けとめました。