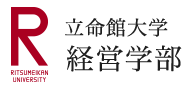| 回生 | 学びを知る 1回生 | 学びを広げる 2回生 | 学びを深める 3回生 | 学びをまとめる 4回生 | |||
| 学びの流れ | 基礎演習を通じて大学での「学び」を知ります。また、経営学の基礎科目を履修し、基礎的な知識や考え方、分析方法を修得します。 | 学科・コース指定専門科目を履修し、経営学の基礎を固めます。また、興味・関心や専門的な力量形成を目指し、「プレゼミ」や4つの「インテンシブプログラム」での学びを通して、経営学を広く知り、多様な学びに挑戦します。 | 学科・コース展開科目を履修します。あわせて、ゼミナール(専門演習)の履修を開始し、講義と小集団科目での学修を通じて、専門性を深めます。 | ゼミナール(専門演習)を継続的に履修し、より専門性を深めつつ、4年間の学びの集大成として「卒業論文」の執筆を行います。 | |||
| 国際経営学科・経営学科共通 | 〈総合基礎科目〉 |
国際経営学科 |
国際マーケティング論
Strategic Marketing International Strategic Management Global Business Management 国際人的資源管理論 Cross Cultural Management Human Capital Management 日中ビジネス論 アジア経営論 比較経営史 比較企業論 International Accounting 国際金融論 |
||||
| 経営学科 | 戦略 |
企業ネットワーク論
イノベーション戦略論
戦略経営論 International Strategic Management Global Business Management オペレーションズ・リサーチ 経営情報論 データサイエンス論 生産システム論 技術革新論 ベンチャーファイナンス |
|||||
| マーケティング |
マーケティング・マネジメント
製品開発論
消費者行動論 国際マーケティング論 Strategic Marketing サービス・マネジメント論 小売マネジメント論 広告論 デザイン戦略論 デザイン組織論 |
||||||
| 組織 |
経営組織論
人的資源管理論
国際人的資源管理論 非営利組織論 企業倫理論 環境経営論 比較経営史 Cross Cultural Management Human Capital Management 比較企業論 中小企業論 日中ビジネス論 アジア経営論 |
||||||
| 会計・ ファイナンス |
管理会計論
原価計算論
監査論
実証会計論 財務会計論 連結会計論 International Accounting 証券投資論 コーポレートファイナンス 国際金融論 |
||||||
|
〈学部共通専門科目〉 |
組織の経済学 会社法 商法 金融法 税法 労働法 国際取引法 |
||||||
| インテンシブプログラム(アジアビジネスプログラム、創発系デジタル人材育成プログラム、会計キャリアプログラム、産官学連携事業継承教育プログラム) | |||||||
| 小集団 |
基礎演習
プロジェクト研究
プロジェクト研究(GBL型) |
プレゼミ |
専門演習Ⅰ・Ⅱ | 専門演習Ⅲ・Ⅳ・卒業論文・ビジネスレポート | |||
| 外国語の選択 | 〈国際経営学科〉英語コース:[必修]英語 / 2言語英語重視コース、2言語初修重視コース:[必修]英語 [必修]下記選択外国語から1言語 〈経営学科〉 英語コース:[必修]英語 / 2言語コース:[必修]英語 [必修] 下記選択外国語から1言語 【初修外国語】ドイツ語/フランス語/スペイン語/中国語/朝鮮語 |
| 教養科目 | 立命館科目 A群(教養基礎科目〔思想と人間、現代と文化、芸術と創造、社会・経済と統治、世界の史的構成、自然・科学と人類、数理と情報の7分野〕) B群(国際教養科目〔外国語で講義〕)、C群(社会で学ぶ自己形成科目)、D群(スポーツ・健康科目)、E群(学際総合科目〔演習形式など〕) |
本授業では、経営学部で学ぶために必要な、企業と経営に関する基礎的な知識と具体的なイメージを獲得することをめざす。企業の種類、株式会社の原理、企業組織の基本的な形態、労使関係、生産システムといった企業・経営そのものに関する基礎知識に加えて、少子高齢化などの人口変動、環境問題、社会および企業内の人権問題、国際化、経済状況の変化といった、今後の企業経営について考える上で不可欠であるさまざまな社会的状況について、本学の教学理念をふまえながら、映像教材等も交えて具体的に理解できるようにする。
複雑化する社会における企業といった経済主体の多様な経済活動を理解するため、あるいは企業内外の利害関係者とコミュニケーションをとるための手段として活用される会計実務に注目し、会計情報が利用される様々な状況を広く取り上げる。そこで経済主体がどのように会計情報を作成し、また会計情報がどのように提供され、利害関係者がその会計情報をどのように利用しているのか、また会計情報からどのようなことが分かるのか、を体系的に学修する。
マーケティングは、企業などの組織が顧客のニーズと欲求への創造的適応を通して、政治・経済・社会・文化の諸環境や顧客、競争、取引などの広範な諸関係のなかで市場を創造・維持していく活動である。マーケティング論では、マーケティング・コンセプト、戦略、マーケティング機会、消費者行動についての初歩および、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、ブランド、製品とサービス、価格、チャネル、コミュニケーションについての基礎を学ぶ。
この授業では、初めて経済学を学ぶ経営学部生を対象に、経営学や現実のビジネスの事象を理解するために必要な経済学の基礎を解説する。経済学を学ぶ意義は、世の中のさまざまな経済活動の基本的な原理や仕組みについて体系的かつ論理的に理解し、物事を多角的な観点から考えることのできる柔軟な思考を身につけることにある。ミクロ的な内容としては、特に企業経営との関連が深い、消費者の満足や企業の利潤と費用、市場における競争の問題などについて取り上げる。マクロ的な内容としては、家計と企業を結ぶ経済循環や経済政策の目的と手段、効果などについて取り上げる。
国境を越えて行われる経営、あるいは国境を跨いで行われる経営を国際経営という。グローバル化する世界における企業の国際経営活動を理解するには、グローバルビジネスの環境を形づくっている多国籍企業の全世界での活動と経済的な力の側面の両方を理解する必要がある。本授業では、主として日米欧などの多国籍企業を対象として、グローバル競争戦略、所有戦略、戦略提携やM&A、グローバル市場に対するマーケティング戦略、研究開発と生産、多国籍企業の組織形態と運営、人的資源のマネジメント、異文化マネジメントなどを理解する。
専門科目を英語で受講するための「ブリッジ」科目として、英語経営学のテキストを用いて、リーディング、ライティング、スピーキングの能力を高めると共に、英語での表現を学習することを目的とする。授業では、アクティブ・ラーニングメソッドを導入し、学生がグループでプロジェクトを立ち上げ、英語で発表資料の作り方、進め方を身に付け、専門科目を英語で受講できるような実力をつける。
専門科目を英語で受講するための「ブリッジ」科目として、「英語経営学入門Ⅰ」で身に付けた、リーディング、ライティング、スピーキングの能力をさらに伸ばすことを目的とする。授業では、アクティブ・ラーニングメソッドを導入し、学生がグループでプロジェクトを立ち上げ、専門分野の内容を英語でプレゼンテーションできる能力を身に付け、専門科目を英語で受講できるような実力をつける。
本科目は、アジア経済の特徴とアジア進出企業の経営投資環境について外観し、市場と産業構造の特質について理解する。第1に、アジア地域や国(東アジア、ASEAN、中国、インド等)の経済発展と市場の特徴を概観する。第2に、アジア諸国の産業構造、変化過程と現在の特徴を理解する。第3に、日本を含めアジア諸国市場のグローバル化、及び日欧米とアジア新興国のビジネスを取り巻く経済状況について考察する。多国籍企業のアジア・マーケティング戦略を考える上で基礎となる開発経済の概念やアジア社会の諸課題についても理解する。
Based on the foundational principles of marketing students learned in their first year, Integrated Marketing develops the understanding of marketing mix by using various case studies of leading global companies. This course examines customer value, product design, marketing channels, communications, management of digital technology and its applications. Students will be able to comprehend strategies and knowledge of marketing mix to explain how companies apply those strategies to gain a competitive advantage in the marketplace.
This lecture is a foundation course for understanding the current state of the global economy and international business. Students will consider the world economy and international business from a wide range of perspectives of organization, strategy, and management. In addition, it pursues the consistency of the theories and business cases. Specifically, they will learn the following topics: "The Historical Background of Multinational Corporations", "International Business Strategy", "International Marketing", "Overseas Production", "The Internationalization of Research and Development", "International Business Structure & Ownership Policies", "The Management of Overseas Subsidiaries." The purpose of learning these topics is for the students to express themselves in English as well.
The purpose is to acquire knowledge of the major topics of accounting in global business activity today. The course aims at understanding how accounting information is prepared, how it provides business information to stakeholders inside and outside the organization, how various stakeholders use that information, and what is and what can be visible from accounting information. Students will also learn how corporate behavior and accounting are linked in order to deepen their understanding.
19世紀以後のアジアは、その内部に深刻な貧困や抑圧を抱えながらも、全体として経済成長を遂げた。そのような経済成長は、政治形態の多様さにも関わらず、アジアが一つの地域経済圏としてのまとまりを形成する過程と不可分であった。近代日本の工業化も、その一部分をなすものとして理解する必要がある。本授業は、このような視点から19世紀以後のアジア地域の経済史に関する諸論点を取り上げて論じ、現代アジア経済が帯びている特徴について、歴史的な視点から理解することを目的とする。
経済の国際化の進展は、輸出入取引にとどまらず、海外での直接の生産・販売活動や多国籍経営を必要としている。マーケティングでも、国家の存在を前提にした、もしくは国境を越えて展開する国際的なマーケティングの究明が必要となってきている。本授業では、主要国のマーケティングの国際比較を含めて、自然・政治・経済・文化などに多様性をもつ国際的な経営環境に対応して展開される、経営体の参入戦略やグローバルなマーケティング・ミックス戦略などを対象とする。
Strategic marketing is a process that can allow an organization to concentrate its limited resources on the greatest opportunities to maximize customer satisfaction, thereby achieving a sustainable competitive advantage. Strategic marketing emphasizes the formulation and implementation of effective market-oriented strategies of a firm through the constant analysis of the customers, the competitors and the corporation when fulfilling its marketing goals and objectives.
International Strategic Management is an ongoing management planning process aimed at developing strategies to allow an organization to expand abroad and compete internationally. Strategic planning is used in the process of developing a particular international strategy.An organization must be able to determine what products or services they intend to sell, where and how the organization will make these products or services, where they will sell them, and how the organization will acquire the necessary resources for these tasks. Even more importantly an organization must have a strategy on how it expects to outperform its competitors.
This course discusses the challenges of managing Global Business in a dynamic, interconnected environment and introduces advanced organizational and managerial approaches. Topics may include: 1) Managing across borders; 2) Global leadership mindsets and competencies; 3) Corporate governance; 4) Information and knowledge management; 5) Managing global cooperation (e.g., joint venture management, post-merger integration); 6) Management issues in Global Business in the 21st century (e.g., SDGs, climate change, risk management, digitization). By the end of this course, students will understand global business management, develop essential skills for multinational enterprises, and apply their knowledge to real-world scenarios, effectively contributing to multinational organizations.
国際人的資源管理とは、本国、現地国、第三国における、本国人材、現地人材、第三国籍人材を対象とした人事計画、採用、人材育成、配置・転換、評価、報酬、福利厚生といった一連の人的資源管理を指す。東西冷戦の終結により経済のグローバル化が進み、多くの旧共産圏諸国が資本主義経済体制に入ったことで市場規模が拡大し、海外進出を拡充させる多国籍企業は増加している。その為、本国人材のみならず外国人材の活用に積極的に取り組む企業が増えている。本授業では、グローバル化における多国籍企業の人的資源管理について理解することを目指す。
This course explores cultural differences and the challenges they pose to global managers. How culture affects organizations, how to manage multicultural teams, how to motivate people, and how to negotiate and lead across cultures are important topics of this course. Students will learn how to assess cultural situations and develop adjustment strategies for international managers. They will also learn how to interpret and reconcile similarities and differences among various cultures. Additionally, students will reflect on steps and successful practices of cultural synergistic problem-solving, preparing for their own assignments in the cross-cultural workplace.
This course covers the comprehensive study of managing human capital in a global context. Human Capital Management emphasizes the strategic importance of effectively managing an organization's workforce. As global business operations expand and multinational firms become more prevalent, it’s not only important within a country but also critical to adeptly manage diverse teams located in different regions. Topics may include: 1) global leadership competencies, 2) remuneration and incentives, 3) performance appraisal, 4) succession planning and global talent development, 5) Diversity/Equity/Inclusion (DEI). Through this course, students will achieve a profound understanding of human capital management in both national and international contexts.
本授業では、中国の経済発展と日中ビジネスを考察対象とする。中国は、社会主義市場経済を標榜して、改革・開放路線のもとで経済改革を行ってきた。最近では「世界の工場」ないし「世界の市場」と称されるほどに、グローバルな視点から急速な変貌を遂げてきた。そこで、本授業では、中国の経済、産業、市場の発展過程、ならびに日中間の貿易と投資の動向変化や、中国の事業環境変化をふまえながら、日中ビジネスをめぐる企業経営についての理解を図る。
今日、アジア経済の急成長にともない、その市場規模も急速に拡大してきた。日本企業をはじめ、先進国の多国籍企業はアジア市場を主な戦場と見なし、積極的に人材や資金など経営資源を投入している。一方、アジア諸国の企業も成長し、その競争力が先進国企業と競争できるほど強くなっている。本授業では、アジアにおける経済社会と企業経営の特質について、とくに経営投資環境、日本企業のアジア進出状況と問題、及びアジア諸国の企業構造・経営戦略などの理解を図る。
経営史は、個別企業経営史、産業経営史、一国経営史に区分され、各国の企業経営の歴史的展開の究明がなされているが、同時に各国比較の視点からも取り組まれている。それによって各国企業経営の発展過程の一般性と特殊性を明らかにしようというのがねらいである。本授業では、さまざまな経営方式・システムを生み出し、企業経営の重要なモデルをなしてきたアメリカとの比較視点のもとに、日本とドイツを取り上げ、経営方式の国際移転の面から考察し、各国の共通性と独自的な展開を明らかにする。
企業の国際活動が拡大深化するとともに、欧州、北米、アジアそして日本の企業はどのような変貌をとげつつあるのか。世界各地域で歴史的に形成されてきた企業制度のなかで、とりわけ株式会社のガバナンスが焦眉の問題となっている。本授業では、現代企業をコーポレート・ガバナンスの視点から類型化し、その特徴を理解する。さらに、企業と社会という視座から、企業行動にみられる多様性や複雑性がなぜ生じるのかを考察する。
International Accounting as a subject of academic inquiry has commonly featured three interrelated domains; 1) accounting standards and practices in individual countries viewed in comparative perspective, 2) accounting issues that arise from cross-border transactions and transnational businesses, and 3) accounting issues associated with the development of global standards of accounting and reporting. In view of the ongoing process to develop International Financial Reporting Standards (IFRSs), there is naturally a growing focus in ‘International Accounting’ on what IFRSs are all about, how they are developed, and what consequences they hold for accounting for each country and business entity affected by them.
本授業では、国際金融論について基本的な内容を扱う。国際金融論は、(外国と資本の貸借取引や財・サービスの売買取引を行う)開放経済の様々な問題について国境を越えた金融取引に注目しながら考察するものである。すなわち、金融論を開放経済に拡張した経済学の体系である。授業においては、はじめに、国際収支、外国為替市場、外国為替レート、開放マクロ経済政策について主に理論的な内容を学修する。その後、発展的な内容として、通貨危機や通貨統合など国際金融に関する諸問題を学ぶ。
本授業では、経営戦略が企業にとって歴史的にいかに重要な役割を果たして来たかのか、経営戦略はどのような論理をもつのか、その論理はどのような経営環境下において有効であるのか、そしてその論理はどのように実践されるのかについて学ぶ。具体的には、①企業の外部環境(一般環境、産業環境、競合環境)および内部組織(資源、ケイパビリティ、コア・コンピタンス、価値連鎖)の分析手法の理解、②ビジョンとミッションの策定手法の理解、③全社戦略および事業戦略の内容の理解、を目的とする。
経営統計論では、さまざまな経営に関する事象に応用された統計的方法について論じる。データとしては、企業構造・活動に関する公的統計や各種調査、財務資料その他経営に関連する統計情報を対象とする。統計的記述および確率的標本分布に基づく統計的推測・検定を理論的基礎として、データの処理・分析などについての基本的な技法を学び,回帰分析を中心に多変量解析や品質管理などの応用技法も取上げる。これらを通じて分析の目的に適した技法の選択と分析結果の理解および報告の仕方とを修得する。
技術経営論では、新製品・新製法を生み出す研究開発、ものづくりの基盤となる機械型および装置型の製造技術、ものづくりを支える生産管理・品質管理、および開発・製造・流通に欠かせない情報処理・通信技術の役割について、基礎的な知識の修得を目指す。これらの知識の修得を通じて、企業経営における研究開発、製造技術、情報技術および生産・品質管理の意義を学び、それらが生み出されるメカニズムとマネジメントの必要性を理解する。
本授業では、12世紀のフランス社会で認識された職業「アントレプレナー」の議論に始まり、1930年以降の経済活動におけるアントレプレナーの役割への理解を深める。その後、現代社会におけるアントレプレナーの役割、アントレプレナーを輩出する環境要因への理解を深め、「アントレプレナーシップ(新しい価値を創造し、社会・市場に輩出するのに必要な能力)」を身につけるための基礎理論とスキルを学ぶ。また、社会起業家やベンチャー企業創業者の行動プロセスの理論面での理解を深める。
事業開発論では、ビジネスを作り上げるための製品開発の視点に加えて、組織づくり、資金調達、ビジネスモデルづくり、ビジネスエコシステム等の広い観点における必要な経営学の理論・フレームワークを具体的・実践的に学ぶ。また、実際、事業開発に関わっている実務者の話しや実例に基づいて事業開発のプロセスとポイントの理解を深める。上記の点を踏まえて、現実的でビジネスに通用するレベルに到達するように考える力とスキルを学ぶ。
情報システムは、情報技術が組織の諸活動に埋め込まれた一連の仕組みと捉えられ、経営実践における顧客価値創造、競争優位性の獲得やビジネスプロセスの効率性向上に貢献することを理由に、企業活動や社会活動の隅々まで浸透し、ますます重要な経営資源となっている。本授業では、企業の事業活動全体を俯瞰するビジネスシステム(ビジネスモデル)を踏まえ、情報システムの概論、基盤技術、開発及び適用例について理解し、経営実践においてどのように情報システムを駆使するかについて学修する。
製造業における品質(Q)、コスト(C)、納期(D)の基盤的条件の一つとして、生産工程における製造技術が挙げられる。製造技術は機械技術と装置技術に大別され、それぞれの技術発達は独自の技術発達の論理を有しており、かつ社会的な諸条件に規定され、企業・産業・国ごとに独自の進化を遂げている。加えて今日の製造技術は発達した情報処理・通信技術を結合し、多品種生産、生産の国際分業を実現するとともに、工場における自動化の進展を促進している。本授業では、産業技術の体系的特徴とその形成・展開プロセスについて理解する。
わが国におけるベンチャー企業は、1990年以降の政策上の強化による「技術革新の担い手」「雇用を創出する主体としての役割」として、その創業過程や運営ノウハウへの関心が高まっている。起業家(企業家)によるベンチャー企業への挑戦は、単に創業者にとって一攫千金を目指す手段ではなく、経済社会への新陳代謝としての役割を担っている。本授業は、現代社会における起業やベンチャー企業についての理解を深めることを目標とする。また、ベンチャー企業と経済社会との係わりを中心に、ベンチャー企業の意義について理解する。
SoSs(System of Systems)として特徴づけられる次世代の産業社会は、様々なコンポーネントや技術が複合的に組み合わされて成立するCoPS(Complex Product Systems)のイノベーションを要請するようになっている。それに呼応して、CoPSのイノベーションも垂直統合型企業によって単独で担われるイノベーションから、企業の枠組みを越えた企業間のネットワークや産官学、そして消費者のネットワークに主導されるようになってきている。本授業では、これら様々なネットワークを介して成立するイノベーションのメカニズムを、歴史的、制度的、技術的、戦略的に明らかにする。
イノベーション戦略論では、ものづくり経営において重要なイノベーションの戦略のありようとその戦略的活用について論じる。画期的および漸進的イノベーション、製品および生産プロセスにおけるイノベーションを実現する戦略、すなわちアーキテクチャ、モジュラー化、プラットフォーム、標準化などの戦略とその組織的対応を取り上げる。さらに、企業が実現しようとする「技術の革新から価値の創造・獲得に至る一連のプロセス」の具体的な事例を取り上げ、企業のイノベーション戦略遂行の現実的な課題を理解する。
本授業では、戦略の策定とともに戦略の実践、および戦略策定と実践の関係について論じる。企業戦略および事業戦略の基本的特徴を提示した上で、戦略的に経営を行うために必要な経営環境分析(一般環境、産業環境、競合環境)、内部要因分析、ビジョンとミッションの策定、全社戦略(多角化戦略、撤退戦略、国際化戦略、提携戦略、M&A戦略等)および事業戦略を策定し、策定した戦略を実行するための手段について、コーポレート・ガバナンス、組織構造とマネジメント、戦略的リーダーシップ、戦略的アントレプレナーシップの諸観点から理解する。
International Strategic Management is an ongoing management planning process aimed at developing strategies to allow an organization to expand abroad and compete internationally. Strategic planning is used in the process of developing a particular international strategy.An organization must be able to determine what products or services they intend to sell, where and how the organization will make these products or services, where they will sell them, and how the organization will acquire the necessary resources for these tasks. Even more importantly an organization must have a strategy on how it expects to outperform its competitors.
This course discusses the challenges of managing Global Business in a dynamic, interconnected environment and introduces advanced organizational and managerial approaches. Topics may include: 1) Managing across borders; 2) Global leadership mindsets and competencies; 3) Corporate governance; 4) Information and knowledge management; 5) Managing global cooperation (e.g., joint venture management, post-merger integration); 6) Management issues in Global Business in the 21st century (e.g., SDGs, climate change, risk management, digitization). By the end of this course, students will understand global business management, develop essential skills for multinational enterprises, and apply their knowledge to real-world scenarios, effectively contributing to multinational organizations.
オペレーションズ・リサーチ(OR)は、企業経営における様々な問題の判断基準や制約を定式化して表すことで、論理的で最適な選択(最適解)が何であるかを考察する学問である。ORへの導入科目である本授業では、主に企業の「意思決定」に焦点を当て、ORの基本的なモデルの学修を通じてモデリングによる問題解決の考え方を学ぶ。必要以上に数学的な厳密性に偏重することは避け、ソフトウェアの活用と関連づけられた実用的な知識と、論理的かつ体系的な思考能力を身につけることを受講生の主な到達目標とする。
情報システムは、企業のさまざまな活動において不可欠なものとなっている。なぜなら、企業はそれを利活用することで大量のデータを迅速かつ正確に処理でき、業務の効率化を図るとともに、蓄積されたデータに基づき種々の意思決定が行われているからである。同時に、そのことは企業でのさまざまな活動や業務と情報システムとが、相互にかつ密接に結びついていることを意味している。経営情報論では、情報技術(IT)の発達とともに、企業が情報システムをどのような目的で導入してきたのか、また、どのように利活用されているのかを学ぶ。
本講義では、企業組織の有するデータを戦略的な情報的経営資源として捉え、データサイエンスの活用により競争優位性を構築するための戦略やマネジメントについて学ぶ。学生は、ビッグデータ、統計やAIなどのデータサイエンスを構成する理論や基礎技術を学習し、同時に、データ駆動型経営などデータを駆使した企業実践の有効性について、経営学の視点から分析し、理解を深めることが出来るようになる。
生産システムは、特定の生産目的に対して関連づけられた、生産活動の連鎖(製品開発・生産準備・購買・製造)、生産活動の管理(計画・実施・統制)、生産要素(労働対象・労働力・労働手段・生産方法)が有機的に連結した集合体である。本授業では、生産活動、技術(製品・製造技術)とは何か、そして製品開発から製造に至る各生産活動の内容と関連をまず明らかにする。そしてグローバルならびに地域の経営環境に注目しつつ、この生産活動の最適編成のための経営・生産戦略、企業間分業の調整(部品、素材企業などとのネットワーク)、マネジメント(生産管理、購買管理など)の展開、さらに製品技術と製造技術、その相互連関による生産と事業モデルの革新を取り上げる。
技術進歩は、新商品の創出や生産方法の変革を通じて、企業経営、企業間関係、産業、流通、さらに経済や社会生活のあり方に影響を及ぼす基礎的かつ直接的な要因となる。企業は、市場の絶えざる要求と企業間競争のなかで、技術進歩の成果を生産・流通システムに取り入れて経済活動に利用し、技術革新を実現しようとする。本授業では、国や産業で異なる政治的・経済的土壌をふまえ、企業・経済活動のなかで技術革新がどのように実現され、それが生産や流通にどのような影響を与えるのかを学び、社会における技術革新の可能性と限界を理解する。
本授業では、ベンチャーファイナンスの主たる手法である直接金融(ベンチャーキャピタル等からの出資による資金調達)と間接金融(金融機関等からの借入による資金調達)を取り扱う。まず、事業資金ニーズの把握、資本政策、実際の資金調達等、ベンチャーファイナンスの基本を学修する。その上で、直接金融については、ベンチャー企業の成長ステージ毎に、その主たる資金調達先となるエンジェル、ベンチャーキャピタル等の特徴とその活用について学ぶ。間接金融については、銀行等金融機関の融資の特徴とその活用について理解を深める。
本授業では、デザインが企業経営において果たす役割について論じる。商品企画、開発、製造、営業販促、流通など、商品や企業価値の創造に携わるすべての部門で、デザインという概念を適切に取り入れてこそ差別的、戦略的な企業経営が達成される。このようにデザインを企業の競争優位性を生み出す重要な源泉として認識し、企業経営に関わる諸活動・諸要素をデザインという切り口から検討することで、学生はデザイン経営の基礎概念から具体的手法までを理解し、経営学におけるデザインの今日的意義を明確にすることが出来るようになる。
交通システム論では、社会、政策、経営の視点から今日における交通の諸問題を検討する。社会的な視点では、交通と社会問題の関わり、とりわけ地域社会への影響や環境問題、交通権などを取り上げる。政策的な視点では、交通問題を克服するための公共交通などの整備、地域的な交通計画の策定、インフラ投資政策、事業規制の緩和などを取り上げる。経営の視点では、交通企業の経営や、物流・ロジスティクスの現状と課題などを取り上げる。これらを通じて、交通システムのこれからのあり方と、企業や社会との関係を考える。
流通は、生産と消費の隔たりを結びつける活動であり、所有権の流れ、財の流れ、流通にかかわる情報の流れという機能を遂行する。商業は、商業者、すなわち卸売業者と小売業者にかかわる活動である。流通論では、商業者の社会的役割である流通費用の節約と流通サービス、小売業種と小売業態、卸売業種と卸売業態、流通イノベーション、流通と商業を育成する流通政策、流通と商業のグローバリゼーションについて、現代に至る具体的な発展を例示しつつ、流通と商業にかかわる歴史と現代、理論を学ぶ。
観光システム論では、観光が今世紀最大の産業となりうると大きな期待を受ける中で、わが国や世界各国における観光ビジネスの実態を社会や企業とのかかわりから論じる。とりわけ、観光ビジネス・プロセスをシステム全体として理解した上で、観光の持続的な発展を実現するための観光を取り巻く環境の理解、観光客の動機や行動パターン、観光地全体の経済的・社会的・文化的特徴と観光政策との整合性などを取り上げる。
本授業は「マーケティング論」の学修をもとに、ブランド戦略、製品戦略、価格戦略、チャネル戦略、コミュニケーション戦略を学ぶ。たとえば、ブランド戦略では、ブランド・エクイティとブランド・アイデンティティ、ブランドの長期戦略、ブランド拡張、ブランド体系とブランド・ポートフォリオ、グローバル・ブランド戦略と地域ブランド戦略を学ぶ。価格戦略では、マークアップ価格設定など価格設定の基本枠組みと具体的な価格適合を学び、チャネル戦略では、流通パートナーシップなどの取引関係とサプライチェーンの管理、延期と投機の原理を学ぶ。
製品開発論では、企業のマーケティング活動の中で重要な位置をしめる製品開発について、その目的と基本的なプロセスを、理論と事例をもとに理解する。新製品を成功させる上で重要な、市場調査の手法や、アイデア・コンセプト開発、他のマーケティングミックス(価格・流通・プロモーション)との組み合わせに加えて、持続的な競争優位性を実現するための、市場形成・市場変容を踏まえた製品戦略について学ぶ。
消費者行動論では、企業と消費者の相互作用を取り巻くマーケティング現象の中でも、企業のマーケティング活動から消費者がいかなる影響を受けるのかについて論じる。具体的には、消費者の購買意思決定プロセスに関連するニーズ、動機、知覚、態度、記憶、製品選択、行動、満足や、製品・価格・プロモーション・チャネルというマーケティング活動の諸要素と消費者行動の関係、消費者間の社会的相互作用、インターネット時代の消費者行動といったトピックを取り扱う。
経済の国際化の進展は、輸出入取引にとどまらず、海外での直接の生産・販売活動や多国籍経営を必要としている。マーケティングでも、国家の存在を前提にした、もしくは国境を越えて展開する国際的なマーケティングの究明が必要となってきている。本授業では、主要国のマーケティングの国際比較を含めて、自然・政治・経済・文化などに多様性をもつ国際的な経営環境に対応して展開される、経営体の参入戦略やグローバルなマーケティング・ミックス戦略などを対象とする。
Strategic marketing is a process that can allow an organization to concentrate its limited resources on the greatest opportunities to maximize customer satisfaction, thereby achieving a sustainable competitive advantage. Strategic marketing emphasizes the formulation and implementation of effective market-oriented strategies of a firm through the constant analysis of the customers, the competitors and the corporation when fulfilling its marketing goals and objectives.
本授業では、顧客との関係性を基盤に統合されたマーケティングとマネジメントについて論じる。サービスの観点からすれば、サービスも製品もそれ自体が単独で価値を持たず、それらの有機的な組み合わせによって、顧客自身が価値創造することを支援するという考え方が重要となる。それゆえサービスにおいてはプロセスのマネジメントが決定的であり、そのプロセス全体に満足した顧客との関係性の構築こそがマーケティングでもある。これらの理解をふまえ、学生はサービスの生産性と品質、市場指向的マネジメント、顧客指向型組織とその従業員などについての知識を深めることが出来るようになる。
小売業を取り巻く市場競争が変化していることから、小売企業の経営における意思決定およびそのマネジメントがますます複雑で難しくなっている。小売マネジメント論では、こうした市場変化と組織的課題を踏まえた上で、小売業の動態と革新、小売戦略、小売企業の組織と人的資源管理、マーチャンダイジング活動、 小売マーケティング、仕入れ・販売戦略、店舗戦略・管理、消費者行動に加え、国際化、サステナビリティ経営、サービス化、小売テクノロジーなどの諸課題についても学ぶことで、学生は小売業への理解を深めることが出来るようになる。
広告は、企業と消費者との接点におけるコミュニケーション機能を担うマーケティング活動の一つである。従来はマスメディアを中心とした広告戦略の企画、実行、効果測定が中心的課題であったが、インターネットやソーシャルメディアの登場により、広告論のあり方も大きく変化している。こうした変化を踏まえた上で、本授業で学生は、広告の機能、効果、具体的手法等の理解に加え、販売促進やPR、人的コミュニケーションといった広告以外のプロモーション、さらには製品や店頭といった他のマーケティング諸要素を含むIMC(統合型マーケティング・コミュニケーション)について学び、広告への理解をさらに深めることが出来るようになる。
近年デザインの役割が拡大されるにつれ、企業のビジョンから製品/サービスのビジョン、製品開発、製造、営業販促、流通、顧客体験、廃棄までのライフサイクルすべてにおいて一貫性を持たせるという意味でデザインが戦略的に関与することが求められるようになってきた(戦略的デザイン)。さらに、戦略的デザインによって創出される製品アイデンティティは適切なタイミングで更新され、複数の製品アイデンティティがポートフォリオとして戦略的に管理されなければならない(デザイン戦略)。本講義では、デザインにおける2つの戦略的側面を基礎概念から具体的手法までを理解することで、学生は経営学におけるデザインの役割を深く理解することが出来るようになる。
近年デザインの役割が拡大されるにつれ、ビジョン創造やアイデア創造における従業員やユーザー、人々の主観性の活用や、プロダクトライフサイクルを通したデザイナーおよびデザイン部門の関与等、デザインを最大限活用するためには、ミクロおよびマクロの両面から組織的な対応が必要となってきている。本講義で学生は、そのようなデザイン特有の組織的な課題をミクロおよびマクロ組織論の観点から学び、デザイン活用における組織の重要性を理解出来るようになる。
組織のマネジメント(管理)とは何かということから始まり、組織、特に企業の経営管理に関するこれまでの代表的な理論を概観する。具体的には、科学的管理法、ファヨールの管理過程論などの古典的な理論からホーソン工場の実験を経て人間関係論、近代組織論など、理論の発展とそれらが社会に及ぼした影響を学ぶ。さらに、組織とそれを取り巻く環境と経営管理との関係を検討する。そして生産管理の基礎も学び、組織の形態と管理との関係、組織で働く人々の働く意欲やリーダーシップと管理の関係を理解する。
企業論は、経営学及び経済学の視点から現代社会の基幹組織である企業の本質を探求する学問である。本授業では、企業の形態、株式会社の特質、企業の目的と社会的責任、現代の企業が直面している諸問題などのテーマを取り上げ、企業に関する基礎的知識を確実に修得することを目指す。企業とは何かを理解するためには、企業の具体像をつかみ、株式会社の仕組みや運営を知ることが不可欠である。これらを踏まえて、企業間関係や企業のグロ-バル化など現代企業の直面する問題についても理解を深める。
本科目は、アジア経済の特徴とアジア進出企業の経営投資環境について外観し、市場と産業構造の特質について理解する。第1に、アジア地域や国(東アジア、ASEAN、中国、インド等)の経済発展と市場の特徴を概観する。第2に、アジア諸国の産業構造、変化過程と現在の特徴を理解する。第3に、日本を含めアジア諸国市場のグローバル化、及び日欧米とアジア新興国のビジネスを取り巻く経済状況について考察する。多国籍企業のアジア・マーケティング戦略を考える上で基礎となる開発経済の概念やアジア社会の諸課題についても理解する。
組織行動論とは、組織内における人間の行動と態度に関する体系的な学問であり、そこで得られた知識を、主に組織とそこに属する個人のパフォーマンスと個人の職務態度の向上に役立てることを主な目的としている。そして、心理学、社会学、社会心理学、文化人類学、政治科学などの分野で得られた知見に基づいた応用行動科学である。組織の中の個人に関しては、ワーク・モチベーション、個人の意思決定など、組織の中の集団に関しては、リーダーシップ、チーム、コンフリクトと交渉などを取り上げる。
経営史は、現代企業の生成・発展をその社会経済的背景との関連で考察し、両者の相互の作用関係を歴史的に究明する学問である。この授業では、近世以降現在に至る企業経営の主要問題について、資本主義の歴史的条件をふまえて考察する。経営史研究の課題と方法を明らかにした上で、日本における事例を中心としつつ、アメリカをはじめ諸外国とも比較しながら企業経営にかかわる諸問題を考察する。さらに、1990年代以降の資本主義のグローバル段階における企業経営の主要問題を現代資本主義の変化・特質をふまえて考察する。
19世紀以後のアジアは、その内部に深刻な貧困や抑圧を抱えながらも、全体として経済成長を遂げた。そのような経済成長は、政治形態の多様さにも関わらず、アジアが一つの地域経済圏としてのまとまりを形成する過程と不可分であった。近代日本の工業化も、その一部分をなすものとして理解する必要がある。本授業は、このような視点から19世紀以後のアジア地域の経済史に関する諸論点を取り上げて論じ、現代アジア経済が帯びている特徴について、歴史的な視点から理解することを目的とする。
This lecture is a foundation course for understanding the current state of the global economy and international business. Students will consider the world economy and international business from a wide range of perspectives of organization, strategy, and management. In addition, it pursues the consistency of the theories and business cases. Specifically, they will learn the following topics: "The Historical Background of Multinational Corporations", "International Business Strategy", "International Marketing", "Overseas Production", "The Internationalization of Research and Development", "International Business Structure & Ownership Policies", "The Management of Overseas Subsidiaries." The purpose of learning these topics is for the students to express themselves in English as well.
組織の定義から始まり、組織が成立、存続していくためにはどのような条件が必要なのかを代表的な理論から学ぶ。そして組織と環境の関係や組織が環境を戦略的に選択していくことも学ぶ。また、企業の代表的な組織形態、組織と技術の関係を理解する。さらに環境、組織のライフサイクルや規模などさまざまな条件に応じて、組織構造だけでなくインセンティブ・システムを含む適切な組織デザインができるような知識を修得する。さらにリーダーシップの理論を学んで、どのように組織を動かしていくのかをみていく。
人的資源管理論は、ヒトを、他の経営資源と同じく価値を創造する資源であるという見方に立った人材マネジメントの理論である。人的資源管理論の理論・管理技法は、アメリカにおいて誕生し、その後、日本に国際移転された理論・管理技法であり、経営戦略と密接に結びついている点に特徴がある。そして、人的資源管理の管理技法は、雇用管理、賃金管理、キャリア開発、福利厚生制度など多岐に及んでいる。本授業では、人的資源管理の理論とその管理技法、人的資源管理・人的資源管理下の労働の諸実態について学ぶ。
国際人的資源管理とは、本国、現地国、第三国における、本国人材、現地人材、第三国籍人材を対象とした人事計画、採用、人材育成、配置・転換、評価、報酬、福利厚生といった一連の人的資源管理を指す。東西冷戦の終結により経済のグローバル化が進み、多くの旧共産圏諸国が資本主義経済体制に入ったことで市場規模が拡大し、海外進出を拡充させる多国籍企業は増加している。その為、本国人材のみならず外国人材の活用に積極的に取り組む企業が増えている。本授業では、グローバル化における多国籍企業の人的資源管理について理解することを目指す。
非営利組織は、現代社会において国内外でますます活躍の場を広げる一方で、事業の継続的な発展を目指すにあたり、民間企業と政府の運営と同じように様々な経営上の問題に直面している。本授業では、非営利組織の定義や役割、成り立ち、範疇など基本概念を理解する。また、非営利組織に関わる人材や資金、組織の統治・アカウンタビリティー、アウトカム、パートナーシップなどの問題を、民間企業の経営との違いを念頭におきながら、経営学的なアプローチに基づき明らかにする。
いま我が国では政治、医療、環境などの様々な分野で「倫理」の実践が叫ばれ問題となっている。それは企業という組織体についても例外ではない。本授業では、企業の特質などに関する基本的な理論を学んだ後、企業が果たすべき責任や企業行動規範などを分かりやすく解説する。さらに、現実の企業を舞台にして頻発している非倫理的な活動に焦点を当てながら、そうした企業活動がなぜ発生するのか、また倫理性を喪失した企業が、どうすればそれを回復し倫理志向的な企業として再生して行けるのか、といった問題について議論する。
企業は、一方では、法律・規制に対応するために、もう一方では、新たなビジネスチャンスを求めて、環境問題に向き合っている。本授業においては、環境汚染、公害問題、法令違反など、企業活動が環境に対して及ぼす負の影響とともに、ブランド、レピュテーション、エネルギー効率など、環境問題が企業価値に対して及ぼす正の影響について、企業の社会的責任(CSR)など、企業と社会の関係を分析するうえで有用と考えられているフレームワークの観点から論じる。
経営史は、個別企業経営史、産業経営史、一国経営史に区分され、各国の企業経営の歴史的展開の究明がなされているが、同時に各国比較の視点からも取り組まれている。それによって各国企業経営の発展過程の一般性と特殊性を明らかにしようというのがねらいである。本授業では、さまざまな経営方式・システムを生み出し、企業経営の重要なモデルをなしてきたアメリカとの比較視点のもとに、日本とドイツを取り上げ、経営方式の国際移転の面から考察し、各国の共通性と独自的な展開を明らかにする。
This course explores cultural differences and the challenges they pose to global managers. How culture affects organizations, how to manage multicultural teams, how to motivate people, and how to negotiate and lead across cultures are important topics of this course. Students will learn how to assess cultural situations and develop adjustment strategies for international managers. They will also learn how to interpret and reconcile similarities and differences among various cultures. Additionally, students will reflect on steps and successful practices of cultural synergistic problem-solving, preparing for their own assignments in the cross-cultural workplace.
This course covers the comprehensive study of managing human capital in a global context. Human Capital Management emphasizes the strategic importance of effectively managing an organization's workforce. As global business operations expand and multinational firms become more prevalent, it’s not only important within a country but also critical to adeptly manage diverse teams located in different regions. Topics may include: 1) global leadership competencies, 2) remuneration and incentives, 3) performance appraisal, 4) succession planning and global talent development, 5) Diversity/Equity/Inclusion (DEI). Through this course, students will achieve a profound understanding of human capital management in both national and international contexts.
企業の国際活動が拡大深化するとともに、欧州、北米、アジアそして日本の企業はどのような変貌をとげつつあるのか。世界各地域で歴史的に形成されてきた企業制度のなかで、とりわけ株式会社のガバナンスが焦眉の問題となっている。本授業では、現代企業をコーポレート・ガバナンスの視点から類型化し、その特徴を理解する。さらに、企業と社会という視座から、企業行動にみられる多様性や複雑性がなぜ生じるのかを考察する。
現代日本における企業の圧倒的多数は中小企業である。中小企業は多様な産業分野でさまざまな製品やサービスを提供して人々の生活を支えている。また、雇用を創出し、地域経済・社会の担い手となり、新しい産業・事業を展開する存在としても重要な役割を果たしている。しかし、その一方で中小企業は、経営資源の制約や競争・取引関係上の不利など特有の問題を抱えており、近年ではグローバル化をはじめとした経営環境の急激な変化への対応も迫られている。本授業では、日本の中小企業が果たしている役割と抱えている問題を理解する。
本授業では、中国の経済発展と日中ビジネスを考察対象とする。中国は、社会主義市場経済を標榜して、改革・開放路線のもとで経済改革を行ってきた。最近では「世界の工場」ないし「世界の市場」と称されるほどに、グローバルな視点から急速な変貌を遂げてきた。そこで、本授業では、中国の経済、産業、市場の発展過程、ならびに日中間の貿易と投資の動向変化や、中国の事業環境変化をふまえながら、日中ビジネスをめぐる企業経営についての理解を図る。
今日、アジア経済の急成長にともない、その市場規模も急速に拡大してきた。日本企業をはじめ、先進国の多国籍企業はアジア市場を主な戦場と見なし、積極的に人材や資金など経営資源を投入している。一方、アジア諸国の企業も成長し、その競争力が先進国企業と競争できるほど強くなっている。本授業では、アジアにおける経済社会と企業経営の特質について、とくに経営投資環境、日本企業のアジア進出状況と問題、及びアジア諸国の企業構造・経営戦略などの理解を図る。
今日の会計学の主要なトピックについての基礎知識を修得することを目的とする。どのようにして会計情報が作成されているのか、どのようにして組織内外の利害関係者に経営に関する情報を提供しているのか、それらの情報を種々の利害関係者がどのように利用しているのか、またどのようなことが会計情報から分かるのかを理解することを目指す。また、より理解を深めるために、企業行動と会計がどのように結びついているのかについても学修する。
金融論とは、市場経済における金融の役割や機能について、経済理論を用いて明らかにする学問分野である。貨幣や金利、リスクの概念を理解し、それらの相互関係について解明することを目的としている。また、経済システムにおいて銀行が資金仲介者として果す役割やそのあり方について考え、銀行の信用創造機能がマクロ経済に与える影響や、通貨当局が経済の安定化を図るために行う金融政策の手段や効果について分析する。さらに、金融監督当局による金融機関に対する監督・規制の目的や効果について考察する。
本授業では、経営者や、さまざまな利害関係者がそれぞれの立場から行う企業の経営状態の分析に関して、その基礎知識とともに、明確な視点に基づいた企業分析の方法を修得することを目的とする。具体的には、入手可能な会計情報に基づいて、その加工や分析を行うための手法を学び、分析結果を適切に理解するための知識について学修する。授業においては、具体的な事例を題材として取り上げ、実際に分析作業を行うことで、分析能力の向上と分析結果の解釈をより精緻なものにすることを目指す。
本授業では、企業経営という多面的な活動の中の資金調達に関わる活動に焦点を絞る。名称は『資金調達論』とされているが、調達という入り口の活動のみに限定した授業ではなく、調達した資金の投資、もうけた利益の分配、という資金の流れを通した企業経営のメカニズムについて議論することになる。以上をふまえて、この授業では①投資の意思決定に関する内容、②資本構成に関する内容、③配当政策に関する内容、の3点を取り上げる。
現代の組織における経営管理目的の会計である管理会計の意義・役割について、伝統的な管理会計の基本原理をはじめ、具体的な諸概念と諸技法および管理会計システムに関する知識を修得することを目的とする。より具体的には、組織経営における、経営計画と統制のためのマネジメント・コントロールおよび意思決定を通じた管理会計の有用性と限界を学ぶことで、管理会計がどのような機能と役割を果たしうるかについて理解することを目的とする。
財務会計、管理会計の双方に情報提供を行うのが、製品・サービスの原価計算である。本授業では、原価および原価計算の基礎的な概念と技法についての知識を身につけ、現代の企業経営における原価計算およびコストマネジメントの意義や目的およびその利用に関する有用性と限界について理解することを目的とする。実際原価計算や標準原価計算など、制度としての原価計算の基礎を踏まえ、原価管理、差額原価収益分析などの原価情報の利用について学修する。
監査は、企業の財政状態や経営成績を示す財務諸表に信頼性を付与することを目的とする。監査があって初めて会計が完結し、また、監査があって初めて金融市場が機能する。そのため監査は、高い専門能力と経験、独立性、職業倫理、厳密な業務規範と品質管理に関する規範を必要とし、プロフェッションとしての自主規制、行政による管理、裁判制度によりその実効性が担保される。本授業では、監査上の基礎概念(重要性、リスク、内部統制、試査、適正性など)の他、監査基準、職業会計士制度、証券市場規制について、その歴史と現状および問題点を、事例等を通じて検討する。
実証会計論は、現実に行われている会計実務を客観的に捉え、事実の解明を目指す学問である。この科目では、会計現象が生じる原因と結果を説明し、予測するための理論を構築することを目的とする。利用可能なデータを用いた統計的因果推論により、会計情報の市場における有用性や企業ガバナンスへの影響を評価する。本授業では、実際の会計データを用いて統計的分析を行い、仮説を検証することで、会計実務に対する洞察を深める。また、証拠に基づく政策形成(EBPM)の手法を学び、証拠に基づいた政策決定の重要性を理解し、会計実務の改善に貢献することをめざす。
本授業では、個別の会計基準についての知識ではなく、それらの背景にある経済学的な論理について学ぶ。具体的には、財務会計情報がどのような性質を持ち、市場参加者をはじめとする企業の利害関係者がそれをどのように利用しているのか、彼らの行動にどのような影響を与えるのかについて、これまでの学術研究の成果をたどることで、財務会計の機能についての理解を深める。その上で、会計基準を設定する際にどのような点について考慮すべきか、また、会計基準を読み解き理解する際にどのような点に注意すべきかについて習熟する。
連結会計とは、親会社および子会社など支配従属関係にある企業グループを単一の組織体とみなし、その経営成績および財政状態を把握するために連結財務諸表を作成する会計である。連結財務諸表は、親会社および子会社などそれぞれの法人格に基づいた個別財務諸表が作成された後、連結会計特有の手続きを経て作成される。本授業では、連結会計特有の手続きとその背後にある概念について学修し、連結財務諸表情報の作成プロセスと情報の特徴をつかみ、企業グループの経済活動を理解することを目的とする。
International Accounting as a subject of academic inquiry has commonly featured three interrelated domains; 1) accounting standards and practices in individual countries viewed in comparative perspective, 2) accounting issues that arise from cross-border transactions and transnational businesses, and 3) accounting issues associated with the development of global standards of accounting and reporting. In view of the ongoing process to develop International Financial Reporting Standards (IFRSs), there is naturally a growing focus in ‘International Accounting’ on what IFRSs are all about, how they are developed, and what consequences they hold for accounting for each country and business entity affected by them.
本授業では、現代ファイナンスを理解するうえで必要な、証券価格とリスクの分析、ならびに資産運用をめぐる基本的な理論を体系に学ぶ。また、それに先立ち金融仲介機関のしくみや金融市場をめぐる制度や規制について学び、それらが円滑な金融システムの維持にどのような役割を果たしているかについて学修する。これらを学ぶことによって、経済主体の戦略的な投資や運用の意思決定などの実務に応用可能な基本知識を身に着けることを目標とする。
コーポレートファイナンスとは、企業とステークホルダーとの間の制度的問題の解明を目的とした学問分野である。特に株主に対する利益還元政策、またステークホルダーとの利害対立が存在する中での企業行動に焦点を当てたコーポレートガバナンスについて論点を整理する。さらに企業の流動性リスクを低減させる手法である短期資金管理や運転資本管理についても焦点を当てる。この際、コーポレート・ガバナンス改革、ESGの重要性の向上など、近年の構造的な変化を理解したうえで、望ましい企業金融のあり方について考察する。
本授業では、国際金融論について基本的な内容を扱う。国際金融論は、(外国と資本の貸借取引や財・サービスの売買取引を行う)開放経済の様々な問題について国境を越えた金融取引に注目しながら考察するものである。すなわち、金融論を開放経済に拡張した経済学の体系である。授業においては、はじめに、国際収支、外国為替市場、外国為替レート、開放マクロ経済政策について主に理論的な内容を学修する。その後、発展的な内容として、通貨危機や通貨統合など国際金融に関する諸問題を学ぶ。
会計情報の作成手法である簿記のうち商業簿記について、実践的に基礎知識を修得することを目的とする。具体的には、各種会計事象についての仕訳、総勘定元帳への転記、試算表の作成、精算表への転記ならびに決算整理仕訳を通じた貸借対照表と損益計算書の作成という簿記一巡を遂行できる基本的な能力を養成した上で、クレジット売掛金、手形取引、金融商品、債務保証、リース会計、貸倒引当金ならびに各種引当金や為替換算会計、企業結合、連結会計といった基本的な株式会社会計までを実践できるようにする。
会計情報の作成手法である簿記のうち工業簿記について、実践的に基礎知識を修得することを目的とする。具体的には、まず材料費会計、労務費会計、経費会計、製造間接費会計といった製品原価を構成する基本的な要素の会計処理について学んだ上で、単純個別原価計算・各種総合原価計算(単純、工程別、組別、等級別)・標準原価計算・直接原価計算などを通じて工企業の財務諸表を作成できるようにする。また、直接原価計算を学ぶ際には、短期利益計画・損益分岐分析・原価分解といった分析手法も合わせて修得する。
経営学を学ぶうえで必要となる統計データの利用と分析の方法について、最も基礎的なレベルからの理解を図る。集団現象に関するデータの収集方法、その集団の特質をデータに基づいて記述する方法(基本統計量、度数分布表、ヒストグラム、相関と回帰)、確率理論にもとづき標本データから母集団の特性値を推定する方法(母比率、母平均の推定)までを範囲とする。なお、授業の理解に必要な数学的知識については授業内で補足する。
本授業は、一般に大学初年度レベルとされる線形代数の内容の一部を、経営学分野とのつながりが深いいくつかの問題との関連を確認しながら学修する。微分積分とともに、線形代数の知識は数理モデルや統計的分析手法を正しく理解するためには必須である。特に、複数の「数」を見通しよく一度に扱うためには線形代数の知識が有用となる。本授業では応用分野の学修に進む前の準備段階として、問題演習を行いながら、線形代数の基本的な概念や論理の理解を深めることを目指す。
本授業は、一般に大学初年度レベルとされる微分積分の内容の一部を、経営学分野とのつながりが深いいくつかの問題との関連を確認しながら学修する。線形代数とともに、微分積分の知識は数理モデルや統計的分析手法を正しく理解するためには必須である。特に、数量の「変化」を考察するためには微分積分の知識が有用となる。本授業では応用分野の学修に進む前の準備段階として、問題演習を行いながら、微分積分の基本的な概念や論理の理解を深めることを目指す。
本授業では、経営学部における諸学修に必要なコンピュータの利用方法について、基礎的な知識と技能を修得することを目的とする。具体的には、学内情報システムおよびインターネット利用の方法、情報倫理、セキュリティなどの基礎知識に加え、学内のメールや授業支援ツール、および文章作成、表計算、プレゼンテーションに必要となるアプリケーション・ソフトウェアの基礎的な活用方法を学修することで、その後の学修・研究活動においてコンピュータを有効に活用できるようになることを目指す。
本講義においては、ビジネスにおけるデータの重要性が増し続けていることに鑑み、データ分析の演習を通じて、データを用いて新たな科学的および社会的に有益な知見を導く基礎的な方法を学ぶ。具体的には、「基礎統計」と「情報処理演習」での学びを前提にしつつ、Excel等のツールを利用しながら、データのビジュアライゼーション、統計学や機械学習のモデルを使用したデータ分析を実践する。これにより、学生はエビデンスに基づいたレポート・論文執筆に必要なリテラシーを身につける。
情報処理では,与えられた問題(データ)から求める結果(出力)を得るために、「どのように1つ1つの処理を組み合わせ、最終的な結果(出力)に辿り着くのか」という過程(プロセス)を,プログラミング言語を用いた実習を通じて学ぶ。また,これらの実習を通じ,ものごとを系統立て,かつ論理的に考える力を養う。
アメリカなどにおいて英語によって行われる簿記について、実践的に基礎知識を修得することを目的とする。具体的には、各種会計取引についての仕訳(Journal Entries)、総勘定元帳(Ledgers)への転記、試算表(Trial Balance)の作成、精算表(Work Sheet)への転記ならびに決算修正仕訳(Adjusting Entries)を通じた貸借対照表(Balance Sheet)と損益計算書(Income Statement)の作成といった簿記一巡を、アメリカ会計基準に従って遂行できる能力を獲得することを目指す。
アメリカなどにおいて英語によって行われる会計実務について、基礎的な理論を実践的に修得することを目的とする。具体的には、棚卸資産会計(Accounting for Inventories)や固定資産会計(Accounting for PPE)ならびに金融投資の会計(Accounting for Financial Investments)といった各種の資産会計、貸借対照表貸方の負債と純資産の各種項目について学んだ上で、連結財務諸表やキャッシュ・フロー計算書を、国際会計基準との相違を意識しながらアメリカ会計基準に従って作成できる能力を獲得することを目指す。
民法は私法の基本法として位置づけられ、総則・財産法・家族法で構成されている。民法Iでは、初めて民法を学修する学生を対象に、基本テキストを採用し、総則・財産法を中心に理解を図る。具体的には、民法の導入科目として、民法とは何か、民法の法源、民法の歴史と原理に触れつつ、民法総則の人と物、法律行為と意志表示、法律行為の有効要件、行為無能力制度、意志の欠缺・瑕疵ある意思表示、代理など、契約の成立や債権債務に関わる法律規定を概説する。
民法IIでは、民法Ⅰの学修を基礎に、社会で必要とされる債権総論及び債権各論を中心に理解を図る。具体的には、契約の成立に関わる契約総論の規定、契約の効力に関わる契約総論、債権総論の規程、契約の解除について触れるとともに、典型契約の中からおもな契約の性質、それぞれに特別の要件や効果について概説する。すなわち、申し込みと承諾、危険負担などの双務契約の効力、債務不履行責任の要件、契約解除の要件・効果、売買契約、消費貸借契約、賃貸借契約などである。また、債権総論においては、債権の発生、効力、消滅、譲渡等を取り上げる。
グローバル化、ICTなどめまぐるしく変化する経済環境のなかで、現代の日本経済の現段階とその特質を明らかにすることが日本経済論の課題である。具体的には、対外経済関係、産業、労働、財政、金融など日本経済のマクロ的現実を相互の関連を重視して、直面する日本経済の課題を多角的に検討する。それにより、経営学を学修してゆく上で、前提となる日本経済の基本的な知識を獲得する。
ミクロ経済学は、経済を構成する最小単位である家計や企業の行動を分析する学問分野である。本授業では、まずはじめに経済主体、家計・企業の行動の分析を通じて導き出される需要関数と供給関数を説明する。次に市場における価格の決定メカニズム、およびそこから派生する資源配分の効率性について学修する。また競争が不完全だったり、外部性が存在したりするような場合に市場メカニズムがうまく機能しないことを理解し、政府や規制がどのような役割を果たすかを理解する。
今日、経済のグローバリゼーションが改めて問われている。グローバリゼーションの進展は、経済発展をもたらし、米欧日中心の世界経済に新興国が登場し、その存在感を高めている。同時に貧困の広がりと格差の拡大、民族問題、紛争、地球環境の悪化をもたらしている。さらに欧米の政治が転換を向かえ、一部の国では脱グローバル化が見直されている。これらを踏まえ、本授業では、国際貿易、国際金融、多国籍企業に関する基礎理論や実証を取り扱い、世界経済の現実と歴史的背景及びその諸現象の仕組みについて理解を図る。
本授業では、マクロ経済学の基本的な内容を取り上げる。マクロ経済学は、ミクロ経済学とともに経済学の基本となるものであり、経済を大きな視点から捉えて、一国全体の生産量や投資、消費、失業、物価等の変数について考察するものである。授業においては、GDPやその関連変数、国民経済計算を学んだ後、消費や投資の決定に影響を与える要因および、乗数メカニズムやIS-LM分析の学修を通じて経済政策(金融政策・財政政策)の効果について考える。さらに、それらと関連してインフレーション、失業、経済成長についても学ぶ。
経営学の主たる対象は企業である。それらは市場経済を基礎とした社会のなかで成立し活動する組織であり、市場社会の経済学を基礎として捉えることができる。本授業では、経営学が捉える企業を、市場経済のなかから生み出され、市場経済とともに発展・変化する存在であるとの経済学的基礎において理解を深め、企業の経営行動をより広い市場経済や社会との関係のなかに位置づけて、その中で客観的な目と主観的な目との区別と関連ができることを主たる内容とする。
会社法は、会社組織の形成からその運営、さらに消滅までを規制対象にしている。これは、会社に出資または投資する者、経営する者、会社の取引相手方といった会社と関係する人々の私的利益の調整を目的とする。本授業では、会社法上の制度につきその趣旨等の基本事項の理解と、そこで重要な論点に関する学説・判例を理解することを目的に、会社法および関連する特別法・法務省令の中で、経営学部の会社法科目に相応しい内容を扱う。
金融法とは、銀行などの金融機関を取り巻く法規制及び金融取引に関わる法律を総称したものである。本授業では、金融機関の設立と役割に関する法と規制(具体的には、銀行法や預金保険法等)と、金融機関の具体的な諸業務に係わる法律等(具体的には、銀行取引に関する法等)について学修する。金融機関を取り巻く法律・規則等の特徴や内容の理解、及び金融システム維持の重要性について把握できるようになることを目的とする。
本授業では、所得課税法(所得税法、法人税法)を中心に、経営学部の税法科目に相応しい内容を扱うことによって、税法の基本原則や基礎理論について概説する。実際の取引にどのように税法が適用されるか、重要判例に触れつつ、税法の諸問題について考察することで、税法の基本原則と憲法規定との関係、税法条文や施行令・規則、通達、判例や裁決例などの調べ方や読み方、基本的な各税の仕組み、税理士制度についての理解を深めることを目的とする。
本授業では、人的資源管理にあたっての法規制の理解を目的とする。具体的には、正社員やパートタイマー・派遣労働者などの採用・人事異動といった雇用管理、労働時間・休憩・休日・年次有給休暇・賃金・福利厚生といった就業条件管理、就業規則と懲戒・労働災害・ハラスメントといった職場環境管理、労働組合の結成・団体交渉・団体行動に対する労使関係管理、裁判所・労働委員会・労働基準監督署といった権利救済機構を扱う。
本授業では、国際取引の現状や特徴から、国際取引法の課題を明らかにし、適用される法として国際私法、統一私法、国際的統一規則、公的規制法規とその相互関係を考察する。国際的物品売買から派生する諸問題では国際物品運送、国際貨物保険、国際的代金決済、製造物責任などについて、国内法、国際条約、諸国の法の比較法的視点も入れて考える。また、国際技術移転、プラント輸出、国際投資の法的枠組みの現状を概観するとともに、国際取引紛争の解決手段としての国際訴訟、国際商事仲裁などに触れる。
© Ritsumeikan Univ. All rights reserved.